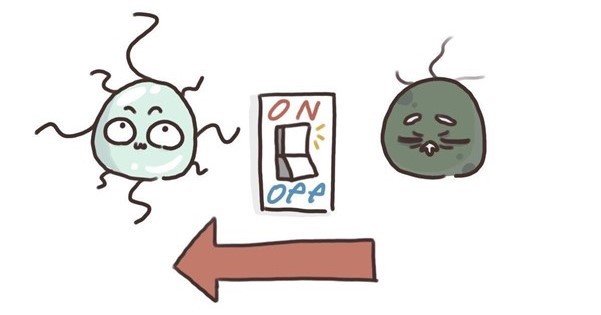ウクライナのインフラはなぜ止まらないのか 日本の企業人とも重なる死闘、初めて描く書籍

2022年2月のロシアによる侵攻以来、ウクライナが3年半以上も戦い続けられるのはなぜか。その陰にある電力や通信、金融、運輸などのインフラ企業の奮闘を初めて描いた「ウクライナ企業の死闘」(産経新聞出版)が今月出版された。著者でNTTチーフ・サイバーセキュリティ・ストラテジストの松原実穂子さんは「危険をかえりみず働くウクライナの名もなき企業人たちの奮闘に畏敬の念を覚える」と話す。
娘を残し殉職した技術者ら
昨年11月、ウクライナ南部オデーサ。国営電力会社の変電所が攻撃を受け、電気技師の男性2人が死亡した。勤務中の急襲だった。
1人は高度な技能を持つプロフェッショナル。もう1人は全面侵攻後、23年5月までウクライナ軍に従軍し、復員後は電気技師として働いていた。それぞれ、10歳と14歳の娘が残された。同社はフェイスブックの投稿にこうつづった。
「このような犠牲は、残念ながら、ウクライナの家庭の灯りを守る従業員たちの勇気と献身を痛切に思い起こさせる」
本書によると、ロシアによる全面侵攻以来、ウクライナ電力網の4割を運営する大手電力会社「DTEK」では6千本以上の送電線と1千カ所のインフラ施設を復旧させた。一方で開戦から1年だけで、ロシアの攻撃により従業員4人が殉職したほか、非番時に空爆で11人が死亡。従軍中の126人が戦死した。
技術者たちは常に砲撃の危険にさらされており、空襲警報が鳴っているときは防空壕に飛び込む。近くになければ橋の下など隠れられる場所を探す。送電線の修理中に地雷を踏んで命を落とした技術者もいるという。
軍人ではない普通の人々が
著者の松原さんは、サイバーセキュリティーの専門家。今回のロシアによる全面侵攻後も、重要インフラへのサイバー攻撃をめぐる両国の攻防について情報収集してきたが、やがて、そうした企業で働く人々の献身的な闘いに深く心を打たれたという。
インタビューに応じる松原実穂子さん=東京都千代田区(安元雄太撮影)「私もNTTというインフラ企業で働いているが、現場に踏みとどまって発電所などの運用や修理を続ける技術者たちの状況は、過酷という月並みな言葉では足りない。途方もないプレッシャーの中で業務を続けている」
本書では電力・エネルギーのほか、通信、金融、運輸の各インフラ業界に一章ずつを割いている。携帯電話の基地局がミサイルやドローン攻撃で破壊されても、現場に走り修理に当たる通信会社の技術者ら。空爆の中、悪路を通ってATMまで現金を届ける銀行員たち。身の危険を冒して鉄道を走らせ、国民や兵士、物資を運ぶ鉄道マン…。
松原さんは「軍人ではない普通の人々が、どんなに打撃を受けても、それにあらがい、対応し、素早く立ち直るレジリエンスの能力を発揮している。さまざまな苦境に屈せず、立ち向かい続けている」と指摘し、こう続けた。
「そのさまは、東日本大震災や能登半島地震など数々の大規模自然災害にもひるまず、インフラを復旧し経済や社会生活を支えてきた日本の企業人たちの矜持とも重なる」
台湾有事の安全保障へ教訓
ウクライナへの軍事侵攻が始まって、すでに3年半以上。この間、戦争についておびただしい数の本が出版されたが、戦時経済と安全保障を支えるインフラ企業の闘いに光を当てた本は、国内はもちろん、海外でも見当たらないという。
「ウクライナ企業の死闘」(産経新聞出版)松原さんは、ウクライナ企業の経験が、日本が直面する台湾有事リスクなどへの備えになると指摘する。
「台湾有事での日本の役割、とりわけ自衛隊や在日米軍が果たし得る役割を考えると、日本の重要インフラが狙われてもおかしくない。平時のいまこそ、たとえばウクライナでは業界ごとの縦割りの事業継続計画(BCP)しか作っていなかったことなど、彼らから教訓を学ぶべきだと思う。企業人だけでなく、重要インフラの所管官庁の方々にも読んでもらいたい」
(まつばら・みほこ)早稲田大卒業後、防衛省などに勤務。現在はNTTチーフ・サイバーセキュリティ・ストラテジスト。著書に「サイバーセキュリティ」「ウクライナのサイバー戦争」など。令和4年、第23回正論新風賞。産経新聞「正論」メンバー。
大阪・関西万博ウクライナ館には、戦時下で働く大手電力会社「DTEK」のヘルメットが展示されている(松原実穂子さん撮影)