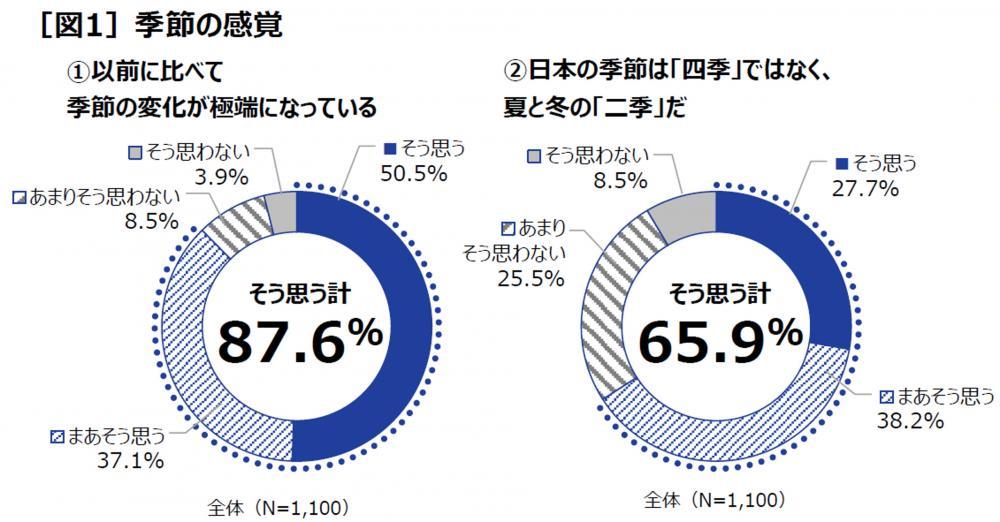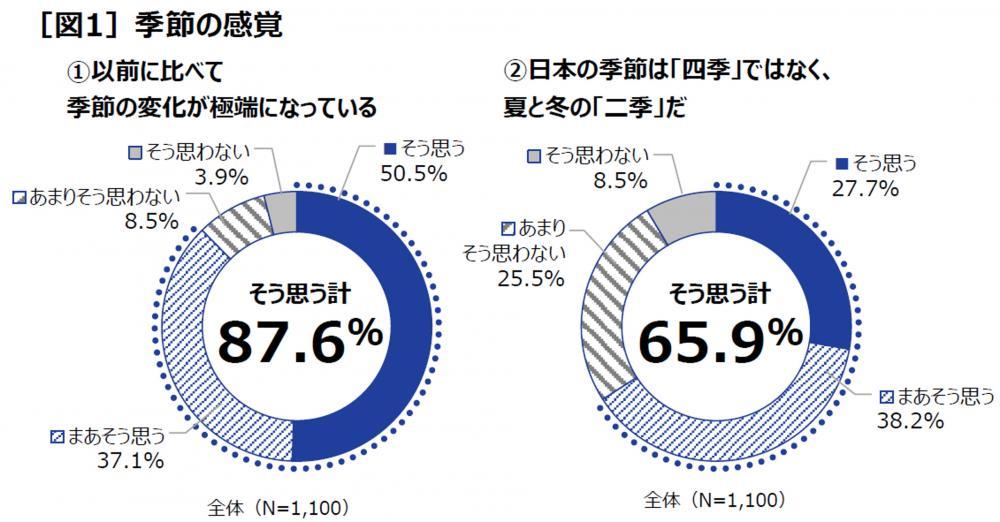大河ドラマ『べらぼう』の時代…遊郭・市中「梅毒感染者」どのくらい? 杉田玄白も記録した“驚異的な”まん延状況

近年、性感染症のひとつである梅毒の感染者数が高止まりを続けている。国立感染症研究所によれば、2024年には全国で1万4663人と、過去最多を記録した2023年に次ぐ高い水準だった。
梅毒の主な感染経路は性交渉などの性的接触や母子感染だが、近年の流行においては異性間の性的接触による報告数が増加傾向だという。さらに、感染者のうち男性の約4割が直近6か月以内の性風俗産業の利用歴を、女性の約4割が従事歴を持つとも報告されている(2022年第3四半期(第27~39週))。
折しも現在、NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』では江戸の華やかな吉原遊郭が描かれ、大きな話題を呼んでいる。遊郭もまた、性風俗産業であり、梅毒とは深い関わりがあった。
遊郭および市中には、どのくらいの梅毒感染者がいたのだろうか。また、治療はどのようになされていたのか。感染症史に詳しい奈良女子大学・鈴木則子特任教授に聞いた。
杉田玄白も記録した「梅毒患者の多さ」
日本に梅毒が伝来したのは16世紀初頭で、江戸の町には比較的早い時期から広まっていたとされる。
初期の記録は少ないが、大河ドラマの主人公・蔦屋重三郎(通称「蔦重」)が生まれた18世紀半ば頃から、医学書の中で梅毒について頻繁に取り上げられるようになったと鈴木特任教授は言う。当時の記録には、次のようなものがある(いずれも意訳)。
「100人の患者を診ると、60〜70人が梅毒である」(中神琴渓/大津・京都)「身分の高い者から庶民に至るまで、梅毒にかかっている者は半数以上におよぶ」(片倉鶴陵/相模)
「大都市では10人中8~9人が梅毒にかかっている」(永富独嘯庵/長州)
また『解体新書』生みの親で、蔦重と関係の深い平賀源内と親交のあった杉田玄白も「(自身が)毎年1000人以上を治療しているうち、700〜800人が梅毒患者である」と、驚異的な多さに言及している。
「これらの記録からは、当時いかに梅毒がまん延していたかがうかがえます」(鈴木特任教授)
ただ、江戸のような都市では身近な病だった一方、地方の農村部などではまれな病だった。これは、「遊郭、そして遊郭通いの習慣の有無によって、感染率に差が生じたことを示唆している」と鈴木特任教授は指摘する。
発掘調査からは、江戸の町の中でも特に庶民が暮らす下町で梅毒感染者が多かったことがわかっている。
「江戸時代に埋葬された墓地の発掘調査では、骨にまで梅毒トレポネーマ(病原体の細菌)が侵食した痕跡(骨梅毒)が確認されています。中でも、庶民が多く埋葬された下町の墓地では約7%に骨梅毒が見られたことから、実際の梅毒感染率は70%を超えていたと推測され、その深刻さが垣間見られます」(鈴木特任教授)
一方で、武士階級の墓の骨梅毒率は3%であり、庶民の方が明らかに感染率が高かったという。その背景として、鈴木特任教授は「梅毒に対する意識の差」を指摘する。
「もちろん、武士にも遊郭から梅毒を持ち帰る者はいました。しかし、家の継承を非常に重視する武家では、梅毒という病への嫌悪感や差別意識が庶民に比べて強く、遊郭通いや感染者との婚姻により家の内に持ち込まれることへの警戒心も強かったと考えられます。
他方、庶民は家の継承より日々の生活に追われていたケースも少なくなく、梅毒への警戒心が相対的に弱く、結果として母子感染が広がり、庶民の感染率を高めた可能性があります」(同前)
ただし庶民でも、女性が梅毒に感染すれば結婚が難しくなるなど差別的な扱いを受けることもあったと、鈴木特任教授は補足する。
下級遊女ほど梅毒に感染していた?
文献などから、梅毒が性交渉によって感染するものであるとの認識は、梅毒が伝来した当初から人々の中にあったことがうかがえるが、不特定多数との性的接触が感染リスクを高めるとは考えられていなかったようだ。
そして江戸時代中期以降には、梅毒はそもそも「遊女の体に生じる病」であるという考え方も、医学書などから読み取れるという。鈴木特任教授は次のように続ける。
「当時の人々は、下級の遊女ほど梅毒に感染しており、上級の遊女は比較的安全だという共通認識を持っていました。
しかし、これはあくまで“イメージ”にとどまります。実際には、遊女が相手にする客の数が感染リスクに影響を与えていたと考えるのが自然です。
大河ドラマに登場した『瀬川』のような高級遊女であればあるほど、その遊女を“買える”客の数は限られてきますし、特定の客だけを相手にするようになります。一方で、下級遊女は不特定多数の客を次々に相手しなければなりません。
この労働環境の違いが、感染する確率に差をつけていたと言えるでしょう」
さらに江戸時代、売春が行われていたのは遊郭の中だけではなかった。
「梅毒に感染し働けなくなった遊女は、遊郭の外に売り出されることもありました。彼女たちは街娼(がいしょう)となり、街角で身を売るようになります。そして、それを買うのは庶民です。こうして、梅毒は市中に広がっていったと考えられます」(鈴木特任教授)
水銀、生薬、温泉…人々がすがった治療法
ペニシリンの普及により梅毒の発生が激減したのは、第二次世界大戦後のこと。それよりはるか以前の江戸時代には、どのような治療法があったのだろうか。
「江戸をはじめ、梅毒がまん延していた都市では、医師たちがさまざまな治療法を考案した記録が残っています。中でも多く使われたのは、水銀と、山帰来(さんきらい)という生薬です。
水銀は、皮膚症状の緩和には一定の効果があったものの、病原体自体を死滅させることはできず、水銀中毒を引き起こす危険性もはらんでいました。
一方、輸入薬である山帰来は高価であったため一般庶民には手が届きにくく、症状を軽減する効果自体についても、水銀のように早くはあらわれません。
いずれも決定的な治療薬とは言えず、症状を緩和する効果しかないので、実態としては自然治癒(※)に期待するしかありませんでした」(鈴木特任教授)
※ 梅毒は一時的に自然軽快しながら進行するため、その期間が「治癒した」と捉えられていたケースも考えられる
また湯治に救いを求める人も多く、西の城崎、東の草津をはじめとする温泉地が人気を博したとの記録も残っている。
現在は効果的な治療法があるが…
前述のように、特効薬であるペニシリンによって梅毒が激減するのは第二次世界大戦後のこと。
日本では1948年より性病予防法(1999年廃止、現在は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」に継承)に基づき全数報告が開始され、2000年代には500~900例程度で推移していた。
ところが、2011年頃から増加傾向となり、2019〜20年には一度減少するが、2021年以降は再び増加に転じ、現在に至っている。
現代においては効果的な治療法があるにもかかわらず、感染が拡大している現状は憂慮すべき事態だ。決して「過去の病気」と油断することはできない。
- この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいて執筆しております。