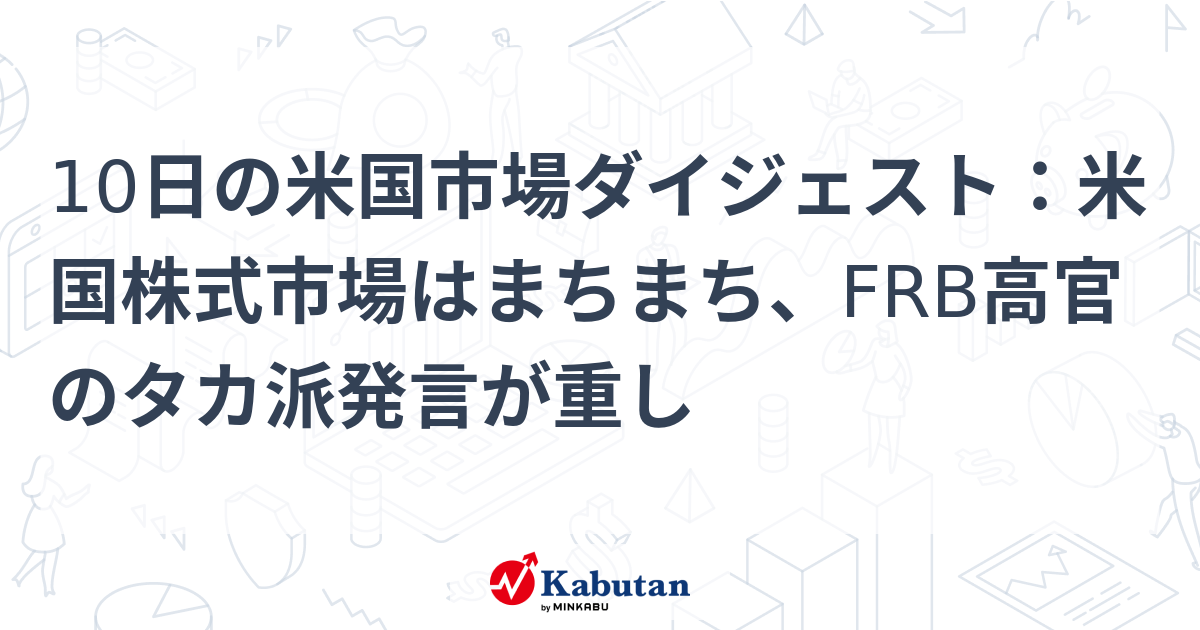10月14日、Windows 10サポート終了!公式に提供される延長オプションを解説します

Windows 10パソコンが、1つの大きな節目を迎えようとしています。
それはMicrosoftが定めたWindows 10のサポート終了日、2025年10月14日。
これは単に「OSが古くなる」という話ではありません。
お使いのPCの安全性とあなたの大切なデータを守るための「デジタル世界の健康診断」を受けるべきタイミングが来た、という重要なサインです。
「すぐに買い替えなんて難しい」「今の環境をできるだけ長く使いたい」
様々な事情を抱えるユーザーのために、Microsoftはいくつかの選択肢を用意しています。
この記事では、サポート終了が具体的に何を意味するのかという本質から解き明かし、あなたにとって最適な次の一手を見つけるための判断材料を、詳しく解説していきます。
そもそも「サポート終了」とは? 本当のリスクを理解する
Microsoftによる「サポート」とは、主に以下の2つの提供を意味します。
新たに発見されたウイルスやサイバー攻撃の脆弱性を塞ぐための、もっとも重要な「防御パッチ」。
OSの不具合修正や、新しい機能の追加などを行うシステム。
サポート終了後の2025年10月15日以降、このうち特に重要な「セキュリティ更新プログラム」の提供が停止します。
これは、たとえるならば「家の鍵の新しい交換サービスが受けられなくなる」ようなものです。
世の中で新しいピッキング手口が見つかっても、あなたの家の鍵は古いまま。日を追うごとに、空き巣(ウイルスやハッカー)にとって格好の的となってしまうのです。
お使いのPCがインターネットに接続されている限り、このリスクは避けて通れません。
サポート終了後も安全に使い続けるには?
ではどうすればいいのでしょうか?
その解決法は無料または有料の拡張セキュリティ更新プログラム(ESU)に登録すること。
これまでもWindows 10ユーザーは、年間30ドル(約4500円)でESUに加入できましたが、それに加えてMicrosoftは、費用をかけずにデバイスを保護するための選択肢を新たに2つ提供しています。
設定をクラウドに同期するWindowsバックアップを有効にする。
Bingの利用や製品購入などで貯まるMicrosoftリワードポイントを1,000ポイント利用する。
なお、どちらの無料オプションも、Microsoftアカウントを持っている(または新規作成する)ことが条件となります。
具体的な登録手順は?
では上記の条件をクリアしている場合、どのように手続きを行えばいいのでしょうか?
Windows 10をまだお使いであれば、このプログラムに関するプッシュ通知が届いているはずです。
もし通知が来ていない、あるいは見逃してしまった場合でも、設定アプリから登録手順に進むことができます。
- PCを最新バージョンにアップデートする。
- 設定 → Windows Update に進む。
- 「Windows 10のサポートは2025年10月に終了します」という表示の下にある、「延長セキュリティ更新に登録してデバイスの安全を確保する」を探して選択。
- 有料プランを含む3つの登録オプションのいずれかを選択して完了。
これにより、今後もPCに重要なセキュリティ更新が配信されるようになります。
ESUは「未来への橋渡し」。恒久的な対策ではないことを心に留める
この延長プログラムは、あくまで本格的な移行を準備するための「橋渡し」です。Microsoftも、これを長期的な解決策とは位置付けていません。
ESUで提供されるのは、致命的な脆弱性を防ぐための最低限のセキュリティ更新のみです。
新機能の追加や性能向上、技術的なサポートは一切含まれません。
つまり、PCの使い勝手は向上せず、徐々に最新のソフトウェアや周辺機器との互換性の問題も発生する可能性があります。
(※なお、WordやExcelなどのMicrosoft 365アプリは、Windows 10上でのサポートが2028年10月まで継続される予定です。)
この1年という猶予期間を、「何もしなくて良い期間」と捉えるのではなく、「次の一手を計画的に準備するための戦略的な時間」と位置づけることが、あなたのデジタルライフを豊かにする鍵となります。
著者紹介:Emily Long
デューク大学卒業後、ワシントンD.C.のアトランティック・メディア・カンパニーが発行するGovernment Executive誌で、連邦政府の労働力に関する記事を数年間執筆。フリーランスとして10年近くの経験を持ち、テクノロジーに加え、個人金融や旅行などの分野を執筆している。Lifehackerに加え、Wirecutter、Tom's Guide、ZDNETにも寄稿。