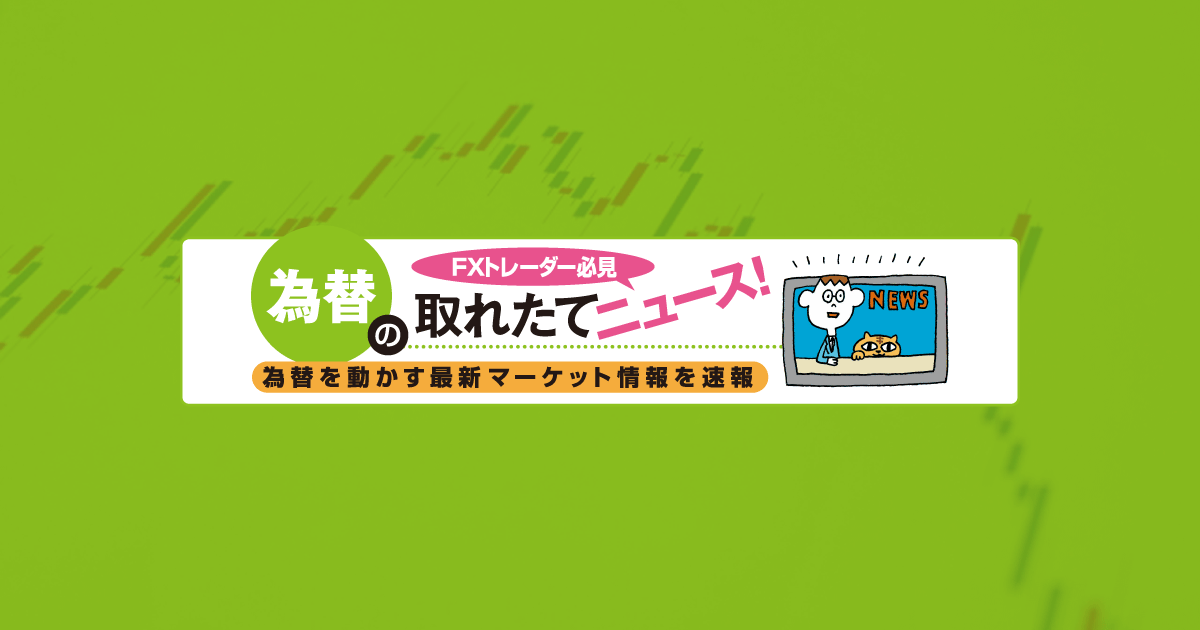首都高「日本橋地下トンネル」ついに工事本格化 現場で見えてきた「世紀の難工事」とは 八重洲線休止後の現状

首都高都心環状線の「日本橋川区間」を地下化する工事が本格化しています。そんななか2025年4月25日、工事前の現場が報道公開されました。
日本橋川の上空から「高架」消す大事業
首都高都心環状線の「日本橋川区間」を地下化する工事が本格化しています。
そんななか2025年4月25日、工事前の現場が報道公開されました。
都心環状線は、神田橋JCTから日本橋川の上空を高架へ抜け、江戸橋JCTで箱崎方面と分かれ、南下して京橋・築地方面へ向かいます。
この日本橋川区間を、地下化していきます。江戸橋JCTのランプは廃止され、都心環状線は新ルート「新京橋連結路」(八重洲~京橋)へ切り替えられる計画です。
日本橋地下トンネルは、八重洲線が東京駅方面に向けて地下へ潜り始めるところで分岐し、江戸橋方面へ地下を抜けていきます。
その地下トンネルを工事するにあたって、2025年4月5日に八重洲線が閉鎖。長期間の休止となりました(2035年度まで)。
八重洲線にクルマが通らなくなったので、いよいよトンネル工事が本格的に始まっていきます。今回の報道公開は、その現場で行われました。
八重洲線が地下へもぐっていく「八重洲トンネル」の入口では、信号機が「赤」を点灯していました。首都高の担当者いわく、通行止めにしたあとも念のため赤信号を点灯し続けているとのことです。
トンネルから130mあたりのところから、大々的な工事が始まります。4車線の日本橋地下トンネルに対応するため、既存の八重洲トンネルを拡幅する工事です。しばらくした先でいよいよ地下トンネルが分岐し、左カーブで東進していく構造です。
分岐部は、江戸橋方面が本線扱いとなり、八重洲方面へ行くには左分岐のランプに入るという構造となります。
ここからが大変で、地下には水道やガスなどの埋設管、そして無数の地下鉄トンネル、さらには地上にも歴史のある橋があり、壊すわけにはいきません。また、川の中で工事を行いますが、川をせき止めるわけにもいきません。
そのため、地下工事は非開削工事の3つの特殊工法「鉄樋工法」「アンダーピニング工法」「縦断ハーモニカ工法」というものが採用されます。
鉄樋工法は、川底に「とい」(家屋の屋根にあって、雨水を流す水路)のようなものを設置し、川の流水を確保するものです。
アンダーピニング工法は、橋の下をジャッキアップしていったん仮の杭で受けるというもので、構造物が完成したら、そこへ橋を乗せていくこととなります。常盤橋は明治初期からのもので、歴史的建造物として大切に扱わなければなりません。そのため、常盤橋を現地でそのままにしておくための苦肉の策が、この工法です。
縦断ハーモニカ工法は、トンネルの大断面を縦横いくつかの四角形に分割し(漢字の『田』のようなイメージ)、それぞれ小断面ごとに掘削を進めていくものです。一気に大断面を掘削するのに比べて、細やかな施工管理が可能となります。
今後、日本橋地下トンネルへの切り替えは2035年度の予定(八重洲線も復活)で、そのあとに5年かけて、使われなくなった日本橋川上空の高架を撤去していくとしています。
担当者も「現在はまだ設計が全体完了していませんが、設計の段階からこのような特殊工法の選定や検討など、困難をきわめました」と話しています。
八重洲線の通行止め開始とともに、いよいよ工事本格化となった日本橋地下化工事。地上からはなかなかその姿を捉えることは難しいですが、静かに「世紀の難工事」がはじまっていきます。