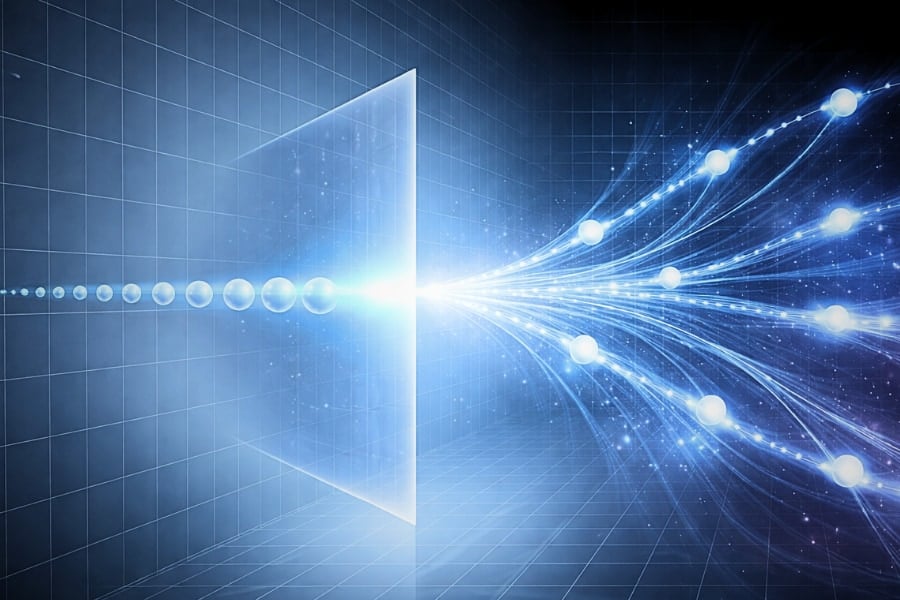イスラエルを苛烈な攻撃に駆り立てる論理(東京大学准教授・鶴見太郎):時事ドットコム

なぜイスラエルのガザ攻撃はこれほどまでに苛烈で執拗(しつよう)なのか。日本におけるこの地の紛争の平均的な理解からすれば、1948年にイスラエル国家が強引につくられ、追い出されたり支配下に置かれたりしたパレスチナ人の当然の抵抗が問題の根源である。しかし多くのイスラエル人にとっては、それはもうはるか昔の話である。
建国後にイスラエルにやってきた移民とその子孫の方が現在のイスラエルのユダヤ系人口(イスラエルの人口の2割は建国後も辛うじて領内に残ったアラブ系)の過半数を占め、彼らからすれば、ユダヤ人国家であると聞いてやって来た時にはイスラエル国家はすでに存在していた。
ガザについては、2005年にユダヤ人入植地をすべて撤退させたことがイスラエルの大きな譲歩であると記憶されている。最後まで激しく抵抗する入植者たちをイスラエル当局が引きずり出す様子をイスラエル人は想起する。
むろん、パレスチナ人からすれば、そもそも入植地があることが不当なうえ、撤退後もイスラエルが国境管理を厳重に行うことに変わりがないばかりか、ユダヤ人がいなくなったことでイスラエルは遠慮なくガザを締めつけるようになった。
だがそのことは、ハマスに圧力をかけるためのやむを得ない措置だったと一蹴される。そして、パレスチナ人だけが集住した状態のなかでハマスはイスラエルにロケットを幾度となく打ち込み、挙句に2023年の10月7日を迎えたというわけだ。
戦闘が始まった時点での平均的なイスラエル人の感覚からすると、復讐という意味合いに加え、もはやハマスを是が非でも殲滅(せんめつ)しなければならないというものだった。
軍事的手段の常態化
軍事に対する垣根が元来低いことも、ガザ攻撃を苛烈なものにする背景だ。軍事力によって建国し、度重なる危機も軍事力によってはね返してきたイスラエルでは建国来、男女とも兵役があり、対象となるユダヤ系国民の一体感を高めるとともに、危機に対して武力で対抗することが常識となっている。相手が音を上げてから交渉に入るというスタイルだ。
軍は自分自身や自分の家族・友人に関係することであるため、イスラエル兵に犠牲が出る作戦に対しては、アメリカなどの志願制の国よりも慎重になるといわれる。だが、その反面で、身内であるからこそ、いったん戦争が開始されると、軍の戦争犯罪に対する追及は弱くなるようにも思われる。
1990年代半ばからハマスなどによるテロが頻発するようになって以来、イスラエルは過剰な報復とともにハマスを物理的に遮断する方針で一貫してきた。パレスチナ人の苦境がハマス支持を増やすことにある程度感づいてはいても、物理的に抑止することが優先されてきた。
結局はそれがハマスの暴発を招いたと考えることは十分にできるが、多くのイスラエル人はハマスに対する姿勢が甘かったと考え、2023年の段階ではユダヤ系国民の圧倒的多数がガザ攻撃を支持した。
ハマスが死を厭わず武器を持って攻撃を仕掛けてくる以上(それほどまでに追い詰めてしまった以上)、いまさら武器を置いて話し合おうというモードに切り替えることが想像しにくくなっているのも確かだ。
2025年8月の段階でも、イスラエル国家安全保障研究所の調査では、ガザでの人道状況に関して、イスラエルのユダヤ系国民の74%が「まったく苦痛でない」「特に苦痛でない」と答えている。それは、ヘブライ大学付属のアコルド・センターの調査で、イスラエル国民の64%がガザには「無実の人間はいない」と考えている結果から説明できるだろう。つまり、ハマス成員でなくとも同罪だというわけだ。命綱となっているハマスに反対したからといってイスラエルが助けてくれるわけではないなか、パレスチナ人にとってこれほど理不尽な認識はない。
もちろん、戦争が長期化するにつれ、ネタニヤフ政権に対する批判は高まっている。今年に入って、各種調査で戦争継続を求めるイスラエル国民は少数派となっている。ガザ市を占領するという8月上旬の政府決定に対して、テルアビブを中心に数十万人が参加する、戦争開始以来最大規模の反対デモが起こった。
もっとも、デモの参加者の大半の理屈は、この作戦がまだガザで生きているとされる人質20名の命を危険にさらすというものである。筆者は現在北部の都市ハイファに滞在しており、その時から3週にわたってデモを観察しているが、ガザの飢餓にフォーカスする集団はいつも後ろの方で遠慮がちに行進しており、デモ隊の1~2割しか占めない。
これは人質が全員解放されたときに何が起きるかを暗示している。作戦に対する歯止めがなくなるのである。ハマスはそれを理解しているはずで、だから全員の解放には応じられないのだろう。
パレスチナ人への憎悪と宗教シオニスト
しかし、なぜイスラエル国民の多くは、温度差はあれ、これほどまでにパレスチナ人を憎悪するのか。その大きな源泉は1世紀以上の歴史のなかで培われてきたシオニズムに求められる。19世紀終わりから20世紀半ばにかけて、ポグロムと呼ばれるユダヤ人の街に対する襲撃がユダヤ人口の中心地だった東欧で吹き荒れた。それに対して助けが来ることがないなかで、一部のユダヤ人が自助自衛の精神を高め、それがパレスチナにユダヤ人の民族的拠点を築こうとする動きを意味するシオニズムの源流となった。
パレスチナに移住後もユダヤ人に対する攻撃は、ユダヤ人に非がないポグロムと同一視される流れができ、ホロコーストによってその認識はさらに強化された。ポグロムもホロコーストもアラブ人は無関係であるにもかかわらず、ユダヤ人に対する攻撃者をナチと同一視する傾向は、アラブ人やパレスチナ人との戦闘が繰り返させるたびに強化されていった。
さらに1970年前後から、世俗派が主流だったシオニズムのなかで、宗教シオニストと呼ばれる潮流が台頭するようになった。彼らはユダヤ教によってシオニズムを正当化し、しかも、西岸やガザを含め、すべてをユダヤ人が手中に収めなければならないとする主張を譲らない。
ネタニヤフの政党リクードの党是でも西岸・ガザは含まれるべきとされるが、宗教シオニストはさらに非妥協的だ。ネタニヤフ政権には彼らの二つの政党の党首が入閣しており、連立政権のカギを握っている。
イスラエル国民の多数派は、ガザ攻撃をイスラエルの安全保障のためと理解する一方で、彼らは、いわばどさくさに紛れて、ガザを一気にイスラエルのものにしてしまおうと画策し、ガザ征服を強硬に訴えるのである。彼らは、宗教シオニストのエコーチェンバーともいえる入植地に生まれ育ち、パレスチナ人の具体的な顔を知らないまま、彼らへの一方的な憎悪を強めている。イスラエル人口の1割程度を占めるにすぎないとはいえ、彼らの出生率は高く、今後のさらなる影響力拡大が懸念される。
1世紀前同様に国際社会が傍観する状況では、この一方的状況が改善されることはないだろう。(2025年9月5日掲載)
◇ ◇ ◇
鶴見 太郎(つるみ たろう)1982年岐阜県生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。博士(学術)。日本学術振興会特別研究員、エルサレム・ヘブライ大学・ニューヨーク大学各研究員、埼玉大学研究機構准教授等を経て、現在東京大学大学院総合文化研究科准教授。専門は歴史社会学、東欧ユダヤ史、パレスチナ・イスラエル紛争。著書に、『ロシア・シオニズムの想像力』『イスラエルの起源』『ユダヤ人の歴史』、共編著に『帝国と民族のあいだ―パレスチナ/イスラエルの重層性』(近刊)など。