【認知症対策】 日本政府は薬剤誘発性認知症を軽視していないか?
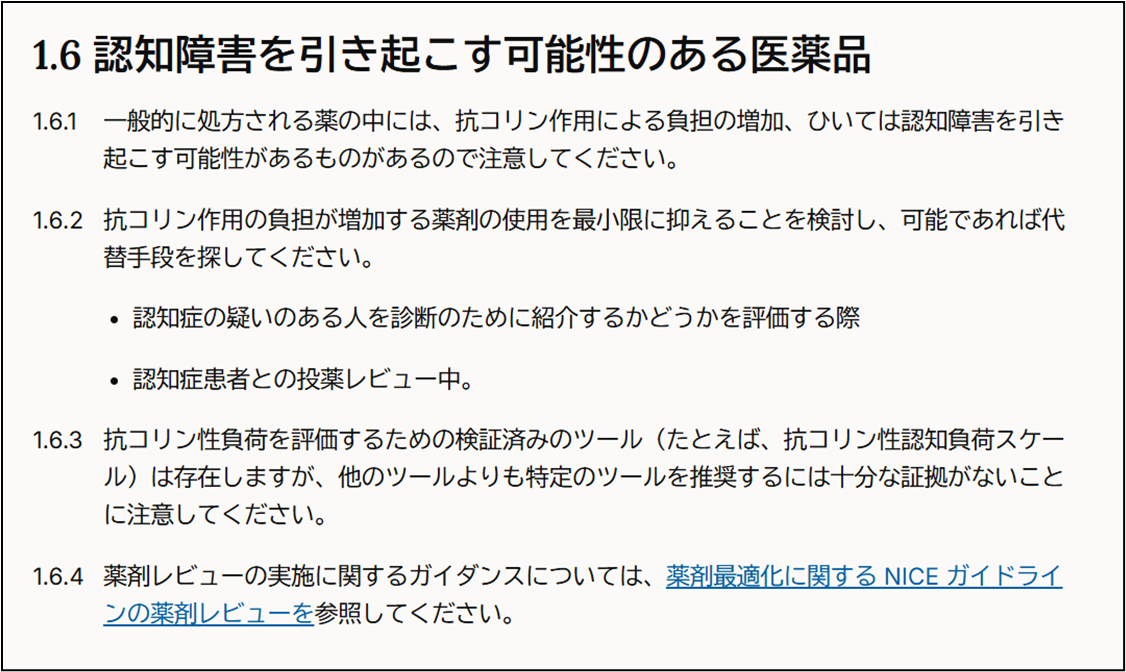
こんにちは。兵庫県川西市議会議員の長田たくや(ながたく)です。本日は、令和6年度の特別会計決算審査がありました。私は副委員長のお役を頂戴しました。審査項目は、保険事業(国保・後期高齢者・介護)と用地先行取得事業の4つです。なお、委員会ではすべて決算認定されました。
今日は、介護保険事業の「認知症対策」に関するお話をします。
日本では「認知症をどう支えるか」は語られても、「認知症をどう作らないか」という視点が欠けています。海外では、薬による認知機能障害を明確に政策の中に位置づけているのに対し、日本では医療の副作用という“構造的な原因”がまるでタブー視されているかのよう避けられています。高齢社会でこそ、「薬でつくる認知症」を見直すべきでしょう。
■ 薬剤が引き起こす認知症医薬品の使用によって認知症様の症状が引き起こされたり、発症リスクが高まることが知られています。ここでは、薬剤誘発性認知症としておきます。
認知能力の低下(記憶・理解・判断)という軽い初期症状から、幻覚妄想などの重症例まで幅が広く、薬剤をやめたら症状が改善する「可逆性」の障害から、アルツハイマー型認知症のように進行性の疾患につながるケースもあると言われています。
■ 具体的な薬剤【抗コリン薬】最も強く関連が指摘されています。アセチルコリンという神経伝達物質を阻害し、記憶・注意・判断力を鈍らせます。
代表薬:三環系抗うつ薬(アミトリプチリンなど)抗ヒスタミン薬(ジフェンヒドラミン)
排尿障害薬(オキシブチニン、ソリフェナシンなど)
この中で多いのだと、女性が良く服用する排尿障害薬ですね。日本人の研究
参照:日本人高齢者における抗コリン薬使用と認知症リスク~LIFE研究
海外のエビデンス(認知症が1.5倍のリスクに)参照:Cumulative Use of Strong Anticholinergics and Incident Dementia
【ベンゾジアゼピン系睡眠薬・抗不安薬】GABA神経系を抑制して、一時的に鎮静・催眠をもたらしますが、長期使用で記憶障害や判断力低下を生じやすくなります。
代表薬:エチゾラム(デパス®)トリアゾラム(ハルシオン®)ブロチゾラム(レンドルミン®)
ゾルピデム(マイスリー®)※厳密にはベンゾジアゼピン系ではない
市民病院のニュースレター参照:一宮市立市民病院
海外ガイドライン:参照:高齢者において潜在的に不適切な薬剤(Beers Criteria®アメリカ)
■ 日本の認知症政策と法体系日本では認知症に関する法律がありませんでした。
2015年、認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)が作られましたが、薬剤性認知症に関する記述はありません。
2019年、新オレンジプランを改訂した認知症施策推進大綱(現行:2019年6月閣議決定)を策定しました。こちらにも記述はありません。普及啓発(共生社会)・予防(軽度認知症)・研究(原因究明や治療薬)がメイン施策です。そして2024年1月に「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が制定されました。基本施策が、”認知症患者に対する国民の理解”や”バリアフリー化”、”社会参画”ですから…。海外でも法律にまで及ぶところはありませんが、本法から派生する認知症施策推進基本計画にも薬剤性認知症の言及はなされていません。類するものとしてポリファーマシー(多剤併用)対策として薬剤師を加配する程度が記載されているのみです。――これが問題なのです。
■ 市町村レベルまで計画が求められる市町村は、この法律・計画の元で認知症に対する実行プランを作れと言われます。川西市では、「認知症アクションプラン」が作られています。もちろん薬剤誘発性の「や」の字も出てきません。
ですから、私は委員会でこう言いました。「認知症の方に寄り添いましょう、自分らしく生きましょう、脳を活性化させて予防しましょう、と手を加えたところで、認知症を誘発する医薬品を大量・長期服用してたら、あまり意味がないですよね。絶対に増えていきますよ。一方、海外では系統立てて対処しています。本気で認知症対策したいのであれば、やれることはあります。」
■ 海外の例イギリスでは、NICE(英国国立医療技術評価機構)のガイドライン(NG97 Dementia)には、「抗コリン薬の長期投与は認知機能を悪化させるため、避けるべき」と明記されています。
これは法そのものではありませんが、NHS(国民医療制度)下ではNICEガイドライン遵守が義務化されており、実質的に法的拘束力に近いとされています。
日本でも、日本神経学会が作っている「認知症診療ガイドライン」に記載こそされているのですが…まず診断から除外すると言及されています。
また、どんな薬剤が影響するかは列挙され、海外情報なども記載はされてはいるのですが、具体的に減薬すべきだ、などの提言は見つけられませんでした。
■ 国のマターではあるが医師の処方権があるため、それにかなり遠慮しているというのが日本の状況です。これは本来は国の所管ですが、市でも国保レセプトデータを分析することは可能です。該当する薬剤レセプトを抽出し、長期処方されている方を特定してレポート化する。医師に確認するなど、やりようはいくらでもあるでしょう。医師会・薬剤師会への協力を仰ぎ、服用患者数を減らすことで、薬剤誘発性認知症のリスクを減らすこともできます。
やれることは必ずあります。今後は、やる気と技術の両面から実施可能性を確認していきたいと思います。介入することで、少しでも要介護件数が減れば、使われる税金がそれだけ少なく済むのです。
今年度の決算認定の上、最後に意見をお伝えました。”ハンセン病の歴史を振り返りますと明治40年、1902年から患者の「隔離政策」が始まり、医師会・メディア・政府、すべてが賛同していました。一方、1960年にはWHOで「ハンセン病は適切な治療があれば隔離は不要」と明言され、欧米諸国では次々と隔離政策を廃止したのです。それでも日本は政策を転換せず、患者を「施設に閉じ込めたまま」にしました。日本が隔離政策をやめたのは1996年。他国に”変化”があるにもかかわらず、90年間も人権侵害を維持してきました。私が他国の状況を兼ね合いに出したのは、この歴史を振り返るとその意味を強く感じていただけるでしょう。だからこそ、市ができることもありますよと、提案もさせていただいたのです。”
最後までお読みいただき、ありがとうございました。素敵な1日でありますように。ご意見・ご感想はこちらまで↓[email protected]•━━━━━━• ∙ʚ🐤ɞ∙ •━━━━━━•各種SNSもフォローを宜しくお願いします。X(旧Twitter)FacebookインスタグラムLINEオープンチャット(ニックネームで参加可能)•━━━━━━• ∙ʚ🐤ɞ∙ •━━━━━━•



