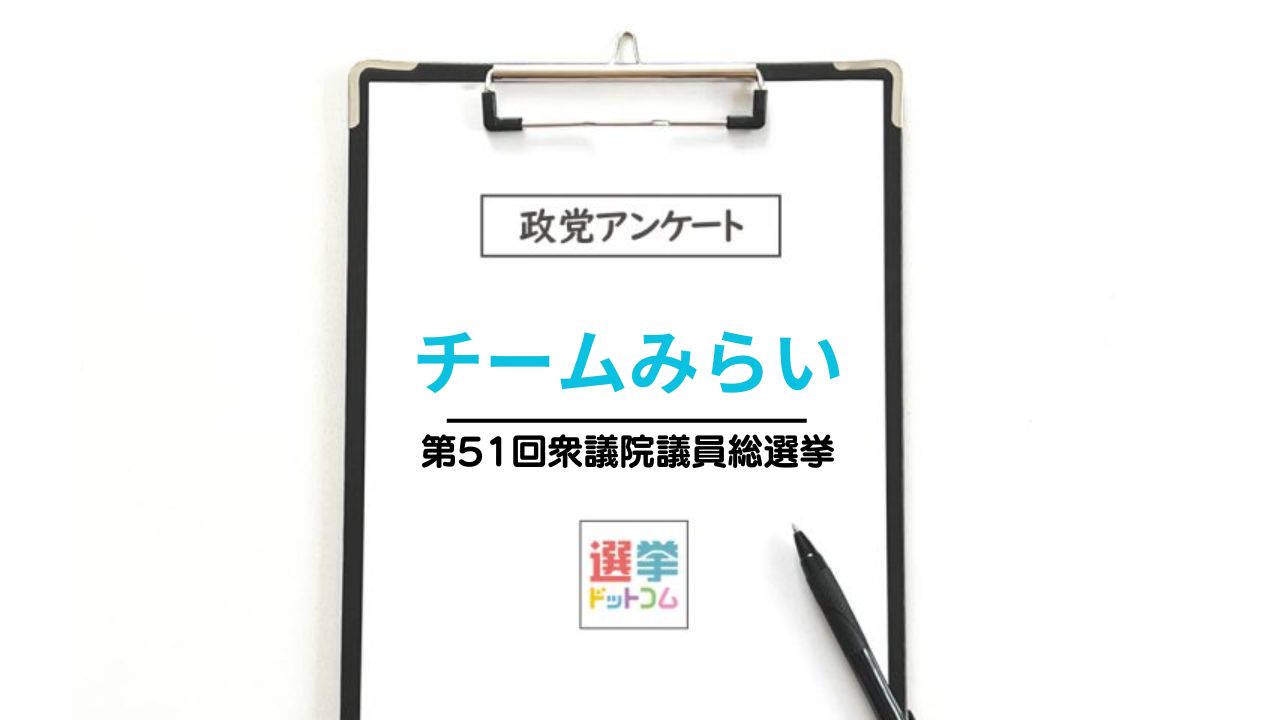「これから5年で倍増する」の衝撃…専門家が語るクマ被害「全国で8万頭&人間の味を学習」の悪夢(FRIDAYデジタル)|dメニューニュース

全国で「8万頭」…「5年前からわかっていました」
クマによる被害が止まらない。’23年のクマによる死亡件数は6件、’24年は3件だったが、今年は10月31日現在、クマによって犠牲になった人は12人と過去最多。環境省によると、今年度上半期(4〜9月)の全国のクマの出没件数は2万792件で、昨年度同時期の1万5832件を大幅に上回り、秋田県に自衛隊が支援に向かうことも決まった。
「こうなることは5年前からわかっていました。大変なことになりますよと、警告を出し続けていたんですけど……」
無念そうにこう言うのは、クマなどの野生動物の保全管理を研究している、兵庫県立大学の横山真弓教授。東北地方の場合、クマが人里に出没するのは、ブナの実が大凶作のためといわれる。しかし、横山教授はこう話す。
「ブナの実が凶作でエサがないというのは、秋だけのこと。けれど、4月からクマは出没し始めているんです」(横山真弓教授・以下同)
確かに環境省の調査によると、全国で4月775件、5月2461件、6月4142件と出没がブナの実の不足だけではないことを裏付けている。
「クマは桑の実やサクランボなど、いろいろなものを食べています。それらが少しでも凶作になると、人里に出てしまう事態になってしまいました」
東北森林管理局では平成元年から37年間、ブナの結実調査を行っている。それによると、7割の年が凶作か大凶作。計算上、5年に一度は凶作になっているのに、これほどクマが出没していない。
’23年にもクマの大量出没が話題になったが、何が原因で、こんなに出没しているのか。
「クマの生息数が増えているんです。環境省が発表した‛20年調査の『クマ類(ヒグマ・ツキノワグマ)の分布・生息状況』によると、北海道、秋田県、福島県、長野県、岐阜県には4000頭以上のクマが生息しているとなっています。私たちの研究で、クマは年間15%ぐらい増えることがわかってきました。何も捕獲せずにいると、5年間で倍になる計算になります」
4000頭以上いるという数値は、あくまで概算。クマが大量出没した’23年に秋田県では2000頭ほどを殺処分したが、
「今年は2年前よりも被害が大きいといわれています。ということは、2000頭以上増えていることが示唆される。そこから推定すると、秋田県だけで1万頭ほど生息している可能性があります」
’20年には7000頭以上、’23年には9000頭以上を全国で捕獲しているが、それでも増えていることを考えると、
「’20年の環境省の調査をみると、その段階で全国で5〜6万頭はいるのではないかと思われます。それなりの頭数を捕獲しているので、倍増はしていないと思いますが、5年後の現在は8万頭になっている可能性もある。そのぐらいの勢いで増えています」
クマは「人間の味」も学習してしまった…
「私たちの研究で、クマは年間15%ぐらい増えることがわかってきました。何も捕獲せずにいると、5年間で倍になる計算になります」と横山教授(PHOTO:横山真弓教授提供)人里に降りてきたクマの映像を見ると、親子連れの姿をよく見かける。
「山の中でも密度が高まればエサ場を争うことが起きていて、当然オスのほうが強いですから、親子が押し出されて人里へやって来る。人里へ来れば、田畑や果樹園が広がり、おいしい匂いが充満している。 しかも、人間はクマを見ると逃げてくれる。クマは非常に学習能力が高いといわれていて、『人間は怖くない』という学習が積み重なっている可能性があります」
学ぶのは「人間は怖くない」ということだけではない。10月11日には、宮城県でキノコ採りをしていた人がクマに襲われて亡くなるという事件があった。
「クマもキノコが好きなので、クマにしてみれば自分のエサ場に侵入者が来たということで、攻撃を仕掛けた。 ご遺体は、クマにとっては『肉』に変わってしまう。それによって『人間は食べ物』と学習してしまった。 また、10月16日には岩手県北上市で露天風呂を掃除していた人が襲われた事件がありましたが、おそらく『人間を獲物』と学習した可能性があり狙って襲ったのではないかと思います」
ほとんどの地域で増加傾向だ(環境省「クマ類の生息状況、被害状況等について」より)東日本では、クマの生息数を把握できていない!?
それにしても、なぜ、こんなにクマの生息数が増えてしまったのか。
「太平洋戦争前までは、燃料となる薪を取るために日本は禿山だらけの状態でした。同時に毛皮の需要も高かったので、野生動物は乱獲された。クマも絶滅危惧種に指定されるほどでした。 その後、狩猟規制を強化して、野生動物は数を回復させていきました。戦後はガスや電気が普及し、山の資源を使わなくなったので、1990年ごろには豊かな森林が回復して、動物たちも増えていきました」
しかし、九州では絶滅、四国も20頭以下と、西日本では’90年代まで絶滅の危機が深刻化した。’99年には「特定鳥獣保護管理計画」制度が始まり、西日本ではクマの保護に乗り出した。
集落に侵入したクマも殺処分せず、一度は麻酔で眠らせ、クマの年齢や栄養状態、繁殖状況などを調べて、マイクロチップを埋めて山に返した。また、イノシシ用の罠にかかったクマには唐辛子スプレーなどをかけて人間や人里を嫌いにさせて放獣する「学習放獣」を導入するなどして、できるだけ殺さない取り組みをしてきた。そうした取り組みの結果、西日本では正確な生息数を把握することができた。
保護政策をとった結果、100頭もいないのではないかといわれていた西日本のクマも、’10年には600頭に。このまま同じ方策をとっていると、どんどん増え続けてしまうということで、’12年には『学習放獣』をやめ、集落に一度でも来たら殺処分。’16年には狩猟も解禁した。
「’17年からは、集落から200m以内に来たクマを捕獲するという『ゾーニング捕獲』をスタートしました。環境省から800頭生息していたら絶滅の危機はないというガイドラインが出ていたので、700〜800頭に抑えるようにしています。 近畿地域でもドングリが大凶作だった昨年には大量出没が起きましたが、なんとか対処することができました」
一方、東日本はそれなりにクマがいたため、特別に管理することはしなかった。その結果、東日本には精度の高いデータが極めて少ない。たとえドングリなどが豊作であっても、里に行けば効率よくエサを得られると学習しているクマを放置すれば、季節に関係なく人里に出没するだろうと横山教授は言う。
どうすればいいのか。
「まず科学的な管理。クマの個体数を把握し、適正な個体数にコントロールするための司令塔となるような科学行政官を配置していかなければなりません。今は捕獲するのにも、クマに対する知識が少ないハンターさんたちにお願いしている状況で、非常に危険な状態です。不安の声も多数寄せられています。専門的な捕獲者の育成・配置も重要です」
なんだかとても時間がかかりそうだ。
「とりあえずは予防原則という形で、人の生活圏の近くにいるクマは、あらかじめ捕獲して、個体数を大幅に減らす取り組みが必要です」
人里に出てきたら、それだけで殺される。かわいそうな気もするが……。
「もちろん、かわいそうです。何度も殺す現場に立ち会ってきましたが、慣れることはありません。かわいそうだと思いながら、やっている。メンタル面でも大変な作業です。 現場の方たちには、そういう作業をやっていただいているということを理解しなくてはいけない。しかし、個体数管理をやらないと、次の凶作のときには、もっとひどいことになると思います」
これ以上増えたら、たとえ山の木の実が豊作でも、エサが足りなくなることも考えられる。人間と共生するためには、個体数を管理するのは必要なことなのだ。
▼横山真弓 兵庫県立大学 自然・環境科学研究所教授。兵庫県森林動物研究センター 研究部長を併任。ニホンジカ、ツキノワグマ、イノシシなど人との軋轢が深刻な野生動物の保全管理を研究。おもなテーマは、モニタリング手法の開発、個体数や個体の栄養状態のモニタリング、行政と連携した保護管理の実行。そのほか、GPS首輪による行動追跡、人獣共通感染症、ニホンジカの食資源化などにも取り組んでいる。
取材・文:中川いづみ