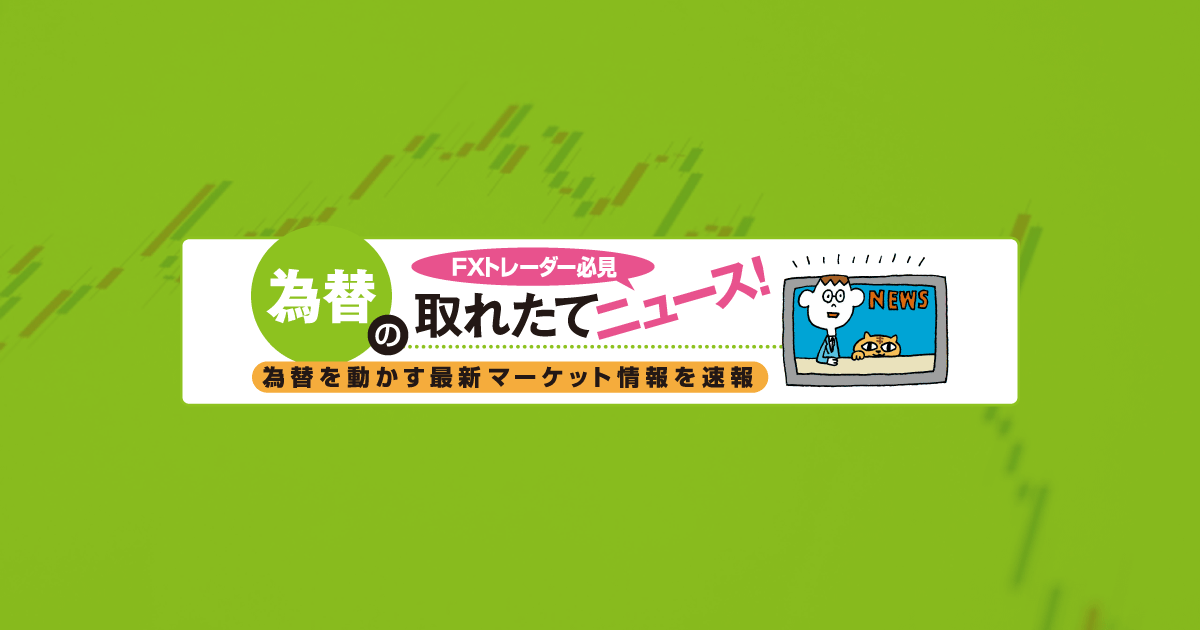トランプ流に「中国モデル」の影、企業に異例の介入-揺らぐ自由市場

トランプ米大統領が政府権限を全面的に行使し、企業活動に直接介入する構えを鮮明にしている。自身が掲げる経済・外交政策上の目標を達成することが狙いだ。
トランプ政権はエヌビディアとアドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)に中国向けの輸出を認める見返りとして、売上高の15%を米政府に納めさせるという仕組みを導入。前例なき措置に踏み切った。
直近では、米政府がインテルの株式の10%を取得し、同社の筆頭株主となる可能性も浮上。前月には、米国防総省が知名度の低いレアアース採掘会社MPマテリアルズの優先株4億ドル(約590億円)相当を取得することを決めた。
トランプ政権によるこうした一連の動きは、ウォール街およびワシントンの政策関係者の間で驚きをもって受け止められており、数十年にわたるキャリアの中でも目にしたことがない異例の措置との声が上がっている。
成功すれば、民間投資家や確定拠出型年金401kプラン加入者に恩恵が及び、安全保障の面で中国への優位性を一段と高める可能性がある。一方で、リスクの高い賭けでもあり、最終的に納税者に損失が発生し、市場を予測不可能な形で歪めることにもなりかねない。
ポートフォリオ・ウェルス・アドバイザーズのリー・マンソン最高投資責任者(CIO)は「単に海外に販売するのに米政府への支払いを大統領から命じられるセクターが次々と出てくるのではないかと懸念している」と指摘。「これが一体どこで終わるのか。中国市場に関与し、先端技術の知的財産を有する企業にどう投資すべきか全く分からない」と述べた。
企業への直接介入は、第2次トランプ政権を象徴する動きとなりつつある。
トランプ政権はこの他、日本製鉄による米鉄鋼大手USスチール買収を巡り、政府が「黄金株」を確保した。これにより、USスチールの決定に関して、トランプ氏が個人的に関与できる権限を得た。これらの事例はいずれも、政権が「勝者」と「敗者」を選別する構図を生み出しており、資本の自由な流れを損なうリスクがある。
中国モデル
米国の自由市場経済において、政府が企業の株式を取得することは通常ない。もっとも、例外はある。例えば2008-09年の世界的な金融危機時には、シティグループや、アメリカン・インターナショナル・グループ(AIG)、ゼネラル・モーターズ(GM)といった米主要企業を政府が支援した。
インテルは目下、業績が低迷しているものの、差し迫った経営破綻の危機にはない。
そのため、こうした直接介入政策に伴うリスクは何かとの問いに対して、投資家や議員、国家安全保障の専門家からは「不確実性」や「未踏の領域」といった表現が繰り返し聞かれた。
ピーターソン国際経済研究所のゲイリー・ハフバウアー上級研究員は「これは米国では見られなかった国家主導の政策であり、中国モデルが米政府内に浸透しつつあるようなものだ」と指摘する。
トランプ氏が進める企業への介入政策はある意味、1期目で展開した国家の経済ツールを進化したものとも言えそうだ。第1期には、長年使用されてこなかった貿易措置を引っ張りだし、通商法301条に基づく中国への追加関税を導入。通商拡大法232条に基づき、鉄鋼などへの追加関税も発動した。
これらの政策は市場に動揺をもたらし、支持を得たわけではなかったが、トランプ氏の支持者らの間では、中国などの外国製品が米市場に大量に流れ込むのを抑制したとして評価する声も出ていた。
トランプ氏は2期目においても、型破りの政策を進める構えだ。
カーネギー国際平和財団の米国家政策プログラムで客員研究員を務めるピーター・ハレル氏は「関税や輸出手数料、MPマテリアルズとの取引といった大きな経済問題について、トランプ氏は1期目にはなかったようなやり方で法的限界に挑む構えだ」と話した。
原題:Trump Targets America Inc. With New Brand of US Statecraft(抜粋)