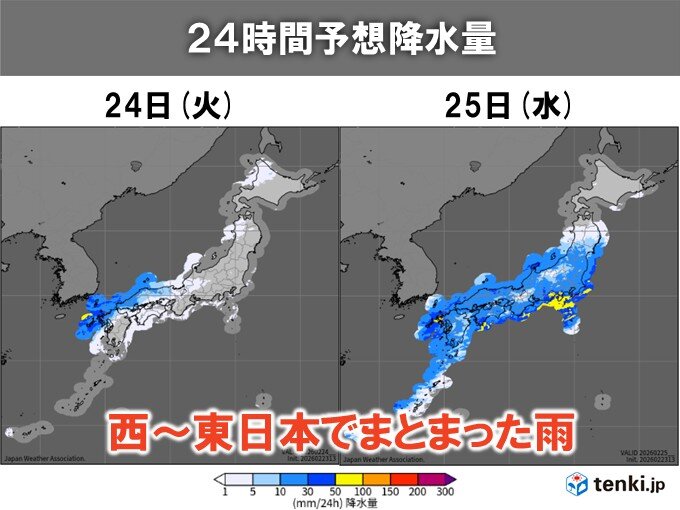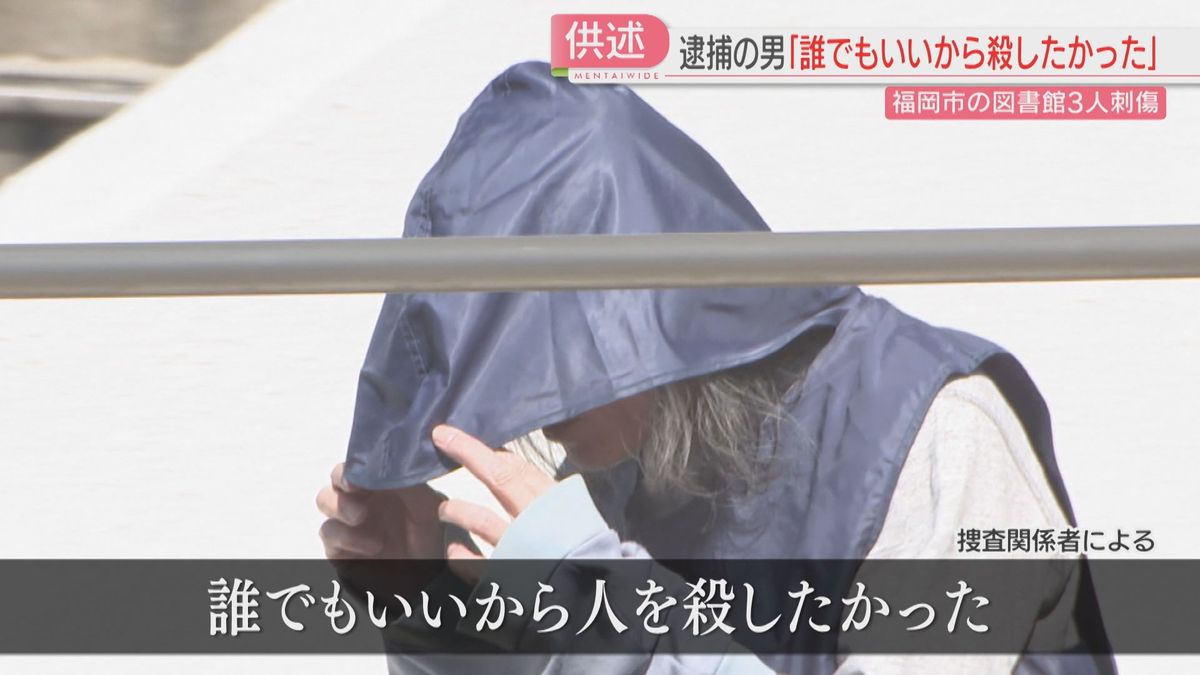コラム:「対米投資80兆円」の不平等=熊野英生氏
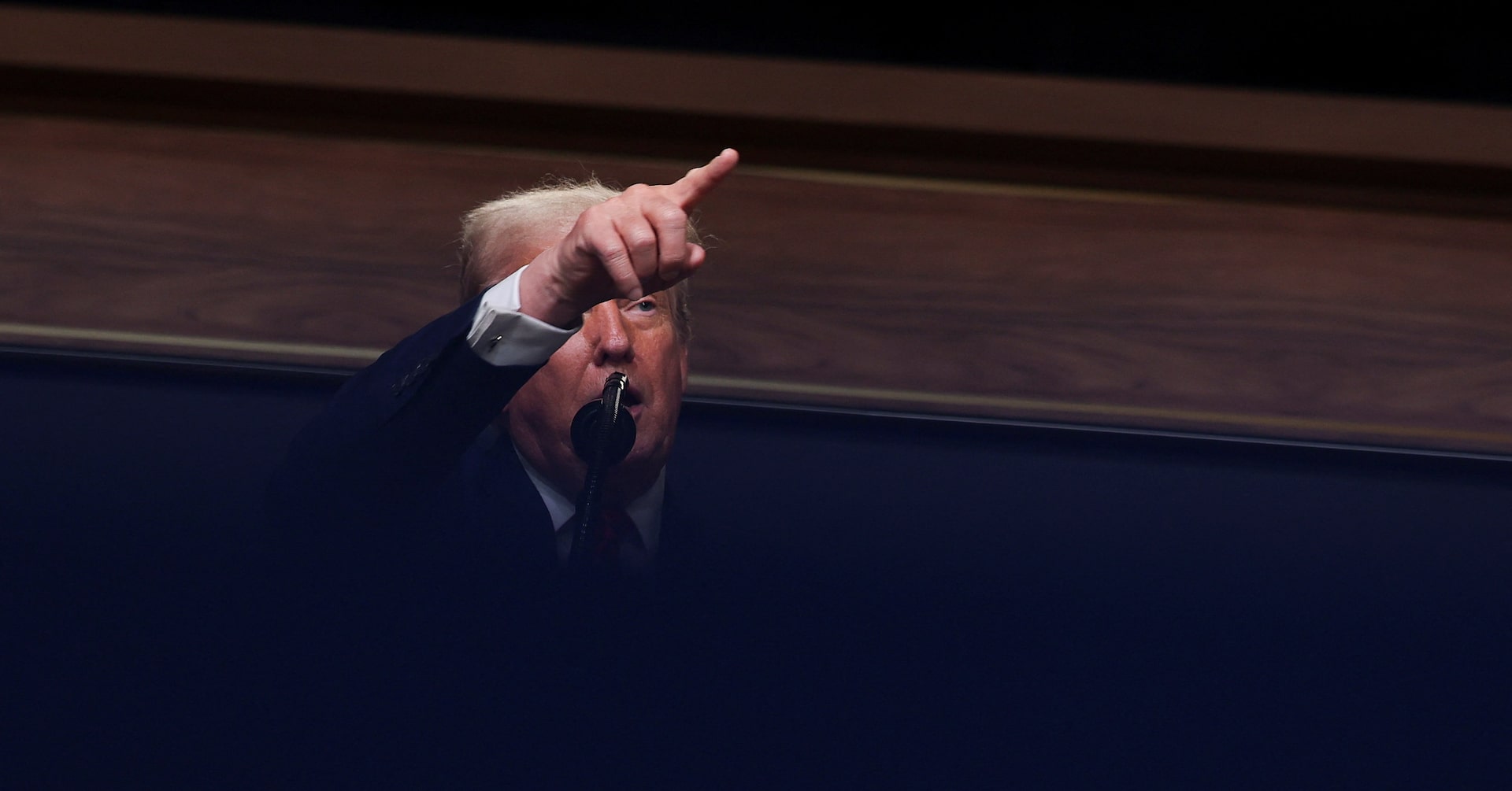
[東京 7日] - トランプ関税交渉が日本を含めて複数の国々との間で合意に達した。相互関税15%も甚だしく不平等であるが、その見返りとして差し出す5500億ドルの対米投資もまた不平等である。まだ、今はそれが約束だけでリアリティーのない計画だから腹を立てる人も少ないのだろう。赤沢亮正経済再生相によれば、合意文書もないそうだ。トランプ関税として要求された25%という数字を引き下げるために、対米投資額を事前に検討されていた4000億ドルから5500億ドルへと上積みしたらしい。欧州連合(EU)も韓国も相互関税率15%で決着しているが、やはり相応に吹っかけられて、対米投資の上積みに追い込まれたのだろうか。何とも後味の悪さが残る。
この5500億ドルは、1ドル145円で計算されて「80兆円の対米投資」と呼ばれている。すでにこの呼び方が使われているので、それを踏襲することにしよう。本稿ではその対米投資のリスクについて考えていくことにする。
<対米投資ファンドの狙い>
今思うとトランプ大統領の狙いは、関税率引き上げで各国を脅して、対米投資を集めてくることにあったとも考えられる。日本が5500億ドル、EUが6000億ドル、韓国が3500億ドルで、3カ国・地域合計1.5兆ドルにもなる。2026年11月の中間選挙では鬼の首でも取ったかのように「巨大投資を米国内に呼び込んだ」と誇示するつもりなのだろう。
米国の国内総生産(GDP)統計では、24年の固定資産投資(非住宅)は4.0兆ドルになる。3カ国・地域の1.5兆ドルがどれだけ大きいかがわかる。ラトニック商務長官によると、この投資は米政府が巨大投資ファンドを設立して、米政府の指示に基づいて各国企業が投資を実行するそうだ。
問題は、トランプ政権から指示された米地域に日本企業が進出して、高い採算性が得られるか不明である点だ。さびれた地域に進出させられて、高コストで労働者を雇えと強要されても、日本企業は自主的には進出しないだろう。たとえ手厚い税制優遇があったとしても、採算確保は難しいのではないか。
トランプ政権は、海外企業の投資を地域振興のように使うつもりだろうから、採算性などはほとんど考慮しないと筆者はみている。
国際分業の合理性を否定して、高関税で自国に呼び込んだ進出企業を儲けさせようとしても、それは所詮無理だろう。1980年代に先進各国が南米に投資した案件が不良債権化したという歴史的教訓を思い出す。日本政府や日本企業が80兆円を不良債権化させかねないプロジェクトに安易に乗るべきではない。
<80兆円はドル高圧力となるか>
ところで、この対米投資ファンドは為替にはどう作用するのだろうか。80兆円の投資がファンド形式になるという理解がなければ、その理屈は飲み込みにくい。この対米投資の計画が伝わった当初、トランプ氏の「利益の配分は米国と日本で9対1になる」という発言が広く知られるようになった。この9対1は、出資金の負担割合のことである。ファンドは出資金のほかに融資の部分がある。おそらく融資部分は9割くらいで、そこのファイナンスは日本の金融機関が行うのだろう。その融資には日本政府が債務保証をつけて、信用補完を行う。そうしたサポートがなければ、80兆円ものファイナンスを民間金融機関によって実行することは不可能だろう。
ポイントは、ドルで融資をするときに円売り・ドル買いと同じ取引の圧力が生じて、円安へと需給が動かされる可能性が高いことだ。円キャリー取引と同じようなことが起きると考えればわかりやすい。無論、一気に80兆円のファイナンスを行う訳ではなく、トランプ氏の大統領任期3年半をかけてじわじわと進むかたちになるだろう。
ここで問題なのは、円キャリー取引と違って、ポジションが巻き戻されて円高が急伸することがない点だ。むしろ、前述したように米国内で不良債権化すれば、それが円安圧力として作用する。
さらに対米投資が各国から行われて、それがドル高圧力を生み、その後、投資内容が不採算になると、各国通貨安の要因となってドル高傾向を持続させるという歪みになり得る。
<トランプ政策の欠陥>
今さら言うことではないが、トランプ氏の政策方針はよく練られた内容ではなく、国民感情に合わせて都合よく政策を後付けしたものだろう。いずれ様々な論理破綻を起こすに違いない。日本はトランプ政権と心中しないように距離を取るのが国益だと筆者は考えている。
例えば、高関税と対米投資で自動車産業を育成できるだろうか。米国の自動車市場は巨大であるが、供給能力を大きくしていくと、輸出拡大によってより規模の利益を追求した方が競争力を高められる。一方、ドル高が進むと、米国以外に輸出するのは不利になり、米国外からの輸入品によって脅威にさらされる。
保護主義は、自国産業の競争力を継続的に高めることには貢献せず、逆に非効率な産業を温存させることになる。
トランプ氏の頭の中では、中国の産業育成がイメージされているのだろう。半導体産業が必要とする初期投資を政府の支援で強力にサポートすれば、規模の利益が働いて、競争力を高められると思っているのだろう。その目的を果たすために、日本や欧州に対して防衛費・軍事費の増額を要求して、米国製の装備品やハイテク機器の購入を求めてくるのではないか。
しかし、外交・軍事面でより強く米国依存になることに強い不安を抱く国々が増えることで、米国産業とは一線を引いて取引を制限する動きも広がるのではないだろうか。
少し論点は違うが、トランプ氏の米国ファーストに対して、日本の参院選では日本ファーストを掲げる政党が躍進した。この躍進のすべてがトランプ氏によるとは考えないが、日本でも反米感情が高まっていく可能性は否定できない。そうなってしまうと、トランプ氏の指示に従う日本企業にも厳しい目が向けられかねない。しかもそうした反米感情は、日本だけでなく世界中で巻き起こる可能性があるだろう。
編集:宗えりか
*本コラムは、ロイター外国為替フォーラムに掲載されたものです。筆者の個人的見解に基づいて書かれています。
*熊野英生氏は、第一生命経済研究所の首席エコノミスト。1990年日本銀行入行。調査統計局、情報サービス局を経て、2000年7月退職。同年8月に第一生命経済研究所に入社。2011年4月より現職。
*このドキュメントにおけるニュース、取引価格、データ及びその他の情報などのコンテンツはあくまでも利用者の個人使用のみのためにコラムニストによって提供されているものであって、商用目的のために提供されているものではありません。このドキュメントの当コンテンツは、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、また当コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。当コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。このドキュメントの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。ロイターはコンテンツの信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、コラムニストによって提供されたいかなる見解又は意見は当該コラムニスト自身の見解や分析であって、ロイターの見解、分析ではありません。
私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」, opens new tab