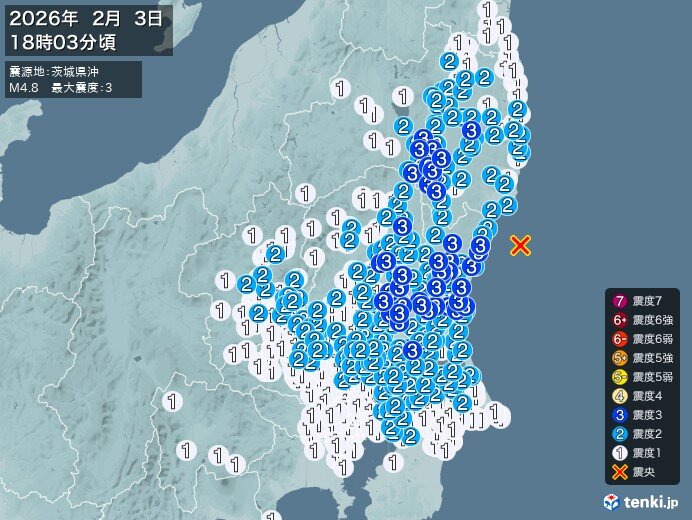千年に一度のレモン彗星が最接近 オリオン座流星群と奇跡の競演

2025年10月2日、ポルトガルのダークスカイ・アルケバ天文台で観測されたC/2025 A6(レモン彗星)。緑の光を放ちながら、地球に近づいていく。(PHOTOGRAPH BY MIGUEL CLARO)
[画像のクリックで拡大表示]
10月21日、レモン彗星「C/2025 A6」が地球に最接近する。今回の接近後、この彗星を見られるのは1000年以上先だ。
「彗星はごく普通に見られるものですが、今年地球から観測できる中で最も見ごたえがあるのは、間違いなくレモン彗星です」と、米アリゾナ州立大学隕石研究センター所長のロンダ・ストラウド氏は言う。
レモン彗星はどこから来るのか、夜空のどこを探せば見られるのか、いつまで見られるのかなど、この彗星について知っておきたいことを紹介する。
宇宙空間には何もないわけではない。われわれの太陽系の周辺には、氷や塵(ちり)の粒子が散りばめられており、それらは惑星、恒星、さらには銀河の間にも存在する。
氷や塵が太陽系に存在することを示す証拠が彗星や小惑星だ。それらは約46億年前、巨大で濃密なガスと塵の雲から太陽系が形成された際に残された残骸なのだ。
太陽が活動を開始したあと、残されたガスや塵は徐々に集まって塊を作り始めた。その熱から遠く、冷え切った外縁部では、彗星が形成された。氷の多い領域は、やがて「カイパーベルト」(海王星の軌道より外側で、冥王星をはじめとする太陽系外縁天体がある領域)や、さらに遠方の「オールトの雲」(太陽系のさらに周縁を取り囲む氷微惑星などがある領域)へと発展し、凍りついた無数の彗星の巨大な貯蔵庫となった。
「彗星は非常に研究しがいのある天体です。なぜなら、太陽系の原始的な構成要素がたっぷりと詰まっているからです」とストラウド氏は言う。「彗星が凍結状態にあるということは、そこに含まれる塵や氷の多くが、何十億年もの間ほとんど変化していないということなのです」
レモン彗星はひとつではない
1月3日に初めて姿を現したとき、レモン彗星の見た目はごく平凡で、ただ夜空に浮かぶぼんやりとした光の点でしかなかった。アリゾナ大学が運営する観測プロジェクト「カタリナ・スカイサーベイ」の責任者で、当日の観測を担当していたカーソン・フルス氏は、これはよくあることだと述べている。
「彗星は、"点灯"するまでは観測できないことがあります」と氏は言う。「点灯」とはつまり、彗星が太陽に十分に接近して氷がガスとなり、彗星特有の尾を形成するようになることだ。
フルス氏によると、今回の彗星は、これまでに70個ほど見つかっている「レモン彗星」のひとつだという。(参考記事:「パンスターズ彗星とレモン彗星、チリ」)
彗星の名称は、それを発見した天文台、あるいはその天体を最初に発見し、すぐにそれが彗星であると気付いた人の名前にちなんでつけられることが多い(レモン彗星はレモン山天文台で発見された)。フルス氏が発見したとき、今回の彗星はまだ「点灯」しておらず、尾を引く彗星というよりもむしろ小惑星のように見えたという。
「天文台の望遠鏡を稼働させていると、一晩の間に彗星がいくつか見えるのは珍しいことではありませんが、それでもやはり心が踊ります」とフルス氏は言う。