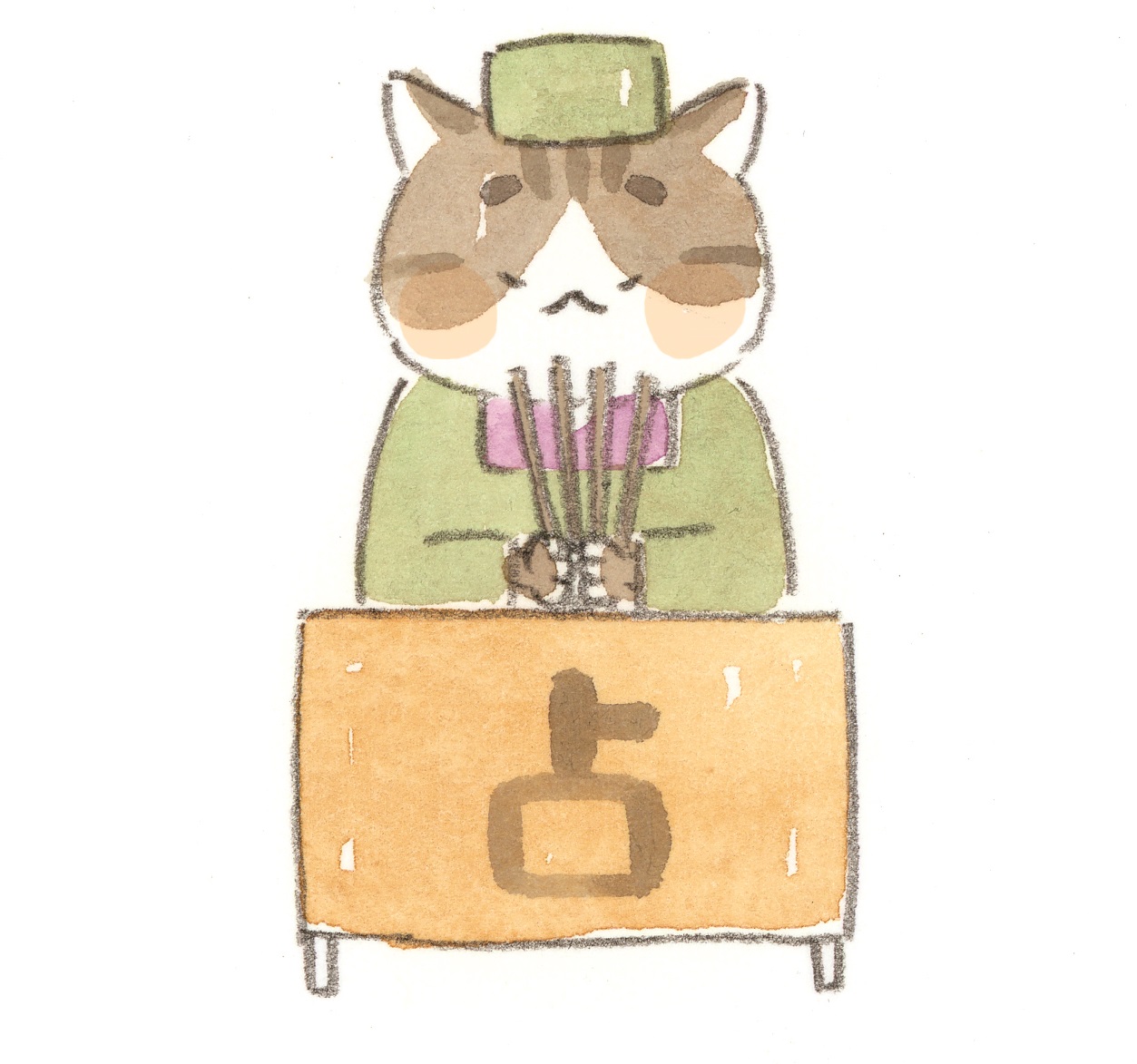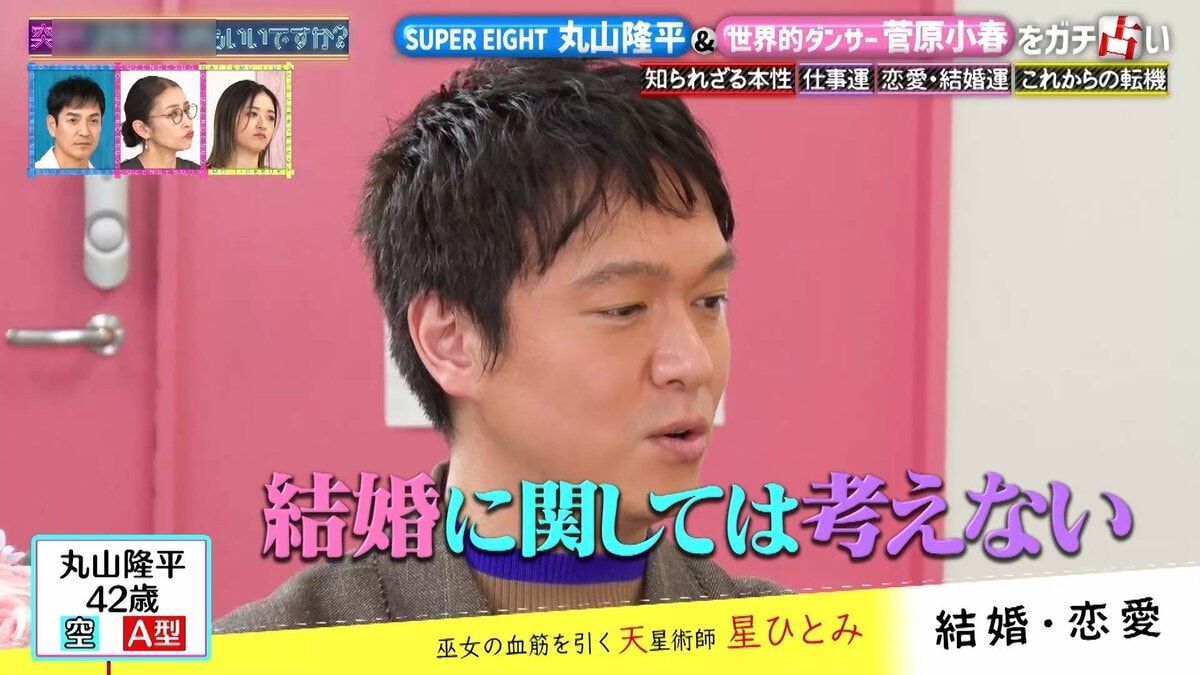METAL GEAR's METAL ARMS:『メタルギア』の銃器哲学【後編】
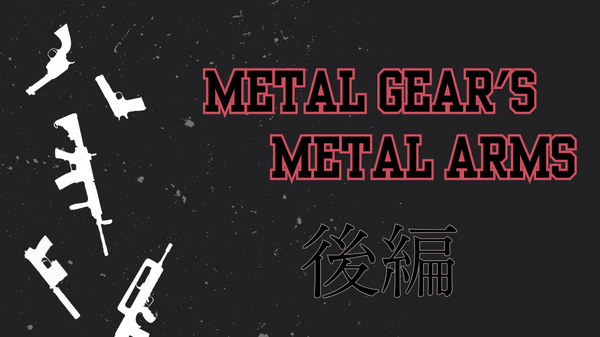
銃器哲学とは、筆者が提唱する「なぜその銃がそこにあるのか」「どのように演出されているのか」を問う試みです。本稿では『メタルギア』シリーズの本編作品に登場する銃器が、どのように演出・選出され、結果的にどのように「ただの道具」以上の存在として機能しているかを読み解いていきます。
「METAL GEAR's METAL ARMS:『メタルギア』の銃器哲学【前編】」はこちらから「METAL GEAR's METAL ARMS:『メタルギア』の銃器哲学【中編】」はこちらからはじめに:「象徴」から「業」へ――銃器で表現される最後の問い
本連載の前編では「信念の象徴」として機能する銃を、中編では「記憶の媒介」から「制度の象徴」へと変化する過程を追ってきました。しかし物語はそこで終わりません。
この後編で扱う『PEACE WALKER』以降のシリーズでは、「もはや国家に属さない兵士たち」が、銃を手に戦い続ける理由を問い続けます。そこでは、銃器は「絆」、そして人間の「業(カルマ)」へとその姿を変えていきます。
シリーズを通して問われ続けてきた「なぜ撃つのか」という問いは、ついにその最終的な帰結へと向かいます。連載全3回の最終回、後編では時代の変化とともに形を変えてきた“銃の意味”を辿りながら、メタルギアシリーズが最終的に描き出した「銃器哲学」の到達点を見ていきます。
『METAL GEAR SOLID : PEACE WALKER』の銃器哲学:無主の軍隊の象徴、組織と絆の媒体
「そこには、国も、思想も、イデオロギーもない。俺達は必要とされる土地へ赴き、俺達のために戦う。」
ーー BIG BOSS
『MGS4』にてソリッド・スネークの戦いは終わりましたが、メタルギア世界の歴史の空白はまだまだ残っていました。そこで2010年に携帯機のPSPで発売されたのが『METAL GEAR SOLID PEACE WALKER』(以下『PW』)です。
1974年の中米コスタリカ、冷戦の真っただ中にありながら軍隊を持たないこの平和な国を舞台に、10年前のスネークイーター作戦で世界を核戦争の危機から救い、ビッグ・ボスの称号を戴いたかつてのネイキッド・スネークはMSF(Militaires Sans Frontières、フランス語で「国境なき軍隊」の意)を築き、新型メタルギア「ピースウォーカー」をめぐる陰謀に立ち向かうこととなります。
『PW』において、銃器は個人の哲学や信念ではなく、「組織を形成するパーツ」として描かれます。それはまるで、兵士というパーツを結びつけ、秩序立てる媒体。すなわち「絆」としての銃器です。
プレイヤーはミッションごとに装備を選定し任務に出撃します。その中で、銃器の性能は単なる数字ではなく、「どの隊員にどの役割を与えるか」を決定づける情報となっていきます。ここで描かれる銃は、劇的な一丁ではなく、積み上げられた兵站と組織力の象徴であり、個人よりも共同体を語る存在です。
『PW』ではいわゆる開発ツリー形式により、ゲームの進行によって増加する組織としての資源・技術・人員を投入し、銃器を研究開発していく事となります。
初期装備のM16A1から始まり、開発に伴いサプレッサーの脱着が可能になり(開発ランク3)、急な接近戦に対処可能なアンダーマウントショットガンが装着されたり(開発ランク5)、途中に派生選択肢として、より特殊部隊向けなM16A1カービンであるM653の開発運用が可能となります。
開発ツリーとM16A1からの発展の様子、段階的にオプションが増え、派生型として画像一番下のカービン銃M653に派生する他の登場銃器も実に多岐にわたり、研究発展のベースガンとして狙撃銃は9種類が、LMGでは5種類が存在します。
そしてそのそれぞれが(割り切った架空兵器・超兵器の類を除いて)世界観に沿った、違和感を覚えない範囲でのリアリズムを確保してなおゲームに馴染んでおり、年代的に「登場すべき銃」のみならず「登場してもいい銃」という逆方向からのものまで含めたハイレベルな時代考証を感じさせます。
狙撃銃のSVD、シモノフ対戦車ライフル、ワルサーWA2000、WA2000は1974年当時まだ存在していないが違和感はないまた『PW』はシリーズで初めて「協力プレイ」を本格的に導入した作品でもあります。そこでは仲間と役割を分担し、互いに異なる銃器を手に戦場を進むスタイルが推奨されました。すなわち、銃器は「単独潜入の象徴」から「協調の表現」へと、役割そのものが変化したのです。
協力プレイを象徴する武器 最強合体兵器 人間パチン虎、それぞれが必要なパーツを武器として持ち込み発動させる方式で、ゲーム中最大威力を誇る敵勢力が展開するAI兵器群――特に「ピースウォーカー」は、核兵器の発射意思さえ人間から奪う機械であり、銃を「語る道具」ではなく「記録装置」に変えてしまう存在でした。
核抑止の失敗ーー人間が躊躇や葛藤により報復核を撃てないというリスクを排除するために開発された AI搭載自動報復歩行戦機 ピースウォーカーこの恐るべき兵器に抗う手段として、兵士たちは再び「人が人に銃を渡す」という原始的な営みに回帰していきます。
「銃が人を繋ぐ」という表現が、ここまで直接的に機能したメタルギア作品は他にありません。
『PW』は、「無主の軍隊」における銃器の意味を問うたある種の実験作でもあり、それはこの後の『MGSV:TPP』のシステム的土台になることになります。
『METAL GEAR SOLID V: GZ』&『METAL GEAR SOLID V: TPP』の銃器哲学 :支配構造を暴くためのレンズ、そして復讐の道具、そして業そのもの
「殺してください、ボス……助からないのなら、せめてあなたの手で……!殺してくれ ボス……殺せ!!」
ーーダイアモンド・ドッグズの一兵士
2014年と2015年にリリースされた、『MGS:V』の序章と位置づけられた『METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES』(以下『GZ』)と、本編として発売された『METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN』(以下『TPP』)は、スネークの「変質」と「幻肢」の物語を描きました。
1975年を舞台とする『GZ』にて、スネークたちMSFの面々が築いてきたものは崩壊し、9年後の1984年からの、MSFに代わる傭兵組織 ダイアモンド・ドッグズ での再起を描いた『TPP』へと連なる物語において、登場する銃器たちは、いよいよ「業(カルマ)」そのものとして表現されます。
『GZ』では、たった数時間の潜入の中に、銃が持つ抑止力・加害力・そして倫理的負荷が凝縮されています。夜のキューバ、悪名高きグァンタナモ米軍基地で銃声を響かせた時点で状況は破綻し、銃を構えることの責任が一瞬で降りかかってくる。この時、銃は「選択」の象徴であると同時に、「後戻りできなさ」を帯びた道具へと変貌します。
続く『TPP』では、戦場そのものが巨大な「暴力の市場」として描かれ、銃器は兵士と、当時勃興を始めた初期のPMCオペレーターとセットで価値を持った「商品」として存在し、奪い合われます。
『PW』でのシステムを踏襲・発展させたマザーベースでの開発システム、ミッションによる鹵獲と研究、各兵士の銃の扱い方――すべてが主人公(ビッグボス=ネイキッド・スネーク転じてパニッシュド・ヴェノム・スネーク)という「個人」ではなく、ダイアモンド・ドッグズという「組織」に集約されていく中で、銃は「復讐の道具」に留まらず、「支配構造そのものの鏡」として機能するのです。
パニッシュド・ヴェノム・スネークそして同時に、核兵器の開発・放棄をオンラインで管理するシステムが、武器を「人類の業」として突きつけてくる。
今作において、銃はこれまでの実銃の描写から一転、架空銃となりましたが、『TPP』ではそれを覆い隠すほどの極端なカスタマイズ機能により自由度を与えられています。
サイト、バレル、カラー、使用弾種まで、徹底的に「個人の嗜好」が反映できるのです。
基本装備の一つであるライフルのUN-ARCとカスタム例、この時点でフォアグリップ、ドットサイトとブースターのタンデムという高度なカスタムだが、まだまだ序の口と言える同じくUN-ARCだが、高度なガンスミス機能が解禁されてからのカスタム例、現代的伸縮ストックと、そして使用弾の変更によりマガジンが変更された姿しかしそれは同時に、「何を選ぶかは、何を背負うかでもある」という事実を如実に突きつけてきます。
穏やかさと清廉さを感じさせる白で塗った「復讐のためのショットガン」は凄惨な死体を作り出します。
赤と黒の、怒りを感じさせる迷彩を施した「非殺傷の麻酔拳銃」で基地を一つ無力化する事も出来ます。
そしてコスト節約重視、あるいは縛りプレイの一環として最低限の装備で出撃したとして、カスタマイズや塗装も施されていない、ある種「無垢」とさえ思えるライフルを敵からディスアーム(武装解除術)で奪い、そのままその敵も、その仲間も撃ちぬく非道に繋がる可能性があります。
言い換えれば、「選ばないこと」で「覚悟のない暴力になる可能性を選んでいる」とも言えるのです。すべては自由ではありますが、選択と結果からは逃れられない。
『TPP』での銃器ペイントメニュー、非殺傷モデルに一部バレル等の配色が設定されているが、その他制限はない『TPP』ではヴェノム・スネークの腕が義手(バイオニックアーム)となり、それを武器として使用するギミックが追加されます。この描写は、もはや銃を超えた暴力の人格化であり、「銃に囚われた者が銃すら超えてなお暴力に手を染める」悲しみと暴走の象徴です。
バイオニックアームの機能の一つスタンアーム、最大チャージで広範囲の攻撃判定を持つまた、リフレックスモード・マーキング・サプレッサーといった「便利機能」が揃っていながら、すべての選択が倫理性を突きつけてくるため、プレイヤーは「撃つべきか撃たざるべきか」を常に問い続けることになります。そしてこのゲームが描く「選択の重さ」は、銃器の造形や演出にも浸透しています。
『MGSV』に登場する銃器については、「醜い架空銃だ」という批判が根強くあります。 しかし、いちガンファンの筆者としては、「むしろそれでよかったのではないか」とすら考えています。
その理由は、そもそも『MGSV』における銃器の描かれ方が、英雄的でも美的でもないからです。仮に実銃が採用されていたとしても、期待されるような「魅力的な描写」がなされていたかは疑問です。
この作品において銃器は、「武器そのものに酔わせるような演出」がない中で「個性」や「美学」から遠ざけられており、プレイヤーの憧れの対象として描かれることを拒んでいるようにさえ見えます。
架空銃の採用は、昨今盛んに語られる権利の都合のみにその原因を求めるのがためらわれるほどに、「制度化された戦争において、兵器が個性や機能の一部を失う」という、MGSVの思想を体現する演出として機能しているのです。
作中の架空銃も決して設計として破綻しているわけではなく、むしろ元となった実銃やその設計思想の解釈は緻密で、アクセサリーの選定も現実に即したセンスが感じられます。
多くの作品が実銃を登場させながらも不自然なアクセサリーのデザインや組み合わせを描いてしまうのとは対照的に、『MGSV』の架空銃には「マイナーでメディア露出が殆どない実銃」のようなーーまさに確かなリアリティを備えているものが数多くあります。
ダイアモンド・ドッグズの標準拳銃的扱いでムービー等にも度々登場するAM D114、アメリカンよりもヨーロピアンな印象がやや強いが、114が45口径=11.4ミリを表すとすれば、実際にミリメートル表記を優先するヨーロッパ製という設定と考察する事も可能Sz.-336 SMG、モデル名とルックスから明らかにチェコ等のSMGを意識した銃。他の銃と共用のドットサイトは大型だが、時代設定に即したものFN FNCやベレッタAR70の要素を強く感じるアサルトライフルのAM-MRS-4、黎明期のドットサイト・テープ等で並列に固定されたマガジン・標準のピストルグリップを転用したフォアグリップの組み合わせは、パナマ侵攻時の米軍特殊部隊等で実際に見られたMosin-Nagant小銃を中心にWWII期の小銃の特徴を併せ持つ、狙撃銃のRENOV-ICKX SR。半分露出されたバレルはイギリスのエンフィールドライフルのスポーターモデルに近い特徴で、下の開発レベル5の姿などは「古い銃に現代改修キットを使って構成した姿」そのものにもかかわらず、それらが「格好良く」見えないのは、銃そのものの問題に尽きず、描かれ方にも理由があります。派手な演出や英雄的な象徴付けから切り離され、ただ戦場の道具として冷たく映し出されることで、銃は結果的に「格好いい」というその機能、その輝きを奪われているのです。
この作品での銃は、もはや「格好良さ」や「強さ」の記号ではありません。人や世界を分かりやすく救済したり、導いたりする存在ではありません。
それは、「幻肢」のような信念を求め続けた者が、自らの正しさを証明するためにすがる「業」の記号、そして「痛み」の形に他なりません。
総括:『メタルギア』の銃器哲学
以上、発売順にメタルギアのメインシリーズを振り返りつつ、その中で描かれた銃器の在り方――「銃器哲学」について考察してきました。
振り返れば、初期作品において銃器は「攻略のための道具」でした。
そこから『MGS』と『MGS2』で「信念の象徴」に、『MGS3』では「時代と人を語る存在」に進化し、やがて『MGS4』では「制度に囚われた自由」、『PW』では「無主の軍隊の絆」、そして『MGSV』では「支配構造と復讐の鏡像、そして業そのもの」へと深化していきました。
メタルギアというシリーズにおいて、銃器は常に変化し、問いかけ続けてきました。
「銃で何を語るのか。何を語らせるのか。」
ただの装備ではなく、キャラクターの人生、思想、歴史、社会、そして罪や覚悟までもを語らせる道具としてーー
この問いに真正面から向き合い、これほどまでに深く描いたシリーズは、他にありません。
「銃器で語る」とは、単に銃器の描写が詳細ということではありません。繰り返しになりますがそこには、銃を通して「何を語るか」「何を語らせるか」という姿勢が問われています。
結論として言えるのは、メタルギアの銃器哲学とは、「銃器を通して人間を描き、時代を映し出し、問いを残すという姿勢」と、それを支える「緻密な知識と体系的な思想」そのものです。
そしてこの全体像は、ガンアクションを愛する我々すべてにとっての原点であり、今後の基準であり続けるはずです。
銃器はこのシリーズの主役ではありません。しかし、その存在を通して描かれたのは、時に肯定され、時に否定されながらも、決して答えがひとつに収束しない「人間」という存在の複雑さそのものでした。
メタルギアは、その複雑さを銃器というレンズの一つを通して映し出し、最後まで答えを押し付けることなく、問いを託しました。
そしてその問いは、連載中に頂いた読者の皆様からの反響の数々をまさに好例として、いまも世界中で「メタルギアであの銃がさ……」といった形で、盛んで楽しい語り合いとして続いています。
おわりに
筆者である私は現在31歳ですが、私の世代では銃器趣味の人に「なぜ銃にはまったの?」ときっかけを質問すると「『メタルギア』でかっこよく描かれていたから」という答えがある種お決まりです。
この「質問」と「答え」のやりとりが、新たな世代によって繰り返されるようになるかもしれない出来事がもうすぐ訪れます。
2025年8月28日、本連載でも特に大きく触れた『MGS3』のリメイク作品である『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』が発売されます。
あの日に触れ、興奮し、恐れ、そして銃を撃つこと・暴力をふるう事に恐ろしさと罪悪感を覚え、しかしなおも夢中になったゲーム体験が帰ってきます。
長らく新作が出てなかった事もあり、もはや忘れ去られるのみかと絶望されていた伝説のシリーズに、これからのビデオゲーム、そして銃器趣味を一緒に支えてくれる若い方々が触れる機会ができた事がとても喜ばしいです。
拙文となりましたが、当記事が皆さんが『メタルギア』というシリーズへの関心を新たに持つ、あるいは蘇らせるきっかけになったら、これ以上に嬉しい事はありません。ここまでお読みいただきありがとうございました。
『MGS4』での印象的な台詞、「日はまた昇る」という一言を思い出しながら、今連載の締めにしようと思います。
それではまたの機会に、ミリタリーコンテンツクリエイターグループ ミリドー!代表、フユトでした。