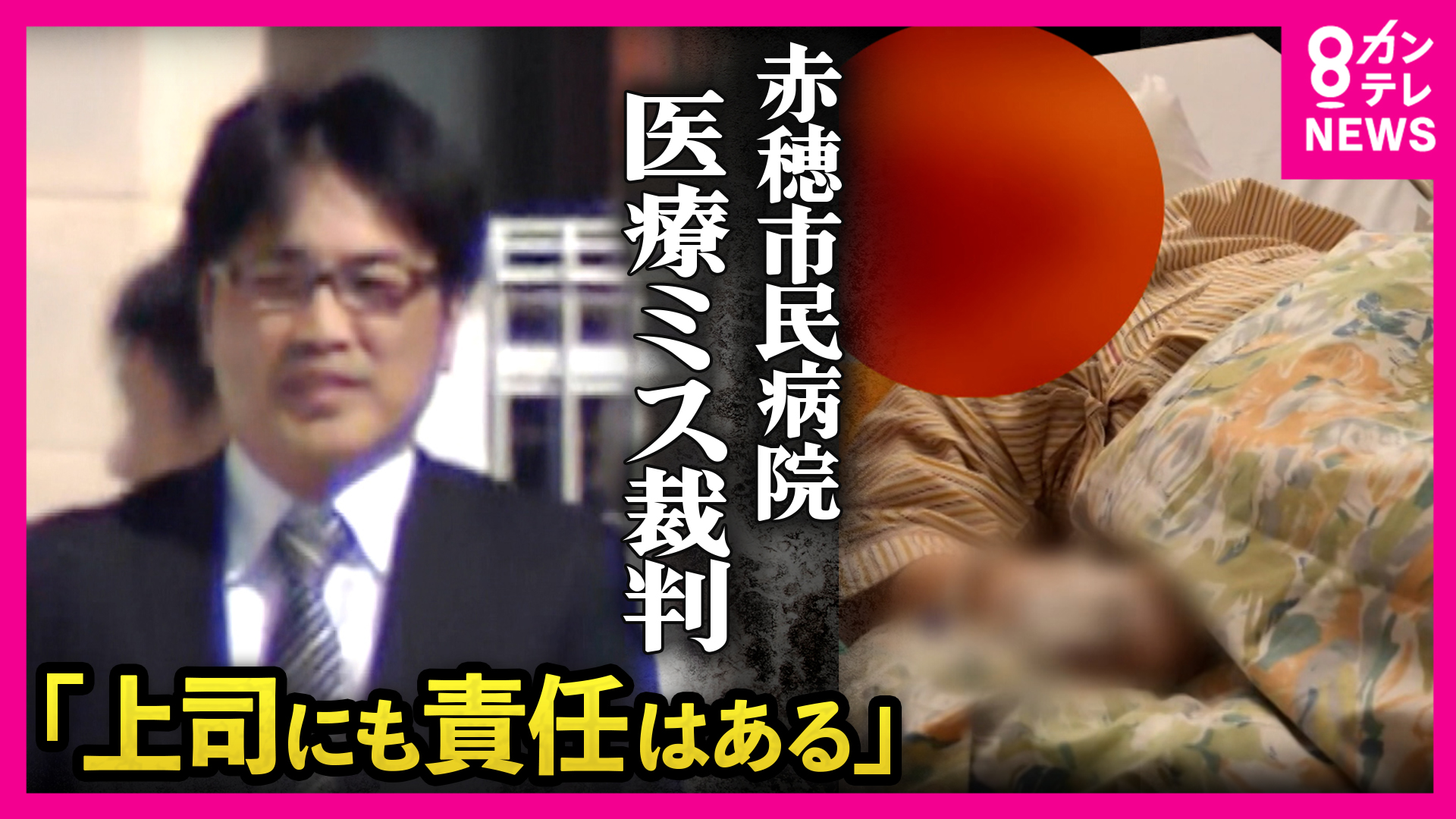給食無償化「しない」という選択 鹿児島県東串良町 元酪農家町長が語る1000円「いただく」真意とは

明治中期の創立時に植栽されたけやきが、133年後の今もグラウンドの中央にそびえ立つ町立池之原小学校。4時限目の終了を告げるチャイムに「けやきっ子」と呼ばれる全校児童273人の浮きたつ声が重なった。給食の時間だ。 町は8月末、総事業費15億8433万円を投じ、新しい給食センターを落成した。以前から給食米は町内産だが、炊飯は町外の業者に委託していた。悲願の自前炊飯でホカホカご飯を提供できるようになり、子どもたちも大喜び。「ご飯がうんまか!」。好きな献立を尋ねた記者に6年い組の男子が言った。 大隅半島の平野部にあり、米、野菜、畜産、漁業など1次産業が盛んな町。一般会計当初予算は70億円前後だが、センター建設に伴う財政出動が無償化しない理由でもない。 発端は2016年2月の町長選。現職を破って初当選した宮原順町長(75)は当時、65歳の現役酪農家だった。公約の子育て支援として、給食費の半額を助成。先駆的な取り組みとして注目を集めたが、無償にまでする考えはなかった。 3期目当選後の24年1学期から、物価高に対応するため給食費を700円値上げした。一方で保護者負担をそれまでの2000円から1000円に減額し、残りを町が負担する予算案を決めた。折しも政府の無償計画が浮上し、他の自治体も無償化に乗り出した頃。議会は「なぜ無償にしないのか」と問うた。 「いただきますの心を育むため」――。答弁台に立った宮原町長は1000円の真意を語り始めた。
宮原町長に1000円の真意を聞いた。 例えば、子どもたちが大好きなお肉。唐揚げになる鶏は、ふ化して50日後、豚は生まれて半年後、牛は2年2カ月後に食肉処理され、人の食べ物になる。米も4、5カ月、農家が朝晩水管理や除草など手間暇かけて育てる。野菜や果物も同様だ。 町長になり、命の尊さと農業の大切さを給食を通して訴えようと思った。「いただきます」の感謝の気持ちを伝えたいと思った。 給食費を一部でも払うことで、そうしたことに興味を抱き、知ってもらえると考えた。当初は2000円、物価高が顕著になった昨年から1000円は払ってくださいとお願いしている理由だ。 保護者も、払うことで意見を言う気持ちになる。私たちも、聞く耳を持たなければとなる。無償化したからできなくなるわけではないが、互いのコミュニケーションをつなぐ役割もあると思う。 19歳から69歳まで酪農業を続けた。ホルスタイン70頭を飼育していたが、牛は健康維持が大変で、乳頭の状態には細心の注意が必要だった。管理を怠ったり、失敗したりすると、命に直結する。 ある時、牛の乳房内を見る機会があった。周囲に毛細血管がびっしりと張り巡らされていて、赤い血液からカルシウムやビタミンなどがにじみ出て真っ白な牛乳になることを目の当たりにした。 乳頭をマッサージしたり、お湯で拭いたりするのは、子牛が飲みたがっていると母牛に錯覚させ、牛乳を作り出してもらう目的もある。文字通り、命を分けていただいている。1000円を「いただく」ことで、「いただきます」の意味を考えてもらえると思う。 酪農家だった50年間は「卵と牛乳は値段が上がらない」時代だった。日本は今も飼料のほとんどを輸入に頼っていて、燃料もそうだが、価格は国際情勢に左右されがち。売り上げの7割は経費で消える。就農時に町内に39軒いた酪農家は今、4軒にまで減った。 国が本当に給食費を無償にするならば、一つお願いがある。 東串良町も給食の地産地消を進めてきた。特に米は100%町内産で、耕作放棄地を集めて規模を拡大した農家が提供している。こうした地方の努力を守り、発展させる仕組みが必要だ。「いただきます」の後景にある1次産業も忘れないでもらいたい。
「給食無償化」と言っても、地域によって考え方の相違があり、それぞれの事情がある。学校給食を学校設置者の自治体などに義務付けた学校給食法(1954年施行)により、地方は創意工夫を重ねてきた。それだけに、半年や1年で納得いく制度を作れるとは思えない。「タダにすれば良い」では子どもたちも愚弄(ぐろう)する。学校給食を通じて何を実現するか。期待されているのは国家の哲学だ。 (栗田慎一)
日本農業新聞