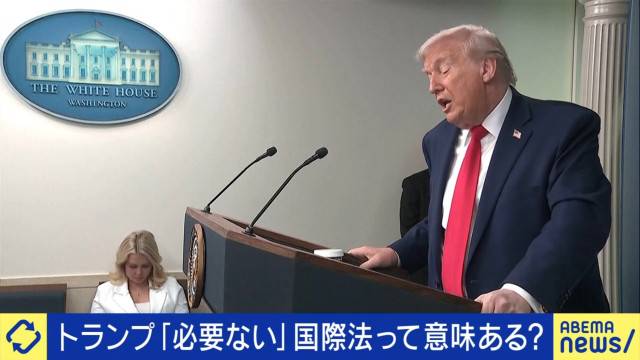佐渡島の岩海苔を摘んで伴海苔(板海苔)を作る食文化を体験した (1

今回の舞台は佐渡島の一番西南、小木半島にある沢崎という小さな集落。
岩海苔は全国の海で食べられている食材であり、地方によって、地域によって、集落によって、その食文化はグラデーションのように変わっていくもの。
よってこの話は、あくまで沢崎の場合として、お読みいただきたい。
佐渡島のお土産の定番である岩海苔。これの現場を見てみたかった。 冬になると、島内のスーパーにも生の岩海苔が出回る。「旅先のスーパーで買い物して、自炊する日々に憧れて」より。私が沢崎を訪れたのは二月の中旬。案内をしてくれたのは、沢崎集落に住む「伴海苔(ばんのり)同好会」の高野さん、山本さん、寺尾さんのお三方。
入り江を跨ぐ橋の上から撮影した沢崎集落。訪れたのはいいけれど、「今日は風が凄いでしょ。危ないから、やめておいたほうがいいんじゃない」と、全員がまったく乗り気ではなかった。
もちろん天気が悪いことはわかっていたので、まあそうですよねと思いつつも、せっかくここまで来たのだからと岩海苔を摘む場所まで案内してもらった。せめて現場を見てから諦めたい。
「ダメだと思うけどなー」といいつつも先導してくれる伴海苔同好会の三人。今はトンネルができたからすぐだけど、昔はこの山を越えて岩海苔を採りに行ったんだという話を聞きつつ(二つ上の集落の写真参照)、目的地へと到着。
ところで岩海苔はサザエやアワビと同様に漁業権が設定されており、集落ごとのルールで守られているため、その許可を持つもの以外は採ることができないのだが、今回は取材として特別に同行させていただいている。ライターをやっていてよかったなと心から思える大事な時間だ。
岩海苔も漁業権の対象なので、許可なく採取することは禁じられている。ザパーン。
「あそこにコンクリートを流して作った平らな海苔畑があるんだけど、波をかぶっちゃっているからダメだな」
ザパーン。
海苔畑ってなんですか。遠くの波打ち際に、まるで駐車場のような平らな場所が見えた。あれが海苔畑なのだそうだ。
そもそもは自然の岩に自生するものを収穫していたのだが、岩海苔が育ちやすく、そして収穫しやすい場所として、こうして人工的なスペースを用意するようになったのだという。
これか。佐渡にはいくつかこういう海苔畑があるそうで、岩海苔という言葉と収穫する場所のイメージが違っておもしろい。ギャップ萌え。
それにしても波がすごい。この海岸が北西を向いていて、思いっきり北西の風なので仕方がないのだが。
昔ながらの岩海苔摘みを体験する
私が悔しそうに海を眺めていたら、風裏となる磯にいけば少しは採れるかもと教えていただいた。
ぜひお願いしますと即答し、来た道を戻って案内してもらう。
ぐるっと回って岬の反対側まで来た。こちらにはコンクリートの海苔畑はなく、自然のままの岩場が広がっており、その波打ち際にモサモサと短い赤茶色の海藻が生い茂っていた。
どうやらこれが岩海苔のようだ。
海苔畑を訪れることができなかったのは残念だが、こうして昔ながらの海苔摘みができるのも貴重な体験。風裏の場所とはいえ二月の佐渡なのでまあまあ寒かったが、せっかくなので素手で岩海苔に触れて、ありがたく摘ませていただく。
岩海苔はしっかりと岩に根付いているので(根はないけれど)、これはなかなかの重労働。ゴツゴツした岩肌からはぎとらないといけいないので(この作業を「へぐ」と呼ぶ)、指紋が削れてなくなりそうだ。
これを仕事にするのであれば、磯にコンクリートを流して平らな場所を作りたくなる気持ちがよくわかった。
これは大変な仕事だ。ちなみに岩海苔はスサビノリやウップルイノリなど、磯に生えるノリ類の総称であり、場所によって微妙にその種類や割合が違う。イワノリという海藻がある訳ではない。
こういう知識はちょっと調べれば簡単にわかるものだけれど、この場で聞いた以下の話は、どこにも載っていないものだろう。
岩海苔を採るのは年末年始ぐらいから一月一杯くらいまで。今の時期(二月中旬)でも採れなくはないが、海苔が固くなってくるし、色も抜けてくる。
沢崎集落で岩海苔を採っているのは30人くらい。順番で回ってくる当番というものがあり、その人が海苔の育ち具合や凪(海の様子)をみて、その年の解禁日と時間を決めて各家に伝達する。勤め人も多いので、なるべく土日が好ましい。抜け駆け厳禁。
二回目以降に採る日も当番が決めて、何回か採ったらみんなの了解を得た上で「口開け」をする。口が開けたら(権利を持つ人であれば)自由にとってよくなる。今シーズンは例年になく岩海苔の育ちがよかったこともあり、二回目を採ったらすぐに口が開けた。
最高に貴重な時間なのです。今シーズンは1月5日が解禁日で、その日に採れた海苔を一番海苔と呼び、もっとも価値が高い。ただ岩海苔がしっかり成長して歯ごたえと風味が強くなる二番海苔や三番海苔を好む人もいる。
摘んだ岩海苔を洗ってそのまま干したものを「島へぎ」や「ひのり」と呼び、板状にしたものは「伴海苔(ばんのり)」。沢崎での伴海苔の生産はおそらく明治のはじめ頃からで、40~50年前までは貴重な収入源として集落のみんなが作っていたが、かなり手間がかかるので今も沢崎で作っているのは同好会の6人だけ。
これは60年くらい前の話だが、その頃はまだ貴重だった手袋が使用禁止だった。持っている人だけがたくさん採れるから。ゴム長ではなく藁草履の時代で、岩海苔は寒さを我慢をした人のものだった。次第に指サックが解禁になり、手袋もよくなり、現在に至る。
などなど。
伴海苔の作り方を習った
貴重な岩海苔摘み体験に続いて、伴海苔の作り方も同好会の皆様に一から十まで丁寧に教えてもらった。
「昔は冷凍庫なんてなかったから、採ったその日に干さないといけなかった。だから一日で千枚作ることもありましたが、今は30~40枚くらい。
若い人はやりませんね。我々みたいに定年退職をして、時間に余裕があるから作れる。伴海苔は趣味ですよ。勤めに出ている人には手間がかかりすぎる。
岩海苔は砂が歯にあたるとイラっとします。だから私は島へぎよりも、完全に砂が抜ける伴海苔が好きです」
集落にある沢崎開発センターのキッチンにて。私はまったくの部外者ではあるのだが、次世代の引き継ぐ人が現れることを願いつつ、理解できた範囲で工程とその歴史を記録させていただく。
Page 2
まずは岩海苔を刻んで、徹底的に砂を落とす。
砂のある海苔というものは、砂出しの甘いアサリよりもイラっとするらしい。
私が摘んできた岩海苔を触り、「これは砂がすごいな」と笑う伴海苔同好会の会長。 今日採ってきた岩海苔はジャリジャリだし量も少ないので、冷凍してあった貴重な一番海苔を解凍してもらった。 「今年の一番海苔は成長がよかったから、鷲掴みで簡単にとれた」と長い岩海苔を見せてくれた。 日本の包丁でタカタカタカタカタカンとリズミカルに岩海苔を叩く。ちょっとフラメンコっぽかった。 下が開いている仕切りを入れたたらいに岩海苔を流して泳がせ、苦味になる塩分と砂を洗い落とす。砂金取りの逆の発想だ。大昔はたらいで洗うだけだったが、井戸にポンプが設置されてからはこの方法とのこと。②板状にする
二つの枠と海苔簾(のりず)を使って、刻んだ岩海苔を板状(伴)にする。
昔は夫婦で作業を分担し、父親が海苔を刻み、母親が板状にする流れ作業で作ったそうだ。
沢崎の伴海苔は21×19センチ(一般的な板海苔は21×18センチ)と決まっている。 枠もそうだが海苔簾も手作りで、ススキの芯を集めて作ったもの。一日に千枚の板海苔を作ったということは、この簾が千枚あったということだ。今も作れる人はいるのだろうか。 容器に水を張って、簾を挟んだ枠を左手で抑えて底につけて(簾が1センチくらい沈むように)、岩海苔を軽く一つかみ乗せる。 枠の中に満遍なく広げる。昔は底につけるのでなく、水面に浮かせた状態でやったそうだ。安定しないので水平を保つのが難しいだろうけど、慣れるとそのほうが早いのだろう。しかも簾を5枚くらい重ねていたのだとか。 枠を浮かせると板状になった海苔が現れるので、そっと枠を外す。 枠から簾を持ち上げて、慎重に立てかけて水を切る。この作業をやらせてもらったのだが、見ての通り簡単ではなかった。薄いところと厚いところができたり、どうしても四隅のひとつが欠けてしまったり、なかなかきれいな板状にはなってくれない。
「紙漉きと同じ要領ですが、こればっかりは経験です。薄くすれば穴が開くし、厚くすると噛み切れない。均一にするのは何年やっても難しい。うまくできたと思っても、乾燥すると余計にムラが目立つんですよ」
時間とグラムさえ計れば失敗しないタイプの料理とは根本が違う難しさ。その土地で生まれ育った人(あるいは移住した人)にだけ許される、最高の趣味だなと思った。
③海苔を干す
海苔簾を竹竿に刺していき、ある程度溜まったら乾燥させる場所へと運ぶ。
干す工程にもノウハウがたくさんあった。
ある程度まで水が切れると、ぶら下げても剥がれない。 冬は風が強い日も多いので、屋外ではなく屋内に干し、ストーブを焚きながら丸二日ほどかけてしっかり乾かす。 そのままだと海苔が丸まるので、突っ張り棒と呼んでいる竹串を挟んで伸ばすという人類の英知。 一つ一つの行程に長年に渡って培われてきたノウハウが存在していた。 黒々と干しあがった伴海苔。最終チェックをする
干しあがったらできあがり、ではなく、極力砂が残らないようにするための最終チェックを怠らない。
砂への対抗心がすごい。絶対にジャリっと言わせてたくないのだろうが、ここまでやっても残ってしまうこともあるのだとか。完全手作りの厚い海苔だからこその苦悩。
海苔のほうを抑えて、優しく簾をはがしていく。 鐵の板とローラーでゴリゴリ。これによって海苔を伸ばしつつ、感触で砂を発見する。手で触ってもわからない砂が、この方法だとわかるそうだ。 ようやく伴海苔の出来上がり。こうして手間暇かけて作った沢崎産の伴海苔は、基本的には販売をしていないものの(趣味だから)、その一部を佐渡市のふるさと納税の返礼品用として納品しているそうだ。
集落によっては直売所などで販売しているところもあるようだが、今後は後継者不足によってさらに貴重になっていくのかもしれない。
味見をさせてもらった
伴海苔は焼き海苔ではなく乾海苔なので、このまま食べるのではなく、サッと加熱してこそ本領を発揮する。
部屋を暖めていた灯油ストーブの上で、漆黒だった色が鮮やかな深緑になるまで炙ったものをいただくと、バリっとした歯ごたえと確かな磯の風味が堪らない。醤油をちょっと垂らすともう最高。
育つ環境、摘む大変さ、加工の難しさを知ることができたからこそ、その思い入れがさらに味を膨らませる。
焦がさないようにサッと炙る。「酒のつまみにいいんですよ。これは作った人だけの特権の味。
厚すぎるから海苔巻きには向かないけれど、お餅を巻いたり、おにぎりやのり弁にしたら抜群じゃないですか。ラーメンとか蕎麦みたいな麺類にもよく合います」
鮮やかな深緑色になった。これをつまみに佐渡の地酒を飲んだら、そりゃ堪らないでしょうよ。岩海苔でうどんを作った
ここからは余談。岩海苔のお礼という訳でもないのだが、摘んできた生の岩海苔とこの伴海苔を使ったうどんを作らせてもらった。
持参した家庭用製麺機をさりげなく取り出すと、「懐かしいなあ、これ子どもの頃に使っていたわ。作ったのは蕎麦だったと思うけど」と、予想外の反応が返ってきて驚く。
まさか沢崎にも家庭用製麺機を使った製麺文化があったとは。この話を深掘りしたいところだが、今日のところはとりあえず我慢だ。
「これは生地を伸ばして切るやつだろ」という、珍しがるのではなく懐かしがる反応でびっくり。 私が採ってきた岩海苔の砂を丁寧に洗い流し、つゆで軽く煮る。出汁はアゴ(トビウオ)が貴重品になってしまったのでアジの焼き干しを使用。 佐渡産の小麦粉をブレンドしたうどんを茹でて、岩海苔たっぷりのつゆに入れる。さらに炙った伴海苔も乗せて、「のりのり岩海苔うどん」の完成だ。 こうして一緒にうどんを食べられたことが、なんだかすごくうれしかった。繊維が長いままの生岩海苔を煮たものと、伴海苔にして炙ったものでは、同じ岩海苔でも食感と風味がまったく違う。その両方が楽しめるのだから、海苔好きには堪らない一杯となった。
「うまいな。コシのあるうどんに岩海苔がよく合っている。でも一つ言わせてもらうと、ちょっと石の取り方が甘かったな!」
編集部からのみどころを読む
編集部からのみどころ 60年前は手袋が使用禁止だったって話がおもしろいですよね。持ってる人と持ってない人の不公平があるから。
道具が普及するときのちょっとした決め事から当時の様子が想像できます。こういう記録に残らない営み、チョー大事です。(林)
Page 3
今回の舞台は佐渡島の一番西南、小木半島にある沢崎という小さな集落。
岩海苔は全国の海で食べられている食材であり、地方によって、地域によって、集落によって、その食文化はグラデーションのように変わっていくもの。
よってこの話は、あくまで沢崎の場合として、お読みいただきたい。
佐渡島のお土産の定番である岩海苔。これの現場を見てみたかった。 冬になると、島内のスーパーにも生の岩海苔が出回る。「旅先のスーパーで買い物して、自炊する日々に憧れて」より。私が沢崎を訪れたのは二月の中旬。案内をしてくれたのは、沢崎集落に住む「伴海苔(ばんのり)同好会」の高野さん、山本さん、寺尾さんのお三方。
入り江を跨ぐ橋の上から撮影した沢崎集落。訪れたのはいいけれど、「今日は風が凄いでしょ。危ないから、やめておいたほうがいいんじゃない」と、全員がまったく乗り気ではなかった。
もちろん天気が悪いことはわかっていたので、まあそうですよねと思いつつも、せっかくここまで来たのだからと岩海苔を摘む場所まで案内してもらった。せめて現場を見てから諦めたい。
「ダメだと思うけどなー」といいつつも先導してくれる伴海苔同好会の三人。今はトンネルができたからすぐだけど、昔はこの山を越えて岩海苔を採りに行ったんだという話を聞きつつ(二つ上の集落の写真参照)、目的地へと到着。
ところで岩海苔はサザエやアワビと同様に漁業権が設定されており、集落ごとのルールで守られているため、その許可を持つもの以外は採ることができないのだが、今回は取材として特別に同行させていただいている。ライターをやっていてよかったなと心から思える大事な時間だ。
岩海苔も漁業権の対象なので、許可なく採取することは禁じられている。ザパーン。
「あそこにコンクリートを流して作った平らな海苔畑があるんだけど、波をかぶっちゃっているからダメだな」
ザパーン。
海苔畑ってなんですか。遠くの波打ち際に、まるで駐車場のような平らな場所が見えた。あれが海苔畑なのだそうだ。
そもそもは自然の岩に自生するものを収穫していたのだが、岩海苔が育ちやすく、そして収穫しやすい場所として、こうして人工的なスペースを用意するようになったのだという。
これか。佐渡にはいくつかこういう海苔畑があるそうで、岩海苔という言葉と収穫する場所のイメージが違っておもしろい。ギャップ萌え。
それにしても波がすごい。この海岸が北西を向いていて、思いっきり北西の風なので仕方がないのだが。
昔ながらの岩海苔摘みを体験する
私が悔しそうに海を眺めていたら、風裏となる磯にいけば少しは採れるかもと教えていただいた。
ぜひお願いしますと即答し、来た道を戻って案内してもらう。
ぐるっと回って岬の反対側まで来た。こちらにはコンクリートの海苔畑はなく、自然のままの岩場が広がっており、その波打ち際にモサモサと短い赤茶色の海藻が生い茂っていた。
どうやらこれが岩海苔のようだ。
海苔畑を訪れることができなかったのは残念だが、こうして昔ながらの海苔摘みができるのも貴重な体験。風裏の場所とはいえ二月の佐渡なのでまあまあ寒かったが、せっかくなので素手で岩海苔に触れて、ありがたく摘ませていただく。
岩海苔はしっかりと岩に根付いているので(根はないけれど)、これはなかなかの重労働。ゴツゴツした岩肌からはぎとらないといけいないので(この作業を「へぐ」と呼ぶ)、指紋が削れてなくなりそうだ。
これを仕事にするのであれば、磯にコンクリートを流して平らな場所を作りたくなる気持ちがよくわかった。
これは大変な仕事だ。ちなみに岩海苔はスサビノリやウップルイノリなど、磯に生えるノリ類の総称であり、場所によって微妙にその種類や割合が違う。イワノリという海藻がある訳ではない。
こういう知識はちょっと調べれば簡単にわかるものだけれど、この場で聞いた以下の話は、どこにも載っていないものだろう。
岩海苔を採るのは年末年始ぐらいから一月一杯くらいまで。今の時期(二月中旬)でも採れなくはないが、海苔が固くなってくるし、色も抜けてくる。
沢崎集落で岩海苔を採っているのは30人くらい。順番で回ってくる当番というものがあり、その人が海苔の育ち具合や凪(海の様子)をみて、その年の解禁日と時間を決めて各家に伝達する。勤め人も多いので、なるべく土日が好ましい。抜け駆け厳禁。
二回目以降に採る日も当番が決めて、何回か採ったらみんなの了解を得た上で「口開け」をする。口が開けたら(権利を持つ人であれば)自由にとってよくなる。今シーズンは例年になく岩海苔の育ちがよかったこともあり、二回目を採ったらすぐに口が開けた。
最高に貴重な時間なのです。今シーズンは1月5日が解禁日で、その日に採れた海苔を一番海苔と呼び、もっとも価値が高い。ただ岩海苔がしっかり成長して歯ごたえと風味が強くなる二番海苔や三番海苔を好む人もいる。
摘んだ岩海苔を洗ってそのまま干したものを「島へぎ」や「ひのり」と呼び、板状にしたものは「伴海苔(ばんのり)」。沢崎での伴海苔の生産はおそらく明治のはじめ頃からで、40~50年前までは貴重な収入源として集落のみんなが作っていたが、かなり手間がかかるので今も沢崎で作っているのは同好会の6人だけ。
これは60年くらい前の話だが、その頃はまだ貴重だった手袋が使用禁止だった。持っている人だけがたくさん採れるから。ゴム長ではなく藁草履の時代で、岩海苔は寒さを我慢をした人のものだった。次第に指サックが解禁になり、手袋もよくなり、現在に至る。
などなど。
伴海苔の作り方を習った
貴重な岩海苔摘み体験に続いて、伴海苔の作り方も同好会の皆様に一から十まで丁寧に教えてもらった。
「昔は冷凍庫なんてなかったから、採ったその日に干さないといけなかった。だから一日で千枚作ることもありましたが、今は30~40枚くらい。
若い人はやりませんね。我々みたいに定年退職をして、時間に余裕があるから作れる。伴海苔は趣味ですよ。勤めに出ている人には手間がかかりすぎる。
岩海苔は砂が歯にあたるとイラっとします。だから私は島へぎよりも、完全に砂が抜ける伴海苔が好きです」
集落にある沢崎開発センターのキッチンにて。私はまったくの部外者ではあるのだが、次世代の引き継ぐ人が現れることを願いつつ、理解できた範囲で工程とその歴史を記録させていただく。