旅先でカナダ人のふりをする米国人が急増、専門家はすぐばれると指摘 両者の違いはどこにあるのか
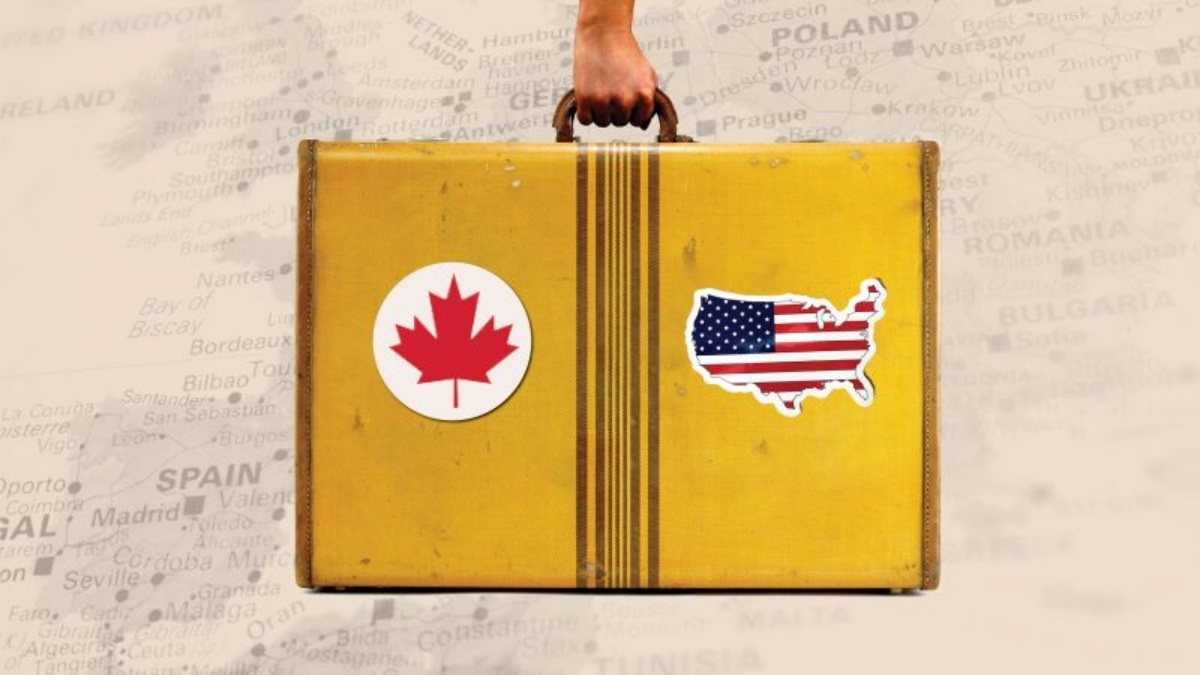
Photo Illustration by Jason Lancaster/CNN/Getty Images
(CNN) この夏、スペインをひとりで旅していたスザンナ・シャンカルさん(37)は、別の旅行者にカナダ人だと信じてもらえないという目に遭った。
シャンカルさんはホテルで、英国なまりの年配男性と話をする機会があった。旅行者同士のよくあるやりとりで、男性からどこから来たのか尋ねられた。ところがシャンカルさんがカナダのバンクーバーだと答えた途端、男性は疑いの目を向け、嘘をついていると非難。驚いた男性の娘が止めに入るほどの問い詰めようだった。
シャンカルさんは米国とカナダの二重国籍を持ち、再生型観光と持続可能な観光に関するウェブサイトを運営している。父親はカナダ人、母親が米国人だ。米アラスカ州で育ち、28歳まで米国で暮らしたのち、6年間をドイツで過ごし、バンクーバーに移住して4年になる。政治的な理由から、米国人としてのアイデンティティーは薄れ、カナダ人と名乗るようになったという。しかし、米西海岸なまりが、シャンカルさんの素性をさらしてしまうこともある。
「彼の疑念は、カナダ人のふりをする米国人がたくさんいることが多少なりとも背景にあると思う」(シャンカルさん)
シャンカルさんの発言は、「フラッグ・ジャッキング」と呼ばれる数十年前から続く慣習のことを指している。これは、米国人が海外旅行中に反米感情を避けるためカナダ人を装うものだ。フラッグ・ジャッキングをする米国人は、バッグにカナダの象徴である「メープルリーフ」を縫い付け、国籍を偽る。慣習の起源は、世間から反感を買ったベトナム戦争時の1960年代から70年代にまでさかのぼる。2000年代初頭にジョージ・W・ブッシュ政権下で行われたイラク戦争で再び増え、トランプ現政権下で復活している。
トランプ大統領が先ごろ、カナダの反関税広告を理由に10%の関税引き上げを宣言したことで貿易戦争は激化。これに加え、トランプ氏が以前カナダに対し併合をちらつかせたことに一部のカナダ人は激怒している。こうした人々は、国外でカナダ人のふりをすることを軽く見る米国人について、ひきょうで偉そうだとネット上で非難。文化の盗用だとも主張する。
さらに、フラッグ・ジャッキングに異を唱える主張のうち、ネット上でよくみられるものの一つは、誰もだまされないというものだ。米国人は、メープルリーフをいくつ身に着けても簡単に見分けられると多くの人が指摘する。
しかし、本当にそうだろうか?
旅行の専門家によれば、カナダ人は「より控えめ」
米国人とカナダ人を相手にしている欧州のツアーガイド数名は、この質問にはっきり「イエス」と答えた。
「固定観念が存在するのには理由がある」と、英ロンドン在住で14年から富裕層向けプライベートツアーの企画会社を運営しているデニサ・ポドラシュカ氏は言う。
「私たちが固定観念を使うのは、その多くが真実だからだ。それは米国人に限らず、誰にでも当てはまる。どの国にもちょっとした癖があり、それによって私たちはお互いを認識している」
旅行先で米国人を見分ける簡単な方法の一つは、実際に姿を目にする前に声が聞こえることだという。
「米国人は声が大きいので、いつも声が聞こえる。とても楽しげで、声が大きい」とポドラシュカ氏は言う。「カナダ人は米国人ほど目立たない。会話はもっと控えめで、テーブルが二つも離れれば、声が聞こえてくることはない」
海外を訪れるカナダ人は、自分の国を明かしたがることが多い。
「カナダ人は自分がカナダ人だとすぐに名乗る」と、パリのプライベートツアー会社の創業者ベルトラン・ダルマン氏は指摘し、他のツアーガイドもこの意見に同意する。カナダ人は米国人と混同されるのを避けるためにそうしていると考えられるという。
ミズーリ大学でホスピタリティーマネジメントの教授を務めるキム・デヨン氏によると、海外における米国人とカナダ人の観光客の違いを検証した学術研究はほとんどない。
一方でキム氏の研究は、観光客の国籍、権利意識、認識している社会的地位が、旅行先での行動にどのような影響を与えるかについての洞察を示している。
「研究結果は一貫して、旅行者の国籍が旅先での行動に大きな影響を与えることを示している」と、キム氏はCNNに語る。「自国よりも先進的だと認識している旅行先を訪れると、不作法を働く可能性は低くなる。一方で同じ人々が自国よりも発展途上だと認識している国を訪れれば、その傾向は高まる」
キム氏は、米国人を対象に調査を実施。自国よりも先進的だと認識しているフランスと、発展途上だと認識しているタイを旅行した時のことを想像してもらった。その結果、米国人はフランスよりもタイでゴミを捨てたり、破壊行為をしたり、不適切な服装をしたりする傾向にあることが明らかになった。



