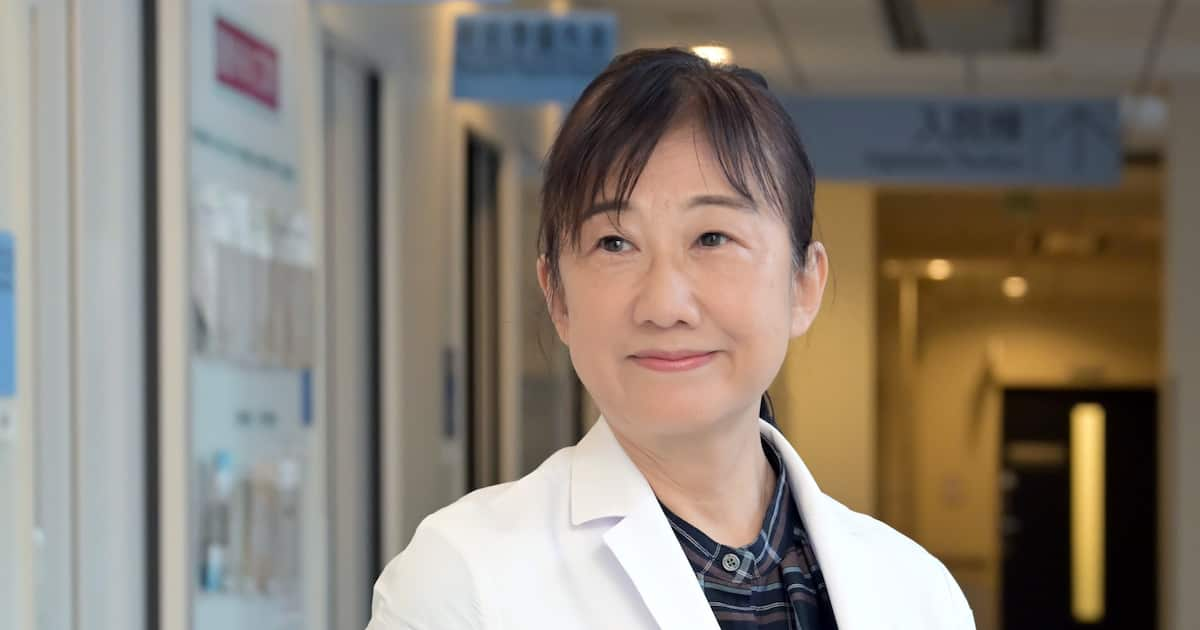研究に必要なのは「運・鈍・根」 ノーベル生理学・医学賞の坂口志文さんインタビュー

今年のノーベル生理学・医学賞の受賞が決まった大阪大の坂口志文特任教授(74)が6日夜、大阪大で産経新聞の単独インタビューに応じ、喜びを語った。主なやりとりは以下の通り。
--受賞の一報を受けたときの状況は
「部屋(研究室)にいたら、電話がかかってきまして、秘書から『英語の電話だ』ということで、(私が)出ました。たまたま家内が部屋にいたので『ああ、そういう電話がかかってきたな』ということに気づいたみたいですけど。喜んでくれていたと思います。電話で話している内容からすると、そういうことらしいと分かりますので」
--今の日本の科学研究の課題は
「なんでもそうですけど、ある程度ベースになる研究資金はいりますよね。学生のサポートも重要だし、実験に使う物に対する支援もそう。それは良い悪いではなく、多ければ多いほどいい。研究者も『(資金が)ほしい』という以上は、自分のやっていることが理解されるように、こういう理由で重要だといわなければいけない。資金をもらう以上は、評価もちゃんと受けると」
--これまでで一番つらかったとき、くじけそうだったときは
「実験はうまくいったり、いかなかったりが当たり前なので。一番苦労したのは奨学金があと1年で切れて、次のがどうなるか。それが取れないと、ポジションも失うわけで。米国はそういうジャングルみたいな所がありまして。それくらいですよね」
--どう乗り越えた
「一生懸命やるしかなくて、だめなら次を考える。それでも飢え死にするというところまではいかないわけで。鈍感なほうだと思います。何とかなるという楽天的なほうですので」
--研究者として大成できたのは、どういう要因があったから?
「『運・鈍・根』というのはありますよね。鈍(感)・根(気)があるから継続できたし、運があるからいろんな人とコラボレーションしたり、人との出会いもあったり、奨学金もある意味、運かもしれないし」
「自分の興味があることを見つけたら、大切にしながら続けていく。大切だと思ったことが変形していき、形になっていくのが重要だと思いますね」
--受賞の実感はわいてきましたか
「だんだん眠くなってきましたが」
--ノーベル賞の賞金はどうしますか
「社会的に面白いことに使えたらなと考えている」