【告知】10月29日、JILISコロキウムで『アニメ制作業界が世界で戦うために本当に必要な政策と支援について』を開催します|山本一郎(やまもといちろう)
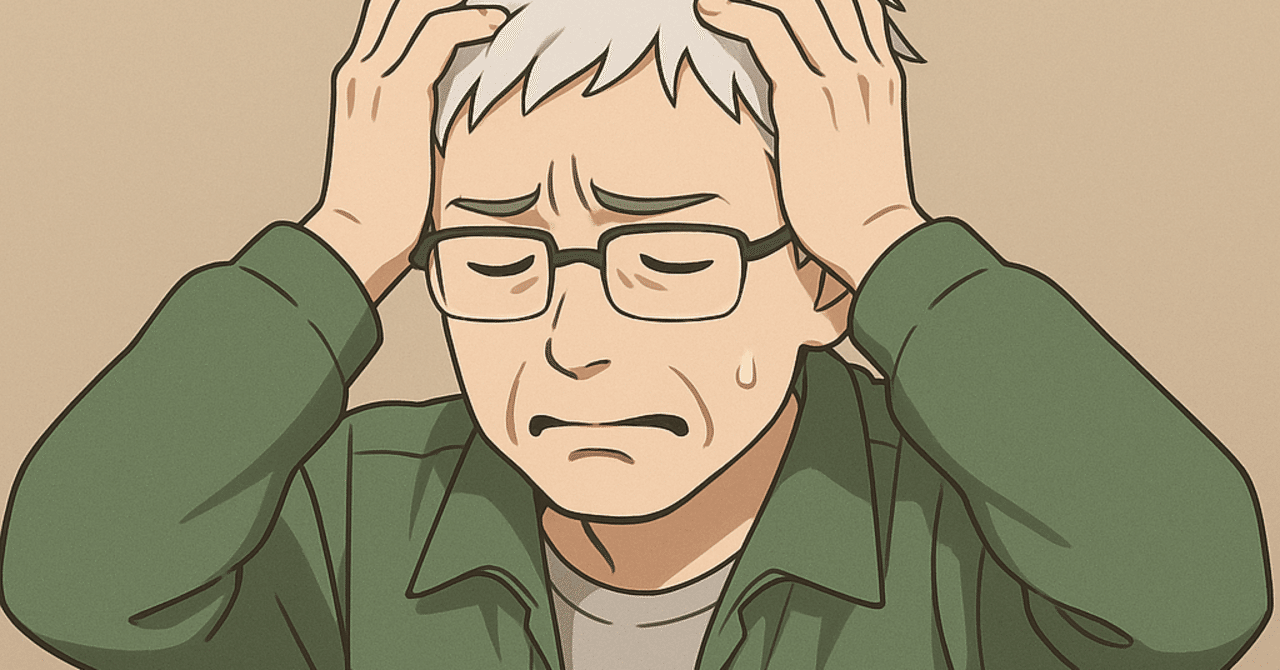
仕事が終わらなくて大変な日々が続いておりますが、私は元気です。
ということで、何事もなかったかのように今月も楽しくJILISコロキウムを開催したいと思っております、ぜひよろしくお願いします。
今回は、岸田文雄政権前後から急成長産業として外貨を稼いでくる切り札産業として注目されるようになった、俺たち私たちのポップカルチャー、アニメ制作業界について細かくお話をしていきたいと考えております。
最近特に話題となった、生成AIの波がアニメ業界を直撃しています。ダイレクトな映像制作だけでなく、作画支援、背景生成、色彩設計の効率化、さらには「ジブリ風」の映像を安価に作れるサービスの登場など、技術的な可能性が語られ始めています。その一方で、アニメ制作の現場からは「本当に困っているのはそこじゃない」という声も聞こえてきます。なもんで、今回のJILISコロキウムでは、アニメ産業が直面する課題の本質を見極め、生成AI時代における持続可能な産業のあり方を探ります。
日本のアニメ産業は世界に誇るコンテンツ産業として成長を続けてきましたが、その足元では構造的な課題が山積しています。生成AIをめぐる著作権の議論もきわめて重要なところでやんすが、アニメを制作する業界が本当に直面しているのはもっと広範で深刻な問題です。人材育成と賃上げの実現、産業基盤の強化、取引構造の適正化、アニメ制作従事者の認定制度の創設、海外販促の強化、SVOD事業者との適正で収益的にも持続性のある取引関係の構築、そして海外アニメ制作会社との競争激化への対応。さらには、クレジットカード決済をめぐる表現規制問題など、技術面以外の課題が次々と浮上しています。
とりわけ深刻なのは、日本のアニメ産業が国際競争の中で相対的な地位をかなりの勢いで失いつつある、という現実です。中国のCGアニメーションは品質が劇的に向上し、もはや日本のアニメと比較しても遜色ないレベルに達してきています。韓国、タイ、ベトナムなど東南アジア各国も制作能力を高めており、かつては日本のスタジオが下請けとして活用していた地域が、今や独自にアニメを企画・制作し、グローバル市場に直接参入するようになってきているんです。マジヤバイけど、日本国内や、英語系ではMy Anime Listなどでのスコアや映画版アニメ作品の目先の興行収入でどうしても一喜一憂してしまうわけですよ。んで、実際に水面下で起き始めているのは日本を経由せずに、東南アジアから世界へ。アニメ制作の主たるプレイヤーが日本から海外へ移行していく可能性は、もはや絵空事ではありません。
この構図は、ソーシャルゲーム業界が辿った道と酷似しています。かつては日本が世界のモバイルゲーム市場をリードしていましたが、いまや中国や韓国のゲームメーカーが主要プレイヤーとなり、国産ゲームは日本市場においてさえシェアを確保できない状況に陥っています。まあ、面白いゲームを圧倒的なマーケティングパワーでタイトル育成する能力をもっていないんだから仕方ないわな。それが数年来続いた結果、ゲーム制作における技術力、広報宣伝を分回る資本力、そしてグローバル展開のスピードで後れを取った結果、気がつけば市場の主導権を失っていた。アニメ産業が同じ轍を踏まないという保証はどこにもありません。むしろ、すでにその兆候は現れ始めています。
こうした危機感は、業界内でも共有されつつあります。俺たち一般財団法人情報法制研究所(JILIS)では、一般社団法人日本動画協会と連携し、アニメ業界の支援・保護、そして次世代の育成を目的とした座談会やシンポジウムの企画を進めています。2025年11月には、映像産業戦略推進研究会との共催で、衆議院第一議員会館にてそれなりに頑張った大規模なシンポジウムの開催も予定されています。岸田文雄さん、日本動画協会理事長の石川和子さん、東映アニメーションの山田喜一郎さん、TRIGGERの舛本和也さんといった業界を代表する方々が登壇し、人材育成と職能認定制度、取引構造の適正化、知的財産権の保護強化、デジタル技術の活用、産業基盤の強化など、多岐にわたるテーマについて議論が交わされる予定です。そのうちちゃんと告知をするので正座待機でよろしくお願いします。
今回のコロキウムは、こうした大きな動きも踏まえて、フランチャイズも含めた広い意味でのアニメ業界ではなく、その原作やアニメーションを作成する狭い意味でのアニメ制作者業界にフォーカスを当ててまいりたいと考えています。もちろん、生成AIという技術的なトピックは世間から見た映像業界の抱える各種問題点の入り口としながらも、アニメ業界が抱える本質的な課題に切り込んでいかないと、自動車業界に次ぐ輸出産業を位置付けられたはずのアニメ業界もまた競争の波にもまれて存続の危機になっちまうのでございます。
まず、人材育成と賃上げの問題です。アニメーターの低賃金と長時間労働は、何十年も前から指摘されながら改善が進んでいません。なぜか国連からもいちゃもんをつけられましたが、待遇を大幅に改善できる大手事業者と、粗末なタコ部屋に机並べてなんとなく仕事をしている零細中小スタジオとが、同じ土俵でごっちゃに「アニメ産業」という括りで雑に扱われていることはそろそろどうにかしないといけません。才能や働きに見合った登竜門をしっかりと整備しなければ若手クリエイターは生活できる賃金を得られず、業界を去ってしまいかねません。また、海外のクリエイターも自在に日本や韓国、東南アジア各国を移動しながら制作活動に従事するというダイナミズムも発生してきています。この悪循環を断ち切るためには、制作費の適正化と、その利益を現場に還元する仕組みが不可欠です。同時に、アニメ制作従事者の認定制度を創設し、技能に応じた適正な評価と報酬体系を確立することも求められていくでしょう。
次に、取引構造の適正化です。製作委員会方式をはじめとする現在の取引慣行には、出資者側の都合もあってリスク分散というメリットがある一方で、制作現場への利益還元がどうしても不十分になりがちという問題があります。特に、NetflixやAmazon Prime Videoなどのグローバル配信プラットフォーム(SVOD)が台頭する中で、これらSVOD事業者との適正な取引関係をどう構築するかは喫緊の課題です。いわゆる「プラットフォーム内プラットフォーム」として、日本のアニメ産業がどのようなポジションを確立できるかが問われています。
さらに、海外販促の強化も重要です。業界からは「クールジャパンは無駄だからやめろ」という声も盛んで、日本のアニメは海外で人気がある、という言説は確かに一面の真実ですが、それをビジネスとして確実に収益化できているかというと疑問符がつきます。海賊版対策、適切なローカライゼーション、現地パートナーとの関係構築など、グローバル展開には多くの課題が残されています。国内外では、クレジットカード決済をめぐる表現規制問題も見逃せません。国際的な決済システムの規約変更によって、日本の表現文化が間接的に制約を受けるという事態が起きています。これは単なる商業的な問題ではなく、表現の自由と国際的なビジネス環境との葛藤という、より根深い問題を孕んでいます。
こうした課題に対して、技術革新はどのような解決策を提供できるのでしょうか。生成AIは効率化のツールとして期待される一方で、クリエイターの仕事を奪うのではないかという懸念もあります。重要なのは、技術をどう使うかという議論だけでなく、技術導入によって生まれた利益をどのように現場に還元し、産業全体の体質改善につなげるかという視点です。
当日は、ゲストとして業界の最前線で活躍されている入江武彦さんをお招きし、みんなお馴染み新潟大学・鈴木正朝先生、弁護士の板倉陽一郎先生と不肖、このわたくし山本一郎の3名とともに、懲りもせずミニシンポジウムの形式で議論を展開する予定です。アニメ産業の未来を真剣に考える方、生成AIと創作の関係に関心をお持ちの方、法制度とビジネスの接点に興味がある方、あるいは日本のコンテンツ産業全体の行く末を案じている方、ぜひご参加ください。
会員の皆様は、リアル会場でのご参加はもちろん、Zoomでのオンライン参加、アーカイブ視聴も可能です。コロキウム後の懇親会では、会員様同士の情報交換や、ゲストあるいはJILIS所属の専門家への多様なご相談も可能です。業界の未来を一緒に考え、行動していく仲間をお待ちしています。
しかし――このイベントについての挿絵を生成AIに頼むと、何度出力しても私が頭を抱えて困っている画像しかいつも吐き出されないのは仕様なのでしょうか。



