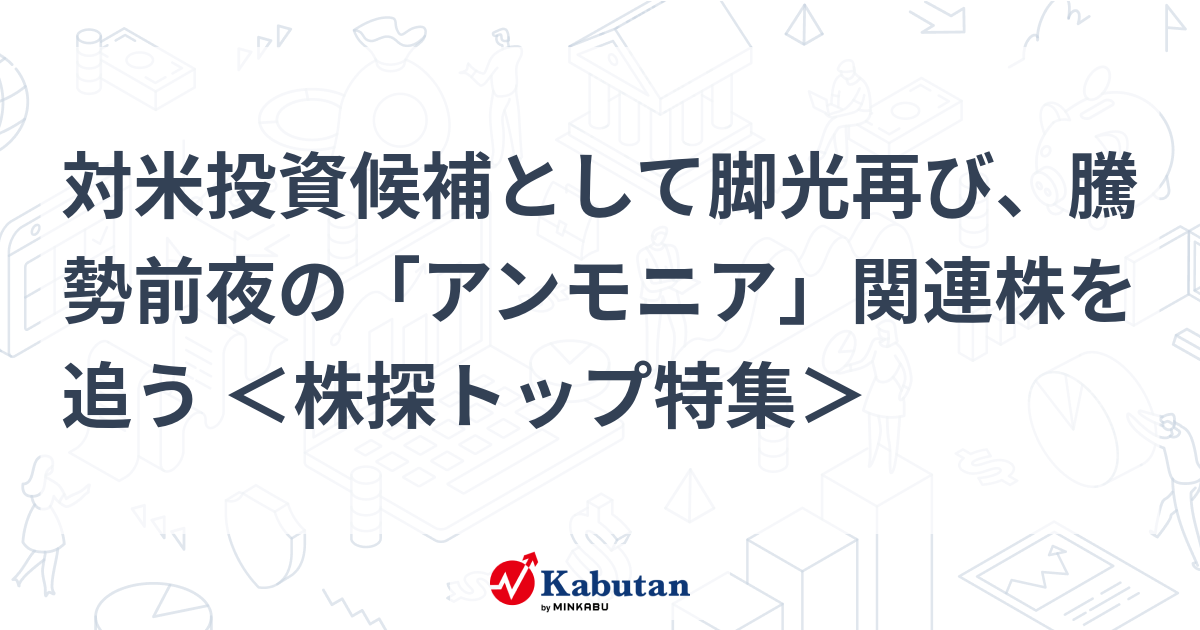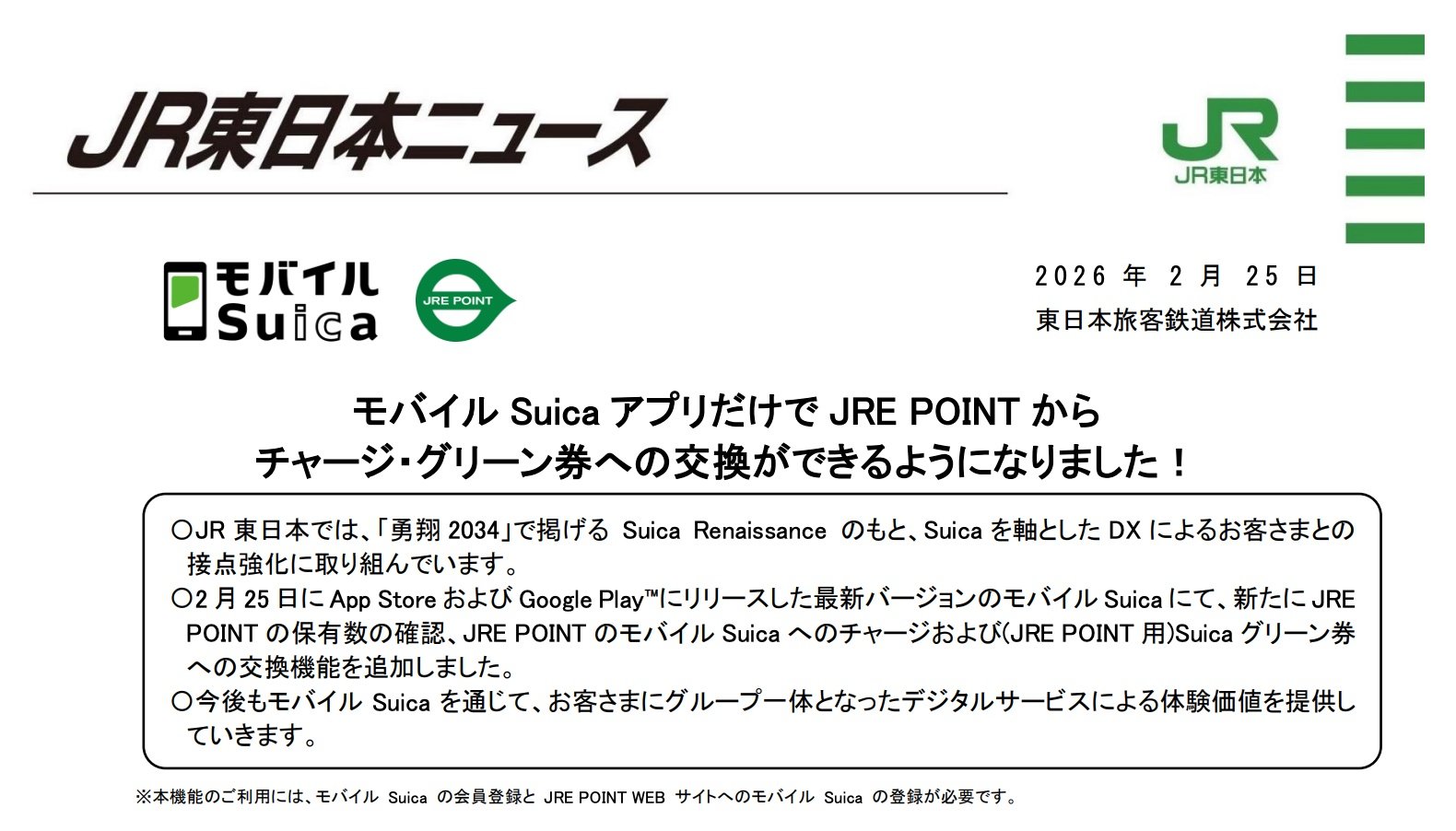トヨタのソフトウエア推進息切れか、出遅れ懸念-保守的な社風指摘も

自動車業界においてソフトウエアの重要性が高まる中、「ソフトウエア・ファースト」を掲げて取り組みを進めてきたトヨタ自動車の社内や周辺からは同分野での出遅れを懸念する声が出ている。
「トヨタはソフトウエアの重要性を理解しているが、対応が遅い」。トヨタと提携して従業員向けにシリコンバレー式のプログラミングのトレーニングを実施しているスタートアップ、コードクリサリスのカニ・ムニダサ最高経営責任者(CEO)はこう話す。
同氏の懸念はトヨタ社内でも共有されている。ソフトウエア中心の改革を推進してきた一部関係者の間では、変革に対する社内のぬるい姿勢に失望の声も上がっているという。
2020年3月、当時社長だったトヨタの豊田章男会長はNTTとの業務資本提携に関する共同会見で、ソフトの進化の速度がハードを上回ることで、車の商品価値が進化の遅いハードの制約を受けるケースも出てきたと指摘。「ハードの強みを生かして、ソフト
ウエア・ファーストの考え方も取り込んでいく」と宣言した。
世界最大の自動車メーカーであるトヨタは、信頼性が高い車を安定して生産することで消費者の支持を勝ち取ってきた。ただ、業界では今後は購入後もアップデートで機能の追加や改善ができる「SDV(ソフトウエア・ディファインド・ビークル)」などが主流になるとみられている。こうした分野では米テスラや中国・比亜迪(BYD)など新興勢力に後れを取っているのが現状だ。
これらの課題に取り組むために21年にトヨタに設立されたのが「デジタル変革推進室」だ。部署のメンバーは技術者から工場の現場作業員まで社内のあらゆる部門から集められ、アナログ文化が根強く残るトヨタにデジタルの未来を導入するという共通のビジョンを掲げていた。
いら立ちの種に
同推進室は市販車の開発には直接関与していないものの、社内業務向けの多くのプロジェクトを手掛けてきた。関係者らによると、実績としてはテストカーの車両管理データベースの構築や社員の休暇申請システムの刷新、工場のホワイトボードをタッチスクリーンに置き換える取り組み、さらには愛知県豊田市内のトヨタ記念病院で薬を運搬するロボットの導入などがある。
また、米エヌビディアとの提携によりリモートワーカー向けに仮想デスクトップ環境を使ったコンピューター利用設計システム(CAD)ソフトの使用を可能にするプロジェクトも実施された。こうした施策は極端に慎重な社風の中では画期的といえるかもしれない。ただ実際の成果は部分的にとどまり、長期的な目標の達成にはほど遠いというのが関係者の見方だ。
改革によって会社全体を刷新する使命を担ってきたが、最近では同室をより大きな「デジタル情報通信本部」に統合するという決定がなされ、その独立性が損なわれるとの懸念もある。トヨタは統合の理由についてデジタルトランスフォメーション(DX)を社内で加速させる狙いがあるとし、分散している事業や社会基盤構築に関わる業務を新組織に集約することで、社内連携や人工知能(AI)の活用によって「新価値創造とビジネス変革を目指す」としていた。
豊田氏のイニシアチブで一定の変化はもたらしたが、トヨタの強みはいまだにハードウエアにあり、電気自動車とガソリン車の両輪でバランスを取る姿勢も変わらない。この慎重さは同社の成功要因でもあるが、一方で変革を急ぐ社内外の人々にとってはいら立ちの種となっている。
ルーティン業務
ブルームバーグの取材に応じた元社員は、調和が重視されすぎる組織文化と創造性を生かしづらい官僚的な体質を指摘している。自動運転に興味を持って入社したにもかかわらず、何年も電子部品の品質管理といったルーティン業務に縛られていたと語る者もいた。
トヨタは5年連続で世界販売首位を維持し、日本最大の企業としての地位を確立しているが、その成功体験こそが変革を妨げる慣性になっていると指摘する声もある。
ただ、現代のテクノロジーへの適応に苦戦しているのは海外勢も含め他の伝統的な大手自動車メーカーも同じだ。独フォルクスワーゲンのソフトウエア子会社カリアドはトラブルと遅延を受けて縮小された。米フォードは次世代電子電気アーキテクチャー「FNV4」の開発プログラムを中止したと、ロイターが関係者を引用して報じている。
バンク・オブ・アメリカ(BofA)の自動車アナリスト、ジョン・マーフィー氏は、トヨタなど旧来の自動車大手が置かれた状況について「車の構造、プラットフォーム、技術、統合されたオペレーティングシステム(OS)などすべてを再構築しなければならない。それは非常に困難な挑戦だ」と述べた。