勉強の成果は “インプット量” で決まる。科学が裏づける、成果を出す人の勉強術
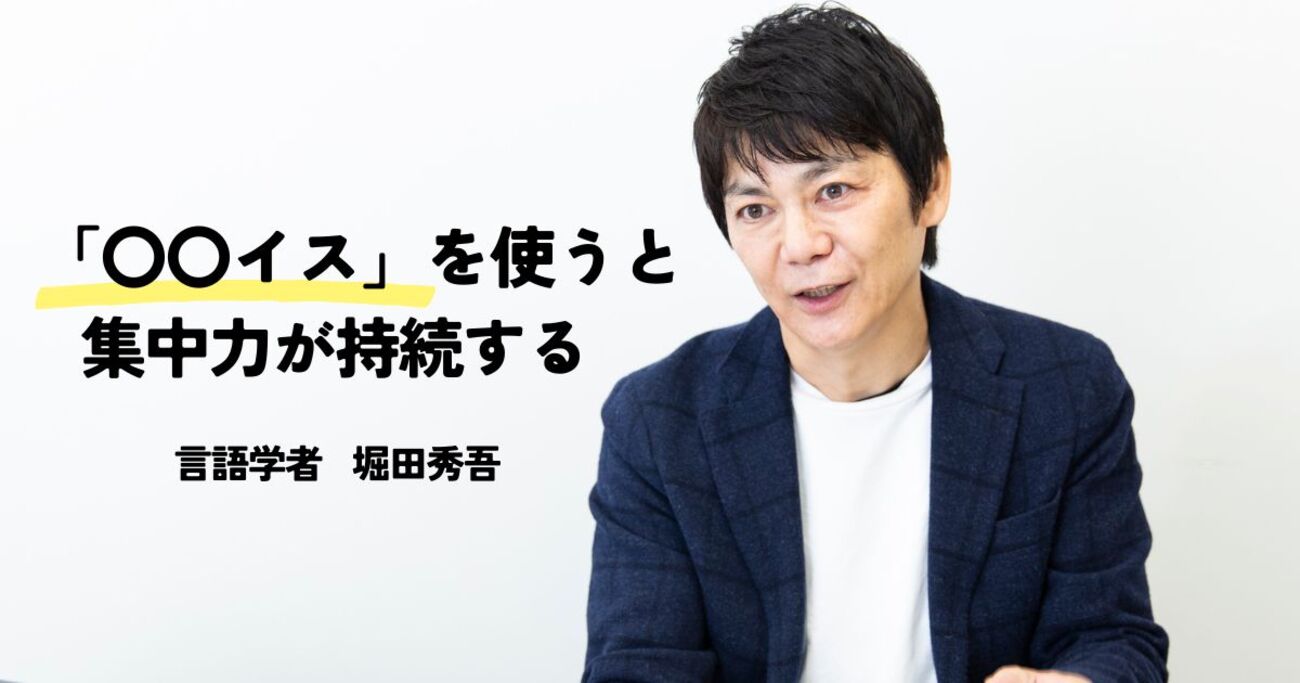
昨今、「アウトプット至上主義」ともいえるような「アウトプットこそが最重要」という話をよく見聞きしますが、それに異議を唱えるのが、明治大学教授の堀田秀吾先生。とくに勉強においては「インプットの量こそがすべて」と語るその真意と、実際にインプットの量を確保し、勉強で成果を挙げるための方法について解説してもらいました。
構成/岩川悟 取材・文/清家茂樹 写真/石塚雅人
【プロフィール】堀田秀吾(ほった・しゅうご)1968年6月15日生まれ、熊本県出身。言語学者(法言語学、心理言語学)。明治大学法学部教授。1999年、シカゴ大学言語学部博士課程修了(Ph.D. in Linguistics、言語学博士)。2000年、立命館大学法学部助教授。2005年、ヨーク大学オズグッドホール・ロースクール修士課程修了、2008年同博士課程単位取得退学。2008年、明治大学法学部准教授。2010年より明治大学法学部教授。司法分野におけるコミュニケーションに関して、社会言語学、心理言語学、脳科学などのさまざまな学術分野の知見を融合した多角的な研究を国内外で展開している。また、研究以外の活動も積極的に行っており、企業の顧問や芸能事務所の監修、ワイドショーのレギュラー・コメンテーターなども務める。『いまの科学でいちばん正しい 子どもの読書 読み方、ハマらせ方』(Gakken)、『燃えられない症候群』(サンマーク出版)、『とりあえずやってみる技術』(総合法令出版)、『24 TWENTY FOUR 今日1日に集中する力』(アスコム)など著書多数。
インプット量が少なければ、アウトプットの質は低下する
勉強で成果を挙げるためには、「インプットの量こそがすべて」だと私は考えています。もちろんただ知識を詰め込むだけでなく、それらの知識をどう応用するかという力も重要ですが、知識がまったくインプットされていなければ、そもそも応用力を発揮することなど不可能でしょう。
このことは、脳の仕組みから考えても明らかです。脳は、インプットした情報をもとに、本人は休憩しているようなときにでも「インキュベーション(incubation)」というプロセスを進めます。インキュベーションとは「孵化」という意味の英語ですが、脳科学においては「問題解決に行き詰まった際に、課題から一時的に離れることで脳が情報を整理・再構成し、ひらめきや新たな解決策が生まれる現象」を指します。
インキュベーションを端的にいうと、「醸成」という言葉がしっくりくるでしょう。勉強というインプットを通じて蓄えた知識同士を比較したりつなげたりすることで応用力を発揮する、または、斬新なアイデアを思いつくといったアウトプットは、このインキュベーションによるものです。
インキュベーションの材料はインプットした情報ですから、それらが多ければ多いほどインキュベーションとアウトプットの質は豊かになります。逆にいえば、インプットした情報が少ないほど、インキュベーションとアウトプットの質は低下し、勉強の成果にも大きな期待はできなくなるというわけです。
すでに身についている習慣に新たな行動を追加する
だからこそ、勉強においては「インプットの量こそがすべて」だと言えるわけですが、この事実が社会人にとって大きな課題となります。インプットの量がすべてということは、勉強で成果を出すには時間がかかるということを意味し、その時間の確保が社会人には難しいからです。
ですから、限られた時間をうまく活用してインプットの量を増やしていく必要が出てきます。そうするための仕組みとして私がおすすめするのが、「ハビット・スタッキング」というものです。ハビット(習慣)をスタック(積み重ねる)する――つまり「現在身についている習慣に行動を追加して、新しい習慣をつくる」という手法です。
一般的に「習慣化は難しい」とされる要因のひとつは、脳がもつ「変化を嫌い、現状維持を好む」という特性にあります。まだ慣れていない新たなことに取り組むと脳が多くのエネルギーを消費してしまい、それだけ生存確率が低下するために、脳はこの特性を獲得しました(『努力も根性もいらない習慣化|脳科学が証明する「続ける人」の仕組み』参照)。
その特性をうまく回避するためのメソッドが、ハビット・スタッキングです。たとえば、「起床したらコーヒーを飲む」という習慣がすでに身についている人であれば、それに加えて「コーヒーを飲みながら英単語を5つ覚える」という行動を追加するという具合です。
この方法であれば、努力など必要なく自然とできる「コーヒーを飲む」という行動を、「英単語を覚える」という新たな行動のきっかけとして活用でき、習慣化成功の確率が大きく高まります。そして、ただコーヒーを飲むのではなく、その時間に勉強を組み込めるという点において、勉強時間の確保という課題の解決にもつながるのです。
「重い椅子」を使えば集中力が持続する
また、限られた時間のなかで効率的に勉強の成果を出そうと思えば、「集中力」も見逃せない要素です。いくら勉強時間を確保しても、勉強に集中できなければ成果から遠ざかることになるのは当然でしょう。
そして、現代社会において集中力の天敵となるのは、やはりスマホです。実際、そばにスマホを置いておくだけでも集中力が低下するという研究結果もあるほど。というのも、たとえなんの通知もなかったとしても、「なにか通知がくるかも」というように脳はスマホを気にしているため、脳のリソースを使ってしまっているからです。ですから、勉強をするときにはスマホを隣の部屋に置いておくなど、物理的に遠ざけることを考えましょう。
また、おもしろいところなら、「重い椅子を使う」というのもひとつの手です。行動経済学では「行動の摩擦」と呼ばれますが、なにかをする過程のアクションが増えれば増えるほど、その行動の実行率は大きく下がる傾向があります。たとえば、コードレス掃除機が目に見える場所に置かれていればすぐに掃除をできますが、従来のコードレスではない掃除機が押し入れの奥にしまわれていれば掃除が億劫に感じるはずです。
このことを逆手にとって利用するのです。キャスターのついた一般的な椅子なら、勉強に集中できずに休憩したくなればすぐに立ち上がることができます。でも、キャスターがない重い椅子ならどうでしょうか? 立ち上がるのが面倒になって、勉強を続けられる可能性が高まります。
これは実際に、若い頃の私が海外留学のための勉強をしているときに実践した手法です。私の場合は、椅子と机をロープでくくって動かないようにしていました。座るのも面倒ではあるのですが、一度座ってしまえばそれこそ立ち上がるのが面倒になります。コーヒーが入ったポットと、小腹が空いたり頭が疲れたりしたときのための飴をそばに置き、6時間でも7時間でも勉強し続けたものです。
もちろん、働きながら勉強をするみなさんがそのように長時間の勉強をすることは現実的ではありませんが、勉強に集中できる環境、そして一度勉強をはじめたら逆になかなかやめづらくなる環境をつくるための参考にしてもらえれば嬉しく思います。
【堀田秀吾先生 ほかのインタビュー記事はこちら】“勉強の大敵” ストレスを解消する「勉強前・勉強中・勉強後」の最強ルーティン「ストレスたまる……でも頑張る」は超危険。8つの変化をもたらす最良のストレス解消習慣なぜかいつも「決められない」人がしている決定的過ち。デキる人ほど “これ” をやらない努力も根性もいらない習慣化|脳科学が証明する「続ける人」の仕組み成功者はルーティンを重視する。成果を出すビジネスパーソンの意外にシンプルな日常習慣(※近日公開)
【ライタープロフィール】清家茂樹(せいけ・しげき)
1975年生まれ、愛媛県出身。出版社勤務を経て2012年に独立。ジャンルを問わずさまざまな雑誌・書籍の編集に携わる。



