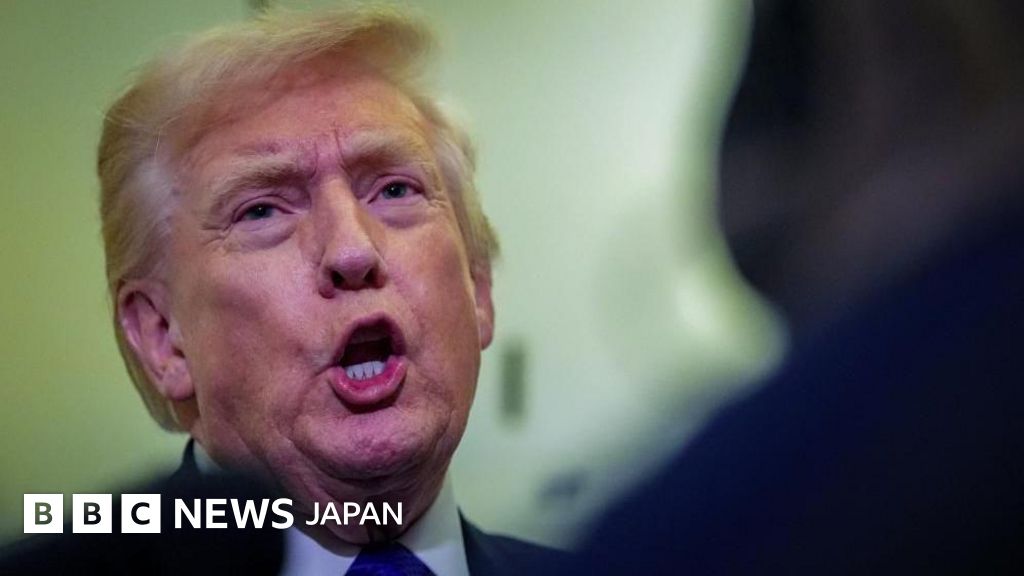温暖化で強風が洋上風力タービンの限界超え? 風使いになるためにはアプデが必要

いったい秒速何メートルの風に耐えなければいけなくなるのか…。
先週ジャマイカを直撃したハリケーン「メリッサ」は、大西洋で観測史上最も強い勢力を保って上陸したハリケーンのひとつになりました。メリッサの前例のない強さは、気候変動が引き起こした異常に高い海面水温によって激化したのだとか。
異常な強風が洋上風力発電を限界に追い込む
世界中で上昇する海面水温の影響で、強風が極端になっているそうです。Nature Communicationsに掲載された新たな研究結果によると、この荒れ狂う風が洋上風力発電にとって大きな問題になっているといいます。
風力タービンは、風の運動エネルギーを電気に変換するように設計されていますが、これまでなかったような強風が限界を超えさせているとのこと。
洋上風力発電所の設置場所を見直す時期
中国南方科技大学のYanan Zhao氏が率いる研究チームは、今回の発見によって、洋上風力インフラは極端化する強風に適応するのが急務であると強調しています。
そして、従来は理想的とされた海域の条件が過酷になりつつあるため、世界全域で洋上風力発電所の設置場所を見直す必要があると指摘しています。
研究論文の共著者である世界銀行のYiheng Tao氏は、米Gizmodoへのメールで次のように述べています。
洋上風力プロジェクトの開発は、強風が激しさを増している地域で進められています。各国が気候とエネルギーの目標を達成するために洋上風力を拡大するなか、設計基準や立地選定に気候変動に対するレジリエンス(耐性)を指標として組み込むことが、長期的な信頼性を確保するうえで不可欠になるでしょう。
過ぎたるは及ばざるがごとし
風力タービンは風が強いほど発電量が増加しますが、物事には限界があります。研究チームによると、風速がタービンの限界値を超えると、損傷や早期の運転停止、経済的損失につながるおそれがあります。
過去数十年間における風速の極端な変化を解明するため、研究チームは1940年から2023年にかけて世界の海洋で観測された1時間ごとの風速データを分析しました。このデータはヨーロッパ中期予報センターが開発したERA5データセットに基づいています。
分析の結果、1940年以降に海洋沿岸地域の約63%で極端な強風が増加していることが判明しました。北東太平洋、北大西洋、南半球の偏西風帯でその傾向が特に顕著なのだそう。
また、アジアとヨーロッパにおいて稼働中および計画中の洋上風力発電所の40%以上が、クラス3タービンの限界である時速約135km(毎秒38m)を超える強風にさらされたことがあるといいます。
アメリカでは、最大発電容量が50.31GW(ギガワット。ギガは10億)に達する計画中の洋上風力発電所の半数以上が、時速135~180km(毎秒38~50m)という極端な強風にさらされる地域に設置される見込みとのこと。20年稼働できるとして、激化する風に耐え続けられるのかどうか…。
激化する風に適応したアプデが必要
研究チームによると、極端な強風の頻度と強度の増加は、地球温暖化に伴う熱帯低気圧(台風やハリケーン、サイクロン)の活動の変化と強い関連性があるそうです。
平均を上回る海面水温は、暴風雨の発生と発達に必要なエネルギーを供給します。これは、ハリケーン多発地域に住む人々にとって重大なリスクとなるだけでなく、クリーンエネルギーへの移行が求められる国際社会にとっても深刻な脅威になります。
極端な強風のなかでも、熱帯低気圧と温帯低気圧による強風が風力タービンを故障させる最大の要因になっているといいます。
世界平均気温が上昇を続けるなか、研究チームは洋上風力発電を激しすぎる強風から守る対策として、リスク評価モデルの改良や設計基準の見直し、より頑丈なタービンの開発、新たな立地基準の導入などを求めており、このような対策が「洋上風力インフラを保護し、その長期的な発展を支えるうえで不可欠」と述べています。
温暖化の最悪の影響を回避するには、再エネのインフラが進行する変化に適応していく必要があるんですよね。
いっそ4度くらい温暖化した世界で最強レベルまで発達した台風やハリケーンの瞬間最大風速に適応できるタービンをつくればいいのにと思いますけど、そうなるとコストが高くなりすぎて、電気代が跳ね上がったりするのでしょうか…。
Source: Nature Communications