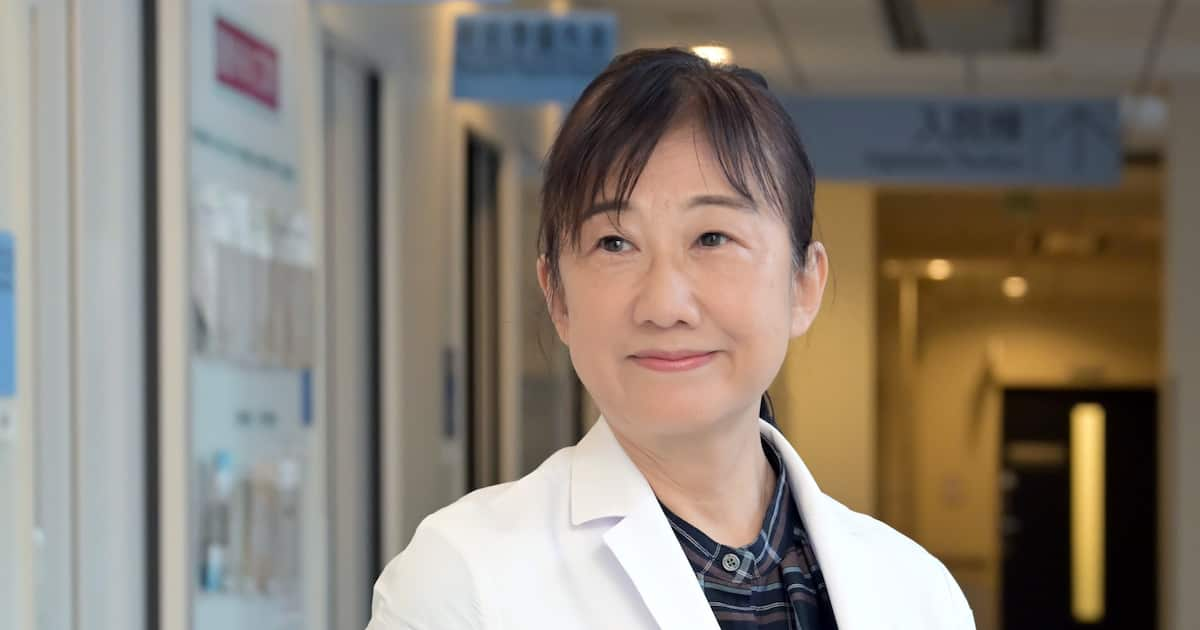シカ牧草食害防止で高い効果 1番草の収穫量2・7倍超に 岩手県の立体柵 実用化へ前進

ニホンジカによる牧草の食害を防ぐ切り札として岩手県が実証実験中の「いわて式ワイヤーメッシュ立体柵」(仮称)が高い食害防止効果を示し、実用化に大きく前進した。5~6月に刈り取る1番草で比較したところ、立体柵内の収穫量は無防備な柵外の2・7倍を超えた。県は今年度、実証実験の場所を増やし、その効果を確認した上で早期の実用化にこぎつけたい考えだ。
令和4年に試作
立体柵は国の研究機関がコンクリートの補強材として使う長さ2メートル、幅1メートルのワイヤーメッシュ(溶接金網)をシカによる牧草の食害調査に使用していたのをヒントにした。長さ2メートルの溶接金網を真ん中で90度曲げる。2枚を向かい合わせで接続すると、1メートル四方のボックスになる。これを牧草地に複数置いていく。
1メートル四方のボックス内でシカは牧草を食べられず、それ以外の牧草の収量を比べれば、食害の被害量が分かる仕組みだ。「このボックスで柵をつくればシカが入ってこれないのではないか」。ひらめいたのが立体柵の生みの親でもある県農業普及技術課技術主幹兼農業革新支援担当課長の中森忠義さんだった。
令和4年に長さ10メートルの立体柵を試作した。同じ溶接金網に防錆塗装を施し、真ん中で90度曲げた2枚に真っすぐな1枚を渡しボックス状にして連結した。「高さと奥行きが1メートルある立体柵を飛び越えられないとシカに認識させること」が中森課長の狙いで、設置カメラの映像でシカが立体柵を嫌がるのを確認できた。
この結果を受けて実証実験が始まった。令和5年11月、盛岡市郊外の広さ30ヘクタールの牧草地のうち1・6ヘクタールと60アールが立体柵で囲われた。1・6ヘクタール内で今年刈り取られた1番草の10アール当たり収量は465・2キロで、無防備な立体柵外の170・3キロの2・7倍を超え、実証実験は立体柵の高い食害防止効果を証明した。
東北6県で最悪
同時に無防備の牧草地では栄養価が高く良質な飼料となる1番草の半分以上をシカが食べていた実態も浮き彫りになった。1・6ヘクタール内で今年収穫した1番草の牧草ロールは22個。無防備だった5年の11個の2倍。実証実験の牧草地を所有する農家は60アール内を含む1番草の収穫増で外部からの牧草の買い入れをとりやめることができたという。
岩手県が立体柵の実用化を急ぐのには理由がある。野生鳥獣による県内の農作物被害でシカが断トツに多いからだ。令和3年から3年連続で被害額は2億円を超え、東北6県で最悪。希少な高山食物への食害や列車などの衝突事故も多発するなど社会問題にもなっており、シカの個体数減少が急務となっている。
平成30年の推計で県内のシカの生息数は10万7000頭。これを減少させるには毎年2万5000頭以上を捕獲する必要があり、捕獲の担い手確保と捕獲の効率化が課題になっている。シカによる牧草の食害を防ぐ立体柵には捕獲と並ぶ個体数抑制の切り札としての期待もかかっている。
実証実験では高い実用性も証明された。まず低コストだ。実証実験で使った溶接金網は長さが2メートルで、幅が1メートルと1・2メートルの2種類。立体柵1メートルの材料費は幅1メートルが929円(税込)。幅1・2メートルは1680円(同)。いずれも1メートル当たりの国の交付金2145円(同)内に納まった。
四角いボックス状で自立する溶接金網を連結した立体柵は設置が容易。電気柵で必須な下草刈りの労力も不要。冬季間も継続して設置できてメンテンナンスも簡単と、広大な牧草地にも対応できるめども立った。
「早期に実用化を図りたい」
シカの生態に詳しい実証実験のアドバイザー、農研機構畜産研究部門動物行動管理グループの堂山宗一郎主任研究員は「シカによる牧草の食害を防ぐ試みはシカの頭数管理において重要な視点。1メートル四方の仕切りがある立体柵はほとんどのシカが飛び越えられないだろう」と高く評価する。
県農業振興課の村田就治特命課長(鳥獣被害対策)は「立体柵の有効性が確認された。さらに実証実験を積み重ねて早期に実用化を図りたい」と話しており、今後の展開が注目される。(石田征広)