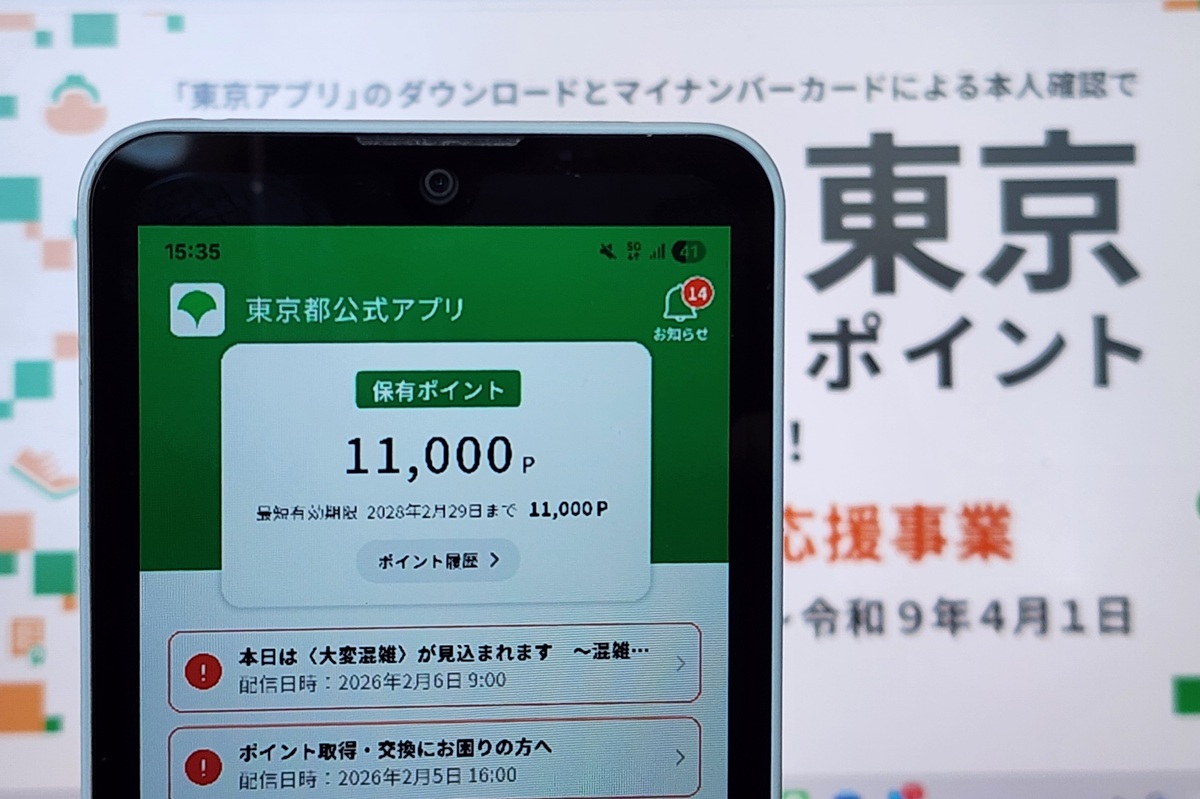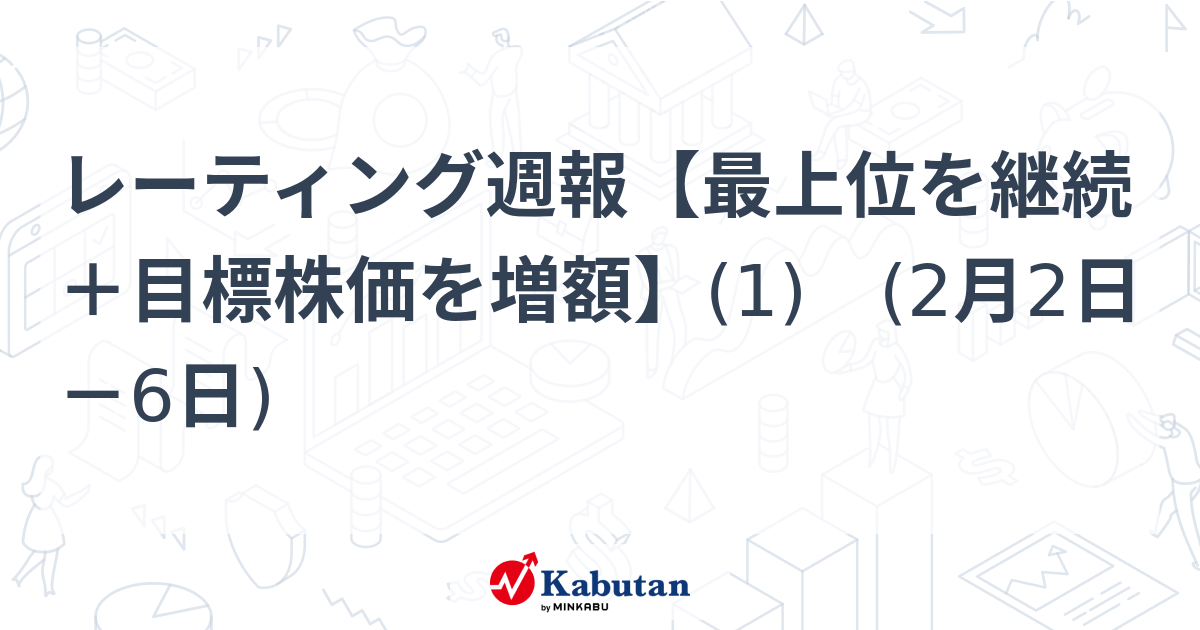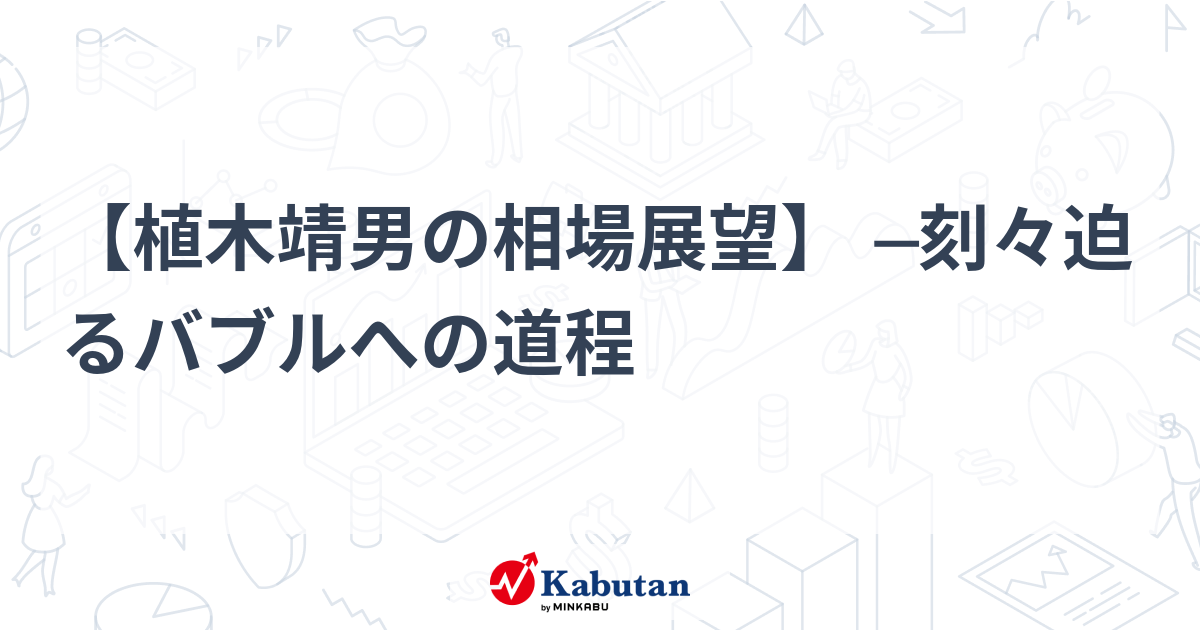円買い介入、市場は効果懐疑的-昨年実施の水準接近で警戒感強まる

為替市場では円が下げ止まらず、過去に当局が為替介入を行った水準に接近してきたが、円安は介入で抑えにくいと市場関係者はみている。
昨年は、日本銀行による利上げが進む中で介入が行われたが、今回は状況が異なる。高市早苗首相が利上げペースの鈍化を訴える中で日本が円を買い支えるのだ。
高市氏の財政拡大策が円安を助長している状況での介入になる。介入を行えば、米国と合意した対米投資最大5500億ドル(約85兆円)の資金調達に必要な日本の外貨準備が枯渇しかねない。
SBI FXトレードの上田真理人取締役は「高市政権の誕生を一つのきっかけとして円安が進んでいる」と指摘。介入で短期的に円安が止まっても、「政策が財政拡大の方向であれば結局は円安に戻る」とみる。
円はこの四半期に入り対ドルで約4.5%下落し、主要通貨の中で最弱となっている。12日の米国市場で一時1ドル=155円04銭まで下落し、13日の東京市場の午前10時時点で154円96銭前後で取引されている。
片山さつき財務相は12日、円安は急激だとし、経済への影響は「マイナス面が目立ってきていることは否定できない」と述べ、市場をけん制した。「投機的な動向を含め、過度な変動や無秩序な動きについて、高い緊張感を持って見極めている」との見解を改めて示した。
財務省が昨年最初に介入に踏み切ったのは円が対ドルで160円17銭程度まで下落した時だった。その後も157円99銭、161円76銭、159円45銭付近で追加介入を行った。当局者は特定の水準よりも、変動の激しさや速さに懸念を示している。
「もし為替介入への警戒感が、1ドル=155円の明確な突破を抑えられない場合、介入のリスクは一段と高まるだろう」と、ラボバンクの外国為替戦略責任者ジェーン・フォーリー氏は述べた。
為替の変動が「過度」と見なされる明確な基準はないが、昨年当局者は1カ月で対ドル10円の変動は「かなり急速」であり、2週間で4%動くのは「なだらかなものとは到底言えない」と指摘した。円相場は10月17日に一時149.38円まで急騰した後、5円強動いた。
円安は輸出企業にとって海外収益の円換算額が膨らむというプラス面がある半面、輸入品のコストを押し上げインフレ圧力を高める。また、円安を放置すれば米国から再び批判される恐れもある。トランプ米大統領は過去に、日本が為替政策を通じて貿易上の優位性を追求していると不満を述べていた。
関連記事:高市政権下で強まる円安基調、為替介入に神経尖らせる市場-QuickTake
市場では、日銀の利上げが伴わない限り、為替介入が実施される公算は小さいとの見方がある。次回の日銀金融政策決定会合は12月19日。前回10月の会合では7対2の賛成多数で政策の現状維持が決まった。
野村証券の後藤祐二朗チーフ為替ストラテジストは「ドル・円が155円を突破するとより強い口先介入のリスクがあり、12月の日銀利上げの可能性も高まる」と読む。財務省による円買い介入と日銀の利上げが組み合わさることで、円は150円近辺かそれ以上に上昇する可能性があると言う。
ベッセント米財務長官の発言もこうした見方を後押しする。同氏は日本政府に対し、インフレと過度な為替変動の双方に対応できるよう日銀に十分な裁量を与えるべきだと呼びかけた。これは事実上の利上げ容認だと受け止められている。
三井住友銀行の鈴木浩史チーフ・為替ストラテジストは、米政権は為替相場への直接介入よりも日銀の利上げが望ましいとみているようだと語った。
高市首相は昨年9月の自民党総裁選時に「金利を今、上げるのはあほやと思う」と発言した。その後は姿勢がやや和らいだものの、今月は「賃金上昇を伴った持続的、安定的な物価上昇の実現は道半ば」と述べ、日銀に慎重な政策運営を求める。
日銀の利上げを待って介入に踏み切る場合、予想外に利上げが遅れると、円安への投機的な動きを抑えることが難しくなる。オーバーナイト・インデックス・スワップ(OIS)によると、日銀の年内利上げ確率は約40%以下で、完全に織り込まれるのは来年4月以降となっている。
ジュリアス・ベアのアジア債券調査責任者、マグダレン・テオ氏は「高いインフレを示すデータが相次いでいるにもかかわらず、日銀が利上げを急がないなら、円売りポジションを大きく変える可能性は低い。こうした環境では、いかなる市場介入の効果も限定される恐れがある」との見方を示した。
— 取材協力 Masaki Kondo