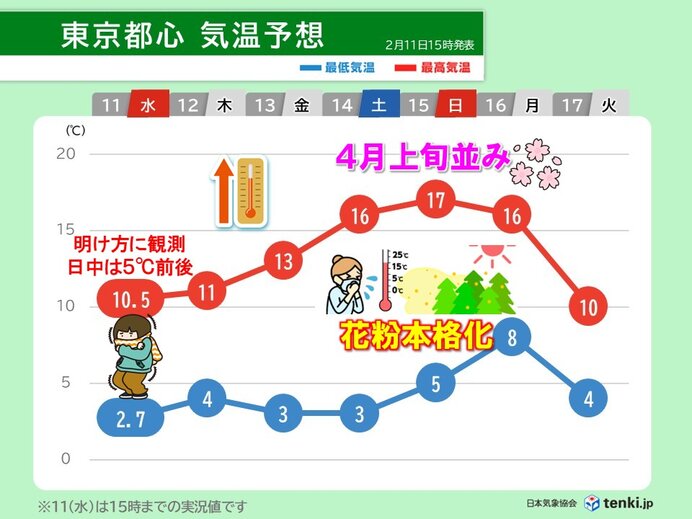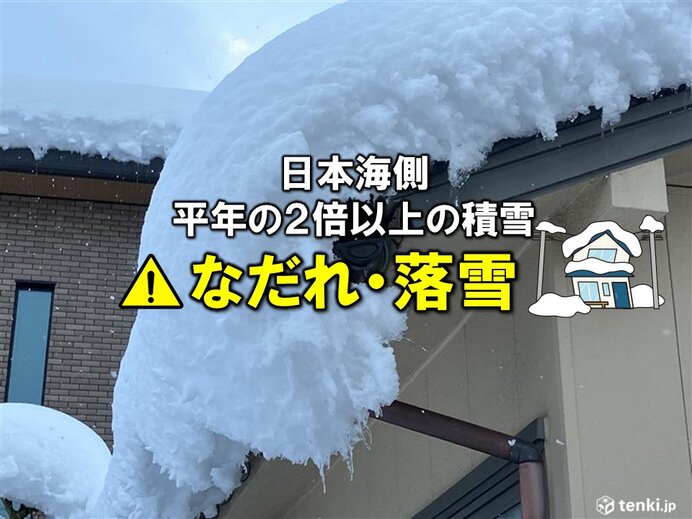「悪魔のような制度」自治医大・修学金等3766万円の“一括返済”巡り卒業生の医師が「違憲」主張 大学側は否定し“反訴”予告

地域医療の担い手を育てるはずの制度は、医師の人生を縛る“悪魔の契約”なのかーー。
8月6日、自治医科大学(栃木県下野市)の卒業生である医師のA氏(仮名)が、同大学の「修学金制度」は違憲・違法であるとして、同大学と愛知県を相手取り、債務の不存在確認と国家賠償請求を求めた訴訟の第2回口頭弁論期日が開かれた。
在学中、大学が総額2660万円を貸与
修学金制度は同大学特有の制度で、入学に必要な資金や授業料などの資金を学生へ提供し、卒業後に一定期間、「僻地(へきち)」等での勤務を求めるもの。
2015年に入学したA氏は同制度に基づき大学から2660万円を貸与されたが、指定勤務先を退職したことで、一括返済を求められていた。A氏は、この一括返済を求める法的根拠となっている契約の条項が憲法や法令に違反すると主張している。
この日は大学側と愛知県側が原告側の主張に対し反論。期日後に会見を開いたA氏は次のように述べた。
「他の大学の地域枠制度など、同様の問題で困っている方の一部は、私のように裁判といった手段を取るに至れないほど『つぶされてしまっている』現状もあります。
これから抜かりなく一つ一つ毎回主張を重ねていき、彼らの助けになるような結論が得られるまで、私自身もつぶれずに頑張っていきたいです」
狂いだした“キャリア設計”
自治医大は旧自治省(現総務省)が主導し、全国の都道府県によって設立されたという経緯を持つ。
大学の運営費用は都道府県からの負担金が中心となっており、全ての学生に、入学に必要な資金や授業料などの資金が「修学金」として貸与される。
この「修学金制度」では、同大学を卒業後、直ちに、大学側が指定する公立病院等に医師として勤務し、その勤務期間が貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間に達した場合、返還が免除される仕組みとなっている。
A氏は当初、経済的な理由から、学費の安い地元愛知県の国公立大学の医学部を目指していたというが、高校の教員からの勧めもあり、自治医大の併願を決めた。
しかし、そこからA氏の“キャリア設計”が狂いだした。
退職後、大学側が一括返済を要求「悪魔のような制度」
A氏は目指していた国公立大学の受験日に“かぶせられる”形で、愛知県庁に出向き自治医大の入学手続きをするよう指示されたという。
「自治医大の募集要項には国公立大の受験を禁じるなどと書いてあるわけでもなく、手続きの日程変更もお願いしましたが、断られてしまい、結果、私は国公立大学の大学受験を断念しました」(A氏)
A氏は卒業後、愛知県職員として研修医になったものの、父親の失職や就労困難な自閉症の弟、妻の妊娠による扶養負担増で経済的に困窮。
一般的な研修修了医師の場合、年収約900万円にプラスして、アルバイトで360万円程度が得られるとされるが、A氏の場合は地方公務員身分のためアルバイトは禁止されており、月収は約43万円に限られた。
A氏は弟の介護や収入面などをふまえ、毎年勤務先が変更される可能性のある指定公立病院等での勤務を継続することは厳しいと考え、2023年5月23日、愛知県に対して2024年3月31日で退職する旨の退職届を提出。
しかし、愛知県側は同日、A氏に対し、退職届を提出するのであれば、臨床研修修了医師となるために不可欠な知多厚生病院での臨床研修は継続できなくなると説明し、退職届の受理を拒否した。
ところが、同年8月末、県側から事実上の解雇(形式上は依願退職)を通告され、2024年3月末に病院を退職。結果、A氏は修学資金2660万円に加え、年10%の損害金1106万円(合計3766万円)の一括返済を求められた。
こうした経緯から、A氏は自治医大側と愛知県側を提訴。今年3月5日に行われた提訴時の会見では「無知な受験生を囲い込んで、卒業後、退職の自由を奪った上、不当な労働条件で使いたおす、まさに悪魔のような制度」と非難し、代理人の伊藤建弁護士も「医師不足解消は大事だが、手段は適法でなければならない」と強調した。
→「無知な受験生を囲い込む、悪魔のような制度」自治医大の修学金貸与制度巡り卒業生の医師が提訴
「最大の問題点は細部の説明不足」
もちろん、A氏自身、自治医大が僻地医療に携わる医師を充足させるための大学だと、受験前から十分認識はしていた。
「この大学を受験し、合格した際には、将来僻地医療で役立つ医師になるのだろうなと、高校生ながらに考えてはいました。
国公立大学の受験を断念せねばならなかったという葛藤もありましたが、最終的にはその点については分かった上で受験・入学をしています。
ただ、今回私が問題に思ってるのは、卒業後の細かい労働条件等についてはあまり説明がされなかった点や、在学中に卒業後のキャリアについて、後出しのような形で、診療科が選べなくなったといった点です。
加えて、入学の前に、具体的な給料の話や将来の勤務先となる、病院の候補についての説明もおぼろげにはあったかもしれませんが、そもそも勤務先を自由に決める予知はなく、どこかを希望したとしても、勤務先は県の『鶴の一声』で変えられてしまう、という細かい説明まではありませんでした。
こうした説明不足が私の考える最大の問題点です」
原告側「居住・移転の自由等に違反するおそれ」指摘
原告側が主張する争点は大きく3つの論点に分かれる。
第一に、A氏が勤務する病院を一方的に指定し、そこでの勤務を強いるのは、居住・移転の自由(憲法22条1項)等に違反するのではないかという論点だ。
第二に、労働基準法14条1項では、労働契約について、医師の場合は期間の定めのないものを除き原則として5年を超えてはならないと定めているにもかかわらず、原告の場合は10年以上の拘束が要求されているという問題だ。
第三に、労働基準法16条では「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と定めており、「退職する場合にはお金を払え」といった規定を設けることは禁じられている。
また、原告側は上記の論点と併せて、損害金とその利息についても違法であると主張。一般的な奨学金と比べて、10%と高い利息が定められている点や、損害賠償の予定あるいは違約金について、平均的な損害を超える部分については無効と定めている消費者契約法9条1項などに反することなどを理由として挙げている。
大学側は違憲性を否定
この日行われた会見では、被告側の主張の一部について原告側から解説、および反論が行われた。
まず大学側は居住・移転の自由(憲法22条1項)の論点について、私立大学であり、憲法が適用されないと主張。仮に適用されるとしても、私立大学には広い裁量があり、建学の精神が尊重されるとした。
また、A氏の勤務先を指定するのは愛知県であり、大学側は居住・移転の自由を侵害していないとの姿勢を見せた。
一方、伊藤弁護士によると、愛知県側の書面には居住・移転の自由に関する記載が不十分だったといい、今後の訴訟で補充するよう求めていくという。
「われわれの主張との間にボタンの掛け違いが生じている」
続いて、労働基準法16条に関して大学側は「(A氏の)使用者ではない」と説明。使用者はA氏の勤務先である病院、もしくは愛知県だと主張し、同条文は適用されないとした。
「文言に当たらないからといって、直ちに当該条項が適用されないのか、というと、事実関係として、高額な利息と損害金が、ある種の人身拘束的な効果を持っていることからすると、形式的な使用者ではなかったとしても、同条の類推適用が認められる予知があると考えています」(伊藤弁護士)
大学側は「医師免許の取得と大学の業務には関係性がない」との主張も展開。
「過去の複数の判例では、業務関連性がある資格等を取得させて、その費用を労働者に負担させるというのは違法だと示されている一方、『会社に勤めていたひとが、会社の費用で留学し、その後すぐ辞めました』といったケースの場合は業務の関連性がないので、費用を返還する必要があると判断されてきました。
しかし、むしろ自治医大は学生に医師免許を取得させるために、都道府県がお金を出して作った大学であり、大学の設置目的と医師免許の取得の関係性は『大あり』だと考えられます」(同前)
消費者契約法の面についても、大学側は修学金制度について「本件契約は金銭消費貸借契約であり、準委任契約ではないから、義務を加重するものではないし、指定公立病院等で勤務しなかった場合、原則どおり返済をすることを求めるものだ」などと原告側に反論。
この点について伊藤弁護士は「本件契約は単にお金を貸すという契約ではなく、労働した場合には返済の免除をするものになっており、労働という義務が実質的に課せられている」として「われわれの主張との間にボタンの掛け違いが生じている」とした。
大学側は反訴を予告「極めて正当な権利行使だが…」
また、大学側は今回、原告側に対して反訴を予告。
「反訴を提起すること自体は、極めて正当な権利行使だが、大学側のスタンスとしては疑問が残ります。
これまでもお金を返すよう形式的なものが送られてくることはありましたが、強制力の伴うものはほとんどありませんでした。
これが裁判で問題提起をし、われわれが『出る杭(くい)』となった瞬間にあちらも裁判で訴えてくるというのは、Aさんの家庭の事情等を考慮したときに、社会的に考えて、ひどい仕打ちだと、私は言いたいです」
次回期日は10月20日で、伊藤弁護士とA氏による意見陳述を予定している。
なお、自治医大側は弁護士JPニュース編集部の取材に対し「係争中のことであり個別にコメントすることは差し控えたい」と回答した。