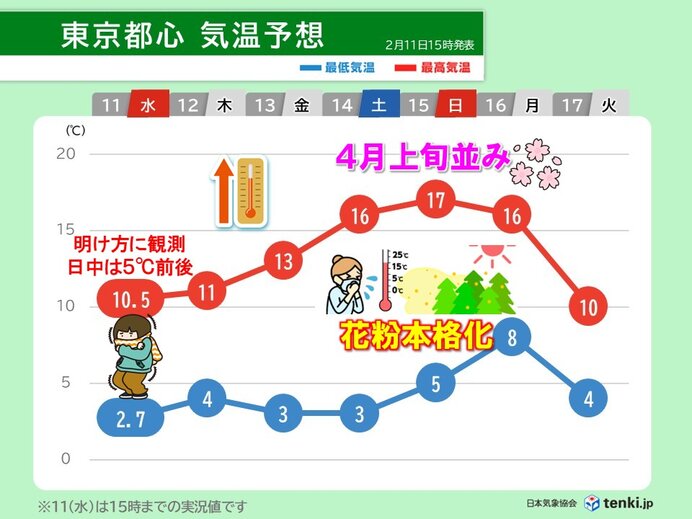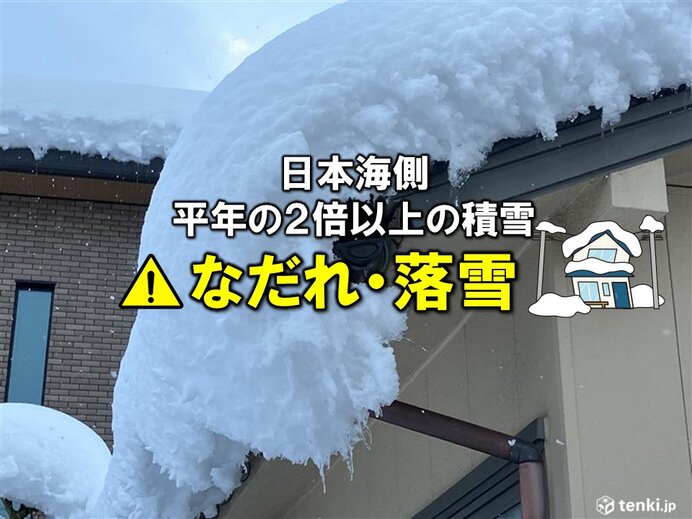「外国人への生活保護は“判例”で憲法違反」は“悪質なデマ”!? 最高裁は何を判示したか【行政書士解説】

インターネット上では昨今、「外国人の生活保護受給」について、常に議論が巻き起こっています。
その中でよく目にするのが「外国人が生活保護を利用することは最高裁で『憲法違反』との判決が出ている」といった内容のもの。一部でまことしやかに流布されています。この言説が「根拠」として挙げるのは、2014年(平成26年)の最高裁判決、俗に「永住外国人生活保護訴訟」と呼ばれる裁判の判決です。
しかし、実は、この判決からは、どこをどう読んでも外国人の生活保護受給を「憲法違反」だなどということは出てきません。もし、判決文を本当に読んだうえでなお上記主張を行うのだとしたら、悪質なデマといわざるを得ません。それどころか、そもそもの事案は「外国人だから」という理由で生活保護申請を却下したものではありませんでした。
改めて、どういう事案だったのか、そして裁判所の判断がどのようなものだったか、実際の事案と判決を紹介しつつ説明します。(行政書士・三木ひとみ)
生活保護の申請が却下された理由は「外国人だから」ではなかった
この永住外国人生活保護訴訟(最高裁平成26年(2014年)7月18日判決)の判決文は、法務省訴訟局の「訴訟重要判例集データベースシステム」で検索すれば、一審・二審の判決文、および「解説」とともに確認できます。
まず、事案を説明します。
原告のXさんは1932年に日本で生まれ、日本の学校に通いずっと日本で暮らしていました。中国国籍であり、「永住者」の在留資格を持っています。同じく中国国籍で永住者の夫・Aさんがおり、夫婦で料理店を営んで生活していました。
ところが、1978年(昭和53年)頃、Aさんが体調を崩し仕事ができなくなったため、Aさんとその父(故人)が所有していた駐車場と建物の賃貸収入で生活するようになりました。
その後、Aさんは認知症を患い、2004年(平成16年)頃から入院していたところ、2006年(平成18年)頃からAさんの弟B(Xさんにとっては義弟にあたる)がXさんの家へ引越し生活を共にするようになりました。
以後、XさんはBから頭を叩かれる、暴言を吐かれる、預金通帳や印鑑を取り上げられるなどの虐待を受けました。そこで、生活に窮したXさんは、2008年(平成20年)大分市に対して生活保護受給申請を行いました。しかし、預金残高が一定程度あることを理由に却下されました。
却下の理由はあくまでも「預金残高が一定程度あること」です。「Aさんが外国人だから」ではありません。
大分市の事実認定に問題あり…結果的に受給できた
本件ではそもそも、Xさんの生活保護申請を却下した前提となる事実認定に問題がありました。
一般論として、「預金残高が一定程度あること」を理由に生活保護申請を却下することは何らおかしくありません。
問題は、Xさんが夫の弟のBに通帳や印鑑を奪われた状態だったことです。
この通帳が、XさんAさん夫妻唯一の収入である賃貸収入の振込先だったため、1円たりとも引き出す事ができなくなっており、実質無収入状態に陥っていたのです。
Xさんが通帳を再発行し、印鑑の変更を届け出れば済む問題でもありませんでした。以下のような複雑な事情があったからです。
まず、Aさんの弟Bは、亡父名義の土地の相続問題が解決していないとして、以下のような主張をしていました。
- Aさんより、預金等を含め資産全ての管理を任された
- 賃貸収入の内訳の一つはAさんの亡父名義の土地(駐車場)を賃貸して得られた収入であり、亡父の相続財産を形成している(※)
- 駐車場とAさん名義の建物の敷地は亡父名義であり、AさんとBも含む相続人3名の協議により遺産分割がされている
※当時、不動産について相続が発生した場合に、登記費用の節約等のため、遺産分割が完了するまで登記名義を故人のままにしておくケースはよくあり、違法ではありませんでした(2024年4月施行の不動産登記法改正により相続登記が義務化され、現在は認められていません)。
また、Bが主張する亡父の遺産の相続問題については、AさんとB以外にもう一人の相続人が外国に居住しているため、解決のめどが立たない状況でした。
この状況では、Xさんが通帳を再発行し、印鑑の届出を行ったとしても、預貯金から生活費等を引き出すと、BがXさんに対し、自身の相続分の侵害に基づく不当利得返還請求ないしは損害賠償請求をするリスクがありました。
上記のような事情により、Xさん名義の預貯金・扶養者である夫Aさん名義の預貯金があっても生活費としてはまったく使えない状態だったのです。
もちろん、Xさんがこれらの事情を説明しなかったわけではありません。生活保護申請を行った際、Xさんに同行した支援センター関係者がこれらの事情を説明し記録もされました。ところが、それらは資産調査で考慮されず、申請が却下されました。
このように、大分市がXさんの生活保護申請を却下した際に、Xさんが「外国人」であることは一切問題となりませんでした。あくまでも、大分市の事実認定に問題があったということです。
なお、最終的に最高裁の判決が出るより前の2011年(平成23年)10月に、Xさんは、生活保護の開始決定を受けることができました。これは、大分市が改めて事実関係を精査し、Xさんが無資産・無収入の状態であると認定したからだとみられます。
もちろん、大分市は外国人が生活保護を受給すること自体を問題視していません。
「外国人の生活保護受給権」が“なぜ”訴訟で問題になったか
ではなぜ、「外国人の生活保護受給権」が問題になったのでしょうか。ややこしいのですが、問題を理解するうえできわめて重要なポイントなので、説明します。
わが国の訴訟制度では、「客観的予備的併合」といって、第1希望の「主位的請求」が認容されなかった場合に、第2希望以下の「予備的請求」について判断がなされるという形で審査してほしい優先順位をあらかじめ指定して訴えを提起することが認められています(行政事件訴訟法7条、民事訴訟法136条参照)。
そして、Xさんが生活保護の受給を求めて提起した訴訟も、「主位的請求」と「予備的請求」と段階的に審査を求める内容でした。
Xさんは主位的請求として、「生活保護法による保護」開始の義務付け訴訟(行政事件訴訟法3条6項2号)を、生活保護申請却下処分の取消訴訟(同条2項)とワンセットで提起しました(※)。
※必ず「取消訴訟」と併合提起することが義務付けられています(同法37条の3第3項参照)
そして予備的請求として、「生活保護法に基づく生活保護基準に従った保護」の給付などを求めて出訴しました。
主位的請求での「生活保護法による保護」と、予備的請求での「生活保護法に基づく生活保護基準に従った保護」とでは、法的な意味合いが大きく違います。
前者の「生活保護法による保護」は、外国人の生活保護受給権が「憲法・生活保護法により保障されている」ことを前提とするものです。「保障される」とは、生活保護申請が却下された場合に、訴訟等によって「違法じゃないか」と是正を求められるという意味です。
これに対し、後者の「生活保護法に基づく生活保護基準に従った保護」は、外国人の生活保護受給権が主位的請求の審判で「憲法・生活保護法により保障されない」とされた場合、「生活保護に準じる保護」が「恩恵として」与えられることになります。
「違法性」を争うには「権利の保障」が必要だった
「恩恵」とされると、国には法的義務がないため、生活保護法に従っていなくても「違法・適法」の問題はそもそも生じません。裏を返せば、訴訟等によっていきなり「違法じゃないか」と是正を求められないということです。
このように、「憲法・生活保護法により保障される」のと、「保障されないが恩恵によって保護を与えられる」のとでは、大きく違うのです。
だからこそ、外国人であるXさんは、「違法な処分」の是正を訴訟によって求めるため、「生活保護受給権が憲法・生活保護法により保障されている」点をまずは主張する必要があったのです。
現にXさんは訴訟提起前に、大分県知事に対し、行政上の不服申し立ての制度である「審査請求」を行いましたが(生活保護法69条参照)、外国人には生活保護受給権が法的に保障されないことを理由に却下(門前払い)されています。
いずれにしても、「外国人に生活保護を【受給させること】が憲法に違反するか」ということは一切、争点になっておらず、原告も被告も問題視していません。また、裁判所もその点については一切判断せず、むしろ、「憲法に違反しない」ことを当然の前提としています。
外国人に生活保護を受給させる「基準」とは
現行制度において、外国人に対する生活保護は、1954年に厚生省(現・厚生労働省)から発出された「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)という通達に則って行われています。
2025年4月現在、「生活保護に準ずる保護」を受けられるのは下記の在留資格に該当する外国人のみです。
- 身分系在留資格(永住者、定住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等)
- 特例法の特別永住者(在日朝鮮人、在日韓国人、在日台湾人)
- 入管法上の認定難民
これら以外の在留資格では生活保護の受給はできません。また、難民認定申請中の人も対象外です。
あくまでも、対象は「日本人と同じ生活実態を有し、日本人と同様に税金や社会保険料を納めることになっている人」「人道・国際協調主義の見地から日本人と同等の保護を与えるべき人」に限られています。
もちろん、その際、「資産」「収入」については生活保護法と同様の基準により審査されます。一部でまことしやかに流布している「外国人は基準が緩い」や「受給しやすい」などの事実は、それを裏付ける証拠も含め、存在しません。これが厳然たる事実です。
Xさんは本来、「資産」「収入」の基準に該当しているにもかかわらず、行政の事実認定の誤りによって、申請が認められなかったのです。そして、繰り返しますが、結果として、Xさんは生活保護の開始決定を受けることができました。
最高裁の判決は生活保護受給権が「法的に保障されない」と言っているのみ
では、最高裁判決の内容は実際にはどのようなものだったのでしょうか。実際の判決文を引用します。
「現行の生活保護法は、1条及び2条において、その適用の対象につき『国民』と定めたものであり、このように同法の適用の対象につき定めた上記各条にいう『国民』とは日本国民を意味するものであって、外国人はこれに含まれないものと解される。
(中略)
したがって、生活保護法を始めとする現行法令上、生活保護法が一定の範囲の外国人に適用され又は準用されると解すべき根拠は見当たらない。
また、昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知は行政庁の通達であり、それに基づく行政措置として一定範囲の外国人に対して生活保護が事実上実施されてきたとしても、そのことによって、生活保護法1条及び2条の規定の改正等の立法措置を経ることなく、生活保護法が一定の範囲の外国人に適用され又は準用されるものとなると解する余地はない。
外国人は、行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得るにとどまり、生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく、同法に基づく受給権を有しない。そうすると本件却下処分は、生活保護法に基づく受給権を有しない者による申請を却下するものであって、適法である」
生活保護法の適用に関する判断をまとめると、以下の通りです。
- ①生活保護法の対象に外国人は含まれない(Xさんに「生活保護法に基づく受給権」は保障されないので、申請却下処分は適法)
- ②生活保護法1条・2条の改正等の立法措置がなければ、同法を一定の範囲の外国人に適用・準用する解釈の余地はない
この判示を読む限り、「憲法違反」という言葉は一言も登場しません。
また、そもそも①の「外国人には生活保護法に基づく受給権が保障されていない」と、「外国人に生活保護受給させることは憲法上禁止されている」とは、まったく意味が異なり、なんらの論理的関係も存在しません。
それどころか、②によると、生活保護法の改正等の立法措置が行われれば、同法を一定の範囲の外国人に適用、準用する余地があるということです。「憲法上禁止されている」との解釈は出てきようがありません。
それに加え、外国人は行政庁の通達等に基づく「行政措置による事実上の保護」の対象となり得るとの判示もしています。また、「行政措置として一定範囲の外国人に対して生活保護が事実上実施」されてきたことを問題視さえしていません。
あくまでも、行政の解釈基準である「通達」によって上位規範である「法律」の効力を決めることは許されない、という当たり前の法原則を言っているにすぎません。
このように、実際の最高裁判決を読めば、「外国人が生活保護を利用することは最高裁で『憲法違反』との判決が出ている」という言説が悪質なデマであることは明らかです。
インターネットが普及し、情報が氾濫するようになった今日、根拠のないデマがあたかも真実であるかのように流布し、人の生命さえもが脅かされる事態が現実のものになっています。上記デマについていささかなりとも信ぴょう性があると思ったことのある人は、そのことについて想像力を働かせて猛省するとともに、客観的裏付けをもって情報を取捨選択することを心掛けてもらいたいと切に願います。
三木ひとみ行政書士(行政書士法人ひとみ綜合法務事務所)。官公庁に提出した書類に係る許認可等に関する不服申立ての手続について代理権を持つ「特定行政書士」として、これまでに全国で1万件を超える生活保護申請サポートを行う。著書に「わたし生活保護を受けられますか(2024年改訂版)」(ペンコム)がある。
Page 2
行政書士法人ひとみ綜合法務事務所所属。 1981年横浜生まれ。3歳で両親が別居し離婚。鬱を患った母と暮らす。同級生からいじめに遭うが、勉学に励み交換留学生として1年間渡米。帰国後、英検1級合格、国際基督教大学教養学部語学科入学、在学中に未婚の母となる。一般企業に入社。その後ストーカー被害に遭いシェルターに入所。無職無収入となるも、水商売や翻訳業で生計を立てながら 2015年行政書士試験合格。
Page 3
行政書士法人ひとみ綜合法務事務所所属。 1981年横浜生まれ。3歳で両親が別居し離婚。鬱を患った母と暮らす。同級生からいじめに遭うが、勉学に励み交換留学生として1年間渡米。帰国後、英検1級合格、国際基督教大学教養学部語学科入学、在学中に未婚の母となる。一般企業に入社。その後ストーカー被害に遭いシェルターに入所。無職無収入となるも、水商売や翻訳業で生計を立てながら 2015年行政書士試験合格。