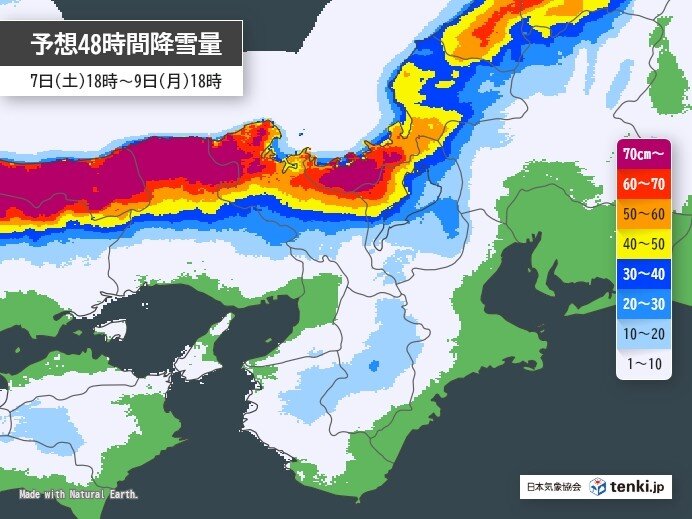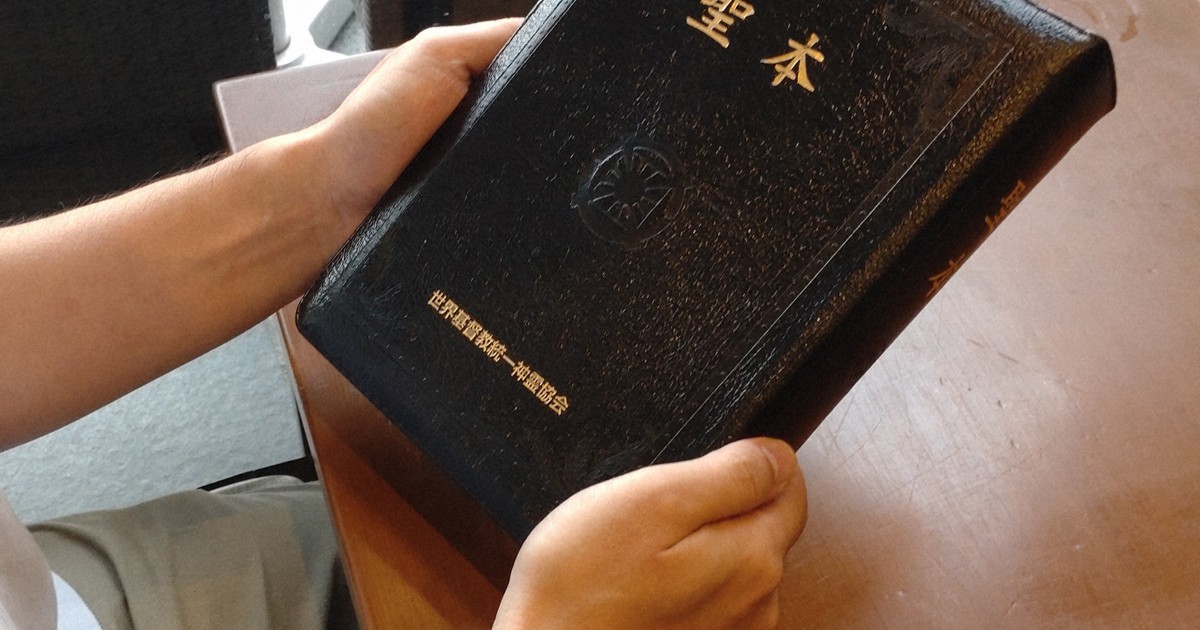「もっと稼げる」との考えか? 揺れる高知県立美術館をめぐり、館長や識者に意見を聞く。県の指定管理公募化の方針に、事業や雇用の継続性を不安視する声が続出

指定管理者「直指定」を県が変更方針。ミュージアムのあり方をめぐり議論が続いている。牧野植物園や坂本龍馬記念館なども対象
高知市にある高知県立美術館が、県による指定管理の運用を巡り揺れている。県が同館など5つの県立文化施設について、管理者を直接指名する「直指定」から民間事業者を含む公募にする方針を打ち出したためだ。県は自主事業の拡大による収益増を目指し職員の待遇改善につなげたいとするが、対象施設や識者から事業や雇用の継続性を不安視する声が続出。7~8月に実施された県パブリックコメント(意見公募)には県内外から約300の団体や個人が意見を寄せ、波紋が広がっている。
1993年に開館した高知県立美術館は、国内有数のシャガール・コレクションをはじめ、近代・現代の美術家や郷土関連の作品など4万1000点超を所蔵し、国内外の多様なジャンルの展覧会を開催してきた。2013年には世界的写真家の石元泰博が遺した作品と資料を核とする石元泰博フォトセンターを開設し、幕末の絵師「絵金」や画家の合田佐和子、コラージュ作家の岡上淑子、具体美術協会の結成メンバーの正延正俊の展覧会を企画するなど、高知ゆかりの美術家の調査研究と紹介に貢献。館内にホールも併設し、本邦初演を含むパフォーミングアーツや映画の様々なプログラムにも取り組む。
2025年2月8日〜4月13日に開催された「浜田浄 めぐる 1975-」展の会場風景 撮影:編集部同美術館は開館以来、外郭団体の県文化財団が学芸業務を含む運営を行ってきた(2005年度まで管理運営委託、以後5期にわたり指定管理者、現指定期間は2029年まで)。同文化財団は同じく公募対象とされた坂本龍馬記念館の運営も行っている。
ほかに県が公募対象とするのは、牧野植物園(県牧野記念財団)、高知城歴史博物館(土佐山内記念財団)、のいち動物公園(県のいち動物公園協会)=カッコ内は現在の指定管理者。いずれも資料保管と調査・研究、展示・教育の機能を持つ施設で、県の文化振興と郷土の歴史や自然環境の保全に大きな役割を担ってきた。
県は、今月19日に開会する9月定例県議会で諮った後、最終方針を決定する予定。対象5施設のうち、高知城歴史博物館がもっとも早く指定管理期間が今年度末に終わり、今秋にも公募による管理者選定が始まる見通しだ。
牧野植物園 撮影:編集部高知県の濱田省司知事は今年6月の定例県議会で、一定規模の集客が見込まれる県有施設は現在管理者になっている外郭団体の管理運営に対する県関与を縮小し、団体の自律性向上を目指す方向性を表明。知事の記者会見記録によると、直指定された管理者は県が払う管理代行料と利用料金から管理業務費を引いた剰余金を県に納付する必要があるが、公募導入後はその納付を免除し管理者の自由度を高め収益を上げやすい枠組みにする。公募での選考は、第三者が入った委員会が審査し、施設の専門性や事業の継続性はそれらを重視した配点基準を設け担保したいとしている。
濱田知事は8月29日の会見で、約1ヶ月間実施したパブリックコメントは文化施設に収益性を求めることへの反対意見や職員の雇用の継続性を不安視する声が多かったと述べ、「誤解を受けている面もあると思うので、しっかりと説明し、あるいは対策を講じていく」と説明。雇用不安は、公募の応募要件を検討するなどして解消に努めたいと話した。施設収益が増えた場合に県が管理代行料を切り下げる可能性に関しては、知事は短期レベルでは否定したものの、「10年、20年先になると、また話が違うかもしれない」(7月17日会見)としている。
2003年に導入された指定管理者制度は、公募が原則だが、高度な専門性や継続性の確保が必要な場合は管理者の直指定も可能で、多くの自治体がミュージアム運営に直指定を取り入れている。東京都や横浜市のように、公募から直接指名する方法に切り替えた例もある。逆のケースは近年、美術館はあまり例がなく、その点でも注目されるようだ。
急な方針転換、困惑する現場
安田篤生・高知県立美術館館長に本件について聞いた。安田館長は、滋賀県立近代美術館でキャリアをスタートし、原美術館(東京)在職中に現代美術家の個展を多数企画し、原美術館副館長や奈良県立美術館副館長を経て、2024年4月に現職に就任した。なお、同美術館は開催中の展覧会「再考《少女と白鳥》第1期 贋作を持つ美術館で贋作について考える」が話題を呼んでいる。
安田篤生 高知県立美術館館長 撮影:井戸宙烈安田館長は取材に「県から県文化財団に指定管理者を公募にする方向性が伝えられたのは方針を変更した少し前で、急な方針転換に財団も館職員も困惑している。県立美術館と坂本龍馬記念館は、いずれも比較的予算規模が大きく、入場者数もある程度確保できるので、県側は『もっと稼げるのでは』と考えたのかもしれないが、そもそも美術館は収益目的の施設ではない。国際組織のICOM(国際博物館会議)の定義でも、ミュージアムは『社会のための非営利の常設機関』と位置付けられている」と回答。
また安田館長は、県が目指す収益改善については、「美術館や博物館はどこも基本的に財政は厳しいが、当館も管理代行料以外に助成金を最大限活用し寄付金を集め、可能な限り経費削減にも努めて運営が成り立っている。公募を導入しても収益増は現実的でないと考える」と指摘。「文化遺産を次世代に伝える役割を担う美術館は、運営に長期的な継続性が必要で、原則5年で管理者が変わり得る公募制はその妨げになりかねない。公募の導入は、学芸員らの雇用不安を招き、離職につながる恐れがあり、優秀な人材が集まりにくくなる」と強調した。
同美術館と坂本龍馬記念館を運営する県文化財団は、公募化に対する意見を8月6日に県に提出。のいち動物公園協会は、施設の専門性や職員の雇用安定のため「継続的に運営が出来るという担保が必要」とする意見書を同4日に県に提出し、協会HPにも掲載した。
識者「まず十分な議論が必要」
土佐が発祥地の自由民権運動の歴史を伝える高知市立自由民権記念館の筒井秀一館長は、「なぜいま公募に切り替えるのか、唐突感があり県の根拠もはっきりしないと感じる」と話す。筒井館長は、県下の文化施設で構成する「こうちミュージアムネットワーク」会長や県立美術館運営委員も務め、文化行政に詳しい。
筒井館長は「地域の文化資料は住民のアイデンティティと活力の源泉で、観光振興や県外からの移住促進にもつながる。自治体は長期的視野に立ち、より地域の魅力や価値を高める継続性がある文化施策を推進するべきだ。公募化により施設が収益追求に追い込まれ、公益性や非営利の社会教育施設であるミュージアム本来の役割が損なわれないかと懸念している」と述べた。防災対策の問題にも言及し、「30年以内に高い確率での発生が予測される南海トラフ地震は、地震と津波の襲来により県内の貴重な文化遺産が多数被災することが予想される。そうした文化財の救出や回復に、ミュージアムは重要な役割を担うことができる」と指摘した。
文化行政の基本方針をまとめた高知県文化芸術振興ビジョンの評価委員のひとりは、「事前に県から評価委員会に相談はなく、専門家や現場へのヒアリングもなかったと聞く。十分な議論や検討がされないまま、文化施設に多大な影響を与える指定管理者制度の運用変更は遺憾に思う」と話した。
本件は、SNS上でも議論を喚起。「事業者同士を競争させ、『稼ぐ施設』にするという発想が残念」「博物館や美術館は本来無償でよく、金儲けの必要はない」「社会に必要な施設を維持するのが行政の役割」など様々な意見が上がっている。直指定は不公平感があるとの指摘、文化施設でも赤字は許容できないといった意見もある。
なお9月11日付の高知新聞によると、県は高知城歴史博物館の山内家資料の保存・管理に限って現運営団体の土佐山内記念財団に委託する方針を固めた。土佐藩を治めた山内家が伝来の宝物など資料一式を県に寄贈・寄託などした経緯があるための措置で、来年度以降は公募と委託の2団体が同博物館を運営する可能性が浮上。県が打ち出した公募導入は、序盤やや迷走気味で、今後が注目される。
ながた・あきこ 美術ライター/ジャーナリスト。1988年毎日新聞入社、大阪社会部、生活報道部副部長などを経て、東京学芸部で美術、建築担当の編集委員を務める。2020年退職し、フリーランスに。雑誌、デジタル媒体、新聞などに寄稿。