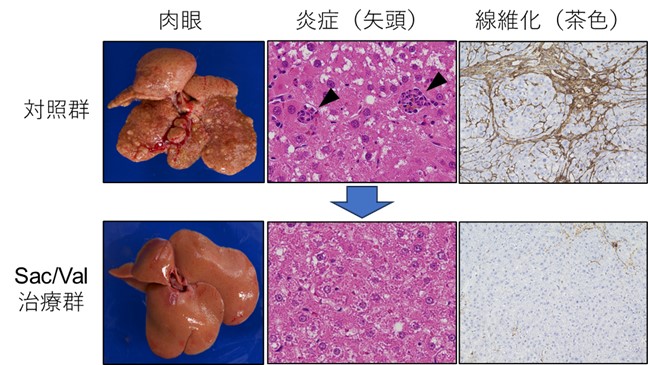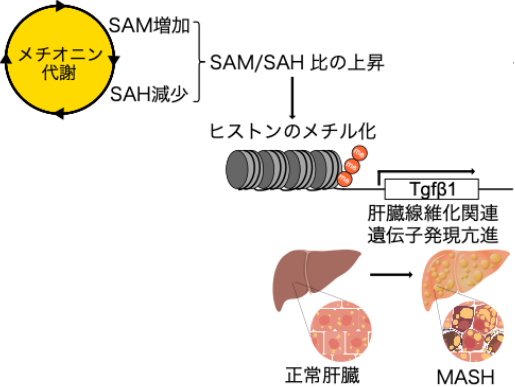ビタミンCでもBでもミネラルでもない…日本人のほとんどが不足している「記憶・集中力アップ」の栄養素(プレジデントオンライン)

10:17 配信
「なんとなく集中できない」「だるい」。最近、学生や社会人の中にはこのような訴えが増えているという。ナビタスクリニック川崎院長の内科医・谷本哲也さんは「そうした症状の要因のひとつに、日本人に見過ごされがちなある栄養素がある。外国では、この栄養素の血中濃度を測定する人も多い」という――。 例えば、机に向かって勉強に励む受験生。両親ができることは食事づくりなどの後方支援です。多くの親御さんは「うちの子にはしっかり食べさせているから栄養もばっちり足りているだろう」と思っているかもしれません。確かに現代の日本は、かつてないほど食に恵まれた時代で、スーパーやコンビニには多様な食品が並び、なんでも選ぶことができます。 ところが、こうした食の豊かさの裏には意外な盲点が潜んでいます。子供も大人も隠れた栄養不足があるのです。つまり、カロリーは足りていても、健康維持に欠かせない栄養素をしっかり摂取できているとは限らないのです。 内科医の私のところにやってくる受験生や社会人には、「なんとなく集中できない」「だるさがある」「風邪を何度も引いてしまう」と訴える方が少なくありません。しかし、診察しても特段問題なく、一般的な血液検査でも貧血などの異常は特に見つかりません。その症状の要因は個人によって異なりますが、私は重要な栄養素のひとつである「ビタミンD」不足が関係している可能性がある、とにらんでいます。■太陽の光から作られる特別なビタミン ビタミンDは「太陽のビタミン」と呼ばれます。日光に含まれる紫外線(UVB)を皮膚に浴びることで、私たちの体内で自然に作られるからです。これは他のビタミンとは異なる、非常に特徴的な性質です。 ビタミンDは食事から摂ることもできます。特にサケやサバなどの脂ののった魚、卵黄、干しシイタケなどがビタミンDを豊富に含みます。しかし、現代の子供たちの食卓では、これらの食材が以前よりも少なくなってきています。ビタミンDが添加された食品(強化食品)は欧米では一般的ですが、日本ではあまり普及していません。そのため、ビタミンDの多くはやはり「日光」か「魚やきのこ」などの食材から摂る必要があるのです。
体内で作られたビタミンDは、肝臓と腎臓で活性型に変わり、骨の健康を保つことは有名な話です。しかし、役割はそれだけでなく、最近では免疫機能や脳の働きにも関与することがわかってきているのです。私の外来には海外出身の方も多く受診されますが、「ビタミンDを測定してほしい」という要望が非常に多いのに気づきました。海外に比べ日本ではそれほど注目されていませんが、最近の医学専門誌で特集記事が組まれていたこともあり、私もビタミンDに改めて注意するようになりました。
■なぜ受験生がビタミンD不足になりやすいのか とりわけ心配なのが、子供たちです。一見、彼らは十分に日光を浴びているように思えるかもしれません。ところが、現実は少し違います。受験期の中高生の生活を想像してみてください。朝から学校へ行き、放課後は塾に直行し、夜遅くまで部屋にこもって勉強をします。こうした生活では、太陽の出ている時間に外に出る機会がほとんどありません。 さらに、冬は日照時間が短く、紫外線も弱くなります。通学時に日差しを浴びる程度では、ビタミンDの生成には十分でないことが多いのです。服装の面でも、制服やコートで肌の露出が少なく、特に女の子は日焼けを避けて日焼け止めを使う傾向が強いため、紫外線をブロックしてしまいます。 食習慣も影響しています。かつての和食は、焼き魚やみそ汁、野菜やきのこを中心とした、微量栄養素に富んだ食事でした。しかし、現在ではパンやパスタ、肉料理などの「洋食化」が進み、家庭でも魚が食卓に上る頻度が減ってきています。実際、農林水産省のデータでは、日本人における食用魚介類の消費量はこの20年で半減していることが報告されています。結果として、ビタミンDの摂取量はかつてよりも少なくなっているのです。 厚生労働省の「令和5年国民健康・栄養調査」によると、10代の若者のビタミンD摂取量は平均で1日あたり5〜6マイクログラム程度でした。これは、日本の推奨量の8〜9マイクログラムを大きく下回っています。特に冬の時期には、紫外線も少ないため血中のビタミンD濃度が低下しやすくなります。つまり、受験勉強に最も集中すべきこの時期に、実は多くの受験生が「気づかないビタミンD不足」に陥っている可能性があるのです。■脳、気分、免疫に与える影響 ビタミンDの役割は骨を丈夫にするだけではありません。近年、脳の中にビタミンDの受容体があることが分かり、学習や記憶、感情のコントロールにも関わっていると考えられ始めています。ある研究では、ビタミンDの補給により血中濃度が高い10代の若者は、記憶力や集中力を問うテストで良い成績を残し、気分も安定していたと報告されています。 また、冬に気分が落ち込みやすくなる「冬季うつ(季節性情動障害)」とも関係があるのではないかと考えられています。日光に当たらないとビタミンDが不足し、それが気分の落ち込みにつながる可能性があるというのです。 さらに、ビタミンDは免疫機能にも深く関わっています。2017年にイギリスの医学誌に発表された大規模な研究では、ビタミンDのサプリメントを定期的に摂取することで、風邪やインフルエンザなどの急性呼吸器感染症のリスクが下がることが示されました。
特にビタミンDが著しく不足している人においては、その効果が顕著でした。血中濃度が10ng/mL(ナノグラムパーミリリットル)以下の人がビタミンDを補うことで、呼吸器感染症のリスクが半分近くにまで下がったとも報告されています。つまり、ビタミンDの欠乏状態を改善することは、冬に流行する感染症を予防する上でも意味のある対策になるのです。
■受験生のビタミンDは足りている? では、受験生はもちろん、社会人も含めビタミンDを十分に摂れているかをどうやって判断すればよいのでしょうか? 最も確実なのは「25-ヒドロキシ(OH)ビタミンD」という血液検査で、体内のビタミンDの貯蔵状態を知ることができます。 数値はng/mLで表され、一般的には30ng/mL以上であれば「十分」、20〜30ng/mLが「不足」、20ng/mL未満は「欠乏」とされます。さらにアメリカでは、20ng/mLあれば健康維持には十分とされていますが、骨と筋肉の健康を最大限に引き出すために30ng/mL以上が望ましいと推奨されています。 ただし、日本で日常的に25-ヒドロキシビタミンDの検査を受けることはあまりなく、骨粗鬆症など明らかな問題がなければ医療機関でもわざわざ検査は行いません。そもそもビタミンD不足の症状は非常にわかりにくいのです。なんとなく疲れやすい、風邪をひきやすい、気分がすぐれない。こうした曖昧な不調は、受験勉強中や仕事のストレスや睡眠不足のせいだと思われがちですが、実はビタミンD不足が隠れている場合も考えられます。 実は50代の私自身も、今回25-ヒドロキシビタミンDの測定をしてみたところ、見事に欠乏状態でした。実際、ある調査では受験生に限らず現代日本人のほとんどでビタミンDが不足していたことが発表されています。日本の一般診療では自費検査になることが多いのですが、数千円程度の費用なので気になる方は医療機関で検査してもらってもよいかもしれません。■家庭でできるビタミンDを補う対策 幸い、ビタミンDを補うのは決して難しくありません。生活の中で少し意識するだけで、十分に改善できる栄養素です。 まずは「日光を浴びること」。冬の昼間に、顔や腕を15〜30分程度日光に当てるだけでも、体はビタミンDを合成します。肌の露出が少なくても、通勤通学時になるべく日差しを受ける、昼食後に短い散歩をするなど、日常の中に太陽光を取り入れる工夫が効果的です。もちろん、日焼けや皮膚がんへの懸念がある場合は、朝や夕方の弱い日差しを利用したり、紫外線の強い夏場には時間を短くしたりし、肌の健康を守るバランスも大切です。 次に、「食事の中での工夫」です。焼き鮭やサバの味噌煮、干しシイタケのお味噌汁、ゆで卵など、昔ながらの和食の中にはビタミンDが豊富に含まれています。苦手でなければ、こうした食材を意識的に食卓に取り入れると良いでしょう。最近では、日光を浴びさせてビタミンDを強化したキノコ類も販売されています。食品表示をチェックして、強化食品を選ぶのも一つの手です。 それでも日光も食事も不十分な場合には、サプリメントを考える価値もあります。日本でも市販されているビタミンDのサプリメントは、1日400IU(10μg)や1000IU(25μg)などの製品が多く、適切に使えば安全です。ただし、ビタミンDは脂溶性ビタミンの一種で、摂りすぎると体に蓄積していまいます。 成人の場合は、1日あたり最大4000IUまでのビタミンD摂取は安全であると考えられています。ただし、それを超える高用量では、腎結石、脱力感、胃腸障害などのリスクが高まることがあるため、注意が必要です。過剰摂取は逆に体に害を及ぼす可能性があるため、医師や薬剤師に相談しながら摂取するようにしましょう。■受験勉強や仕事の活力を支える見えない力 もちろんビタミンDを摂取したからといってただちに試験で良い点が取れたり、仕事のパフォーマンスがよくなったりするわけではありません。そんな魔法の栄養素ではありませんが、体と心をベストな状態に保つための「土台」を支える存在であることは確かです。集中力を発揮し、風邪を引かずに勉強や仕事を続けるためには、健康が何よりも大切です。 子供がいるご家庭の場合、親としてできるサポートは、塾選びや模試の結果だけではありません。食卓と日常のちょっとした工夫が、子供の大切な受験期間を支えるのです。カロリー過多で肥満が世界的に問題になっていますが、ビタミンDの不足などの微量栄養素の不足にどう向き合うかも、未来を担う子供たちの成長や家族の健康を左右するのです。----------谷本 哲也(たにもと・てつや)内科医鳥取県米子市出身。1997年九州大学医学部卒業。医療法人社団鉄医会理事長・ナビタスクリニック川崎院長。日本内科学会認定内科専門医・日本血液学会認定血液専門医・指導医。2012年より医学論文などの勉強会を開催中、その成果を医学専門誌『ランセット』『NEJM(ニューイングランド医学誌)』や『JAMA(米国医師会雑誌)』等で発表している。
----------
プレジデントオンライン
最終更新:5/8(木) 10:17