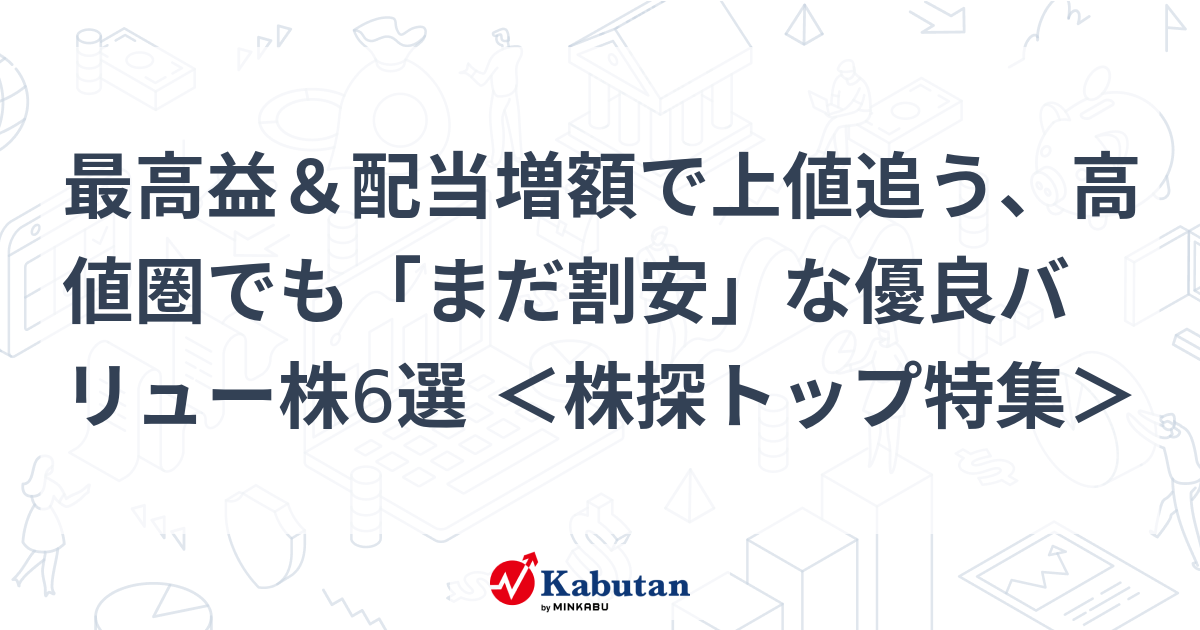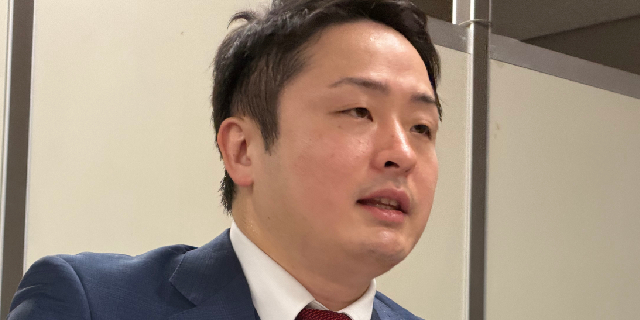コラム:円金利上昇が円高を誘引しない3つの理由=内田稔氏

[東京 30日] - 年初来、日米の金融政策の違いを理由とするドル/円下落観測が根強い。しかし、足元のドル/円はむしろ底堅さを増しており、150円台を回復する勢いだ。本稿では最近の参議院選挙や日米関税交渉の合意が示唆する円相場の方向性と、円金利の上昇が円高に直結しにくい背景を解説し、ドル/円相場を展望する。また、その際の留意点も付言する。
<参院選の結果はインフレ継続を示唆>
物価高(インフレ)対策が主な争点となった7月20日投開票の参議院選挙では、与党が給付金の支給、野党が消費税の税率引き下げや部分的な撤廃など、異口同音に財政拡張をうたった。与党が過半数を割り込み、消費税の取り扱いを巡る野党側の足並みもそろっておらず、いずれの政策もその実現性は不透明だ。ただ、物価高対策に財政拡張で対処するアプローチは共通している。現在のインフレは、言うまでもなく輸入物価の上昇によるコスト増が価格に転嫁される「第一の力」が起点であり、その要因は金融緩和と歴史的な円安にある。そこに手を加えないまま財政拡張による需要喚起が加わると、インフレが加速するおそれがある。日銀が金融政策の正常化(利上げ)を慎重に進める限り、名目金利からインフレ率を差し引いた実質金利が低迷し、為替市場では円安圧力が残るだろう。
<関税交渉合意は円安シグナル>
日米間の関税交渉の合意もドル高・円安材料となりそうだ。15%の関税によって日本の対米輸出は減少しよう。その上、旅客機、防衛装備品、コメや農産品の購入や輸入枠の拡大も相まって、日本の対米貿易黒字は昨年実績(約8.6兆円)から半減しても不思議ではない。これは日本全体の昨年の貿易赤字(約5.5兆円)の拡大を通じた円安圧力となる。対照的に米国では関税による貿易赤字の縮小が見込まれ、こちらはドル安圧力を軽減しそうだ。一方、関税を巡る不確実性の後退によって日銀が利上げを進めやすくなるとすれば、今回の合意はかえって円高につながるとの見方も成り立つ。もっとも、日本の金融政策の正常化観測や最近の長期金利の上昇は、実際には円高には波及しておらず、その理由として以下の3点が挙げられる。
<円金利上昇が円高を招かない背景>
1点目は、次回の利上げがある程度、織り込まれている点だ。日銀は4月に相互関税の詳細が明らかになった後も、不確実性が高まった点を強調しつつ利上げ継続のスタンスを維持してきた。インフレの実績値が目標を3年以上にもわたって上回り続けており、市場でも時期こそ不確かながら利上げ自体にサプライズはない。実際、関税交渉が合意したとの報道を受け、オーバーナイト・インデックス・スワップ(OIS)市場における年末までの利上げの織り込みは55%から90%へと高まった。だが、ドル/円相場は数十銭下落したに過ぎない。それどころか、週末にかけてドル/円は尻上がりに持ち直した。こうした動きを踏まえると、日銀の利上げが円高を招くのは、植田和男総裁が実質金利のマイナス幅の解消に向け、粛々と利上げを続ける姿勢を明示する場合と考えられるが、これまでの言動からその可能性は極めて低い。
2点目はマイナス圏にある実質金利だ。日本の実質金利は政策金利、長期金利のどちらでみても他の主要通貨より低く、水準的にもマイナス圏に位置している。かねて指摘の通りこれが円安の主因と考えられ、多少の利上げではその解消までは見通せない。実際、今年1月に日銀が利上げに踏み切り、多くの海外中銀が利下げを重ねてきたが、ドル安によって下落したドル/円を横目に、多くのクロス円が上昇してきた。2024年を振り返ると、そのドル/円も日米の金融政策が逆行する中で、年初より約15円も上昇して年末を迎えている。
3点目は、長期金利や超長期金利の上昇が、いわゆる「悪い金利上昇」とみなされている可能性があることだ。日銀が国債の買い入れ額を徐々に減らしていくことから需給の悪化が警戒され、超長期金利が急上昇する場面もみられている。さらにインフレへの警戒が加われば、インフレ期待の上昇により長めの国債利回りほど上昇すると見込まれる。仮に財政規律の緩みによるプレミアムが加われば、積極的な投資は手控えられよう。事実、7月23日の40年物国債入札における応札倍率は11年以来、15年ぶりの低さに終わった。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場を見る限り、現時点で日本の財政不安が警戒されているわけではないが、今後の財政拡張の程度次第では状況が変わるおそれもある。CDSに加え、国債の入札結果、超長期金利の水準や長期金利とのスプレッドなどを観測していく必要がある。
<ドルに持ち直しの兆し>
次にドルについてみていくと、ここにきて持ち直しの動きがみられてきた。ドル指数は今年1月をピークに下落トレンド入りし、4月以降は相互関税に端を発したドル離れをカタリストにドル安が加速した。また、トランプ減税の恒久化を含む大型減税の審議が進む中、米格付け会社ムーディーズによる格下げも相まって、5月にかけて長期金利が上昇すると、いわゆる「悪い金利上昇」とみなされた。その結果、ドルは米国からみた海外との金利差が拡大するとかえって下落する金利との逆相関に陥った。
ただ、5月下旬に中国との暫定合意が成立するとこうした動きが沈静化した。米国の株価指数が史上最高値を更新し、大型減税法案が成立した7月4日以降の国債入札でも堅調な需要が確認され、ドルも次第に金利との順相関の関係を取り戻した。そこに関税による税収の上ブレ期待、関税交渉の進展、底堅さを保つ実体経済を踏まえた利下げ観測の後退などが重なり、ドルが反発しつつあると考えられる。米国では企業在庫が減少しており、ここからの仕入れに関税の影響が出始める可能性がある。また、主要株価指数が堅調に推移する限り、個人消費が下支えされるため、利下げは早くて9月だろう。先の円が置かれた状況と合わせて考えると、ドル/円が150円大台を回復する可能性が高い。
<円安見通しに対する留意点>
もっとも、筆者はドル/円の上ブレを見込みつつ、現時点では以下3つの理由から上値目処として155円程度とみている。まず、150円を超えてくれば日銀が利上げ姿勢を積極化すると考えられる。次に、日米双方ともに円安けん制を強める可能性がある。例えば7月17日、青木一彦官房副長官、加藤勝信財務相が相次いで円安をけん制した。昨年162円台目前まで円安が進行したことに鑑みれば、かなり早い。関税交渉の合意が報じられた後、ベセント財務長官もトランプ大統領が不満を抱けば、対日関税が25%に戻る可能性に言及。さらに、通貨政策を担う三村財務官が日米関税交渉に同席していたことも報じられている。以上を踏まえると、日本が米国から円安およびそれを招いている日銀の金融緩和を強くけん制された可能性を否定しがたい。ここからのドル高の程度によっては、これまでの反動からユーロやスイスフランの対ドルでの下げ幅が円の下げ幅を上回るおそれもある。これは、クロス円の下落を通じてドル/円の上値を抑えると考えられ、注意を要する。
編集:宗えりか
*本コラムは、ロイター外国為替フォーラムに掲載されたものです。筆者の個人的見解に基づいて書かれています。
*内田稔氏は高千穂大学商学部教授、株式会社FDAlco外国為替アナリスト、公益財団法人国際通貨研究所客員研究員、証券アナリストジャーナル編集委員会委員、NewsPicks公式コメンテーター(プロピッカー)。慶應義塾大学卒業後、東京銀行(現・三菱UFJ銀行)に入行し、マーケット業務を歴任。2012年からチーフアナリストを務め、22年4月から高千穂大学商学部准教授、24年4月から現職。J-money誌東京外国為替市場調査では2013年より9年連続個人ランキング1位。国際公認投資アナリスト、日本証券アナリスト協会認定アナリスト、日本テクニカルアナリスト協会認定テクニカルアナリスト、経済学修士(京都産業大学)。YouTubeチャンネル「内田稔教授のマーケットトーク」では解説動画を公開している。
*このドキュメントにおけるニュース、取引価格、データ及びその他の情報などのコンテンツはあくまでも利用者の個人使用のみのためにコラムニストによって提供されているものであって、商用目的のために提供されているものではありません。このドキュメントの当コンテンツは、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、また当コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。当コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。このドキュメントの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。ロイターはコンテンツの信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、コラムニストによって提供されたいかなる見解又は意見は当該コラムニスト自身の見解や分析であって、ロイターの見解、分析ではありません。
私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」, opens new tab