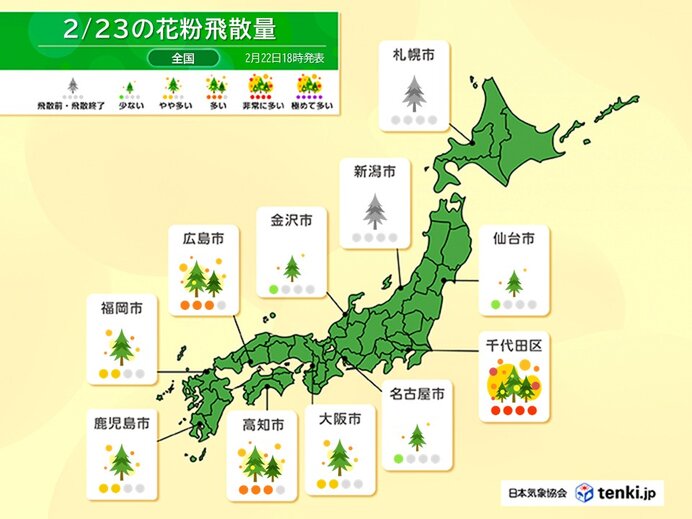中国は尖閣に上陸する気だ 元陸上幕僚長・岩田清文

二〇二五年五月三日に尖閣諸島上空において中国海警局のヘリコプターによる領空侵犯事案が発生しました。日本の主権と安全保障に対する新たな挑戦を提示したといえる重大な問題です。本稿は、この事案に対する日本政府や与党の初期対応を検証します。さらに中国の行動からその戦略的意図を分析します。加えて、中国が展開する「認知戦」の脅威を指摘し、これら複合的な課題に対処するための具体的な政策提言を行います。
岩田清文氏政府の対応を検証してみましょう。五月三日に事案が発生した当日、外務省は通常の外交ルートを通じて抗議しました。具体的には船越健裕外務事務次官が呉江浩中国大使に日本の主権を侵害する行為への抗議の意を表明、こうした行為が再発しないよう求めました。ですが、こうした姿勢は「淡々とした」ものといえます。
これまでの中国海警の行動は、主に尖閣諸島周辺の接続水域での執拗な航行や領海侵入が中心でした。ところが今回の領空侵犯はヘリコプターによって日本の領空に直接侵入した点で決定的に意味が異なり、一段と深刻な主権侵害行為と見なされます。一段ラダーが上がったのです。その事態の深刻さを政府は十分に認識しているのでしょうか。
一方、自由民主党内はどうか。自民党内ではより強い危機感が共有された、といえるでしょう。五月九日の党部会では、中曽根弘文外交調査会長が「いずれドローン(無人機)やヘリが尖閣諸島に着陸しないとは限らない」と懸念を表明、中国政府への「遺憾」や「厳重抗議」だけでは不十分であると指摘しました。
また、木原稔安全保障調査会長は、航空自衛隊(空自)F-15戦闘機の那覇基地からの対応時間や、高度・速度の制約に言及し、現状の対応体制の限界と、無人機増加への対応策の必要性を提起しました。
尖閣諸島は那覇基地から約四百キロ離れ、F-15戦闘機がスクランブル(緊急発進)して現場に到達するには一定の時間が掛かります。今回の事案では、中国海警のヘリコプターが領空侵犯を終え、着艦したころ、F-15は現場に向かう途上にありました。また有人機とは異なる特性を持つ無人機に対し、F-15によるスクランブル体制だけで即対応できるか、といった具体的な問題も指摘されました。
事案発生から十日後の五月十三日、岩屋毅外務大臣は記者会見で「今般の事案は、近接した時刻に、我が国の民間小型機が、尖閣諸島周辺を遊覧飛行していたことを確認しております」と「遊覧」という表現を使いました。ですが一部報道によれば、この民間機は「奮闘する海上保安庁にエールを送りたい」という八十歳代の日本人男性が機長として計画したものでした。政府が対応を協議し、男性に自粛を要請しましたが、聞き入れられずに飛行に至ったものでした。
「遊覧飛行」という表現は一般的に観光やレジャーを目的とした、比較的無害で偶発的な飛行という印象を与えます。ですが、一部報道によれば、これは尖閣諸島周辺の日本の主権維持活動の支援またはその状況の視察という「激励」の意味だったそうです。これが事実なら岩屋外相の「遊覧飛行」という認識は不正確です。「遊覧飛行」という表現によって、中国の動きの深刻さを矮小化してしまう恐れも見逃せません。
岩屋外相はまた「航行の安全を図る目的で」「尖閣の領有権を主張する中国を過度に刺激しないよう飛行の自粛を求めていた」とも述べました。この発言も批判を招きました。「尖閣の領空は我が国の主権が有効に支配され、安全に飛行できる地域ではないのか」という疑問を提起してしまいます。もし民間機が安全に飛行することができない危険空域ならば、それは日本の施政権がこの空域に完全に及んでいないのではないか、という根本的な疑念につながるでしょう。
今後の対応にも岩屋外相は「遺憾」を表明するに留まり、具体的な対策は示しませんでした。こうした発言を見ると、政府の対応は極めて不十分と言わざるをえません。
「日本が非がある」に対抗せよ
今回の中国海警ヘリによる領空侵犯は、単なる偶発的な事案ではなく、中国の明確な意図と計画性に基づいた行動だったと認識すべきです。中国は、日本の民間機の航跡を事前に把握していました。領空侵犯も民間機の尖閣沖到達に合わせたかのようなタイミングで行動を開始しました。これは、中国が周到な準備を行い、事態を意図的にエスカレートさせたものだと言えます。
中国の行動は、これまでの小規模な既成事実を積み重ねながら、現状を徐々に変更していく所謂「サラミスライス」戦術が終焉し、次の段階として尖閣諸島への「上陸」を視野に入れている。その可能性が高いのです。中国はこれからいっそう領海侵入や領空侵犯を繰り返して常態化させ、最終的な占拠・上陸に向けて能力向上を着実に進めている。そのことは明らかです。
二〇二一年から二〇二四年までアメリカ太平洋艦隊の司令官を務め、現在は米インド太平洋軍司令官であるサミュエル・ジョン・パパロ大将が「中国の演習というのは『二〇二七年までに人民解放軍および海警の侵攻態勢を完了させる』という習近平主席の『奮闘目標』に向けた『リハーサル』である」と指摘している通り、今の中国の動きはそうした長期的な戦略的意図を踏まえたものといえます。
日本は「認知戦」の脅威に晒されていることをしっかり認識しなければなりません。中国は五月三日に尖閣を領空侵犯した直後から、国防部や外交部を通じて自分たちの行動は「正当な法執行」だったと繰り返し強調し、自らの行動を正当化する情報発信を活発に行っています。
これに対する日本政府の対応は、前述した外務次官による中国への抗議に留まり、連休中はほとんど動きがなく、岩屋外相の会見は事案が発生してから十日後でした。これは、日本が認知戦に臨んだ対応をほとんど行っておらず、メディアへの情報提供も不十分だったことを物語るものです。
ある元海上保安庁の高官の方が先般、あるメディアに出られて海上保安庁の認識を説明していました。二〇一二年に初めて尖閣に中国海洋局の航空機が入ってきた時も、それは日本政府によって尖閣諸島の国有化を図ったことが理由だった、と述べていました。今回の領空侵犯も日本の民間航空機が尖閣に入ってきたから中国の領空侵犯があった、だから日本が領空侵犯の切っ掛けをつくったのだ、という考えでした。
私は正直、椅子から落ちそうになるほど驚きました。中国が領空侵犯をしたのです。民間航空機が飛行したことは適法な行為です。にもかかわらず、日本側がその切っ掛けをつくったのだ、というまるで日本に非があるかのような発言で、しかも海上保安庁にいた元高官による発言です。非があるのは日本で、中国の行動は正当だった、という中国の認知戦がここまで浸透しているのか、と考えさせられる深刻な出来事でした。
四つの提言
では日本がやらなければならない今後の対応を提言します。ここまでの課題認識に基づいてここでは以下の四つを政策提言します。
まず国家の意思を明確に示すことです。国家のトップが、中国に対し日本の意思を見誤らないようにと明確に表明すべきです。
国家の意思を明確に示す理由はそれが抑止力の根幹をなすからです。抑止力とは単に軍事的な「能力」(ハードパワー)を示すことだけではありません。その能力を行使する「意思」(ソフトパワー)を相手に明確に伝えることで初めて機能します。そしてそれは現場の部隊が効果的に任務を遂行する法的な意味でも政治的な意味でも基盤となります。権威主義的な国家というのは相手国の意思の曖昧さや弱味を見抜くと強硬な行動に出る傾向があります。中国の「グレーゾーン」戦略は正にその典型で「戦争ではないが平和でもない」領域において全面的な戦争には至らないような圧力や威嚇、挑発を繰り返し、徐々にレベルを上げながら相手の主権や権益を奪っていくというものです。ですから、国家のトップが明確な意思を示さなければ「この国は本気ではない」という誤ったメッセージを与えてしまいますし、それではさらなる挑発を招いてしまいます。
安倍晋三元首相が在任中、中国の習主席と会談の際、尖閣諸島について「日本の意思を見誤らないように」と強調していたのはまさにそうした誤りに陥らないようにするためで、正しい対応です。これが重要なのです。
また、尖閣諸島の実効支配を確実なものとしなければなりません。日米地位協定で、米軍射爆撃訓練場として指定されながら一九七九年以降、未使用となっている大正島や久場島を、日米共同訓練施設、特に空自戦闘機の射爆撃訓練場として活用することを検討すべきです。これによって日米同盟の抑止力を強化しつつ、この地域における日本の実効支配を事実として確立することが可能となります。
さらに航空自衛隊の即応体制を強化すべきです。前述したように今回の領空侵犯事案では、那覇基地から駆けつけたF|15の到着が、中国ヘリの領空侵犯に間に合いませんでした。距離的な不利が露呈しました。対応時間の短縮を図るため、宮古島の下地島空港に空自基地を開設し、領空侵犯対応のみならず、有事における制空権を確保できる能力を高めなければならない。そのことを提言します。
下地島空港を軍事利用するには沖縄返還以前の「屋良覚書」や「西銘確認書」という歴史的経緯に根ざしたハードルが存在します。「屋良覚書」と「西銘確認書」は沖縄返還以前の一九七一年、琉球政府と日本政府の間で交わされた文書です。これらの文書では趣旨として空港を航空訓練と民間航空以外の目的では使用しないという約束が交わされました。今も沖縄県が軍事利用に反対する際に根拠として示すものです。また沖縄が抱える米軍基地負担の歴史的背景、あるいは南西諸島のさらなる軍事化への懸念もあって、県だけでなく地元住民による抵抗も強いのです。ですが、現在の安全保障環境は当時とは大きく異なっています。県の管理である下地島空港を国の管理へと改めることを追求すべきです。
海保法二五条という問題
次に海上保安庁の領空侵犯に対応する能力を向上させるべきです。尖閣諸島周辺における日常的な対応を担う海上保安庁の能力向上が喫緊の課題となるからです。海上保安庁に対し、尖閣諸島周辺に限定した対領空侵犯対応任務(民間機や治安機関機に対する警察権行使)を付与することを提言します。
日本の領空侵犯への対応は、原則として航空自衛隊(空自)の任務となっており、海上保安庁には許されていません。海上保安庁法には、海上保安庁が軍隊になることを防ぐ規定(第二十五条)もあります。ですが、他国の治安機関や民間機の領空侵犯に対して海上保安庁が警察として対応することは、この規定が想定する軍事行動にはあたりません。むしろ、同じ治安機関同士が対応することで、現場での迅速な対処が可能となり、事態が不必要に悪化するのを防げます。したがって、尖閣諸島周辺での領空侵犯に備え、海上保安庁に民間機や他国の治安機関機に対する警察権の行使を認め、必要な能力と権限を与えるべきです。
最後に、前述した中国が活発に展開する認知戦に日本政府は抜本的な対応を行うことが欠かせません。今回の事案における政府の対応の遅れと情報発信不足は、日本が認知戦対応を怠っている証左でもあります。
二〇二二年十二月に策定された「国家安全保障戦略」を含む安保三文書では、偽情報を含む認知戦・情報戦への対応能力を強化することと、そのために政府内の体制を整備するよう明記されています。しかし、策定から二年半が経過しても、その具体的な進展は見られません。政府は、この戦略的文書に明記された方針に基づき、認知戦に対応するための組織と体制を早急に整備し、中国のプロパガンダに対抗する情報発信を強化すべきです。
浮き彫りの課題を放置するな
尖閣諸島における今回の領空侵犯事案は、中国の戦略的意図と能力向上、そして日本が直面する認知戦の脅威を明確に示しました。日本は、この複合的な課題に対し、国家意思の明確化、防衛能力の強化、海上保安庁の役割拡大、そして認知戦への積極的な対抗という多角的なアプローチを統合的に実行することで、我が国の主権維持を揺るぎないものにしていく必要があります。
(月刊「正論」9月号より)
いわた・きよふみ
昭和三十二年生まれ。防衛大学校を卒業後、陸上自衛隊に入り、戦車部隊勤務などを経て、統合幕僚副長、北部方面総監などを歴任。平成二十五〜二十八年に陸上幕僚長を務めた。