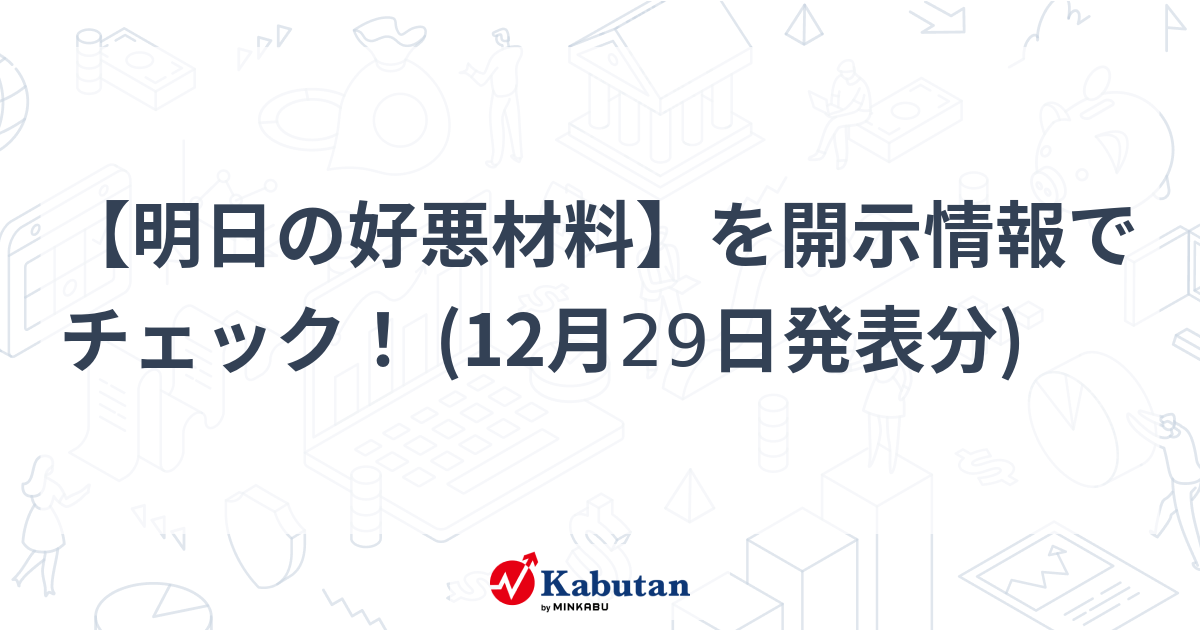予算教書を受けてNASAが声明発表 有人月探査見直しで日本にも影響?

NASA=アメリカ航空宇宙局は2025年5月2日付で、トランプ政権の予算教書公表を受けて声明を発表しました。
有人月探査計画「Artemis」など大幅見直し
この声明でNASAは、月および火星での有人宇宙探査の取り組みを強化するべく月探査に70億ドル以上、火星探査には新たに10億ドルを投じることで、革新性と効率性の維持を保証すると述べています。
一方で、中国初の有人月面着陸に先んじてアメリカが再び月に宇宙飛行士を送ること、そして火星にもアメリカ人を送ることを目指すトランプ政権の優先目標に沿うために、優先度の高い取り組みを推進するとも述べられています。その影響を受ける幾つかのミッションについて、再検討した結果が明らかにされました。
まず、2021年に火星へ到着したNASAの火星探査車「Perseverance(パーシビアランス)」が採取したサンプルを地球に持ち帰る「火星サンプルリターン(Mars Sample Return: MSR)計画」をはじめ、財政的に持続不可能とされる取り組みは終了することになります。
NASAとESA=ヨーロッパ宇宙機関(欧州宇宙機関)が共同で取り組む火星サンプルリターン計画はコスト超過とミッション長期化を理由に見直しが進められており、また中国も「天問3号」で2030年頃にサンプルを地球に持ち帰る計画を立てていますが、民間の関与も含めて完全に終了するのかどうかは不明瞭です。
次に、アメリカが主導する有人月探査計画「Artemis(アルテミス)」については、NASAの大型ロケット「Space Launch System(SLS)」および有人宇宙船「Orion(オリオン、オライオン)」を、2027年実施予定の「Artemis III(アルテミス3)」ミッションをもって引退させる方針も示されました。持続可能性と費用対効果を高めるためとして、その後のNASAによる月探査ミッションは民間の商用システムに支えられることになります。
【▲ Artemis IIIミッションでの退役が明らかにされたNASAの大型ロケット「SLS」。先端にはやはり同ミッションで退役する宇宙船「Orion」が搭載されている。写真はArtemis Iミッションで使用された機体、2022年9月2日撮影(Credit: NASA/Joel Kowsky)】 【▲ 計画の終了が明らかにされた月周回有人拠点「Gateway」の想像図(Credit: Thales Alenia Space/Briot)】また、Artemis計画で有人月面着陸の中継地点として機能する予定だった月周回有人拠点「Gateway(ゲートウェイ)」は、計画そのものの終了が示されました。Gateway向けに製造が済んでいるハードウェアは、他のミッションで再利用される見込みです。
この他にも声明では、2030年で運用を終了するISS=国際宇宙ステーションから商用宇宙ステーションへの移行を進めるにあたり、実施される研究は月・火星探査にとって重要な分野に集中すること、ISSの滞在人数や研究を段階的に削減することや、政権の方針に沿わない一部の取り組みに対する予算措置の終了などに言及しています。
アメリカ国内企業に大きな影響か
【▲ 月に着陸した「Starship HLS」の想像図(Credit: SpaceX)】Artemis IIIミッションよりも先が見通せなくなったことと、Gatewayの計画終了は、アメリカの民間企業に大きな影響を与えることになりそうです。
Artemis計画で使用される有人月着陸船「Human Landing System(HLS)」には、SpaceXが開発を進める大型宇宙船「Starship(スターシップ)」の派生型である「Starship HLS」と、Blue Originが複数のパートナー企業と開発を進める「Blue Moon(ブルームーン)」の有人型がこれまでに採用されていました。Starship HLSはArtemis IIIとその次の「Artemis IV(アルテミス4)」ミッションで、Blue Moonはさらにその次の「Artemis V(アルテミス5)」で使用される予定だったので、今回の声明を読む限りでは、見通しが立つのはStarship HLSの使用のみということになります。
また、Starship HLSはGatewayだけでなくOrion宇宙船と直接ドッキングして宇宙飛行士が乗り移ることも想定されていますが、Blue Moonに搭乗する宇宙飛行士はGatewayで乗り換えることになるはずでした。“乗換駅”として機能するはずだったGatewayが建設されなくなることから、Artemis IV以降のミッションの実施が見通せなくなったこともあり、Blue Moonによる有人月面着陸実施は不透明な状況です。
さらに、Artemis III終了後は退役するOrion宇宙船に代わって月への有人飛行も民間に依存することになると思われますが、アメリカ企業で有人宇宙船を実用化・運用しているのは、2025年5月時点ではSpaceXの1社だけ。月周辺への飛行を想定している有人宇宙船ともなると、少なくとも具体的に開発が進められているのはSpaceXのStarship宇宙船のみとなります。月・火星での有人探査を重視するトランプ政権の方針を考慮すると、NASAによる今後の有人宇宙飛行は、しばらくの間はSpaceXに頼り続ける可能性が高いように思われます。
【▲ Firefly Aerospaceの月着陸機「Blue Ghost」のカメラで撮影されたBlue Ghost自身の影(Credit: Firefly Aerospace)】一方、無人での月探査についてはNASAのCLPS=商業月輸送サービスや同等の取り組みによって民間企業への機会が拡大される可能性も考えられます。ただ、2024年以降に実施されたアメリカ企業による4回の月着陸ミッションでは1機が月に到達できず、2機は着陸時に横転。成功裏にミッションを終えたのはFirefly Aerospace(ファイアフライ・エアロスペース)の月着陸機「Blue Ghost(ブルーゴースト)」による1回のみとなっており、企業側の技術・ノウハウの向上も課題と言えそうです。
なお、2025年6月には日本企業の株式会社ispaceが月面探査プログラム「HAKUTO-R」ミッション2の月着陸を行う予定です。ispaceは2023年4月にも同プログラムのミッション1で月着陸を試みたものの、この時は失敗に終わりました。民間企業による月着陸ミッションのひとつとして、HAKUTO-Rミッション2の成否が注目されます。
NASAの方針転換は日本にも影響あり?
【▲ アルテミス計画で日本が提供する予定の与圧ローバーのモデル。JAXA=宇宙航空研究開発機構のワシントン駐在員事務所にてアメリカの現地時間2024年4月10日撮影(Credit: NASA/Bill Ingalls)】アメリカは日本にとって様々な分野で関係が深い国であり、宇宙開発も例外ではありません。
ミッションを支えるはずだった大型ロケット、有人宇宙船、そして宇宙ステーションの退役や計画終了が発表されたArtemis計画では、JAXA=宇宙航空研究開発機構がトヨタ自動車と共同開発中の有人与圧ローバー「LUNAR CRUISER(ルナクルーザー)」を提供する代わりに、日本人宇宙飛行士による2回の月面着陸機会を得る取り決めが、2024年4月に日米の間で署名されています。
Gatewayもまたアメリカだけでなく、ヨーロッパ、カナダ、日本などが関わる計画でした。与圧モジュールで使用されるバッテリーなど一部の機器は日本が提供することになっていましたし、ロボットアームを提供する予定だったカナダは2名の宇宙飛行士がミッションに参加する取り決めをアメリカとの間で交わしていました。そのうち1名は2026年に行われる予定の「Artemis II(アルテミス2)」ミッションでOrion宇宙船に搭乗することが、すでに決まっています。
日本の有人与圧ローバーは月面で2名の活動を最大30日間支えられる“走る月面基地”としての機能を持ち、無人でも遠隔操作で運用可能とすることが想定されています。Artemis計画の見直しやGatewayの建設中止で先行きは不透明になりましたが、アメリカが今後目指す“より持続的で費用対効果の高い”月探査にとって有人与圧ローバーが引き続き必要だと判断されるかどうかが、日本人宇宙飛行士の月面着陸機会に関わってくることになりそうです。
文/ソラノサキ 編集/sorae編集部