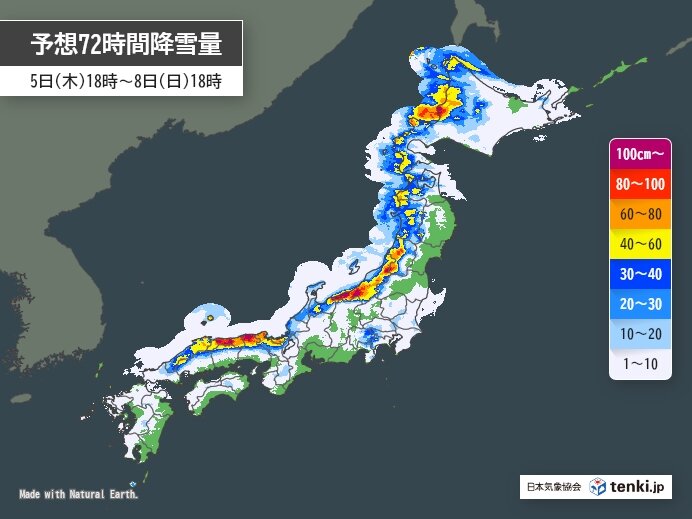医師が警鐘「根拠なき『がんの自由診療』に飛びつかないで」 患者の思いを利用する「ビジネス」の問題点

がん治療目的で、自由診療の「遺伝子治療」を国の承認を得ずに続けていた都内のクリニックに、厚労省などが措置命令を出した。2009年以降、3000人以上もの患者に提供したというが、そもそもこの治療は「有効性や安全性がまったく証明されていない」という。患者がこうした根拠のない自由診療にたどりついてしまう背景には「標準治療への大きな誤解」に基づく不安があると専門家は指摘する。
* * *
専門家は「人体実験そのもの」
措置命令を受けたのは、末期がん患者らを対象に「CDC6shRNA治療」と称する遺伝子治療を行なっていた都内のクリニック。遺伝子組み換え生物の使用を規制する「カルタヘナ法」に基づき、国の承認を受ける必要があるが、その手続きをしていなかった。
09年から3000人以上もの患者に提供していたという。
だが、手続き以前の問題として、そもそもこの治療は「有効性や安全性がまったく証明されていない」のだという。
「動物実験レベルの試験しか行われておらず、人に対する臨床試験データは一つも存在しません。人への試験が行われていない治療を患者に施すなんて『人体実験』そのもので、医療倫理的にきわめて問題だと言えます」
そう指摘するのは、自由診療や代替療法などの問題に長年、警鐘を鳴らし、情報発信を続けている日本医科大学武蔵小杉病院・腫瘍内科教授の勝俣範之医師だ。
わらにもすがる心理を利用している
この遺伝子治療以外にも、がんに対する「自由診療」や「代替療法」を提供している医療機関は数え切れないほどある。公的な保険は適用されないため、高額になるケースが多い。
勝俣さんは、「はっきり言えば、がんの自由診療、と書いてあったら怪しいと思った方がいいです」と言い切る。
効果が期待できる治療法や薬なら「世界的な大発見」の可能性があるため、症例を報告して研究の対象となる。
「わらにもすがりたい患者さん側の心理を、医療機関側が利用しているのです。巧みな宣伝文句を使ったりしていて、もはや医療というより、ただの商売ですよね」
勝俣さんが、注意した方がいいと指摘する宣伝文句やキーワードは次のようなものだ。
Page 2
▽「最先端」「先進」など、これが最も新しい治療法だと印象付ける言葉
▽がんが「消えた」「治った」「どんながんにも効果がある」などのうたい文句
▽「免疫アップ」などと免疫に良いかのようにうたう
▽「この治療のおかげでがんが治った」「効果があった」とするいち個人の体験談
細胞実験や動物実験のデータしかない
すでに効果がないと判明した治療を「最先端」とうたっていることもある。
細胞実験や動物実験のデータしかない治療には注意が必要で、よくよく確認した方がいい。
また、自由診療や代替療法が「効いた」とする個人の体験談はもっともあてにならない。
「ちゃんと確認すると、標準治療と並行して受けていたケースが大半なのですが、それを隠している」(勝俣さん)のだという。
ただ、不安に駆られ、大学病院の主治医が提示する「標準治療」よりもっと優れた治療法があるはずだと、情報を探す患者や家族は少なくない。なぜ、標準治療に不安を感じてしまうのか。
「標準治療」への誤解
勝俣さんはその背景に、「標準治療」という言葉自体への大きな誤解があると指摘する。
それは、標準治療=「ありふれた治療」「普通の治療」と思い込んでしまうということである。
勝俣さんによると、がんの新薬候補の中で、標準治療に採用される確率はわずか0・01%。日本の高校・大学の野球部員がプロになれる確率は0・1~0.2%とされているが、それよりはるかに厳しい。選び抜かれた存在なのである。
勝俣さんは、「標準治療=エビデンスに基づいた『最善』『最良』の医療であるということを、ちゃんと知ってほしいと強く思います。だからこそ、公的保険が適用され患者さんの負担が軽くなるのです。自由診療を受ける必要はまったくありません」と強調する。
自由診療や代替療法に
筆者は5年前に悪性脳腫瘍(膠芽腫)で妻を亡くしている。完治は不可能なきわめて悪性度の高いがん。大学病院が提示する治療より「上」があるはずだと、わらにもすがる思いでネットなどで情報を調べるうちに自由診療や代替療法に行き当たり、すんでのところで立ち止まった経験がある。
半信半疑で、メディアに広告を出していた、がんの自由診療のセミナーに参加したが、モニターに映し出される解説資料を撮影していたら、なぜかスタッフに撮影NGと注意された。
Page 3
壇上の担当者は「論文を書く医者はヒマな医者」などと、論文は根拠にならないと言い切り、どのくらいこの治療を続ければいいのかという質問には明確に答えず、「この治療を途中でやめちゃった患者さん、その後連絡がとれなくなったんですよ。どうしちゃったんでしょうね?」などと不安をあおる言葉を重ねた。
「とにかく早く、早くこの治療を開始したほうがいいんです」と繰り返す別の登壇者。だが、参加していた患者や家族と話をすると、この「早く」にあおられかけている人もいた。
日本人の多くががんになる時代だが、自分や家族がいざ罹患したあとでは、しっかりとした心構えはできないのかもしれない。
遠慮せず主治医に質問を
セカンドオピニオンを求める患者と数多く向き合ってきた勝俣さんは、「患者側が主治医からちゃんと話を聞けておらず、不安に駆られているケース」がとても多いと感じているという。
何を目的にした治療なのか。治癒か温存か。他の治療の選択肢はないか。自由診療や代替療法にエビデンスはあるのか。
「日本には『お医者様が言うことだから…』という医者信仰のような風潮が昔からあり、主治医に失礼だと、疑問をぶつけることを遠慮してしまうのでしょう。こんな『信仰』はもうおしまいにして、質問や疑問点を事前に紙にまとめたり、後から内容を確認するために許可を得たうえで録音をさせてもらうなど、まずは主治医としっかり向き合ってほしいと思います」(勝俣さん)
もし、ネットや書籍などで聞こえがいい自由診療や代替療法などに行き当たっても、主治医に相談してエビデンスなどを確認すること。根拠のない「最先端」に惑わされてしまうような、お行儀の良い患者である必要はないのだ。
(ライター・國府田英之)
こちらの記事もおすすめ 突然の乳がん診断とインドカレー屋のマスターに救われた日 70歳を迎えたアグネス・チャンが語る「生きる力」とは