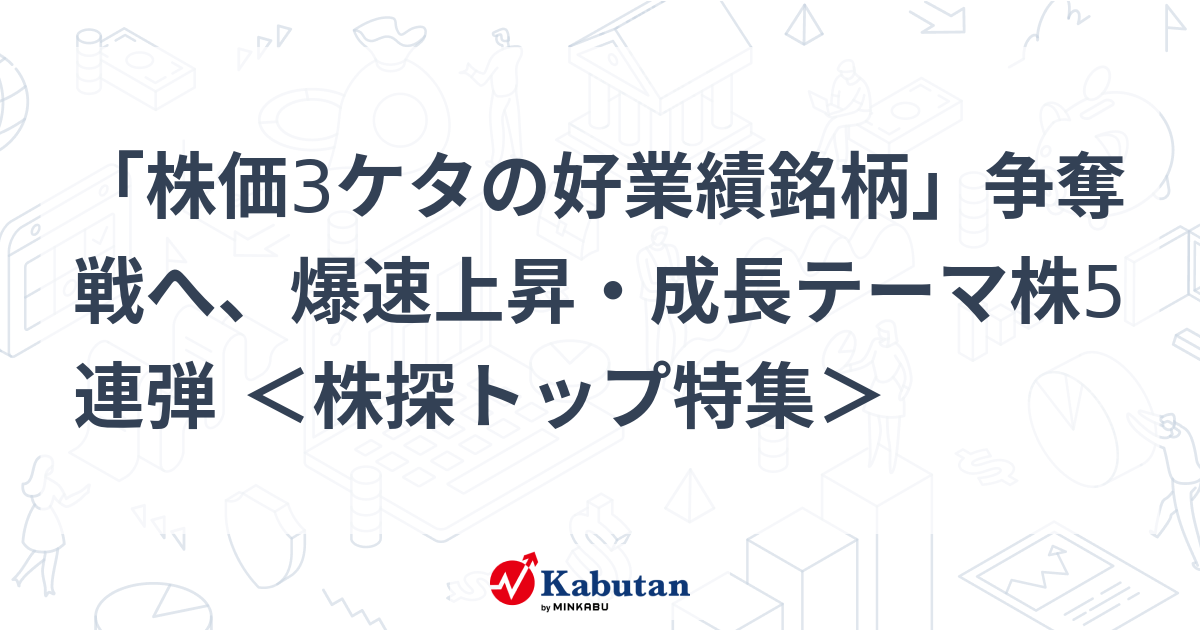ベッセント氏、一躍ウォール街の「時の人」に-日本などと関税交渉主導

米国の輸入関税率を100年強ぶりの高水準に引き上げる上乗せ関税は9日未明(日本時間同日午後)にいったん発動後、同日午後には対中国を除き90日間停止されることになった。
その策定に直接関与していなかったベッセント財務長官は今、この措置が実施されるのを回避するため、主要貿易相手国・地域との交渉を主導する立場にある。
米株価や米国債相場が急落し、輸入関税を巡る強硬姿勢を和らげるよう米政権に対する圧力が高まる状況にあって、元ヘッジファンド運用会社経営者としてウォール街を熟知するベッセント氏は、トランプ大統領の経済チームの最前列に躍り出た形だ。
米金融界の重鎮、JPモルガン・チェースのジェイミー・ダイモン最高経営責任者(CEO)は9日午前、FOXビジネスとのインタビューで、貿易相手国・地域とのディール(取引)を取りまとめるため、ベッセント氏に「時間を与える」よう呼び掛けた。
ベッセント氏はその後間もなく、共和党主導の減税法案を協議するために予定していた同党議員との連邦議会議事堂での会合予定をキャンセル。同日午後にはホワイトハウスで記者団に方針転換の詳細を説明した。
なおトランプ氏自身、ダイモン氏がベッセント氏への信認を表明したこのインタビューを視聴したと、上乗せ関税90日間停止の発表後に記者団に明らかにした。
トランプ政権2期目の財務長官に起用される以前、ベッセント氏はトランプ氏の手法について、「エスカレーションを緩和するため、いったん事態をエスカレートさせる(escalate to de-escalate)」と表現していた。
ベッセント氏は財務長官就任後、このスローガンを用いなくなったが、現在展開されているのはまさにこの表現の通りだ。トランプ氏は、米政府との協議を早々に申し入れた主要同盟国である日本を「優先」する交渉の責任者にベッセント氏とグリア米通商代表部(USTR)代表を起用した。
ベッセント氏は日本に加え、韓国やベトナム、インドなど、中国に近接する国々との交渉を優先する考えを示唆している。
トランプ氏は10日の閣議で、「ディールに取り組んでいる人々」としてベッセント氏をラトニック商務長官の名前を挙げた。ベッセント氏はその場で、財務、商務両省とUSTRが「プロセスを実行する」と述べるとともに、トランプ氏が直接関与するとあらためて説明した。
9日の米株式市場では、90日間停止決定を受けてS&P500種株価指数が急反発した。しかし、関税を巡る数十カ国・地域との交渉は容易ではないと投資家が懸念する中、S&P500種は10日の取引で反落した。
大西洋評議会のジオエコノミクスセンター上級ディレクター、ジョシュ・リプスキー氏は、9日の事態の展開は市場が自分たちの代弁者としてベッセント氏の存在を認めたということだと分析する。
その上で、10日の株価下落は「現実」に戻ったことを示すものだと指摘。ベッセント氏にとって9日は「就任からこれまでの短い期間で最も重要な1日」だったとしつつも、「まだ多くの試練が待ち構えている」との見通しを示した。
関連記事:トランプ氏「移行上の問題」はあり得る、対中関税は計145%に (2)
米財務省報道官はコメントを控えた。
役割転換
昨年11月の時点では、トランプ政権2期目の通商政策のキーパーソンはラトニック氏になるとみられていた。トランプ氏はラトニック氏を商務長官に指名しただけでなく、同氏がUSTRについても「直接の責任」を担って関税・通商政策を主導するとしていたためだ。
また最近では、トランプ氏が2日に発表した上乗せ関税の策定で大きな役割を果たしたナバロ上級顧問(貿易・製造業担当)が、政権内で発言力を増しているように見受けられた。しかし、主要貿易相手国・地域との直接の交渉に当たるのはベッセント氏であり、役割のシフトが生じている。
ベッセント氏は9日、「日本を皮切りに、関税交渉の多くで私が主導的な役割を果たす」と表明した。
こうした中で、トランプ政権の現行のアプローチやベッセント氏の役割が何らかの壮大な基本計画の一環なのか、米資産価格急落を受けた急場しのぎの対応に過ぎないのかは不透明だ。
スティーフルの政策ストラテジスト、ブライアン・ガードナー氏はベッセント氏が一段と目立った役割を果たすのは「投資家にとって心強いサインの一つだ」と話す。一方で、10日の米金融市場の不安定な動きは、投資家を安心させるディールを求める圧力の強さを浮き彫りにしている。
原題:Bessent Emerges as Wall Street Man-of-the-Hour Trade Negotiator(抜粋)