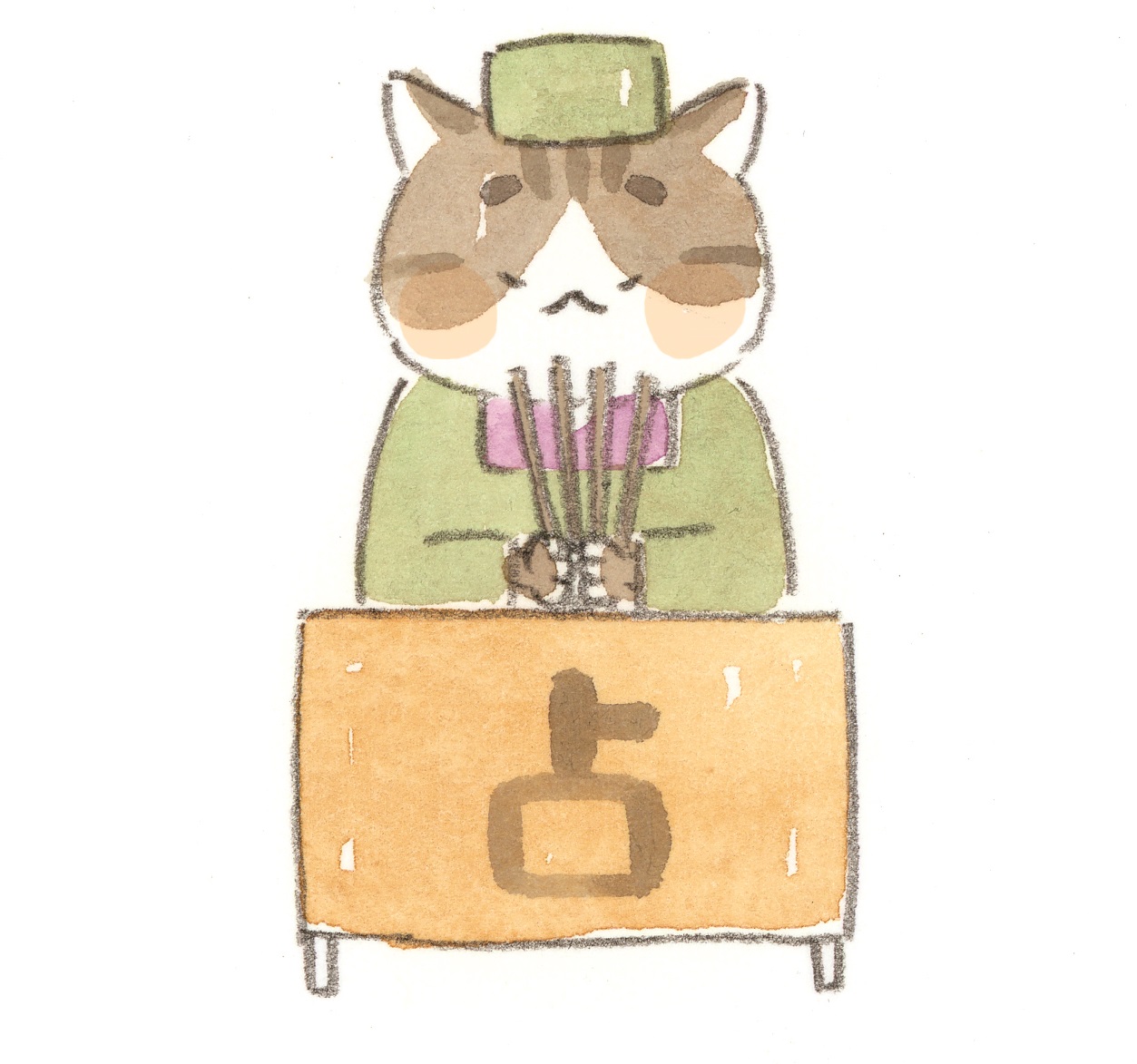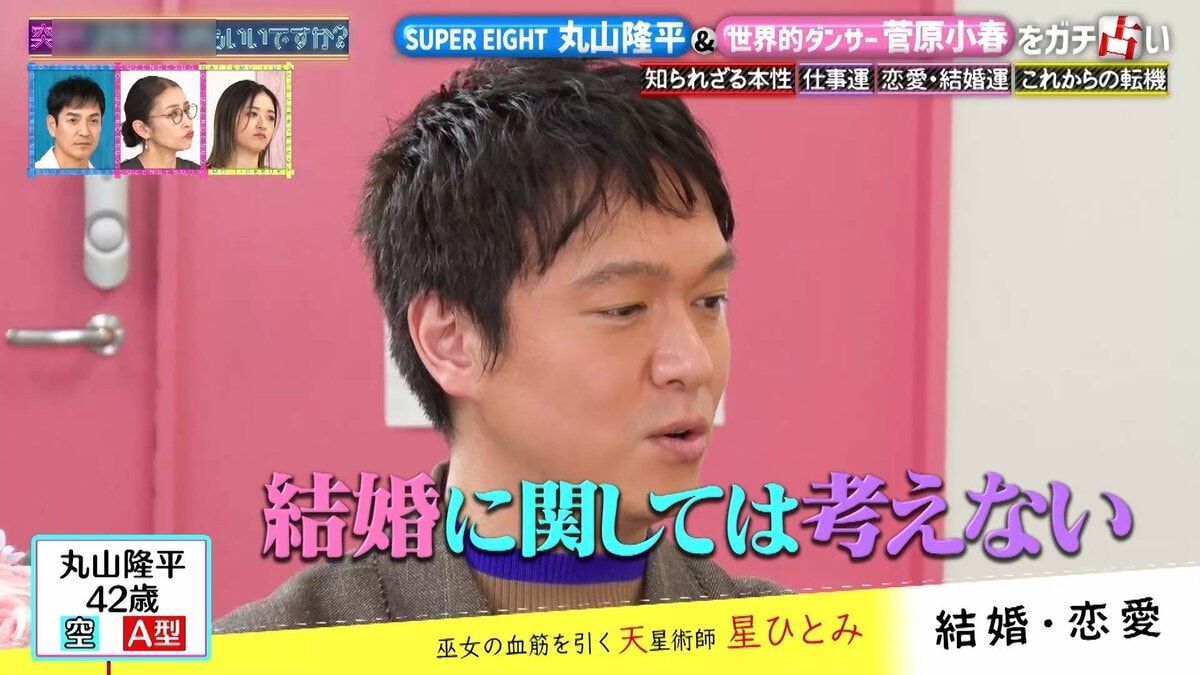【大河ドラマ べらぼう】第32回「新之助の義」回想 「時代の変わり目」より前に狂歌に冷めていた?南畝の思い 一橋家の財政を傾けるほど能に熱中した治済 打ちこわし、黄表紙に見えた民衆の強烈な怒り

ドラマは残り3分の1、後半に向け変革期描く
大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」。1年分の放送のちょうど3分の2という、節目にあたる第32話「新之助の義」です。幕府内の激しい主導権争い、方向転換を迫られつつあるメディア界、現状への不満が高まる市中の人々の怒りが描かれ、身分や立場に関わらず「時代の変わり目」が到来していることをはっきりと予感させる展開になりました。「べらぼう」、中盤を終えていよいよ後半突入です。(ドラマの場面写真はNHK提供)
「この本が世に出るのはまずい」 南畝の焦り
「今、これを出すのはまずいのだ!」。いつも鷹揚として、遊び心を忘れない大田南畝(桐谷健太さん)らしからぬ、焦りに満ちた表情でした。時は天明6年(1786)の秋。田沼時代に我が世の春を満喫していた文芸の世界にも逆風が吹き始めたことを象徴するエピソードでした。
問題になったのは南畝が編者を務め、蔦重が版元になった『狂歌才蔵集』です。勅撰和歌集を模した本格的な作りで、『万載狂歌集』(天明3年)、『徳和歌後万載集』(天明5年)に続く存在として、今も江戸の文芸史に残る作品です。なぜこの出版に南畝が難色を示したのでしょうか。田沼時代の「終わりの始まり」と深く関係します。
後ろ盾だった将軍・家治の死去に伴い、田沼意次(渡辺謙さん)が失脚し、役職を失っただけでなく、米不足などの失政の懲罰として石高も一気に2万石減、と大幅ダウンを喫しました。意次に近かった幕臣も厳しい時代を迎えます。派手な暮らしをしていた勘定組頭・土山宗次郎(栁俊太郎さん)も閑職に追いやられました。土山は狂歌の分野でも名高く、南畝と昵懇だっただけに、直参の御家人である南畝としては気が気ではありません。
朋誠堂喜三二(尾美としのりさん)や恋川春町(岡山天音さん)に冷やかされていたように、この頃、南畝は吉原の松葉屋の女郎を妾にしていました。そうした私生活の事もやり玉にあがるかも、と心配したのでしょう。
世話になった南畝先生から泣きを入れられた蔦重(蔦屋重三郎、横浜流星さん)。「南畝先生が土山様の贔屓なのは江戸っ子なら誰でも知っています。今さら狂歌集一冊出さなかったところで、どうにもならないでしょう」と冷ややかでしたが、南畝の立場になってみれば、事態は深刻でした。
削除跡、丁附の混乱…土山や平秩の作品を取り除いた?
南畝にとって、どれほど問題のある狂歌集だったのかを伺わせる傍証があります。
『狂歌才蔵集』(江戸東京博物館所蔵) 出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/100414380現存する『狂歌才蔵集』です。「古今和歌集」などと同じように、「春歌上」「離別」「羇旅歌」などの章立てからなる格調高い構成です。ところがちょっとおかしなところがあります。
『狂歌才蔵集』(江戸東京博物館所蔵) 出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/100414380上のページの左側をご覧ください。妙な隙間が空いています。ちょうど1首分、歌が入りそう。もともと誰かの歌があり、それを消したように見えます。
「蔦重の仕事としては異例な乱れ」
国文学者で、近世の狂歌や川柳の研究で知られる浜田義一郎氏(1907∼1986)はその論文「『四方のあか』と『狂歌才蔵集』」(1963年)で、この「削除跡」や、一部の巻で丁附け(ページを正しく順番に重ね合わせること)が混乱していること、表記の乱れがあることなどを指摘。「みごとな造本と斬新な編集を特徴とする蔦屋版としては、異例と言わなくてはならない」と評価。狂歌仲間だった土山宗次郎や、やはり優れた狂歌師として知られ、意次らの求めに応じて蝦夷で調査を行った平秩東作(木村了さん)の歌を削除したという見方を示し、「あまり急いだために丁附の字体や字の大きさが狂い、削り放しの一首分の空白さえできてしまった、ということが想像されよう」と推定しています。
南畝に頼み込まれた蔦重、渋々ながらあわてて必要最低限の改訂に応じた様子が浮かび上がってきます。ドラマもこうした見方に沿ってエピソードに組み入れたのでしょう。
その後、南畝は翌天明7年(1787)になり、「ことしの秋文月のころ、何がしかの太守の新政にて文武の道おこりしかば、此輩(狂歌師仲間をいう)とまじわりをたちて家にこもり居しも」などと書き、狂歌仲間との関係を絶ったことを明らかにしています。ドラマだけみると、新たに権力を握った松平定信から睨まれそうだから、狂歌から距離を置いた、という見え方にもなりそうです。しかし事実はもうちょっと複雑かもしれません。
「狂歌の文学性は?」 すでに見切っていた南畝
これより以前から、南畝が狂歌師としての自身について、あるいは狂歌ブームそのものについて、かなり冷めた見方をしていることが書き残したものから伝わってくるからです。
世間をクールに見つめる南畝のスタンスも、ドラマではたびたび紹介されてきました。「世中の人には時の狂歌師とよばるゝ名こそおかしかりけれ」(徳和歌後万載集、天明5年)
「むだ口などゝいふ言は夢にだにもみず、風雅とははやり事とおもひ、詩歌とは子供に小べんをやる事と心得、歌はよまねど狂歌師の株は四五千両のうりかいとはなりぬ」(俳優風、天明5年)
揖斐高・成蹊大学名誉教授は「たばこと塩の博物館」で2023年に開催された展覧会「没後200年 江戸の知の巨星 大田南畝の世界」の図録によせた寄稿(大田南畝の自由と「行楽」)で、これらの南畝の言葉について、「狂歌の大流行がもたらした大衆化と卑俗化あるいは営利化によって、狂歌の文学性などというものはすっかり置き去りにされてしまったと批判的な言辞を弄している」と分析。「寛政の改革が始まったことで、南畝が狂歌壇と絶縁したのは自己保身のためだったという推測も否定はできないであろうが、それ以前から南畝が狂歌と距離を取ろうとしていたことも事実だったのである」と当時の南畝の考え方を解説しています。
江戸時代屈指の知識人であった南畝だけに、人気になり過ぎて刺激の少なくなったジャンルに付き合うのは退屈だったのでしょうか。南畝はその後、一転して幕府内でその高い能力を生かしていく道を選ぶことになります。
大田南畝(四方赤良) 『狂歌百人一首』(江戸東京博物館所蔵) 出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/100411035江戸のカルチャーシーンを席巻し、蔦重をその中心人物のひとりへと押し上げた狂歌というジャンル自体が、そろそろピークを越えた時期、と言えるかもしれません。ここにも時代の大きな節目がありました。
壁にぶつかる治済、しぶとい意次
息子・家斉が将軍になり、これでやりたい放題かと思われた治済。しかし現実はそう簡単ではありませんでした。
将軍がまだ15歳と若いこともあり、うるさい御三家が「定信を老中にしろ」などと政治に口を突っ込みはじめます。
御三卿の治済より格上。しかも尾張の徳川宗睦、水戸の徳川治保、紀伊の徳川治貞と、いずれも領地の統治に優れた手腕を発揮したことで知られます。政治の実務にも明るいのです。一方、治済は「将軍の実父」というだけで、公的な肩書を持たない立場。権謀術数には優れていても、領地を持たないゆえ実務経験はありません。口を出せる範囲も限られます。江戸城内なら様々な工作も仕掛けられますが、相手が一国一城の主の御三家では手の出しようもありません。
その間隙をついて、したたかに立ち回ったのが意次でした。老中の肩書は無くなりましたが、余人をもって代えがたい実務能力と大奥も含めた人脈を武器に、治済と御三家の間を巧みに分断。政治を動かし、「裏の老中首座」とまで言われます。
失脚後の意次をあっさりとは退場させず、入念な書き込みでさらに見せ場を作りました。森下佳子さんや制作陣の意次に対する強いこだわりを思わせました。渡辺謙さんが「史実通り、意次が失脚することには変わりはありませんが、常に民のことを考え、厳しい事態になっても逃げない誠実な政治家でした。そうした姿を見せていきます」と答えていたとおりの展開。さて、簡単に倒れない意次に対し、定信や治済はどのように引導を渡しにいくのでしょうか。
治済が蔦重をマーク?大丈夫か蔦重
ここで思い切ったフィクションが登場しました。江戸城内が思うように行かないからか、治済が江戸市中で混乱を引き起こす工作に直接、関わりはじめます。流れ者に身をやつしたその姿、水戸黄門どころではありません。
治済の命を受けて数々の闇仕事をこなしてきた「丈右衛門」と呼ばれる男(矢野聖人さん)と組み、市井の人々を扇動。「お侍から犬を食え、と言われた」などと流言飛語を広め、幕政への批判を焚きつけます。意次らを牽制する目的があったでしょう。
そして何と言っても気になったのは治済の視線の先。
江戸の民衆のため、田沼家のためと東奔西走する蔦重の存在の重要性に、治済が気付いてしまったようです。蔦重、大丈夫でしょうか。心配です。
大奥周辺の工作を担当してきた大奥御年寄の大崎(映美くららさん)も治済と密談。こちらも動き出しそうです。
治済から大崎へ渡されたこの箱の中身は何でしょうか。この大きさってまさか……。何が起きるのでしょうか。
凄まじい熱中度、治済の能への傾倒
治済をめぐっては、序盤からお芝居、とりわけ能をフィーチャーした場面が目立ちました。今回も御三家とともに能を楽しむ様子を描写しました。これは史実に沿ったエピソードです。治済の能の愛好ぶりは人並外れたものだったからです。
国立能楽堂で2015年、「一橋徳川家の能」という特別展示が行われました。その展示や図録で最も紙幅がとられていたのは治済のトピックです。図録の解説「一橋徳川家と能」によると、一橋家では初代の宗尹むねただ(1721~1765)は能を嫌い、持っていた装束や御鼓、太鼓なども家来にあげてしまうほどでした。ところが息子の治済の代になって一変。家中で能の上演が度々行われようになり、本人も観世座の太鼓役者から太鼓の稽古をつけてもらうようになりました。
次いで邸内に本格的な能舞台をこしらえ、自らは宝生流の役者からシテ(主役)の稽古もつけてもらうようになり、舞う機会も増えました。
定信は能が嫌い
治済の能愛好は一橋家の財政を圧迫し、ドラマで描かれた時期に近接した天明5年(1785)には、財政難のため家中で倹約令がだされ、能の催しを減らすことになりました。が、その後も能の稽古を付けてくれた役者らに多額の褒美を出すなど、治済の能好きにブレーキがかかった形跡は見られなかったそうです。
一方、定信は幼少期は習っていたものの、16歳の頃からは能の稽古は止め、後には武士が能を愛好する事を忌み嫌うようになったといいます。一橋家では治済の息子たちも親に習って幼少期から能を学んでおり、そうした風潮について定信は「厳格な田安家と違い、一橋家では子供を可愛がり過ぎている」と批判的にとらえていたといいます。
今のところドラマの背景として意味ありげに描かれている能ですが、のちに治済と定信が対立する関係になることと合わせて、重要なモチーフになってくるかもしれません。覚えておいてよい要素かも。
「打ちこわし」前夜、我が心のままに生きよ
厳しくなる一方の市中の暮し向き。その貧困が直接の原因となって妻子を奪われた新之助(井之脇海さん)は、恩人の蔦重とも対立するようになります。
蔦重は新之助の住む深川の長屋の人々に差し入れするなど、精一杯の支援はしてきました。しかし、田沼家の内情も知るだけに、何かと為政者側の見方に立ってしまう場面もたびたび。それに対して新之助は「(蔦重は)吉原とそこに落ちてくる田沼の金で財を成した。ひょっとすると田沼の世で一番成りあがった男かもしれぬ」と容赦ない言葉を浴びせてしまいます。それもまた、一面の真実でしょう。蔦重は絶句するのみでした。
田沼の作った世に妻と子は殺された、と考える新之助。「それをおかしいと言うことも許されぬのか。こんな世は正されるべきだと声を上げることも」。その言葉は蔦重の心も震わせました。
「我が心のままに生きる。ワガママに生きることを自由に生きるっていうのさ」。平賀源内の言葉がよみがえってきました。
新之助の生き方にも共感した蔦重。打ちこわしに際して、「捕まったり、死んだりしないでくれ」と懇願。さらに「何に怒っているのかしっかり伝えるべきだ」とメディアの人間らしいアドバイスも送ります。
天明7年(1787)5月20日。江戸の街を大いに揺るがせた天明の打ちこわしが本格化します。赤坂、そして新之助たちの住む深川がその発火点となりました。次回、どんな展開が待っているのでしょう。
強烈な皮肉で庶民の怒りを伝えた黄表紙
のちに打ちこわしを題材にした黄表紙も世に出ました。「べらぼう」にも登場している唐来参和(ドラマでは山口森広さん)作の「天下一面鏡梅鉢」。これは強烈です。
[唐来参和] [作] ほか『天下一面鏡梅鉢 : 3巻』,[寛政1(1789)]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/9892637醍醐天皇の御代で、天下はよく治まっており、吾妻にあるみちのく山や佐渡の金山が焼けて諸国に金や銀が降りました。政治が素晴らしく、盗っ人もいないので、こんなおめでたい時代に家に戸はいらない、と人々は家の戸を壊しましたーーという説明無用の凄い中身。もちろん即刻絶版にはなりましたが、大いに評判になりました。この本を手にした庶民がどれほど留飲を下げたのだろうか、権力者に対する怒りはどれほど激しいものだったのだろうか、と当時の世間の空気を想像させます。これが物語というものが持つ力なのでしょう。(美術展ナビ編集班 岡部匡志) <あわせて読みたい>
視聴に役立つ相関図↓はこちらから