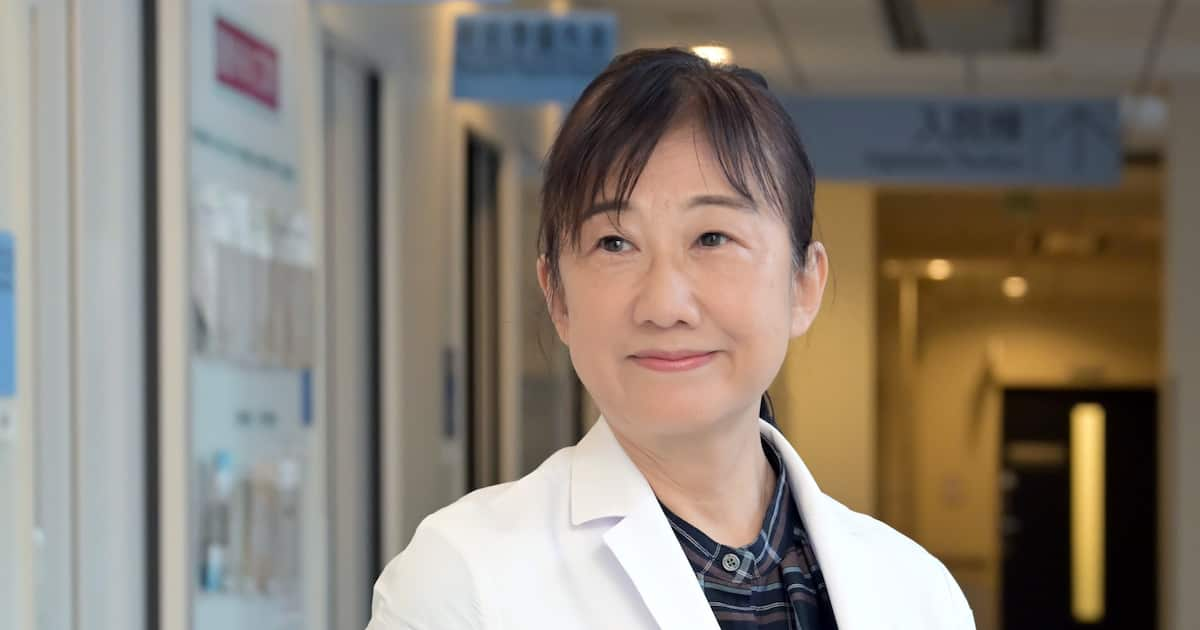高市氏と「昭和100年」日本初の女性総理は共通一次1期生、12歳で石油ショック

「昭和100年」にあたる令和7年に憲政史上初の女性総理に選ばれた高市早苗氏(64)。昭和3年に行われた最初の普通選挙から数えて97年、女性参政権が認められ39人の女性代議士が誕生した昭和21年から79年。奈良のサラリーマン家庭から日本のトップに立った女性が歩んだのはどのような時代だったのか。22日発売の『もし12歳が「昭和100年」を見たら 日本人のための現代史物語』(産経新聞社著、産経新聞出版発売)をもとに追体験してみた。
生まれた年にベルリンの壁
高市氏は戦後16年にあたる昭和36年3月7日生まれ。2日後の9日には福岡県香春町の上清炭鉱で坑内火災が発生、死者70人以上という当時としては戦後最悪の炭鉱事故となった。まだ日本のエネルギーが石炭中心だった時代で、石油が石炭を抜くのは翌年のことだ。
4月にはソ連のガガーリンが人類で初めて有人宇宙飛行に成功、「地球は青かった」の言葉を残した。一方でこの年1月に43歳の若さで米国大統領になったケネディはこれに対抗、さっそく「アポロ計画」を発表し、10年以内に人類を月に送ると演説した。当時は米ソ冷戦の真っただ中で、宇宙開発競争もしのぎを削っていた。
冷戦はさらに激化、8月には東ドイツにある東西ベルリンの間に、東側が有刺鉄線を張って行き来できないようにした。後にコンクリート壁による「ベルリンの壁」と呼ばれるようになり、28年後の平成元年まで続いた。
昭和36年は坂本九の「上を向いて歩こう」が大ヒットした年。岩戸景気真っ盛りの好景気で、「所得倍増計画」の池田勇人首相の時代だった。
中学生で高度成長期は終わり
高市氏は奈良県のサラリーマン家庭に生まれた。隣の大阪で万国博覧会が開かれた昭和45年は小学4年生で、6歳下の幼い弟がいた。当時の万博に出かけたという発言は過去みられないが、令和7年の大阪・関西万博をめぐっては昨年1月、能登半島地震からの復旧復興を優先するべきだとして、当時の岸田文雄首相に開催延期を進言したこともある。
石油ショックにより全国でトイレットペーパーなどの買いだめが起きた昭和48年末は12歳で中学1年生。長く続いた高度成長期は終わりを迎えて不況に突入し、翌年の消費者物価指数は20%超も上昇、急激なインフレは「狂乱物価」とも呼ばれた。
先行き不透明な世相を反映するように『ノストラダムスの大予言』『日本沈没』などの書籍が大ヒット。山口百恵、桜田淳子、森昌子らの「花の中3トリオ」がデビューした年でもあり、小中学生の間では加藤茶の「ちょっとだけよ」が流行語になった。
多感な時期にテロ相次ぐ
高市氏の中高校時代は、「過激派」と呼ばれる極左勢力によるテロが国内外で相次いだ頃と重なる。中2の夏休みにあたる昭和49年8月には東京・丸の内で三菱重工ビル爆破事件が発生、死者8人、負傷者約380人の惨事となり、その後も同じ組織による企業爆破事件が続いた。
翌50年には日本赤軍がマレーシアの首都クアラルンプールで米大使館などを占拠する事件が発生、52年にも日本赤軍による日航機ハイジャック事件があり、当時の福田赳夫首相が「一人の命は地球より重い」として要求に従い、犯人らの仲間を釈放した。この釈放は「超法規的措置」とされたが、各国からは「日本はテロも輸出するのか」と強く批判された。53年には過激派勢力の妨害で成田空港開港が2カ月近く遅れる事件もあった。
高校時代はアルバイトにも精を出していたという高市氏だが、これらのニュースは当時盛んに報道されていた。10代後半の多感な時期に極左勢力の身勝手な行動や政府の対応をどのような思いで見ていたのだろうか。
「旧1期校」に合格
高市氏が高校3年の大学受験期を迎えた昭和53年度は共通一次試験が導入された最初の年。入試制度が大きく変わることで受験生は混乱した。
前年までの各大学の独自試験と違って、マークシートの共通試験を受けてから各大学の2次試験を受ける仕組みとなり、受験生にとってより厳しい変化は「1期校」「2期校」として国公立が2校受けられたのが原則1校になったことだ。高市氏が合格した神戸大学は「旧1期校」だが、以前なら併願できた2期校は受けられなくなった。
両親から「短大でないなら学費を出さない」「女子の一人暮らしはさせられない」と言われていた高市氏は私立の早稲田、慶応にも合格。大学は実家の奈良から往復6時間かけて通学し、学費もアルバイトで稼いでいたという。
当時の国立大の授業料は約15万円で私立の半額以下だったが、女子の四年制大学進学率は12%ほどだった。
キャンパスでは軽音楽部に所属し、ヘヴィメタルバンドでドラムを担当、大型バイクも愛好した。同級生の多くが20歳となり選挙権を得るのは昭和55年。6月に行われた初の衆参同日選では、選挙戦の最中、大平正芳首相が心筋梗塞で急死し自民党が圧勝した。ただ、「早生まれ」の高市氏に選挙権はまだなく、最初の国政選挙への投票はもう少し先になる。
この年は山口百恵が引退し、松田聖子がデビュー。後に「TVタックル」などのテレビ番組で共演することになるビートたけしのツービートらがけん引した漫才ブームに沸いた年でもあった。
均等法には間に合わず
高市氏が初めて国政選挙に投票できたのは3年後の昭和58年7月の参院選と12月の衆院選だ。当時はいずれも中曽根康弘首相。参院は比例代表制が初めて導入された選挙で、自民党が過半数を獲得、衆院選は10月にロッキード事件の田中角栄元総理に懲役4年の実刑判決が出たことから「ロッキード解散選挙」とも呼ばれた。
この選挙で自民党は公認候補だけでは過半数を獲得できなかった。自民、社会両党が与野党の中心だった55年体制下で、自民は新自由クラブとの連立政権を初めて樹立することになった。
翌59年春に神戸大を卒業した高市氏は松下政経塾に入塾、グリコ森永事件が1年を通じて世間を騒がせ、陸上のカール・ルイスが活躍したロサンゼルス五輪が開かれた年だ。「戦後40年」となる翌60年の夏は中曽根首相の靖国神社公式参拝や日航機墜落事故という大きなニュースが続いた。高市氏が大ファンを公言する阪神タイガースの日本一もこの年だった。
61年9月には憲政史上初の女性党首として社会党の土井たか子委員長が誕生し、「女性の時代」が叫ばれた。この年4月には男女雇用機会均等法も施行されたが、高市氏の大学卒業時には間に合わなかったことになる。
最後の中選挙区制で当選
高市氏は昭和62年から米連邦議会に松下政経塾から派遣され渡米、平成元年に帰国した。昭和天皇が入院され、「昭和の終わり」が近づいていたころは日本にいなかった。この間、国内では、後に「バブル」と呼ばれる好景気が本格化、海外では日米貿易摩擦が深刻化する一方、円高で日本人海外旅行者が急増し、「金持ち大国ニッポン」「ジャパンバッシング」などの言葉も生まれた。
テレビキャスターなどを経て国政に初めて挑戦したのは31歳の平成4年7月の参院選。地元の奈良県選挙区で自民党公認に選ばれず無所属で出馬して落選した。翌5年7月、中選挙区制で最後に行われた衆院選も無所属で立候補、定数5の奈良選挙区でトップ当選を果たし、32歳で国会議員になった。
この選挙で過半数を割った自民は下野、細川護熙首相の非自民連立政権が発足した。昭和30年以来続いた55年体制は、すでに高市氏の政界デビュー時には終わっていた。この時の当選同期に安倍晋三、岸田文雄、野田聖子、林幹雄、野田佳彦、枝野幸男、前原誠司、志位和夫らがいる。(一部敬称略)
◇
産経新聞で連載された「昭和『100年』あのとき私は…」が書籍化、『もし12歳が「昭和100年」を見たら 日本人のための現代史物語』(定価税込み2310円、産経新聞出版)として発売されました。昭和元年から100年間の出来事を当時の市井の人々の日記や文集、新聞記事、新聞投稿などを参考に「12歳の目線」で描いた、かつてない歴史物語です。産経新聞社が所蔵する報道写真約300枚に加え、各年の年表やデータなども満載、A5版380ページ超の大型本です。
『もし12歳が「昭和100年」を見たら 日本人のための現代史物語』(産経新聞出版)