「すごい習慣」で仕事や人生を変える 科学的根拠に基づく小さなメソッドの大百科
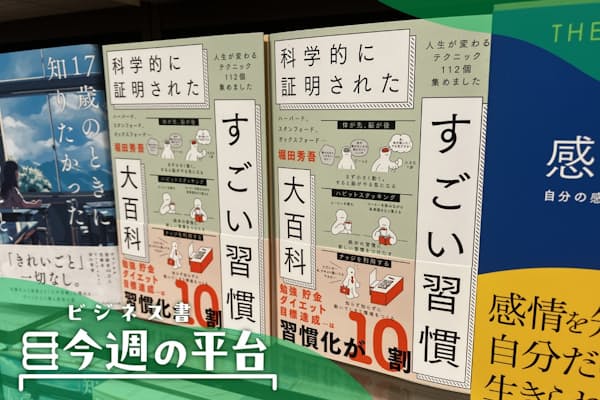
話題の近刊を集めた入り口近くのメインの平台に2冊並べて面陳列する(丸善日本橋店)
本はリスキリングの手がかりになる。NIKKEIリスキリングでは、ビジネス街の書店をめぐりながら、その時々のその街の売れ筋本をウオッチし、本探し・本選びの材料を提供していく。
今回は、2〜3カ月に一度訪れている準定点観測書店の丸善日本橋店だ。ビジネス書の売れゆきは雨がちな天気にも影響されて来店客数が伸びず、このところやや鈍り気味だという。そんな中、書店員が注目するのは、心理学や行動経済学、脳科学などの研究をベースに、「もっとラクに、もっと自然に、習慣化できる方法」を100以上紹介した習慣化テクニックの本だった。
自然に習慣をつくれる3つの原理
その本は堀田秀吾『科学的に証明された すごい習慣大百科』(SBクリエイティブ)。著者の堀田氏は法言語学、心理言語学が専門の言語学者で、明治大学教授だ。ビジネス書の著作も多く、テレビのワイドショーなどでコメンテーターも務める。研究活動を通じて集めた習慣化に関する科学的知見を、すぐに使える形に整理して一冊にまとめたのが本書だ。
まえがきで著者は言う。「私たちの脳や心はもともと"変化を嫌う"仕組みになっています」。それゆえ新しい行動を始めるのがおっくうになったり、続かなかったりする。そこをすり抜けるのが習慣の力だ。
誰でも自然に習慣をつくれる原理があるという。「まず動く」「すでに備わっている習慣にくっつける」「環境を利用する」の3つだ。この原理を知ってうまく利用すれば、仕事や勉強、運動などの成果を高める習慣が身に付き、人生を変えるような一歩を踏み出せると説く。
紹介するテクニックは112項に及ぶ。1つのテクニックごとにどんな効果があるのか、どこの組織・研究者の研究に基づくのかが見出し部分に表記され、見開き2ページの本文で具体的な方法や研究からわかったことなどを解説する。
例えば「別の作業をちょくちょく挟む」という項目では、効果は「集中力/注意力」、根拠となる研究は「イリノイ州立大学 アリガとレラスの研究」と見出し部分に明示される。一方、見開きの本文では、一般人は25分ほどしか集中力が続かず、それは脳が目標をだんだん忘れてしまうからだといった解説が語られていく。研究内容を紹介することで、テクニックの納得感を高める構成だ。
仕事の効率化にはルーティン化が有効
全体は「仕事」「勉強」「ダイエット・健康」「コミュニケーション」「メンタル」「生活」という6つの章に分かれ、各章に16〜21個のテクニックが並ぶ。「仕事」の章では仕事の効率化にはルーティン化が有効といい、先に紹介した「別の作業をちょくちょく挟む」のほか、「あえて乱雑な場所で仕事をする」「目標設定はコピペする」といったテクニックが解説される。
よく言われていることもあるし、そんなテクニックがあるのかと意外感のあるものもある。例えば「勉強」の章で取り上げている「ボールを握って記憶する」とか「テトリスを3分する」といったテクニックだ。大百科とうたっているだけに、112のテクニックが並ぶ目次を眺めて、気になるところを読んで試してみる、といった使い方が良さそうだ。
「習慣や法則を取り上げる本は色々出ているが、この本は入荷してからの動きがいい」とビジネス書を担当する石田健さんは話す。帯にある「習慣化が10割」という言葉に読者が反応しているのかもしれない。
『勉強脳』が3位
それでは、ランキングを見ていこう。20日発表の「ビジネス・経済」のベスト5だ。
1位は銀行が提案する事業承継プランの落とし穴を解説した本。長年のコンサルタント経験から経営者が陥りやすい失敗とその回避策、最適な承継スキームの見極め方を解説する。2位は、富士通で営業部門のデジタルトランスフォーメーション(DX)化に取り組んできた著者がその実践知を語った2024年8月刊の本。本サイトでは「リスキリングbooks」の一冊として〈日本企業「らしくない」アプローチで効率化 富士通が進めた営業DXのポイントは〉の記事で紹介している。
3位は、精神科医が効率的な勉強法を語った本。17年刊の『ムダにならない勉強法』の加筆・再編集版だ。4位は楽しむ人がうまくいくことを説いた自己啓発書。5位は社内評価や転職、人間関係で結果を出すための話し方を解説した本だった。今回紹介した『科学的に証明された すごい習慣大百科』は9位だった。
(水柿武志)



