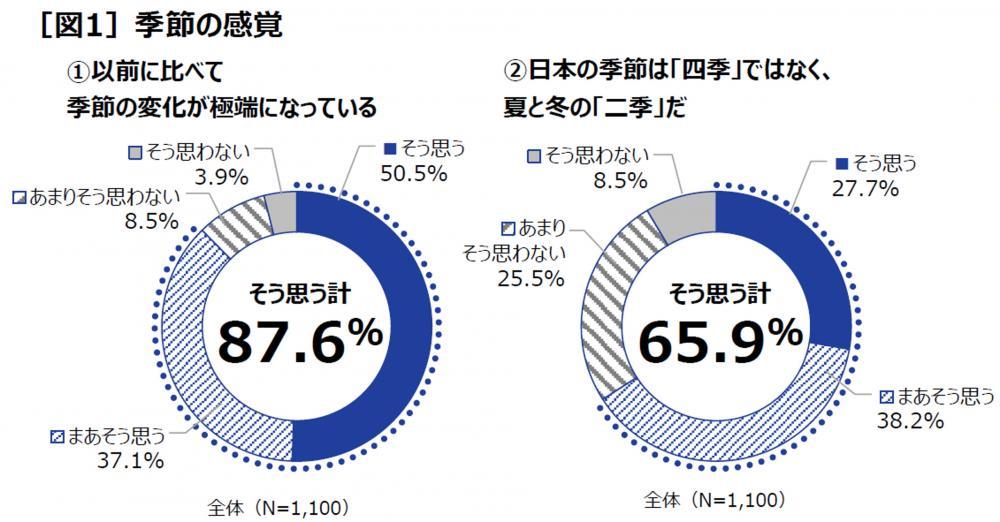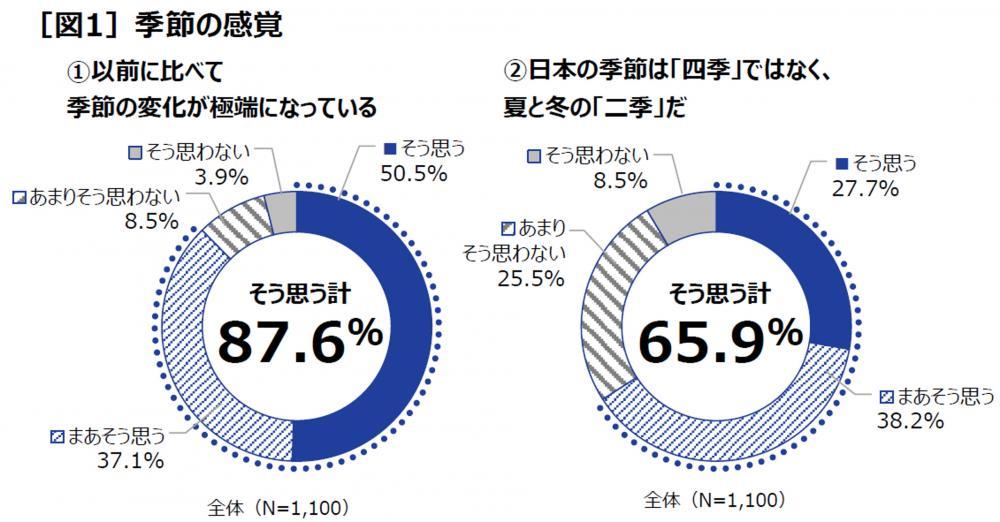認知症リスクを高める「お酒」「タバコ」だけじゃない意外な要因とは?(ダイヤモンド・オンライン)

9/12 10:40 配信
認知症は、特別な人の病気ではなく、誰にとっても身近な問題だ。近年では、何気ない生活アイテムや日常習慣が、認知症のリスクと関係している可能性があることが指摘されている。米国内科専門医・老年医学専門医の山田悠史氏は、著書『認知症になる人 ならない人 全米トップ病院の医師が教える真実』の中で、そうした日常行動と認知症リスクの関係について解説している。今回は山田氏に、普段持ち歩くかばんの中身に表れる「認知症リスク要因」について話を聞いた。(取材・文/新里百合子)● 認知症リスクをもっとも押し上げる要因は? ――著書を拝読し、認知症の最大のリスク因子が「難聴」であることに驚きました。飲酒や喫煙よりもリスクが高いという点は、多くの人にとって予想外の指摘ではないでしょうか。 そうなんです。喫煙や過度の飲酒も、もちろん認知症のリスク要因として知られていますが、実は「難聴」は、人口あたりではもっとも大きなリスクとされているのです。 開始時点で認知機能が正常な人々を対象に、25デシベル以上の聴力障害がある群とそうでない群を比較した8年間の追跡調査では、聴力に問題のある人の認知症リスクが1.9倍にまで上昇することがわかりました。 加えて、中年期における聴力低下が、脳の記憶を司る「海馬」や「側頭葉」全体の容積がより早く減少することと関連しているという興味深い研究もあります。 こうした知見は、聴力の問題が単なる「聞こえ」の不調にとどまらず、脳の構造的変化や認知機能低下の引き金となりうることを示しています。だからこそ、予防的なアプローチが重要なのです。
――脳の構造や機能にまで影響を及ぼすとなると、看過できない問題ですね。日常生活では、どのような点に注意を払えばよいのでしょうか?
● 「難聴」にならないために気をつけたいこと 日常的にテレビや音楽の音量を上げがちな方は、知らず知らずのうちに、聴力にダメージを蓄積している可能性があります。大きな音に継続的にさらされる生活では、時間の経過とともに聴力の低下につながりやすく、結果的に難聴を招き、それが認知症リスクにつながる可能性が示唆されています。 ――そんなにも影響があるんですね。どのくらいの音量から気をつけるべきなんでしょうか? 難聴リスクが高まるのは、一般に80デシベル以上の音です。これは、たとえばにぎやかな居酒屋での会話、ピアノの生演奏、カラオケ店の店内といった音環境に相当します。イヤホンやヘッドフォンでも、このレベルは簡単に超えてしまうんですよ。 ――思い当たるシーンがたくさんあります……。私も電車の中ではついボリュームを上げがちです。 そうですね。通勤中に音楽を大音量で聴くという方も多いでしょうし、静かな場所では音量を抑えていても、周囲がうるさくなると無意識に音を上げてしまうこともある。野球場やコンサート、サッカーのスタジアムなども含めて、大音量にさらされる場面は意外と身近にあるものです。● 持ち歩いているアイテムでわかる「認知症になりやすい人」の特徴 ――テレビやイヤホンの音量は、これからもっと意識したいと思います。日常生活で、ほかに気をつけるべき行動はありますか? また、手軽に“自分の認知症リスク”を確認する方法はありますか 生活習慣を確認する方法といえば、「日頃どんな物を持ち歩いているか」――つまり“かばんの中身”を確認してみるだけでも、その人の生活スタイルや将来的な認知症リスクの傾向をある程度推測できるかもしれませんね。
一見すると関係がなさそうな持ち物にも、実は日頃の“癖”が透けて見えることがあります。たとえば、次のようなアイテムとその使い方を確認することで、生活習慣を見直すきっかけにしていただければいいのではないでしょうか?
● 認知症リスクが高い可能性がある人のかばんの中身 (1)イヤホン まずは、先ほども言及したイヤホンですね。例えば、窓を開けた地下鉄の中は、難聴リスクが高まる80デシベルを超える環境です。その音に負けないようイヤホンの音量を上げると、さらにリスクは高まります。 (2)スマートフォン(受動的な使用を中心とした場合) スマートフォンは、活用の仕方によって認知機能への影響がプラスにもマイナスにも働く可能性があります。SNSを長時間見ることは、うつ病のリスクを高める可能性が指摘されています。そして、うつ病もまた、認知症のリスクであることが知られています。例えば、ある大規模な研究では、うつ病のある人は認知症のリスクが約2倍になると報告されています。 (3)たばこ 約96万人のデータを扱った大規模な研究では、喫煙者は非喫煙者と比較して、認知症リスクが約30%増加することが報告されています。たばこが肺気腫や肺がんの原因になることはよく知られた事実ですが、そこに認知症という病気のリスクも加えておく必要があります。 (4)甘い飲み物のペットボトル 1日1本以上の砂糖入り清涼飲料水を飲む女性は、月に1本未満しか飲まない女性と比べて、糖尿病発症リスクが1.83倍になると報告されています。糖尿病、中でも2型糖尿病は、認知症発症のリスクを高める重要な要因として知られています。 (5)“ウコン系”などのサプリメント類「酒の飲みすぎ前提」で摂るサプリには、生活習慣そのものが不健康である可能性が潜んでいます。過去の研究によると、週に約168グラム以上のアルコールを摂取する人は、それより少ない量を飲む人と比べて、認知症のリスクが約18%高くなるそうです。 アルコールの量を缶ビール(350ml)に換算してみると、1日あたり約2本以上飲む人が「週に約168グラム以上のアルコールを摂取する人」に該当する、ということになります。晩酌や飲み会などで、それ以上飲む習慣がある人は、飲酒量を見直す目安にしていただければと思います。 (6)書籍や資料など勉強するものが一切ない 大人になってから勉強をやめたり、知的な活動に参加しなくなったりすると、脳への刺激が減少します。脳は使わないと機能が低下する臓器であり、日々の生活で頭を使う機会が少なくなると、認知機能が徐々に衰えてしまいます。
一方で、仕事や日常生活での認知的な刺激、つまり頭を使う活動が豊富である人は、認知症のリスクが低いことが知られています。ただ、脳トレやパズルなどの効果は極めて限定的で、認知症を防ぐ長期的な効果はいまだ示すことができていません。仕事以外でも、「継続的に新聞や本を読む」といった、知的な活動が重要です。
● 認知症リスクが低い人のかばんの中身 ――甘い飲み物が糖尿病リスクとなり、それも認知症リスクになっていく……。こうした目線で日常の生活アイテムを振り返ることで、認知症予防意識が高まりますね。では、反対に、認知症になりにくい人の生活習慣や「かばんの中身」には、どんなものがあるのでしょうか? そうですね。たとえば、認知症リスクを下げる生活習慣がある方は、甘い飲み物ではなく水やお茶を携帯していたり、運動習慣があるので運動グッズやスポーツウェアなどを日常的に持ち歩いたりするかもしれませんね。 運動が認知症予防に役立つ可能性についてのエビデンスは思ったほどクリアではありません。ですが、とある研究によると、男性に限っていえば、運動を行った2つのグループで軽度認知障害のリスクが低下し、認知機能のスコアも高かったことが知られています。 昼休みや退勤後にジムへ行くなど、「身体を動かす習慣」がある方は、認知機能とはまた別のところでも多くの健康上の利点があり、それらが間接的に認知機能の維持にも寄与する可能性があります。 また、あまり知られていないかもしれませんが、目から入る紫外線を防ぐことは、白内障の予防となり、脳の健康を守る間接的な手段です。
サングラスを持ち歩いて、日差しが強いところでは装着する習慣も、目の機能を維持して脳への情報の「入口」を守るという視点で、非常に大切なのではないでしょうか。
● スマホを持つことが悪いわけではない!使い方が大事 ――スマートフォンはいかがですか? デメリットの方が多いのでしょうか? SNSの過度の利用がうつ病のリスクを高める可能性が指摘されている一方で、とある研究では、スマートフォンやパソコンなどのテクノロジーを利用する高齢者は非利用者に比べ、認知機能障害(軽度認知障害や認知症の診断、認知機能テストにおける低スコア)のリスクが平均42%低いことと関連することが明らかになりました。 他の研究結果とも統合して考えると、テクノロジー利用がもし脳にプラスに働くとすれば、それは情報検索や文章作成、コミュニケーションなどの「能動的な活動」が認知予備力(cognitive reserve)を高めている可能性が指摘できますね。いずれにせよ、「目的を持った適度なテクノロジー利用」がおそらくもっとも有益なのでしょう。 ――体を動かすことを心がけて、肥満に気をつけるなどの生活習慣が、健康に影響を与え、認知症リスクの確率を上げ下げしていることがよく理解できました。 こうした持ち物は、日々の生活習慣を象徴する“選択の縮図”であるとも考えられます。脳の健康にとって大事なのは、決して特別な対策ではなく、こうした日々の小さな選択、生活習慣の積み重ねなんです。 私たちの体や脳は、日々の生活や環境、遺伝子など、数えきれないほどの要素が複雑に絡みあっています。そうしてリスクが積み重なることで「認知症になりやすくなる」、リスクを下げることで「認知症になりにくくなる」という、確率の上げ下げの世界を生きている、という意識を持っていただきたいと思います。
だからこそ、誤った情報に惑わされ貴重な時間や費用を無駄にするのではなく、科学的根拠に基づいて認知症のリスクを下げ、適切に対処することが大切なのではないでしょうか。
ダイヤモンド・オンライン
最終更新:9/12(金) 10:40