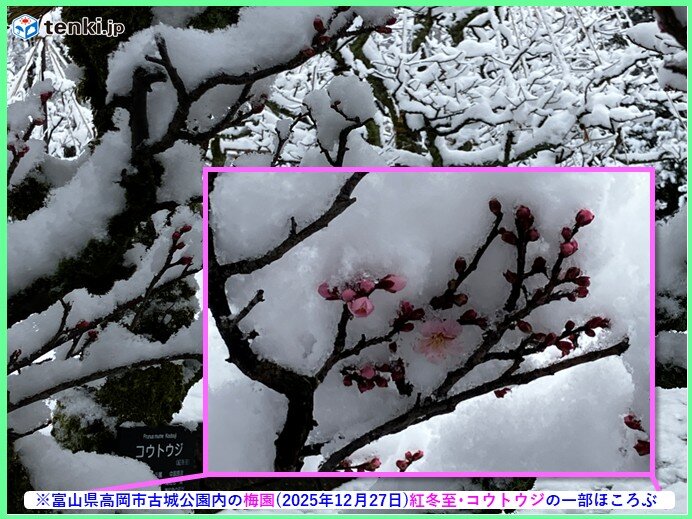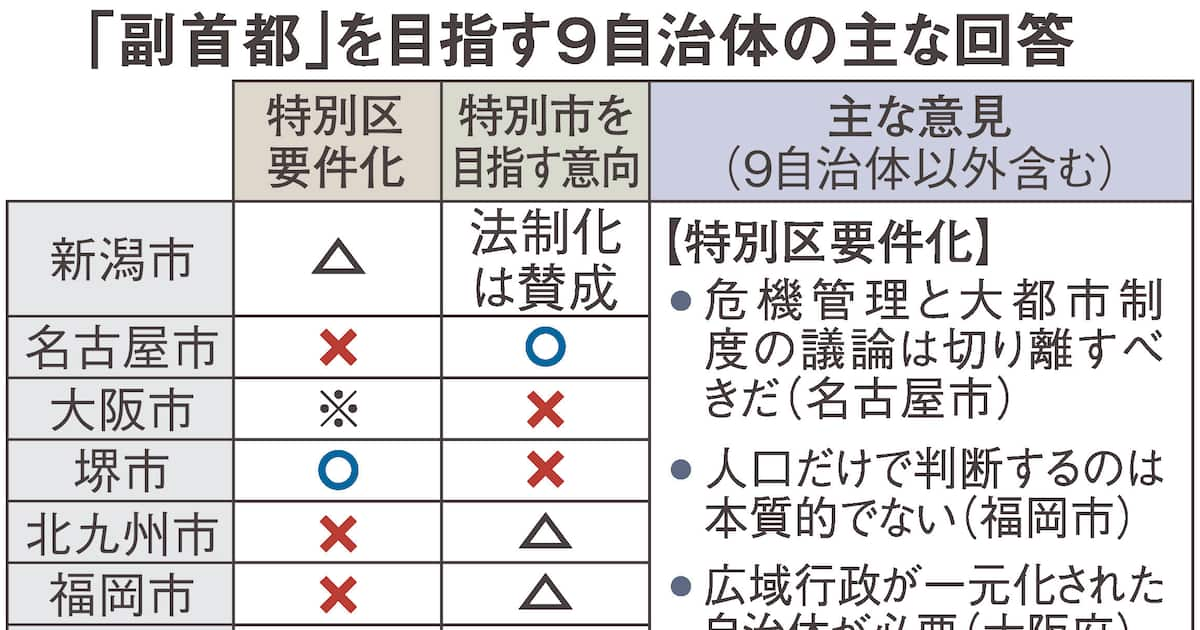世界遺産の知床に太陽光パネル320枚 観光船事故受け、携帯基地局電源用 火災リスクも

北海道の国立公園、知床が世界自然遺産に登録されて17日で20年となる中、世界遺産地域内で携帯電話の基地局を建設する事業が迷走している。3年前の観光船沈没事故で携帯のつながりにくさが課題となり、国や通信事業者が計画。電源供給用の太陽光パネルなどを設置する予定だったが、国の天然記念物オジロワシが営巣している可能性が判明し、国は事業を一部凍結した。環境保護か安全確保か。地元でも賛否は分かれる上、太陽光パネルの火災時の対応なども懸念されている。
知床岬の264枚は凍結
事業のきっかけは令和4年4月、26人が死亡・行方不明となった観光船沈没事故だった。現場一帯が携帯電話の通信エリア外だったことを受け、地元の斜里(しゃり)町や羅臼(らうす)町などが国に通信環境の改善を要請した。
国は「知床岬」など世界遺産地域内外に4カ所の基地局建設を計画。国立公園を所管する環境省は6年3月に事業を許可した。
ところが、このうち知床岬では電源供給のためサッカー場1面分に当たる約7千平方メートルの国有地に、太陽光パネル264枚や蓄電池を設置する計画で、北海道自然保護協会など自然保護団体や地元の斜里町長が見直しを求める事態となった。
環境省によると、基地局へ供給する電源として当初は重油や石油を燃料とする発電なども検討されたが、最終的には太陽光発電が最適との結論になったという。だが、許可後にオジロワシが営巣している可能性も判明し、国や大手携帯電話会社らで構成する「知床半島通信基盤強化連携推進会議」は6年10月、知床岬での事業を凍結した。現在は今後について検討を進めているという。
残る3カ所のうち観光名所の「知床五湖」と世界遺産区域外の「ウトロ地区」はすでに運用中で、既存施設の太陽光以外の電源を使っている。
一方、羅臼町側の「ニカリウス地区」は海岸の約2千平方メートルの敷地に太陽光パネル320枚を設置する計画で、事業者が環境影響調査中だ。完成すればパネルの高さはビルの3階部分に相当する約10メートルになるという。
「ニカリウス地区」の携帯電話基地局建設予定地=北海道羅臼町(環境省提供)鳥の専門家「データ公開を」
ニカリウス地区の計画は現在、知床岬灯台での調査不備を踏まえ、専門コンサルタント会社による整備予定地周辺での環境影響調査が進む。昨年12月の調査では、上空をオジロワシが飛翔したり、木の枝に止まっていたりする姿を確認。建設予定地から300メートルの場所では木の枝に並んで止まる雌雄2羽の成鳥もあり、専門家は「繁殖につながるつがいの可能性がある」と指摘する。
オジロワシの生態に詳しい東京農業大生物産業学部の白木彩子准教授は、知床半島が国立公園特別保護地区や世界遺産地区に指定されているエリアであることも踏まえ、「環境省の手引きでは、繁殖する希少猛禽類に対する環境影響評価には最低でも2回の繁殖期を含む1年半にわたる調査が求められており、これらの保護区ではそれに準じた調査が必要と考える」。
今回の調査は昨年12月と、今年4~8月に行われているが、「期間も回数も不足している」と継続中のニカリウス地区の調査手法に疑問を投げかける。
オジロワシ(日本野鳥の会提供)さらに警戒心の強いオジロワシへの影響は大きな懸念要素だ。設置工事や定期メンテナンスで人の出入りが増えることで営巣を放棄したり、餌場が利用できなくなったりする可能性があるといい、「餌が捕れなくなれば繁殖率の低下を招く恐れもある。一般的に、事業予定地は営巣地から500メートル以上は離すべきとされるが、非繁殖期も含めて餌場やとまり場への配慮も必要」と訴える。
鳥類に対する太陽光パネルの影響については明らかになっていないことが多いが、「科学的な根拠に基づいた対策が必要になる。そのためには調査結果を共有して協議すべき」と話す。
地元漁師らにも温度差
ニカリウス地区がある羅臼町は湊屋稔町長が「漁師の人命が第一」として推進を求め、町の漁協や観光協会など12団体も推進を求める意見書を国に出している。
自然保護団体は「原生的な自然を楽しむ人の利便性のために自然を破壊するのは本末転倒だ」と反対。観光船や漁船は業務無線や衛星携帯電話を確保したほうが費用対効果が高いと主張する。
ただ、衛星電話は機材が大きく、羅臼町で盛んなコンブ漁で使う小さな船には積めないという。
地元漁師の間にも温度差がある。50代の漁師は「守るべきは人間の命」と訴える一方、30代の漁師は「使えるようになれば便利だけど、個人的にはそこまでしなくてもいいんじゃないか」と話した。
別の30代の漁師は最近、ニカリウスの沖合での漁船トラブルを経験したばかりという。エンジントラブルで動けなくなり、わずかに電波が届く沖合まで潮に流されながら電話がつながる場所から電話で救助を要請。仲間の助けで事なきを得た。
知床半島の相泊漁港。漁師たちが作業していた=今月10日、北海道羅臼町(坂本隆浩撮影)主力のコンブ漁は電波が届かない知床半島の先端周辺エリアの沿岸でも操業する。急な天候変化がありそうな時は仲間と一緒に船団で早々に帰港するといい、日ごろからの危険を察知する習慣が事故を未然に防ぐ力になっていることを強調し「個人的には環境を大切にしたいという思いが強い」と語った。
また、町職員の一人は「太陽光パネルにはこだわらない」と話す。最近は大手携帯電話会社が導入した衛星からの電波を受信するサービスがスタート。知床半島の先端周辺では現時点で「携帯電話のショートメールが届くぐらい」だが、環境への影響が懸念される太陽光パネルは「技術革新の進歩が進めば、つける必要はなくなる」というスタンスだ。
消火活動が極めて困難
太陽光パネルによる環境への影響が懸念された知床岬基地は凍結されたが、ニカリウス地区の整備事業は修正がないまま現在も計画が進んでいる。
地元住民の一人は太陽光パネルの火災事故が全国で起きていることに言及。発火した状態でも発電するため消火活動が極めて難しく、知床半島のような場所では現場急行に時間がかかるなど大きなリスクをはらむと指摘し、拙速な議論に危機感を隠さない。
一方、知床が世界遺産に登録された当時の斜里町長で、現在は「知床の自然を愛する住民の会」の会長を務める午来昌(ごらいさかえ)氏(89)は取材に対し、世界遺産に登録されるまでの苦労を振り返りつつ、「人は不便さを乗り越えながら生きる知恵を培ってきた。余計な人工的設備を求めるのではなく、自然そのものの価値や豊かさを守るべきだ。今の不便さこそが生きる知恵であり、自然の恵みをもたらす」と話した。
環境省は取材に対し、知床岬の事業許可について「自然公園法に基づき適切に行われたものと考えている。その報告を受けた知床世界自然遺産地域科学委員会から『オジロワシがいるならより慎重に調査したほうがいい』との助言を受けたとの認識で、こちらの対応に問題はない」と説明する。
また、斜里町が知床岬の計画見直しに方針転換したことについては「地元自治体の要請を受けて進めてきた事業であり、事前調整の中で太陽光パネル設置などは知っていると思っていたので、驚いている。計画は凍結されたが、今後は改めて検討していくことになるのではないか」と話している。
【知床】北海道東北端の斜里町と羅臼町にまたがる地域。長さ約65キロ、幅約25キロの半島で、周辺海域と合わせヒグマや希少な動植物の生物多様性が評価され平成17年7月17日、世界自然遺産に登録された。