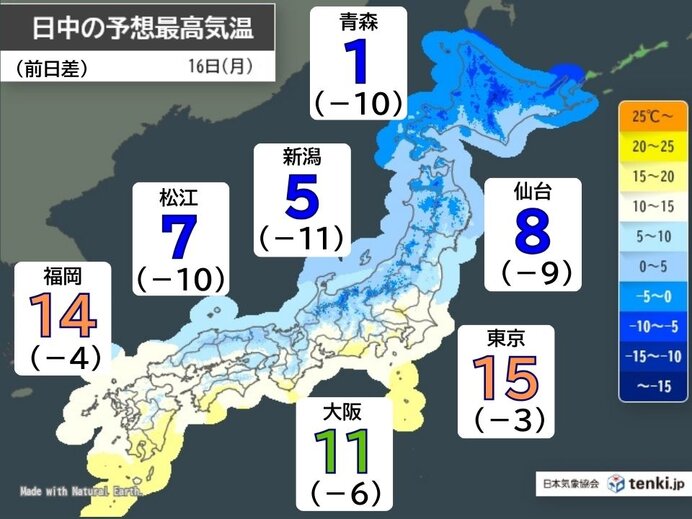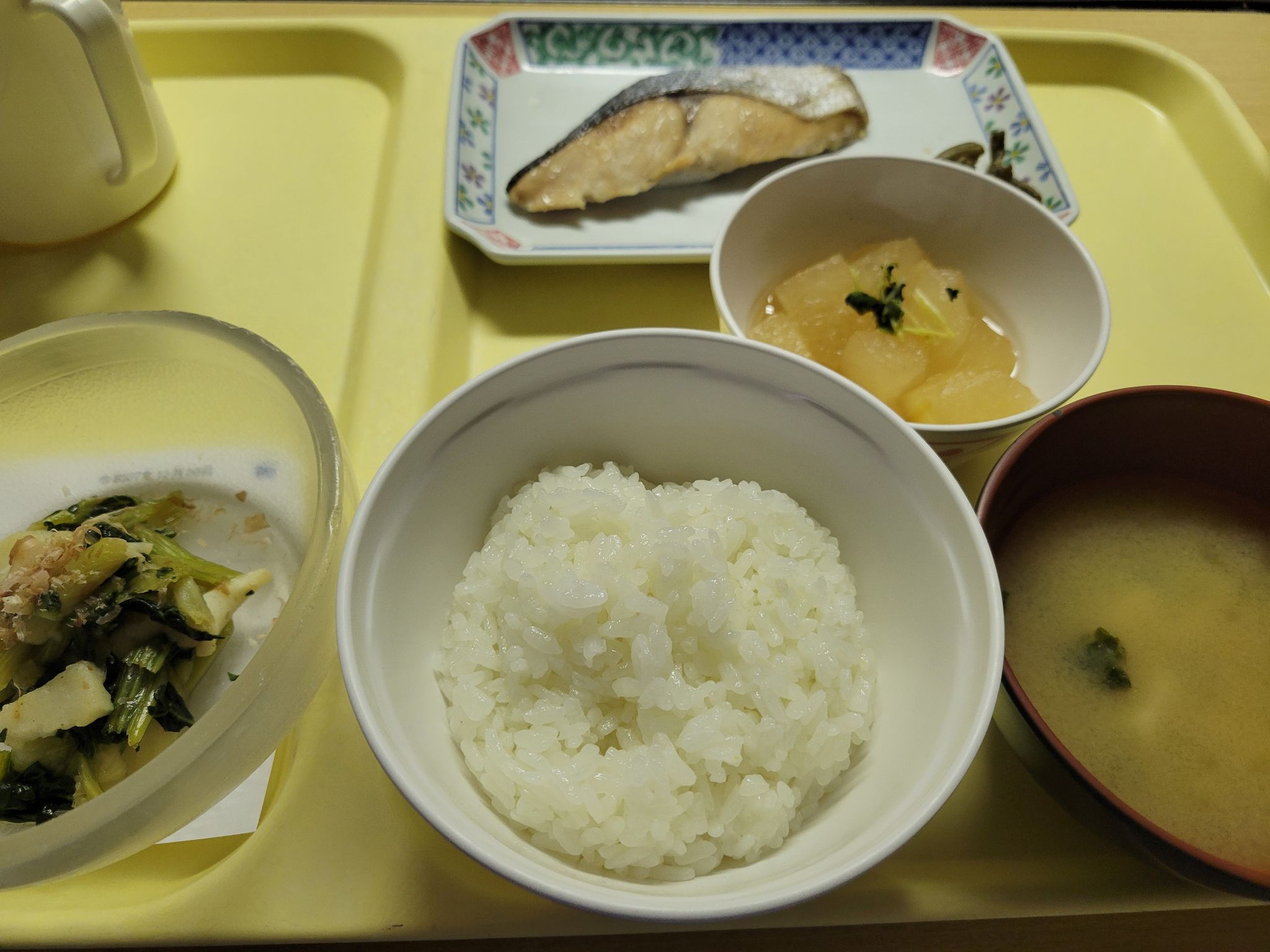自民総裁選、高市・小泉両氏軸に5人の争いに-党再生かけ論戦

自民党総裁選が22日告示され、5人が立候補した。10月4日の投開票に向け、前回上位につけた高市早苗前経済安全保障担当相と小泉進次郎農相を軸に党の再出発をかけて論戦を展開する。
石破茂首相の辞任表明に伴って実施される今回の総裁選に出馬したのは高市、小泉両氏のほか、茂木敏充前幹事長、小林鷹之元経済安全保障担当相、林芳正官房長官の計5人。23日には共同記者会見や討論会に臨む。
減税などの物価高対策、連立拡大を含めた野党との連携の在り方が争点となる。農業政策や防災庁など現政権が進めた政策の進め方を巡っても論戦が交わされそうだ。市場では年内利上げを模索する日本銀行の金融政策への発言も注目されている。
22日の債券相場は下落しており、日銀による早期利上げ観測の高まりを背景に売りが優勢だ。株式相場は上昇した。円相場は午後5時20分現在、1ドル=147円90銭台で推移している。
関連記事:自民総裁選は物価高対策が争点、一律給付は実現困難に-候補者横顔
持論を封印
5人はいずれも昨年に続いての挑戦だ。党所属国会議員の295票と同数に換算した党員・党友票の計590票を争う。前回は約70万の有効党員票のうち石破氏と高市氏がそれぞれ約20万票、小泉氏が約12万票を他の候補者を大きく引き離して確保した。議員票では小泉氏が最多の75票、高市氏が72票、石破氏が46票を得た。
総裁選挙管理委員会が21日発表した党員投票の選挙人数は約91万6000人で前回から約14万人減った。
石破首相が前回獲得した票の行方も鍵となる。保守的な言動と積極財政派として知られる高市氏と、昨年は規制改革とリベラルな政策を掲げていた小泉氏。先週の出馬会見では幅広い支持を得るため、従来の主張の一部を封印した。
高市氏は参院選前の5月、食料品への消費税率(8%)を0%に引き下げるべきだとしていたが、総裁選公約には盛り込まなかった。19日の会見ではレジの対応などで実現には時間がかかり、「今の物価高対策として即効性はない」と語った。日銀の利上げには昨年9月の時点で批判的な発言をしたが、出馬会見では触れなかった。
ただ、22日に出演した日本テレビの番組では、消費減税に即効性がないとした理由として党内で自分の主張が受け入れられなかったことも加えた。「少し時間のかかる問題として選択肢としては排除しない」と今後の検討課題として位置付けた。
同日の所見発表演説会では党内右派にアピールする発言があった。外国人観光客らによるトラブルを挙げ、「日本人の気持ちを踏みにじって喜ぶ人が外国から来るようなら何かをしないといけない」と指摘。外国人政策を「ゼロベースで考える」と強調した。
一方の小泉氏は前回主張した解雇規制改革や保守層が反発している選択的夫婦別姓を導入するための法案提出を公約から外した。演説会では冒頭、石破首相に敬意を示し、党の結束を呼び掛けた。外国人問題は司令塔機能を強化するとした。
消費減税に関しては、物価高対策などを巡る野党との協議も視野に「あらゆる選択肢は排除しないのが基本だ」との見解を日本テレビの番組で語った。
野党との連携
前回総裁選が行われた昨年9月と異なり、与党の議席数は衆参両院で過半数を下回っている。安定した政権運営を行うため、候補の5人から記者会見などで連立の枠組み拡大など野党との連携強化を目指す発言が相次いでいる。
高市氏は「基本政策が合致する野党とできれば連立政権を組む」考えを示した。小泉氏は「野党に幅広く政策協議を呼びかけ、与野党合意を模索する」としている。茂木氏は「新しい連立の枠組みを追求し力強い政権基盤を固める」とし、日本維新の会や国民民主党を選択肢に挙げた。
野党との政策協議を意識した政策も目立つ。高市、小泉両氏らは野党各党が求めているガソリン暫定税率の廃止や、国民民主が特に重視する基礎控除の在り方など所得税制の見直しに言及した。維新が提唱する副首都構想につながる東京一極集中の是正に向けた取り組みを行う方針を打ち出した。
高市氏は、公約で減税と現金給付を組み合わせた「給付付き税額控除」の制度設計着手を明記した。同制度を巡っては、与党と立憲民主党が協議体設置で合意している。
早期の解散を否定
昨年当選した石破氏は首相就任から8日後に衆院を解散したが、今回は候補者全員が22日の日本テレビの番組で早期解散を否定した。
小泉氏は、「国民が求めているのはこれ以上の政治空白ではなく、物価高や治安、社会保障の問題に対して前に進めること」だと指摘。高市氏も「今そんなことをやっている暇はない」と語った。他の3人も両氏の意見に賛同した。
朝日新聞が20、21両日に実施した世論調査によると、新しい自民総裁に誰がふさわしいかとの問いに高市氏が28%でトップ、小泉氏が24%で続いた。自民支持層に限ると小泉氏が41%、高市氏が24%だった。
— 取材協力 Erica Yokoyama, Hidenori Yamanaka and Toshiro Hasegawa