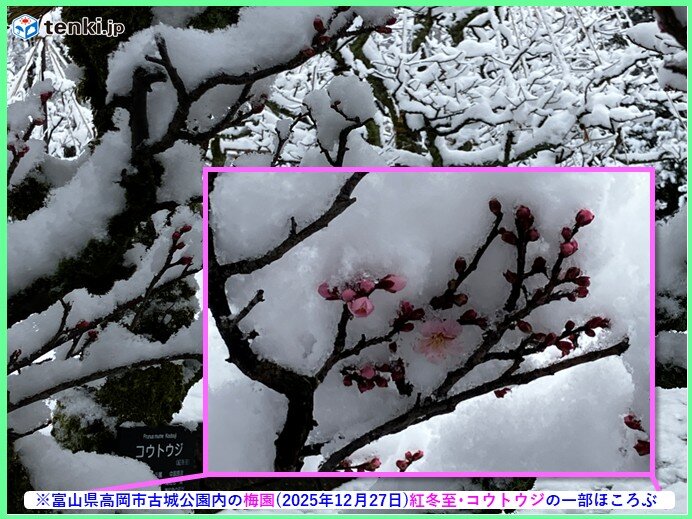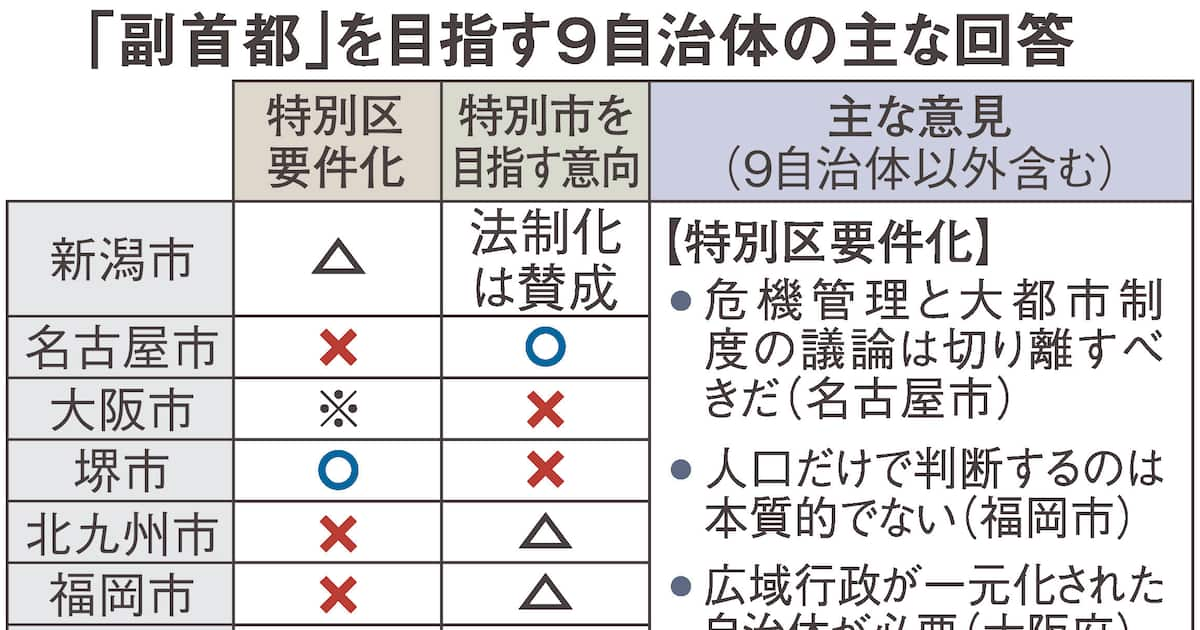SNSと選挙 「8割以上がフェイク情報を見抜けず」 自己評価高い人ほど注意を 山口真一・国際大准教授
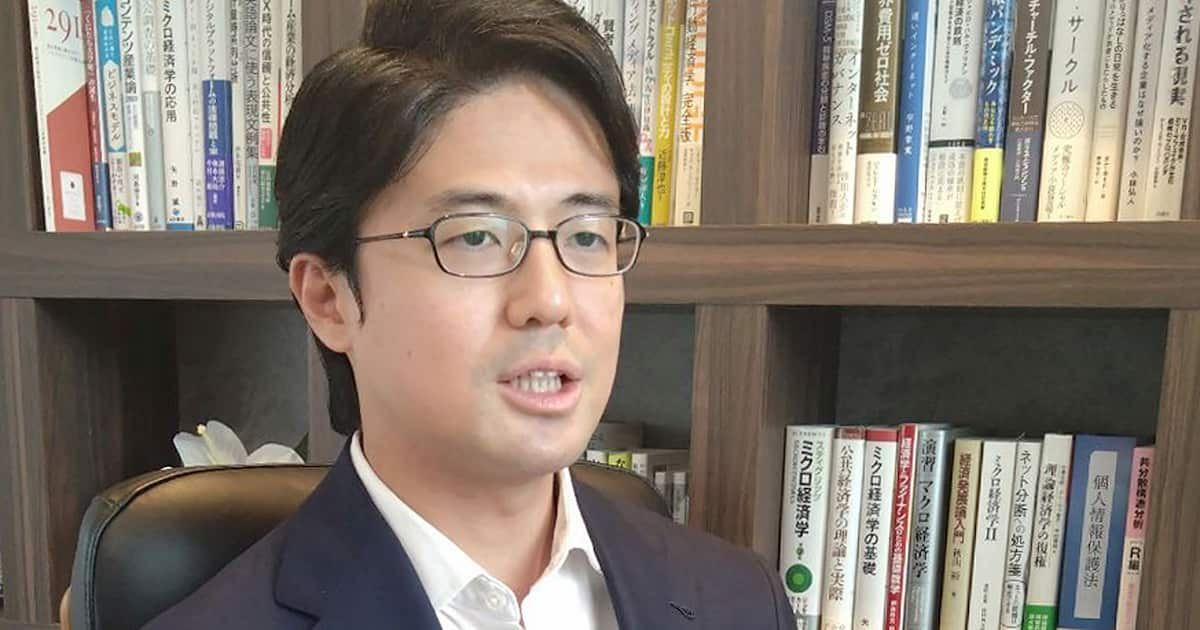
国内外の選挙で交流サイト(SNS)の影響力が増す中、参院選は20日、投開票を迎える。SNSの利用は若年層の政治参加を促す一方、フェイク(偽)情報や誹謗中傷の拡散など課題も顕在化している。ネットメディアに詳しい国際大の山口真一准教授は「8割以上の人はフェイク情報を見抜けない」と語る。有権者はSNS選挙にどう向き合えばいいのか、山口氏に聞いた。
--SNSと選挙の関係は
「東京都知事選と兵庫県知事選のあった2024年が転換点だった。都知事選では石丸伸二氏(地域政党『再生の道』代表)が2位に躍進し、兵庫県知事選では斎藤元彦知事が返り咲いた。いずれもSNS上で人気の候補だった。それまでSNS上で政治的な話題が盛り上がることはあったが、結果に大きな影響を与えることはなかった。20年の都知事選では、SNS上で現職の小池百合子知事を応援する声は少なく、批判的な意見が多くを占めた。だが、結果は小池氏の圧勝で、インターネット上の言説と選挙結果には乖離があった。4年後、状況は変わり、SNSが結果に影響した」
外国人政策が焦点に
--今回の参院選ではどうか
「かなり盛り上がっている。例えば、『日本人ファースト』を掲げ、外国人規制を訴える参政党が支持を広げている。SNS活用にたけており、投稿数が多いだけでなく、神谷宗幣代表の街頭演説などを拡散する支持者に対し、SNSのうまい活用方法を指南している。1つの投稿に対するリポスト(転載)数も多い。その結果、他の政党も外国人政策について言及し始めた。参院選の大きな争点になり、政府も外国人問題に対応する司令塔組織を設置した。この時点でSNSが参院選を大きく動かしているといえる」
--ネット上には膨大な情報があり、取捨選択が難しい
「SNSには良い面も悪い面もある。兵庫県知事選では関心が集まった結果、投票率が約15ポイントも上昇した。デメリットとしては、煽情的な話題や怒りが拡散されやすいことだ。広告収入目当てで過激な投稿をする人もおり、そうした情報が蔓延すると意見が極端化していったり、対立していったりする。兵庫県知事選を巡っては大量の誹謗中傷が広がり、元県議が亡くなってしまった。深刻な民主主義の危機だ」
「本来選挙は、民主主義のプロセスの一つに過ぎない。選挙は競争だが、それが終わればみんなで議論して、よりよい社会を作っていこうというのが民主主義だ。選挙であまりに分断が進むとその後の熟議ができなくなってしまう」
代表にインフルエンサー力
--情報の真偽はどう見極めたらいいのか
「私の研究では偽情報を見聞きした人の中で、それが偽と気づけている人は14・5%しかいなかった。批判的思考態度が取れていると自己評価が高い人ほどだまされやすい。謙虚な気持ちで情報空間に接することが重要だ」
「選挙情報ならば、マスコミ各社がそれぞれの政党の公約や争点を一覧して比較できるように発信している。各政党のホームページもよくまとまっている、また、ネット上で簡単な質問に答えると、自分の考えと一致する候補者や政党が数値で示されるボートマッチもたくさんある」
--SNSでは強いメッセージを発信する政党が強い
「参政の支持率の伸長は衝撃的だ。参政以外でも、国民民主党、日本維新の会、日本保守党、れいわ新選組などは代表が強く、政党というよりは代表にインフルエンサー力がある。そのほかの政党にはこれといったインフルエンサーがいない」
「安倍晋三政権下では自民党もネット戦略にたけていて、若い世代にも支持されていた。当時はネット上で民主党をたたけば閲覧数が増えていたが、今は自民をたたけば閲覧数が増えるようになり、ネットの機運としては自民がかなり低い位置に置かれている。ただネット人気は生ものなので一気にしぼむこともある」
収益化の規制が有効
--先の国会で与野党は偽情報対策などの規制強化に向けた法整備について議論したが「表現の自由」との兼ね合いからまとまらなかった
「海外ではフェイクニュース規制法を根拠に政府批判が抑圧されているケースもある。ただ、マネタイズ(収益化)目的の真偽不明の投稿が有権者の行動に影響を与えるのは問題だ。選挙期間中に限り、選挙に関連したコンテンツによる収益化を規制する方法が有効ではないか。お金がもうからないが表現はしていいので『表現の自由』と両立するのが利点だ。何を選挙関連コンテンツと定義するのかなど議論の余地は少なくないが、早く具体化していくべきだ」
--メディア情報リテラシーの向上も課題だ
「私の調査では、国際的に見ても日本在住の方は情報検証をしない傾向にあった。情報の真偽を見極めたり、正しく活用したりするためにメディア情報リテラシーを教育課程に組み込む段階に来ている」(聞き手 長嶋雅子)
□
やまぐち・しんいち 1986年生まれ。慶応大経済学部卒。専門は計量経済学。研究分野はネットメディア論、情報経済論など。2020年より現職。政府の有識者会議委員や企業のアドバイザーを務める。著書に『ネット炎上の研究』『ソーシャルメディア解体全書』(いずれも勁草書房)など。