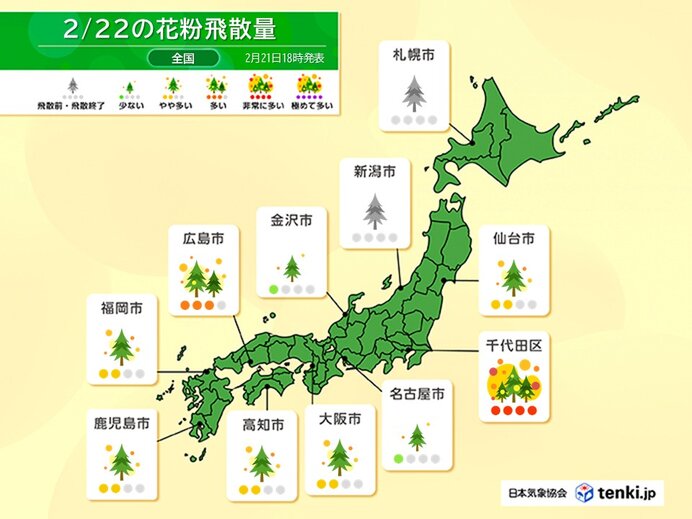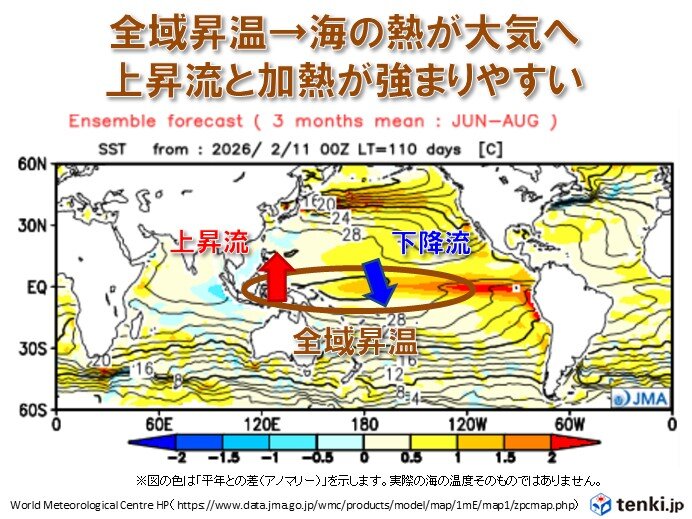「特攻の母」鳥浜トメさんのひ孫 「悩み、苦しみ、出撃した」4代でつなぐ隊員たちの思い

先の大戦末期、陸軍航空特別攻撃隊(特攻隊)の基地があった鹿児島県の旧知覧町(現南九州市)に、隊員から「おかあさん」と慕われた食堂の女将(おかみ)がいた。平成4年に89歳で亡くなった鳥浜トメさんだ。国に殉じた若者たちの思いを後世に。戦後、記憶の結び手として生きた彼女の願いはいま、子供、孫を経て、ひ孫の拳大(けんた)さん(33)に引き継がれている。
出撃前にぎわう食堂、手紙や形見を託した隊員
屋号は「富屋食堂」という。昭和4年の創業で、その後軍指定の食堂に。20年3月に知覧飛行場が特攻基地となり、出撃を控えた隊員たちで食堂はにぎわった。物資が欠乏していた当時、トメさんは苦労して食材を集め、料理をふるまった。
片道だと分かった上での出撃。隊員たちは、トメさんに家族や恋人への手紙や形見を託して飛び立った。
戦後、飛行場は進駐軍によって解体された。トメさんは、その跡地に1本の杭(くい)を立てた。「これが隊員たちのお墓だよ」。2人の娘にそう伝え、毎日欠かさず手を合わせ続けたという。
先の大戦末期、およそ6千人以上もの特攻隊員が散華した。
「彼らは一人一人が悩み、苦しみ、命がけで出撃していった」
拳大さんは隊員たちが等身大の人間だったことを知っている。
トメさんが亡くなったとき、拳大さんは生後4カ月だった。曾祖母の記憶はない。しかし、トメさんの孫に当たる父の明久さんから、思いやりの深かったトメさんの人柄を聞き、隊員たちが出撃前夜をどう過ごし、何を信じて死地へと赴いたかを伝え聞かされてきた。
「ホタル館富屋食堂」の館長、鳥浜拳大さん7月、鹿児島県南九州市(宮崎秀太撮影)伝承のため地元にUターン、年100回講演
トメさんが残した食堂を、父が特攻隊員の遺品やエピソードを伝える資料館「ホタル館富屋食堂」として復元したのは平成13年、拳大さんが9歳のときだ。多くの特攻隊の遺族が訪れ、涙を流すのを目にしてきた。
地元の高校を卒業後、岡山の大学を出て、広島の自動車会社に就職。地元を離れてからも特攻隊が常に頭にあった。「誰かが伝えないと、記憶は消えてしまうんだろうな…」。伝承を手伝おうと、Uターンした。30年のことだ。
令和3年、60歳で他界した父から資料館長の役目を引き継いだ。いまでは年100回ほどの講演をこなす。その傍ら、南九州市内の食堂「知覧茶屋」で腕を振るい、トメさんが隊員たちにふるまっていた味を再現している。
戦争を体験したわけではない。「特攻の母」と呼ばれたトメさんと過ごした思い出があるわけでもない。しかし、先人の思いを知り、後に続く世代へと伝える橋渡しをしたい。それが記憶の結び方だと考えている。
資料館は来年で25周年を迎える。外国からの来館者も増えている。ウクライナや中東ガザで戦火が広がり、世界に不穏な空気が漂っている。拳大さんは呼びかける。「戦争は文字で読むだけの存在ではない。実際に戦い、命を落とす人がいる。今の日本の平和を支える先人たちがいることを、身に染みて感じてほしい」(宮崎秀太)
特攻(特別攻撃)
戦闘員が自らの命を犠牲にして敵に体当たりする戦法。先の大戦末期の昭和19年10月に編成された「神風特攻隊」を皮切りに、終戦まで約10カ月にわたり陸海軍によって出撃が繰り返され、死者数は6千人以上と推計される。特攻兵器の開発も進められ、小型ボート「震洋」を用いた水上特攻や人間魚雷「回天」による水中特攻も行われた。