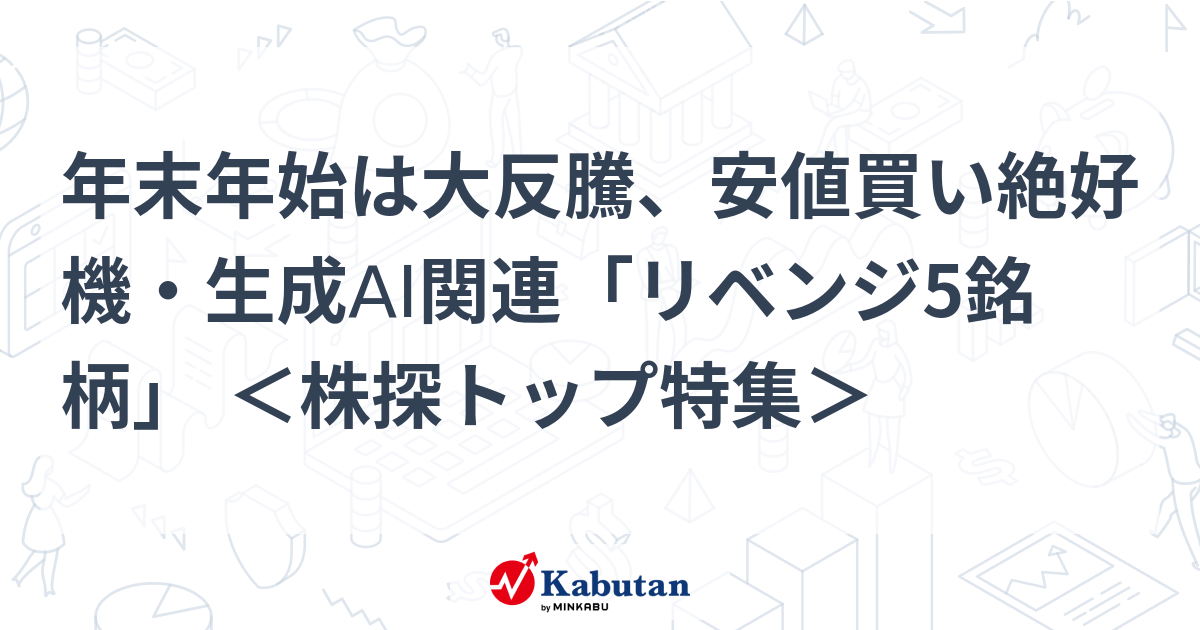【コラム】沈みゆく日産、グローバル化の終焉映す-フィックリング

振り返れば、グローバリゼーションのピークは2018年1月24日だったのかもしれない。
当時、日産自動車、ルノー、三菱自動車の3社連合を率いていたカルロス・ゴーン氏はスイス・ダボスでブルームバーグテレビジョンに出演し、政権1期目のトランプ米大統領による洗濯機および太陽光パネルへの関税賦課について「保護主義が著しく急激に強まるような事態にはならない」と述べた。
販売実績で世界最大の自動車グループになったことに自信を深め、単一企業体制への統合を視野に入れていた同氏にとっては懸念材料ではなかったようだ。
しかし、地殻変動はすでに始まっていた。日産の社内では数週間もたたないうちにゴーン氏の逮捕につながる内部調査が開始され、19年には日本からの劇的な逃亡劇が展開された。その後、連合はフランスと日本の分離を試みるも、ほぼ10年にわたり成功していない。
こうした中、日産が今週発表した24年度決算では6709億円の当期純損失を計上。同時に車両生産工場について27年度までに現在の17から10に削減すると確約した。世界有数の自動車メーカーだった日産は終焉(しゅうえん)に近づいているのかもしれない。
関連記事:日産再建へフル加速、新社長が矢継ぎ早のリストラ策-株下落 (1)
投資家らも同様の判断を下している。日産のPBR(株価純資産倍率)は約0.25倍で推移しており、社債も主要格付け3社全てからジャンク級と評価されている。時価総額は1兆3000億円程度とネットキャッシュの約1兆5000億円を下回っている。仮に1975年から日産株を常に購入し続けていた場合、現在は含み損を抱えていることになる。
ホンダとの共同持ち株会社設立交渉が頓挫したことなどを受けて辞任した内田誠氏の後任として最高経営責任者(CEO)に就任したイバン・エスピノーサ氏は、わずか数カ月で再建計画を打ち出した。日産の再建計画は過去5年間で3度目だ。
もっとも、この計画は内田氏が6カ月前に発表した前回の取り組みの焼き直しに過ぎず、出血を止めるには不十分だろう。
この問題を解決する機会は、内燃エンジンの黎明(れいめい)期以来、世界の自動車業界が最も劇的な変革を遂げていた過去7年間にあった。しかし日産はその期間、ゴーン氏追放を発端とする社内での対立や混乱の対応に追われていた。現在でも2024年度決算短信でゴーン氏の事件を巡る記述が2ページにわたって記されている。
その結果、日産の事業は過去からいまだに前進できていない。ゴーン氏は18年の「世界経済フォーラム(WEF)年次総会(ダボス会議)」で世界最大の電気自動車(EV)メーカーを率いていると主張していたが、日産のEV販売はそれ以降、ほとんど伸びていないのが実情だ。
エスピノーサ氏が打ち出した中国事業の再建計画も悪い冗談のように思える。中国市場での販売は19年以降でおよそ半減している。エスピノーサ氏はプラグインハイブリッド車(PHV)への注力により立て直そうとしているが、日産はあまりにも後れを取っており、存在感はほとんどない。
日産が中国で昨年販売したEVおよびPHVの台数は1万2641台に過ぎず、中国市場でのシェアは0.1%にも満たない。
米自動車メーカーは、過去10年の混乱を自国市場への撤退で乗り切ったが、日産にそれは通用しない。依然として過度なグローバル体制が現在の保護主義的な競争環境への対応を難しくしている。
名目上は日本企業であり、従業員の45%、製造拠点の約35%を国内で占めているにもかかわらず、国内販売はわずか16%だ。売上高の半分以上は北米で、国内工場で生産された車両の約30%が同市場に輸出されている。トランプ政権による25%の自動車関税は、この取引からの利益を完全に消し去るのに十分だ。
ゴーン氏がもたらした1999年以降の日産の復活は、グローバリゼーションによる成功の象徴だった。ゴーン氏自身もダボスで毎年開催されるダボス会議に集まる億万長者「ダボスマン」の体現者とされていた。
しかし、その裏でナショナリズムが消え去ることはなかった。日産の失墜には、純粋な事業の失敗に加え、日仏政府間の代理戦争的な側面も大きく影響した。
競合企業にとっても、沈みゆく日産の姿を喜ぶ余裕はない。主要な自動車メーカーが自国市場に閉じ込められるような世界は、中国企業以外の主要メーカーにとって厳しいものとなる。中国だけが規模、生産技術、EV分野での技術的優位性を確保し、他を圧倒する可能性があるためだ。この猛攻を食い止める最良の方法は国境を越えて協力することだったが、グローバリゼーションによる成功の象徴だった日産の失墜は、その未来への希望を完全に消し去った。
旧勢力が無駄な争いに明け暮れているうちに新たな強国が覇権を握っていくのが世の常だ。国家と同様、自動車メーカーにおいても、このパターンが再び展開されている。
(デービッド・フィックリング氏は気候変動とエネルギーを担当するブルームバーグ・オピニオンのコラムニストです。ブルームバーグ・ニュースやウォールストリート・ジャーナル、フィナンシャル・タイムズでの記者経験があります。このコラムの内容は必ずしも編集部やブルームバーグ・エル・ピー、オーナーらの意見を反映するものではありません)
原題:Nissan Is Dying and Taking Globalization With It: David Fickling(抜粋)