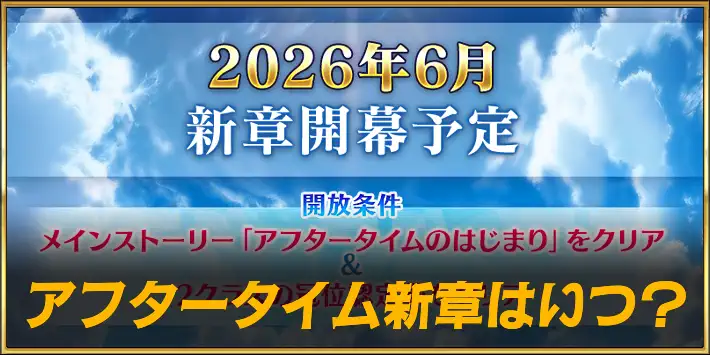「コンビニ」「イザカヤ」はOKだが「スマホ」はNG…在留外国人が自然に使える“日本生まれ”の英語表現とは(文春オンライン)

〈《インバウンド急増》在留外国人が陥る「マイジャパン症候群」とは? 「努力してない」→「やりすぎ」の間で揺れる“不安”〉 から続く 【動画を見る】「コンビニ」「イザカヤ」はOKだが「スマホ」はNG…在留外国人が自然に使える“日本生まれ”の英語表現とは 「日本に住んでいる英語母語話者は、みんな自然にコンビニ、イザカヤといった言葉を使います」 作家のグレゴリー・ケズナジャット氏が語るのは、在留外国人たちの言語使用の実態だ。英語を母語としながら日本語で創作活動を続ける同氏のエッセイ集『 言葉のトランジット 』(講談社)をテーマにした文藝春秋PLUSの番組で、興味深い言語遣いが話題になった。
ケズナジャット氏によると、日本在住の英語話者の間では「コンビニ」「イザカヤ」といった和製英語や日本語がそのまま使われているという。 「それに代わる英語が存在しないから、一言で簡単に言えるのが和製英語だったり、日本語だったりします」 一方で、日本人が頻繁に使う「スマホ」という略語は、彼らの英語には入り込んでいない。 「スマホという言葉を使わないのは発音の問題で、もう少し何か硬い音が欲しい。英語の流れですごく言いにくい」と分析する。 また、「convenience store」と英語で表現した場合、英語圏にあるガソリンスタンドのような形式の店舗イメージが浮かぶため、日本独特のコンビニエンスストアの概念を伝えるには「コンビニ」という表現が最も適切だという。
「翻訳できない言葉は存在しないと思います」とケズナジャット氏は言う。「『木漏れ日』のような言葉も、しっかり説明すれば伝わる。すべて翻訳可能です」 しかし同時に「何かを一言で表現するのは、再現できない場合がある」と指摘。言語にはそれぞれ、その言語を使う人々の共通の経験を表しているものがあり、完全に翻訳しきれない理由がそこにある。 「例えば、同じ地元の人たちと話す時、20年前にあったけれど潰れてしまったお店が話題になる。それは一言で通じますよね。お互いがそのお店を覚えている、という経験があるからです。その経験が自分たちの共通性になり、仲間の証みたいなものにもなります」
Page 2
創作活動において日本語と英語を行き来するケズナジャット氏にとって、思考で使用する言語はどちらなのか。 「多いのは日本語ですね。日常生活で日本語を使うことが多いから。でも両方使っていますよ」 「頭の中でそこまで区別しないで、日本語のセンテンスが出たり英語のセンテンスが出たり」と語る。バイリンガルの思考が垣間見える発言だ。
英語が母語のケズナジャット氏にとって、日本語での創作には特別な意味がある。 「日本語は母語ではないから、母語話者が使うパターンと違っていることもあるでしょう。でも、そのぶん言葉の使い方が少し自由になっているんじゃないか」 母語話者が無意識に従っている言語のルールから解放されることで、新たな表現の地平が開ける可能性を指摘した。 言語は単なるコミュニケーションツールではなく、使用者の生活環境や文化的背景を反映する存在だ。ケズナジャット氏の体験談は、在留外国人がどのように日本語と母語を使い分け、新たな言語表現を生み出しているかを物語っている。
「文春オンライン」編集部