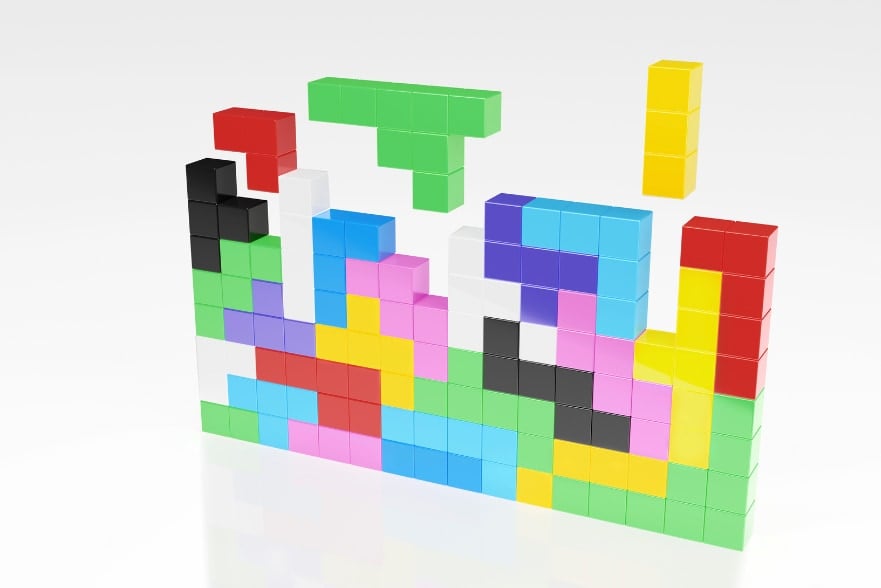トランプ外交で揺らぐ米国への信頼、アジアの同盟国が戦略見直しへ

2015年に当時の安倍晋三首相が1週間にわたり米国を公式訪問した際、日米両国の揺るぎない同盟関係が改めて鮮明になった。ホワイトハウスで開かれた国賓夕食会では、当時のオバマ大統領は、安倍氏の地元である山口県から取り寄せた日本酒で乾杯を行い、日米の友好関係をたたえる俳句を披露した。安倍氏もまた、モータウンの名曲「エイント・ノー・マウンテン・ハイ・イナフ(Ain’t No Mountain High Enough)」を引用し、日本の米国に対する揺るぎない姿勢を示した。
安倍氏はその翌日に日本の首相として初めて米連邦議会上下両院合同会議で演説を行った。同氏は第2次世界大戦での敗戦後に日本が米国との同盟関係構築を選んだ経緯を振り返り、「この道が日本を成長させ、繁栄させた。そして今も、この道しかない」と語った。この43分間にわたる演説はスタンディングオベーションを何度も浴びた。
米国をかけがえのないパートナーとみなす姿勢は、数十年にわたり日本の政策当局者の間でほぼ一貫して共有されてきた。日本は1980年代の日米自動車摩擦や87年の潜水艦技術を巡る問題を乗り越え、第1次トランプ政権時には貿易問題や防衛費を巡る要求に安倍氏はゴルフ外交を通じて巧みに対応した。
だが、第2次トランプ政権での同氏の予測不可能な言動は、日米関係に深刻な影響を及ぼしている。日本に対する15%の関税措置は、貿易戦争の混乱の中ではまだ良好な結果とも言えるが、同盟国であり最大の対米投資国である日本が求めていた関税措置の見直しとは程遠いものだった。日米貿易交渉は長期化し、時に険悪な様相を呈し、石破茂首相の政治基盤を揺るがした。石破氏は、7月の参院選で連立与党が過半数を失ったことを受けて、政権維持に苦慮している。
一方、トランプ大統領のウクライナ危機への対応は、大きな譲歩を引き出すためのディールよりも、同盟国との協調姿勢や集団的安全保障上の利益をトランプ氏が優先できるかを見極める試金石となっている。
こうした状況を背景に、日本国内では戦略的自立の必要性を巡る議論が高まりつつある。米国の核の傘への信頼が揺らぐ中、参院選で躍進を遂げた野党の一部は核兵器保有の是非というこれまでタブー視されてきたテーマにも踏み込んでいる。
日本は長年、米国にとって東アジアで最も信頼できる同盟国で、中国に対する重要な防壁であり、台湾有事などの際に太平洋全域に米軍を展開するための重要な拠点だ。その日本でこうした議論が起きているということは、トランプ氏の言動が米国への信頼をいかに損なってきたかを示している。
もし日本が揺らげば、他国も追随しかねない。米国の同盟国である韓国では核兵器保有に対する国民の支持が根強く、米国の安全保障を巡る方針と貿易交渉を結び付けたトランプ氏の姿勢に対し不信感が広がっている。オーストラリアでも、米英との間で30年かけて原子力潜水艦を共同開発する合意について、妥当性を疑問視する声が上がっている。フィリピンのマルコス大統領は、台湾に近い複数の軍事基地への米軍のアクセスを認めるなど、米国寄りの姿勢を堅持しているが、野党は米国への懐疑的な姿勢を強めており、3年後に政権を奪還する可能性もある。
外交政策専門家の中には、アジアにおける米国の同盟体制が崩壊の危機にあるという見方は誇張し過ぎだと指摘する向きもある。確かに、米軍との共同訓練の拡充や東京近郊に新たな共同軍司令部を設置する計画など、日本は防衛協力を深化させる姿勢を示している。韓国の新大統領も、今月予定される初の訪米に先立ち、米韓同盟の重要性について言及している。
ブッシュ(子)政権下で国家安全保障会議(NSC)のアジア担当シニアディレクターを務めたマイケル・グリーン氏は、「米国の同盟国は、同盟関係を解消し中国に追随したり、核武装による自立を図ったりするのではなく、米国との統合を強めている」と指摘した。
だが、米国の同盟関係のほころびが紛争や地政学的再編、核拡散のリスクを高める中、アジア太平洋地域は不安定化の瀬戸際にあるのではないかとの悲観的な見方もある。
国際シンクタンク、政策・アドボカシー・ガバナンス研究所(IPAG)のサイード・ムニール・カスル所長は5月に、「主要な安全保障条約のうち、たった一つでも破棄されれば、その衝撃は計り知れず、地域全体に予測も抑制も困難な波紋が広がるだろう」との分析を示した。
米国による広島と長崎への原爆投下から6年後の1951年9月、日米両国はこの地域における米国の安全保障政策の礎となる条約に署名した。この条約は日本が主権を回復した後も、米軍が日本国内に駐留することを認める内容だった。
この条約は60年に改定され、米国は日本が攻撃を受けた場合に防衛義務を負う一方で、日本に基地を設置する権利を得た。日本には現在、米軍兵士約5万3000人が駐留している。これは米国本土以外では最大の米軍常駐部隊だ。
日米安全保障条約は、日本の政治を長らく支配してきた保守派の自由民主党にとって信条ともいえるものであり、首相在任期間が歴代最長となった安倍氏にとっても例外ではなかった。
核武装する北朝鮮や強硬姿勢を一段と強める中国からの脅威が増す中、安倍氏は地域安全保障への日本のコミットメントを米国に改めて示すため、防衛姿勢を転換させた。安倍政権は14年に集団的自衛権の行使を容認し、同盟国などが攻撃を受けた場合に自衛隊が防衛することを認めた。
安倍氏はより強固な防衛力の構築を目指していたが、高度に軍事化された近隣諸国との本格的な衝突に際し、日本が自国防衛に苦戦することも認識していた。日本の防衛当局者にとって悪夢のシナリオは、中国・北朝鮮・ロシアとの三正面衝突で、安倍氏は日米同盟が不可欠であることを理解していた。
トランプ氏は政権1期目当時、日米関係の不均衡を批判し、日本の貿易黒字を問題視するとともに、在日米軍駐留費の負担増を要求した。ゴルフを通じて安倍氏との友情が深まる中、両首脳は19年に農産品と工業品の一部を対象とした貿易協定に署名したが、日本にとって極めて重要な自動車産業への影響は回避された。
だが、トランプ氏は2期目開始から数カ月内に、貿易問題と安全保障条約に関する不満を再び表明し、これが日米同盟への国民の信頼を揺るがす結果となった。朝日新聞が2-4月に実施した全国世論調査では、米国が日本を守ってくれるとは思わないと答えた人の割合が77%に上った。ピュー・リサーチ・センターの6月の調査では、トランプ氏が国際問題で正しい判断をするとは思わないと回答した日本人の割合は61%。米国に対する好意的な見方は55%で、1年前の70%から低下した。
こうした日本国内の世論の変化は、参院選の結果にも表れており、「日本人ファースト」を掲げる右派ポピュリズム政党の参政党が支持を伸ばした。同党はより強硬な外交姿勢を主張し、日本が自国防衛のために核兵器を保有すべきかどうかについての議論を開始した。
広島と長崎の記憶が何十年にもわたり、こうした議論を封じてきた。だが、日本は大量の核分裂性物質を保有し、数カ月で核兵器を開発できる能力があるとされ、「核兵器保有の瀬戸際」にいる国と見なされている。参政党は得票数で2位となったものの、獲得議席数はわずかにとどまった。それでも、核兵器保有の是非を巡る議論が始まったこと自体が、日本にとっては大きな転換点となった。
こうした意識の変化は、自民党内でもみられる。トランプ氏が7月に日本に対し25%の関税を課すとの書簡を公表したことを受けて、自民党の小野寺五典政調会長は手紙1枚で通告するのは同盟国に対して大変失礼な行為で、「強い憤り」を感じると非難。石破首相は街頭演説で「なめられてたまるか」と訴えた。
安倍政権で長年にわたり国家安全保障局長を務めた谷内正太郎氏も日本経済新聞とのインタビューで、日米同盟を占領期からの惰性で続けるのと、日本自らの選択として選んでいくのとでは違うとの見解を示した。
米国が安全保障上の信頼できるパートナーであり続けるのかという懸念は、2月末に一層強まった。トランプ氏がバンス副大統領と共にウクライナのゼレンスキー大統領をホワイトハウスの大統領執務室で侮辱し、その後、一時的に情報共有と軍事支援を停止したためだ。日本や韓国、オーストラリアとは異なり、ウクライナは米国と安全保障条約を結んでいないが、それでもアジアの同盟国にとっては衝撃だった。
安倍政権で数年間にわたり国家安全保障局次長を務めた兼原信克氏は、日本にとってウクライナ戦争の教訓は、米国に頼り切っていい時代が終わったということだとの見解を示した。不調に終わった米ウ首脳会談の直後、日本経済新聞に語った。
日本と同様、韓国も安全保障面で米国に依存しており、特に北朝鮮への抑止力として頼っている。韓国には約2万8500人の米軍兵が駐留し、平沢にあるキャンプ・ハンフリーズは米国外で最大の米軍基地だ。李在明大統領は25日にワシントンでトランプ氏と会談を行う予定で、防衛費負担の問題が主要議題となる見通しだ。
オーストラリアも6月、現実を突きつけられた。トランプ政権がオーストラリアへの原子力潜水艦配備を柱とする米英豪3カ国の安全保障枠組み「AUKUS(オーカス)」の見直しに着手すると表明したためだ。バイデン前政権下の2021年に締結されたAUKUSは、米国が30年代初頭までにオーストラリアに対し最大5隻のバージニア級原子力潜水艦を売却し、将来的には次世代の攻撃型潜水艦を共同開発する計画となっていた。
だが、米国防総省は自国の調達が遅れる中で、潜水艦売却が海軍の戦力を損なう可能性があると懸念を示している。潜水艦の配備が頓挫すれば、インド太平洋地域で中国との緊張が高まる中、オーストラリアの安全保障に深刻な空白が生じることになる。
こうした外交的な摩擦を受け、アジアにおける米国の同盟諸国が「プランB」としてどのような選択肢を持ち得るのかという疑問が浮上している。欧州諸国も、トランプ氏が北大西洋条約機構(NATO)への関与をどこまで維持するのか不安を抱いているが、仮に米国抜きでも、ロシアの侵略を抑止できるだけの集団的戦力を有している。
これに対し、アジア太平洋地域の民主主義国家間にはそのような枠組みは存在しない。共同軍事演習や物資の相互提供協定は増えているものの、地域的な相互安全保障の実現にはなお遠く、見通しは立っていない。それは主に、米国を中心とし各国がそれぞれ個別につながる「ハブ・アンド・スポーク型」の同盟構造が長年にわたり安全保障の担保として十分に機能してきたからだ。
元防衛相の石破首相は、地域安全保障協定が潜在的な侵略への抑止力強化につながるとの見解を示している。しかし、長年の歴史的なわだかまりが、こうした合意形成の大きな障害となっている。例えば、1910年から45年までの朝鮮半島に対する植民地支配の歴史により、日本の自衛隊が韓国国内で活動するという構想には、いまなお強い反発がある。
同様の問題はアジア各地にも存在する。ほぼ全ての国が近隣諸国と何らかの歴史的対立を抱えており、それが絶えず緊張の火種となっている。50年代には、米国などの西側諸国が共産主義に対抗するため、東南アジア版NATOとして東南アジア条約機構(SEATO)を設立した。加盟国のうち域内から参加したのはフィリピンとタイの2カ国のみ。他の加盟国は軍事介入のタイミングなどを巡り意見が対立し、SEATOは77年に解散した。
もう一つの要因は、中国の経済的な影響力だ。同国は「アジア版NATO」の創設に繰り返し警告を発してきた。中国は、多くの国々にとって安全保障上の最大の懸念である一方で、主要な貿易相手国でもあり、経済的圧力を外交手段として行使する姿勢を見せている。米中の貿易摩擦の中で、中国が米国へのレアアース輸出を制限したこともその一例だ。
ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)の調査によると、中国は現在、艦艇数で世界最大規模の海軍を擁しており、2024年の国防予算は日本と韓国、オーストラリア、フィリピンの軍事支出を合計した額の2倍余りに達している。
日本と韓国、オーストラリア、ニュージーランドは、ここ10年間でNATOとの安全保障関係を強化しており、欧州の海軍もアジア太平洋地域での活動を活発化させている。しかし、代替となる集団安全保障体制がない以上、米国の存在は欠かせないのが現実だ。
トランプ氏は引き続き同盟国に対し、米軍による防衛の対価として負担増を求めるとともに、各国の防衛費も増額するよう圧力をかけていくことが予想される。ヘグセス米国防長官は、アジアの同盟国はNATO諸国にならい、防衛費を国内総生産(GDP)の5%に引き上げるべきだと述べている。これに対し、日本の昨年末時点の防衛費はGDP比で1.4%、韓国は2.6%にとどまっている。日本は来年、在日米軍の駐留経費負担を巡る新たな5年契約の交渉が始まる見通しで、大きな節目を迎えることになる。
トランプ氏の取引重視の外交姿勢と大胆なディールを好む傾向を踏まえれば、アジアを含む世界の同盟国が当面、不安定な状況にさらされ、「パックス・アメリカーナ(米国の覇権が形成する平和)」に代わる選択肢を模索し続けるのは間違いないだろう。
グリーン氏は、「トランプ氏の狂人理論は、予測不能な行動が敵対勢力を混乱させる有効な戦術であるとする考え方で、中国に対しては効果があるかもしれない」と指摘。「だが、同盟関係の維持においては、混乱から得られる利点など一切ない」と論じた。
(アラスター・ゲイル氏はブルームバーグ・ニュースの東京支局を拠点に、日本の政治とアジアの安全保障を担当している)
原題:US Allies in Asia Grapple With Once-Unthinkable Options: Essay(抜粋)