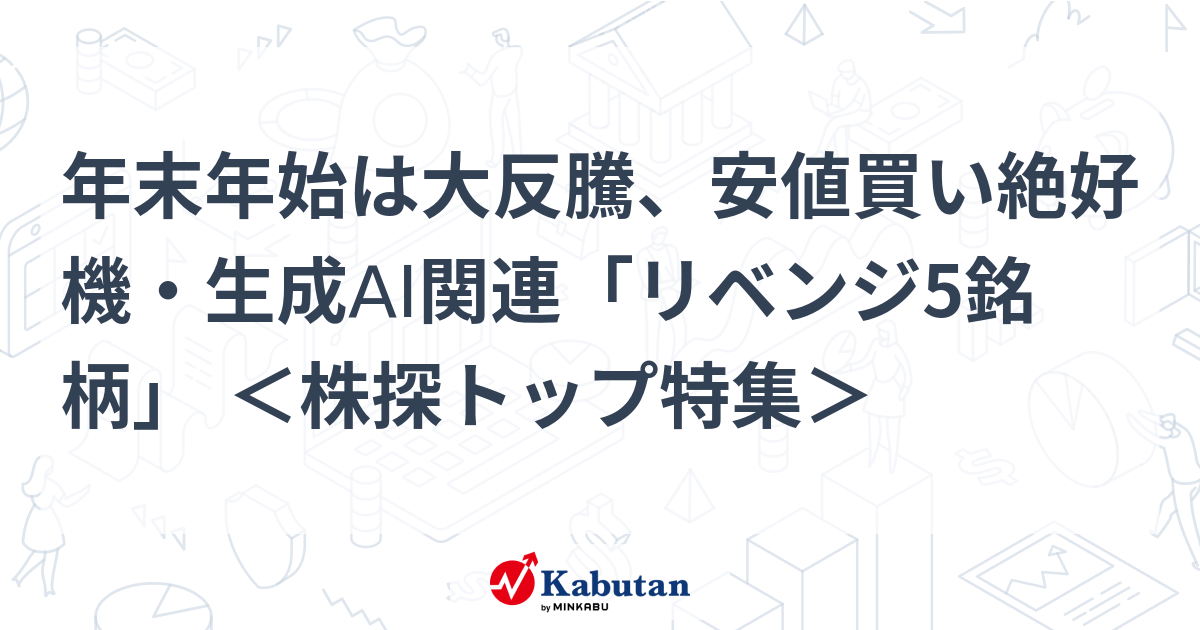【コラム】米中の90日間休戦、FRBの救いにはならず-ダドリー

米中が相互の関税率を90日間引き下げることで合意したことで、貿易戦争は最悪期を脱したとの楽観論が再び台頭している。しかし筆者には、これが「突破口」となるようには思えない。米連邦準備制度理事会(FRB)が対応しきれないほどの経済的打撃が及ぶ余地は依然として大きい。
まず、今回の関税一時停止が持続する保証はなく、全体の流れを変えるものでもない。関税率は依然として高く、インフレを助長し、成長を阻害する水準にある。イェール大学予算研究所によれば、平均実効関税率は17.8%に達しており、トランプ政権2期目の開始時点の約2.5%から大幅に上昇している。その影響で物価水準が約1.7ポイント、失業率が約0.35ポイント上昇する可能性があるという。
次に、90日間の関税停止は、トランプ政権の政策を巡る先行き不透明感をかえって長引かせるだけだ。その結果、企業は支出や投資、雇用の意思決定を先送りすることになる。
さらに、FRBは今後も、インフレ抑制と成長支援という難しい判断を迫られ続ける。短期的には、政策金利を据え置いたままインフレ期待を注視する忍耐強さが求められるが、その結果、景気悪化への対応が遅れるリスクもある。利下げを求めるトランプ氏の不満も招くだろう。
実際、FRBに選択の余地はほとんどない。今のようにリスクがどちらに偏っているか分からない状況では、さらなる情報を待つしかないのだ。仮に現時点で大きな措置を講じても、それが成功する確率はせいぜい五分五分だろう。
2021年以降にインフレ率が当局目標の2%を上回り続けていることを踏まえれば、FRBが置かれている状況はなおさら厳しい。成長を優先しようとすれば、インフレ期待の抑制が難しくなり、制御不能な価格上昇スパイラルを引き起こすリスクが高まる。これはFRBが取ることのできない非対称リスクだ。
ただ、忍耐強さもリスクを伴う。失業率の動向から景気後退を判断する「サーム・ルール」の提唱者、クラウディア・サーム氏が指摘するように、労働市場の弱さは自己増幅的な性質を持っている。解雇が消費を抑制し、それがさらに企業の収益を圧迫し、追加の解雇を招くという悪循環が起きやすい。歴史的な傾向を見ると、失業率が0.5ポイントを超えて上昇すると、景気後退に陥る可能性が高まる。昨年は例外で、失業率が上昇したのは雇用の弱さではなく、労働市場に参加する人が増えたためだった。しかし今回は状況が異なる。雇用の伸びが鈍化しており、強制送還や国境での取り締まりによって労働力人口の増加も抑えられている。
では、FRBは今後どう動くのだろうか。インフレ率や経済成長見通し、通商政策の方向性が明らかになるのは、おそらく9月以降になるだろう。その時点で利下げが必要となれば、労働市場の悪化を食い止めるために積極的に動くことが求められる。特に、関税による供給ショックが金融政策の効果を弱める可能性を考えるとなおさらだ。米経済がリセッションに陥った場合には、200-300ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)程度の利下げが必要になるだろう。
現時点でFRBに非はない。新型コロナ禍の局面ではインフレ対応が後手に回ったが、が、今回は状況が異なる。金融政策では対応できない通商政策の影響に直面しているのが実情だ。FRBが経済を安定成長させ続けるための適切な対応方針が早期に明確になることを願うしかない。
(ニューヨーク連銀の前総裁、ウィリアム・ダドリー氏はブルームバーグ・オピニオンのコラムニストです。このコラムの内容は、必ずしも編集部やブルームバーグ・エル・ピー、オーナーらの意見を反映するものではありません)
原題:The China Deal Doesn’t Solve the Fed’s Problems: Bill Dudley(抜粋)