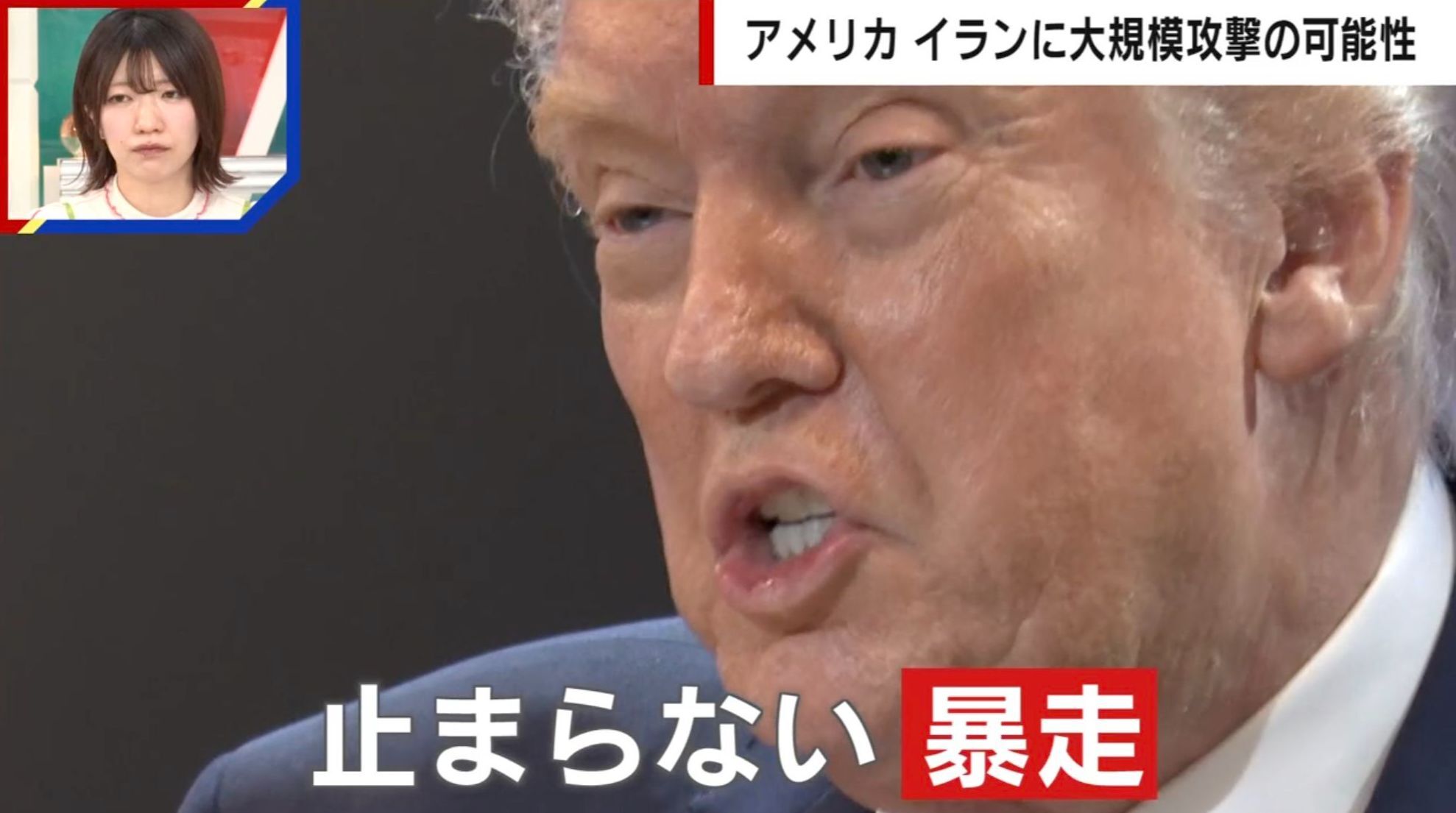深さ9500メートルに及ぶ超深海帯で生態系を発見、光のない極限環境で繁栄

超深海を探査する海洋研究者らのチームが、ロシアと米アラスカ半島の間に位置する海溝での潜水艇調査で、海底に生物群を発見した/Institute of Deep-sea Science and Engineering/Chinese Academy of Sciences (IDSSE, CAS)
(CNN) 超深海を探査する海洋研究者らのチームが、ロシアと米アラスカ半島の間に位置する海溝での潜水艇調査で、海底に生物群を発見した。太陽光エネルギーを使う「光合成」の代わりに、海底の割れ目から湧き上がるガスを使って有機物を合成する「化学合成」の生態系としては、最も深い場所での観測とされる。
中国科学院深海科学・工程研究所の杜夢然(ドゥモンラン)研究員らが先月30日、英科学誌ネイチャーに発表した。
ドゥ氏はこの潜水調査が残り30分となった時、深度5800~9500メートルの「ハダル(超深海)帯」に延びる海溝の最後の一区間を探査しようと決めた。約2500キロに及ぶこの区間で発見したのは、二枚貝類や筒状の殻を持つ深海生物「チューブワーム(ハオリムシ)」などの「驚異的な生物群」だった。ドゥ氏らのチームによれば、これほどの深さで化学合成生態系が見つかったのは初めて。
ハダル帯の大半は海溝の内部にある。この深さで「生命が存続し、繁栄するには特殊な技が必要だ」と、ドゥ氏は説明する。
米海洋大気局(NOAA)によると、そんな技のひとつが、二枚貝やチューブワームの内部に共生する細菌だ。細菌は海底からの湧水に含まれる硫化水素やメタンの化学反応から生じるエネルギーを使って、有機物を作り出す。太陽光が届かない極限環境の中、この有機物を栄養源にして生態系が形成される。
ドゥ氏によれば、チームの研究は同様の生態系がハダル帯の別の場所にも存在する可能性を示し、こうした生物がどれくらいの深さまで生存できるのかという新たな研究機会を提供している。
メタンが支える深海の生態系
ドゥ氏らのチームが調査で採取した堆積(たいせき)物の試料を分析したところ、高濃度のメタンが検出された。深海の堆積物に含まれるメタンは通常、ごく少量にとどまるという。
そこで同氏らは、生態系内の微生物が堆積物中の有機物からまず二酸化炭素を生成し、その二酸化炭素からメタンを生成しているという新たな仮説を立てた。二枚貝やチューブワームに共生する細菌は、このメタンを使って化学合成を行うと考えられる。
もともと化学合成生態系は、海の表層から沈んできた生物の死骸、生物由来の粒子といった有機物に依存すると考えられていた。だがこのように、現地でメタンを生成する微生物も、有機分子の供給源になっていることが明らかになった。
メタンは炭素を含む化合物のひとつで、地球規模の炭素循環の一端を担っている。ドゥ氏は、炭素循環における海溝の役割が予想外に大きいことも示されたと話す。
これまで長年にわたり、メタンは海洋プレートが別のプレートと出会う「沈み込み帯」の下に圧縮された流体として貯蔵され、それが深海底からの「冷湧水」を通して放出されると考えられてきた。だがこの深さで化学合成生態系が見つかったことから、海溝はメタンの貯蔵所であるだけでなく、リサイクルセンターにもなっているのではないかと、ドゥ氏らは仮定する。
同氏はこの仮説について、「堆積物中に大量の炭素がとどまり、微生物によってリサイクルされているという意味だ」と述べた。最近の研究では、ハダル帯の海底に貯留できる二酸化炭素は周りの70倍にも上ると報告されている。メタンと二酸化炭素が代表的な温室効果ガスであることを考えると、海底のようなカーボンシンク(炭素吸収源)は、地球にとって極めて重要な意味を持つ。