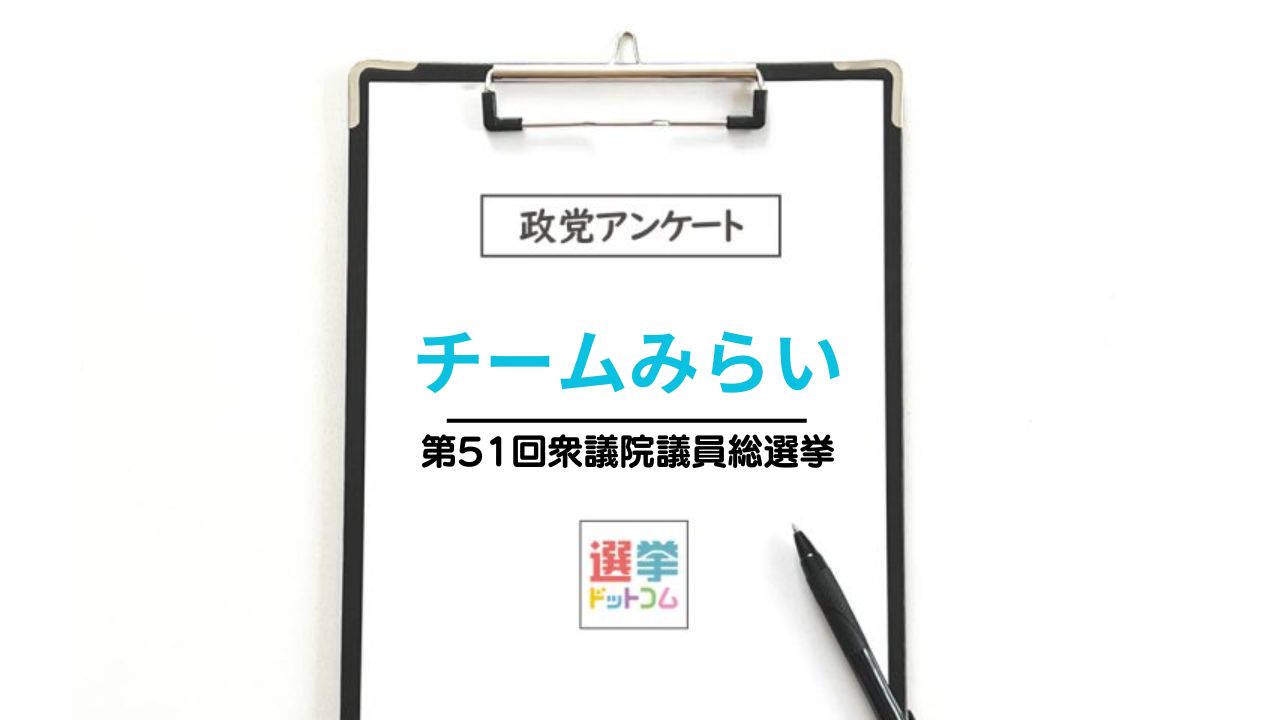そりゃ「愛子天皇」が待望されるわけだ…島田裕巳「悠仁さまに国民がどうしても抱いてしまう微妙な感情の正体」(プレジデントオンライン)

「愛子天皇待望論」の背景には何があるのか。皇室史に詳しい宗教学者の島田裕巳さんは「愛子内親王が多くの国民から愛されるのは、一人っ子であることが大きく影響しているのではないか」という――。 【写真をみる】御誕生3カ月頃の愛子さま ■天皇家の“一人っ子”である愛子内親王 愛子内親王は一人っ子である。 最近は、一般の家庭でも一人っ子は増えている。2021年の調査では、結婚後15〜19年が経過した夫婦の子どものうち、19.7%が一人っ子という結果が出ている。この調査とは、厚生労働省が設置した国立社会保障・人口問題研究所によるものである。 同じ調査だが、2002年には8.0%だった。ということは、およそ20年で一人っ子は倍増したことになる。 私は1953年、昭和28年の生まれである。当時、学校の同級生で一人っ子というのは珍しかった。一人っ子の割合は1990年代に入ってから徐々に増えている。これからも増えていくであろう。 そこには、何より晩婚化や晩産化が影響している。最近では、経済的な理由から二人目をもうける夫婦が減っていることも大きいだろう。皇族の中に一人っ子が現れるのも、そうした時代の傾向によるもので、愛子内親王はその象徴である。 歴史を振り返ってみても、天皇の子どもが一人っ子という例は少ない。それも、かつては「側室」の制度があり、母を異にする兄弟姉妹が多く存在したからである。あるいは、現在の皇室典範では認められていないが、以前は養子をとることも当たり前に行われていた。そうなると、一人っ子にはならないのだ。 ■“一人っ子皇子”は一条天皇のみ 唯一の例外が第66代の一条(いちじょう)天皇である。一条天皇は986年から1011年まで在位した。それは平安朝の宮廷文化がもっとも華やかだった時代である。藤原道長が権勢をふるい、清少納言が『枕草子』を、紫式部が『源氏物語』を執筆していた。 一条天皇の父は第64代の円融(えんゆう)天皇である。円融天皇には妻として2人の中宮、2人の女御、2人の更衣がいた。中宮が正妻にあたる皇后で、女御はその下、更衣はさらにその下である。光源氏の母が更衣で身分が低かったことが、『源氏物語』の「桐壺巻」では強調されていた。 6人も妻がいながら、円融天皇の子どもは、女御の藤原詮子(せんし)との間に生まれた懐仁(やすひと)親王だけだった。詮子は道長の姉で、懐仁親王が一条天皇として即位している。 本当に懐仁親王は円融天皇の子どもなのだろうか。拙著『日本人にとって皇室とは何か』(プレジデント社)でも述べた、日本の後宮の開放的な性格からすると、それを疑いたくもなってくる。 私が調べた限り、一人っ子として生まれた皇子は懐仁親王だけである。一人っ子の内親王という例はない。その点で、愛子内親王は皇族として特別な生まれなのである。