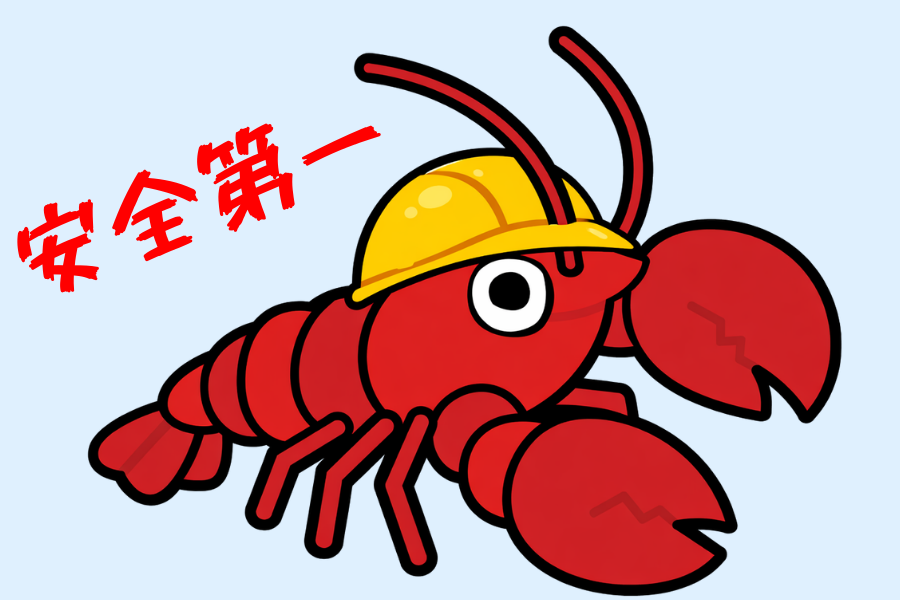ジョロウグモのメスが共食い、科学者が観察 侵略的外来種として米国で注目の的に

黄金色に輝く糸で巨大な巣を作るジョロウグモ(Trichonephila clavata)。米国では侵略的外来種として、2014年以降、東部で急拡大し、注目を集めている。巣は単体で存在する場合もあるが、集合住宅のようにモザイク状につながり、樹上まで長く伸びた巣に10~15匹のメスが同居している場合もある。だが寛容的とされるジョロウグモも、互いを攻撃し、時には共食いすることが7月10日付けで学術誌「Arthropoda」で報告された。 【実験映像】ジョロウグモのメスの共食い ジョロウグモは東アジア原産のクモだ。メスは、手のひらほどの大きさで、体は黄色と黒の模様のあるブドウの粒につまようじが刺さっているようだと、米ジョージア大学の生態学者アンディ・デイビス氏は説明する。「クモが嫌いな人にとっては、悪夢のような存在でしょう」 そんな恐ろしげな外見ではあるが、ジョロウグモは人やペットに害を加えることはないと同氏は言う。実際、ジョロウグモは臆病なクモであることが、デイビス氏らの研究チームによって明らかになった。 クモの顔に息をひと吹きすると、大方のクモは数分間動きを止めるが、ジョロウグモは1時間以上も動かなくなってしまうという。「私たちはジョロウグモを『世界一臆病なクモの一種』と呼んでいます」 だからこそ、ジョロウグモのメスたちに共食いの兆しが見られた時、研究チームは大いに興味をそそられた。 最初の兆候は1匹のメスが別のメスにしがみついていたことだった。次は水槽に入れた2匹に間に攻撃があった。そしてついには同時に放った2匹が決死の戦いを繰り広げた。
デイビス氏の学生たちはジョロウグモを捕獲し、どういった状況で争いが生じるかを調べた。論文によると、同等の大きさのメス2匹1組を25組、それぞれプラスチックの食品保存容器に入れたところ、40%の確率で争いが始まったという。 メスたちは互いの脚を引きちぎったり、また別のケースでは勝者が敗者に鋏角(きょうかく、食べ物をつかんで口に運ぶための牙状の器官)を食い込ませていたりしたと、デイビス氏は言う。戦いで優位に立つのは通常体の大きい方だ。 しかし、大きさの違うメスを容器に入れた27回の実験の内、争いは18%の確率でしか起こらず、しかも挑発するのは必ずしも体の大きいメスというわけではないことにチームは驚いた。 だが、プラスチックの食料保存容器はジョロウグモの普段の活動の場ではない。この点がジョロウグモの行動に影響を与えたとも考えられる。 ジョロウグモは巣を歩き回るのに適した長い脚をもっていると、今回の研究には参加していないが、米バルドスタ州立大学の生態学者エリン・グラバルチク氏は指摘する。 「地面の上のジョロウグモは、生まれたばかりのシカの赤ちゃんのようにふらふらとしか歩けません。プラスチックの容器に入れられたことがジョロウグモにストレスを与えた可能性は否定できません」と同氏は言う。 そこでデイビス氏のチームは、野外にある空の巣という、より自然な環境で実験を試みた。2匹1組のペアを14組用意し、1組ずつ巣に放った。すると争いを起こしたのはたった1組だった。勝者は敗者をあたかも獲物のように自ら吐き出す糸でぐるぐる巻きにした。 「争いが起きなかったことは意外ではありません」と、グラバルチク氏は言う。実験に使われたクモの巣には、巣の持ち主だったクモの存在を示す化学物質などが残っていたのだろう。そしてジョロウグモには仲間と平和を維持する手立てを持っているようだ。 その方法の1つが振動によって相手とコミュニケーションをとることだと、デイビス氏は言う。「共同で暮らしている場合、ジョロウグモは何らかの方法で共食いを避けているのです」 自然環境の中で行われた実験とはいえ、実際のメス同士の衝突が再現されたわけではないではないと、今回の研究には参加していなが、独自に研究を行っている米アトランタ在住の生態学者ロバート・ペンバートン氏は言う。 ジョロウグモは動き回るのではなく、獲物をじっと待ち伏せるタイプだと同氏は言う。今後、巣の持ち主で同じ実験を行うことで、ジョロウグモが侵入者に対してどう反応するかより正確に観察できるだろう。
文=Carolyn Wilke/訳=三好由美子