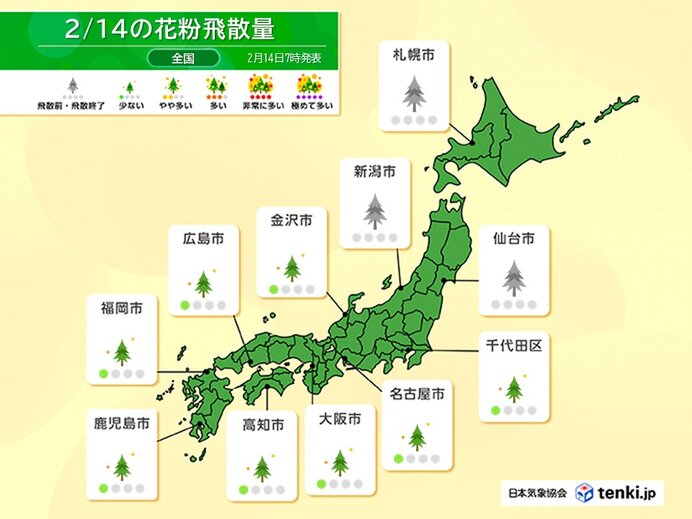「ステマ」・「ステルス移民」・「ステルス機」の時代を生きる困難

JICAが「ホームタウン」事業の撤回を表明した。これについて、これ以上の「ステルス移民はやめろ」という声と、「排外主義はやめろ」という声が、戦いあっている。
JICAは「国際交流は移民ではない」と説明する。抗議者は「ステルス移民だ」と主張している。折り合いがつかない。
私は国際協力と呼ばれる分野を専門研究でカバーするし、実務の方々との交流もかなりある。21世紀になってからの業界の動きを、日本国内で、国際的に、色々と観察し、思うところも多々ある。今回の騒動の背景には大きな社会構造と政策経緯がある。簡単には言えない。一言で言えば、国際協力の業界は岐路に立っている。「The Letter」には少し書いた。
そのうちに一般向けでも書いてみたいと思うが、今日は違う話を書いておきたい。
「ステルス」についてだ。
自民党の総裁選をめぐり「ステマ」騒動が持ち上がった。「ステマ」は、「ステルスマーケティング」の意だ。私はあまり馴染まないがない概念だったので、興味を覚えた。これまでも「Dappi」が類似例としてあった、などと語っている方が多々いらっしゃる。
小泉進次郎氏インスタグラムより
それ以外にも、偽装された世論の声を作る現象は、SNS等でよく見るものだ。「犬笛」と呼ばれている大衆扇動術も、自ら「ステマ」要員を動員しないだけで、効率的に同じ効果を狙うものだと言えるだろう。
評論家や学者が、他の学者を、「虚栄と独善」にやられて「闇落ち」した「親露派」の「老害」といった言葉で揶揄してみせたりするのも、SNS時代の言論界の「ステルス」世論工作の一つと言えるだろう。最近では、学会の書評で、「ロシアを利する可能性が内容を含んでいる」という示唆がなされた、として話題を集めたような事件も起こっている。
参議院選の際には、ロシアの選挙妨害の指摘が話題になった。参政党の候補が「スプートニク」に取り上げられた、というところから端を発した話だった。ところが「親露派」が、子ども家庭庁を批判する者でもあったため、子ども家庭庁の批判は外国勢力の妨害だったことを示唆するポストを、三原大臣が行ったこともあった。
「親露派」認定のアカウントは、政府に批判的な投稿を繰り返している「反グローバル」派であるのが基本パターンだ。このこと自体は、世界的に起こっている思想現象のことである。そのため、アカウント凍結措置を受けたのは、「親露派」だったかもしれないが、要するに「反グローバル思想」を持って「政府批判をしていた人たち」でもあった。これは思想の問題であり、ロシア政府の選挙干渉の問題には自動的にはつながらない。
しかし「親露派」の撲滅推進運動の声を上げた政府関係者や国際政治学者・軍事評論家の方々などは、いわばロシアが「ステルス」世論工作をしている、と主張していた。
ところが今回の自民党総裁選で、「ステルス」を取り締まっていたデジタル大臣側のほうが、「ステルス」をやっていた、という構図になり、非常にややこしいことになった。
「ステルス」という概念は、少なくとも私は、軍事技術の進展の歴史の中で、使ってきた。軍事技術の発展により、主要な軍事大国は、レーダーで識別されないステルス軍用機を多数持っている。戦闘機を「ステルス」にするのが基本的だったが、ロシア・ウクライナ戦争では、「ステルス」無人機が実践投入されていることも確認されている。
ロシア機とされるドローンがポーランドとルーマニアの領空を侵犯したとされる。これについてロシアは否定する立場を取っており、ラブロフ外相は、国連総会演説においても、NATO構成諸国による陰謀だ、と主張した。
フィンランド湾からバルト海に抜けるルートを飛行したロシアのMIG-31が、エストニアの領空を侵犯した、とエストニアが主張した。ロシアはやはり領空侵犯を否定している。エストニア政府が発表した飛行ルートを示した地図だけでは、領空侵犯が12分にわたって発生した、ということを読み取ることができない。この地図を紙に印刷して、エストニア代表が、国連安全保障理事会において「領空侵犯の証拠だ」と主張したため、曖昧な雰囲気がさらにいっそう広がることになった。
ウクライナのゼレンスキー大統領は、ハンガリーのドローンがウクライナの領空を侵犯したという内容のSNSポストを発信した。これについて、ハンガリー政府は、嘘を並べて挑発するのはやめろ、証拠を出せ、と激しく反発している。ウクライナとハンガリーの間の関係の劣悪化は、すでに周知の事実となっており、泥仕合の様相だ。
ゼレンスキー大統領は、「ジョージアは欧州ではなくなった」と解説する国連総会を行ったばかりのところだ。「親露派」に乗っ取られた、という意味だが、当然、ジョージア政府関係者からの反発を受けている。さらにゼレンスキー大統領は、「モルドバが危うい状態にあるのでウクライナが支援しているが、欧州諸国も助けるべきだ」という主張を、空席が目立った国連総会議場で行った。EUの正規メンバーは、ウクライナが決定する、と言わんばかりの態度には、今後も様々な意見が投げかけられるだろう。
モルドバ政府は現在、選挙にロシアが干渉している、と主張している。欧州全域で、選挙のたびに、「親露派の取り締まり」「親露派の立候補禁止」「親露派の干渉による選挙結果の取り消し」措置をめぐる騒動が起こるようになった。構造的な事情として、思想的に「反グローバル」を掲げる勢力は、欧州全域で急速に勢力を広げている。もはや騒動が起こらない欧州の選挙のほうが珍しい。
20世紀初頭には、ナチスのプロパガンダ術に代表される大衆扇動術が、歴史を動かした。これは発達したマスメディアの効果を最大限に利用するものだった。
現代では発達したSNSを活用して、「ステルス世論工作」による大衆扇動術が、歴史を動かそうとしている。
これらの双方ともに、人間の心理を利用した世論工作術であり、抜本的な対策は難しい。画期的な方策がある、という主張自体が、「ステルス世論工作」である恐れが強いのが普通だ。
地道に生きていくのが、難しい時代だ。
■
国際情勢分析を『The Letter』を通じてニュースレター形式で配信しています。
「篠田英朗国際情勢分析チャンネル」(ニコニコチャンネルプラス)で、月2回の頻度で、国際情勢の分析を行っています。
■