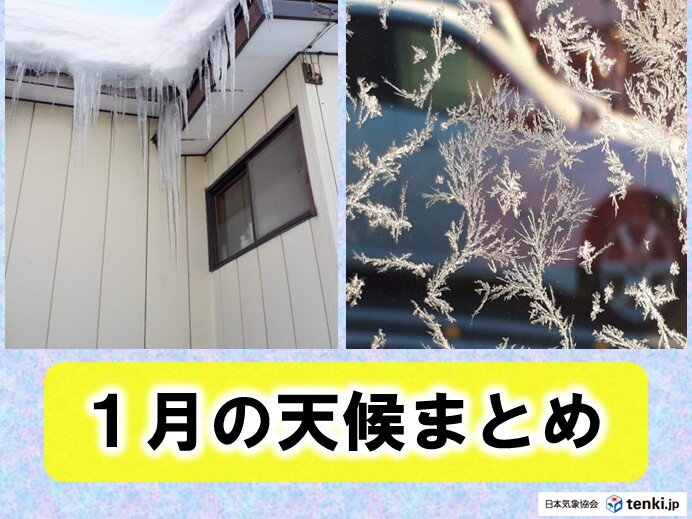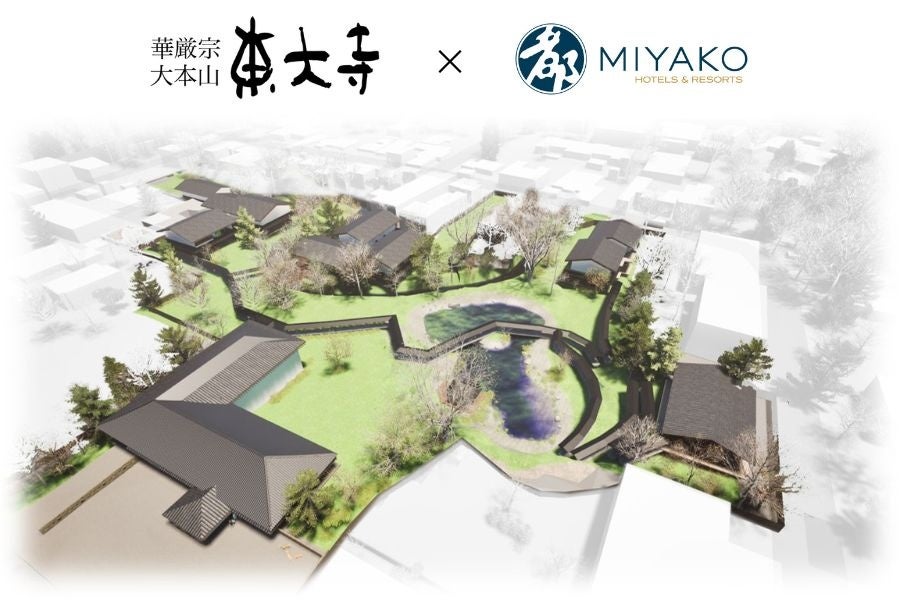店員がオーダーを忘れても、みんなが笑顔のレストラン。「注文をまちがえる料理店」が見せる、あたたかい世界

東京・原宿で9月21、22日の2日間、「注文をまちがえる料理店」が開かれた。
このレストランでは、店員は注文を忘れてしまうかもしれないし、間違った料理を持ってきてしまうかもしれない。
実際にナポリタンを頼んだ客にはオムライスが運ばれ、店員は自分が担当したテーブルがどこだったか忘れてしまうこともあった。
ここは、認知症の症状を持つ人たちがホールスタッフを務める料理店。
レストランでの体験を通して、社会の認知症への向き合い方について問いかけている。
2日間のレストラン型イベント「注文をまちがえる料理店」が開かれたのは、東急プラザ原宿「ハラカド」のレストラン「FAMiRES」。
認知症の症状がある70〜90代の計36人がホールスタッフとして、注文を取ったり、料理を運んだりした。
スタッフを務めた36人は、東京都や神奈川県、埼玉県にある高齢者用グループホーム施設などの利用者。施設を通してイベント参加について声をかけ、本人や家族が希望する人たちがスタッフを務めた。
主催するのは一般社団法人「注文をまちがえる料理店」。2017年の初開催以来、「まちがえちゃったけど、ま、いっか」をコンセプトに、各地で同様のイベントを開催してきた。
原宿でイベントが開かれた9月21日は、「認知症の日」で「世界アルツハイマーデー」。全国で一斉に同イベントを開催しようと実施したクラウドファンディングで1300万円以上が集まり、原宿以外にも、北海道から沖縄までの各地で全国34団体が同様のイベントを開催した。
レストランでは各テーブルに1人、認知症の症状があるスタッフが担当としてつき、サポート役スタッフと共に、接客に臨んだ。
注文を取るのも、水や料理を運ぶのも全てゆっくりだ。時には、今さっきやっていた作業を忘れてしまうこともある。
それでも客は笑顔で、時には「大丈夫ですよ」とやさしく声をかけ、接客する姿をあたたかく見守った。
この日のメニューはコース仕立てで、サラダとスープに続いて3種類から選べるメインメニューがあり、最後にデザートが提供される。
メインメニューの「ふわとろたまごのオムライス」にはテーブルでケチャップを、「ナポリタン」にはチーズをかけ、「ハンバーグ」には旗を立てて仕上げるというパフォーマンスもあった。
イベント前には少し不安な表情を見せていたというスタッフの水越妙子さん(92)も、いざ接客がスタートすると、ナポリタンに粉チーズをかけながら冗談を飛ばし、客を笑わせていた。
会場には、働く親の姿を見にきた家族や、グループホーム施設関係者の姿もあった。
働く水越さんの姿を見学に来たという息子の50代男性は、「働かせてもらってお客さんと笑い合っている光景を見て、本当に涙が出そうになりました」と話した。
栃木県に暮らしていた水越さんは認知症の症状が出る前、4年の間に2度の水害で被災し、床上浸水の被害に見舞われた。以降、暗い表情でいることも多く、今回イベントで笑顔で働いている姿を見て、驚いたという。
男性は元々、注文をまちがえる料理店について本を読んで知っていたため、施設を通して水越さんに声がかかった際、「ぜひ!」と返事したと話す。
水越さんが暮らす練馬区のグループホーム「愛の家」のホーム長で介護福祉士の半田龍子さんも、共にイベントの様子を見に来ていた。楽しんで働く姿を目にし、「参加してもらって良かった」と話す。
「来る前は少し不安のような表情を見せていましたが、水越さんは元々、有名歌手のバックダンサーをされていた方。担当するテーブルのお客さんとも笑顔でたくさん話されていました。
最初は現場に行った時にうまく動けるかと不安もありましたが、実際やってみると笑顔で働いていて、こういう経験は大切だと思いました」
グループホームでも、コンビニに一緒に行って買い物をするなどの経験もしている。ホームに入居する前の生活を思い出すことにも繋がり、非常に重要だという。今回の就労体験もとても意味があるものだとした。
イベント開催のためのクラウドファンディングに参加し、そのリターンとして食事に参加した男性は、7歳の子どもと来場。
クラファンに参加した理由について「なかなか認知症の方と接する機会もない中で、意義がある活動だと思って応援した」と明かした。
各テーブルでは、料理が配膳された後、スタッフが席につき、交流する時間もあった。男性のテーブルを担当したかねこさんは、まるで久しぶりに会った孫に接するように笑顔で会話し、接客も楽しんでいた。そんな姿を見て、男性はこう話した。
「私たちもいつか高齢化する。認知症の症状がある方々を社会から断絶するのではなく、一緒にできることはなんだろうと考えるこの取り組みはすごく素敵だ思いました。
今はどこか、『間違えてはいけない』雰囲気がある厳しい世の中になってしまっている。そんな中で、『ま、いっか』というコンセプトで、『間違える料理店』を開くというのは素敵な発想だと思いました」
イベント終盤では、店員を務めた人たちにショートインタビューをし、会場全員から拍手を送る場面も。認知症になる前は「元々、喫茶店をしていました」という人もいれば、「初めてこんな仕事をしました」と話す人も。
しかし皆口々に「楽しかったです」「頑張りました」「全然疲れてないですよ」と笑顔を見せた。
食事が終わった後には、各テーブルのお客さんと、テーブルを担当した店員とで、チェキで記念写真も撮影した。
一般社団法人「注文をまちがえる料理店」の理事⻑を務める介護福祉士の和⽥⾏男さんは、このイベントを続けていくことで、「次の世代をつくっていく人たちに何かを感じ取ってもらい、それがより良い社会のあり方に繋がっていけば」と話す。
イベント1日目にスタッフとして働いた一人は、イベント終了後に「すごく楽しかった」と話していたけど、何をしたかは覚えていなかったという。
和田さんは「でも、それでもいいんですよね」と笑顔を見せる。
「何があったかということは、どうってことなくて。楽しい思いをしたと感じていることが素敵なんじゃないかと思いました。それが続くような社会になっていったら、皆が生きやすくなるんじゃないかなと思います」
原宿でのイベントは2日間だったが、2017年から日本各地で継続してきたように、今後も各地で「注文をまちがえる料理店」を開いていく予定だ。
料理店発起人の小国士朗さんは、継続していく意義について、ハフポスト日本版の取材にこう話した。
「『認知症』という言葉を知らない人はいないと思いますが、認知症に対して『触れたくない』『見たくない』ものというイメージを持つ方もまだまだいらっしゃると思います。
この『注文をまちがえる料理店』をやることによって、認知症の状態にある人たちが普通に働いて、そこにお客さんとして普通に美味しいごはんを食べてきて……という状況をつくることができる。みんなが普通に触れ合え、お互いを知り合える場所をつくっていければ、認知症の見え方も変わってくるのではないかと思います」