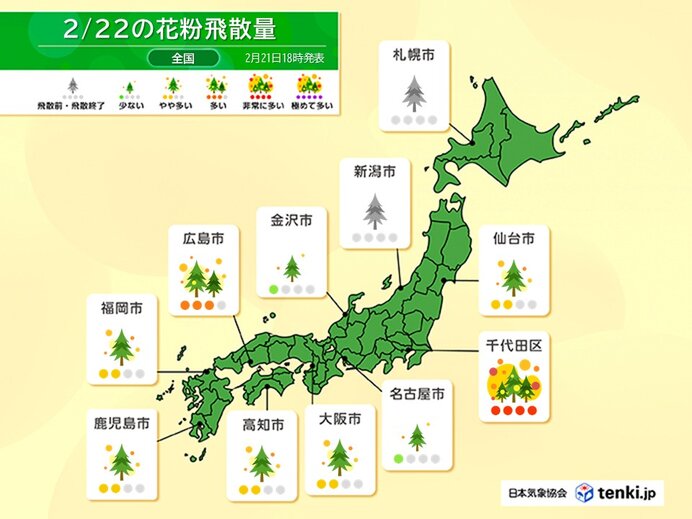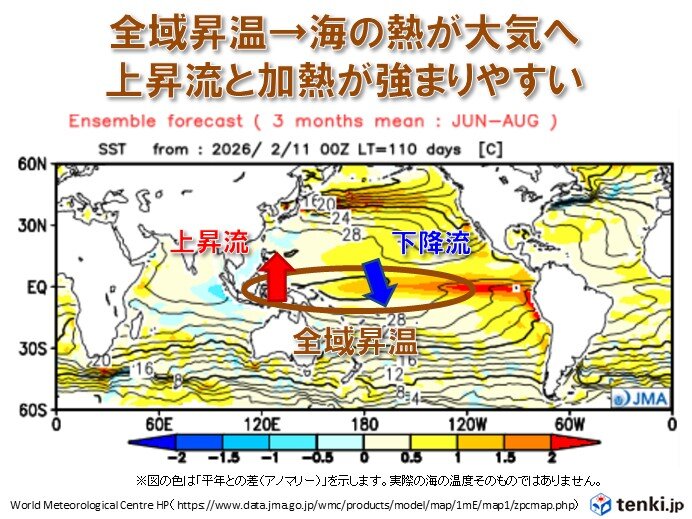「日本の娘を守れ」政府、占領軍に“慰安所”提供 軍の性犯罪助長か

1945年8月、第二次世界大戦で敗戦し、連合国軍の進駐を待つ日本政府は、占領軍兵士向けの性的な「慰安施設」を急ピッチで整備した。
その大義名分は、「一般の婦女子」を占領軍の性暴力から守るための「性の防波堤」が必要という理屈だ。衣食住の提供や高給をうたい、性の相手をする女性をかき集めた。
今回、毎日新聞はアーカイブから当時の紙面や写真を掘り起こし、慰安所設営の経緯や実態を検証した。
なぜこの国策は実行に移されたのか。そして、日本社会はこの負の歴史から脱却したといえるのだろうか。
<主な内容> ・敗戦処理内閣 首相の念頭にあった恐怖 ・本紙広告でも女性募集 業務説明なく ・「女のニコニコ顔は誤解を招く」 ・本紙が報じた占領軍の「蛮行」とは ・「占領成功」の裏にあった性暴力 ・日本社会は本当に変わったか
後編は、慰安所の実態を長年研究してきた一橋大の平井和子・客員研究員のインタビューを8月16日6時に公開します。
敗戦直後に「性の防波堤」議論
第二次世界大戦末期の1945年7月、米英中からなる連合国軍がポツダム宣言で日本に降伏を迫った。日本は鈴木貫太郎内閣のもと宣言受諾を決定。8月15日に終戦を迎え、鈴木内閣は総辞職した。
連合国軍による占領が決定的となる中、8月17日には東久邇稔彦内閣が発足した。
東久邇首相の著書「私の記録」によると、首相は自らの使命として、憲法の尊重、軍の統制とあわせて「秩序の維持」を掲げた。
そして組閣初日の閣議で取り上げたのが、日本の女性を占領軍の性暴力から守るための「性の防波堤」=慰安所の整備だった。
「日本の兵隊のしたこと」
元毎日新聞記者・住本利男氏(1908~85年)の著書「占領秘録」によれば、当時の警視総監・坂信弥は、国務大臣・近衛文麿から「日本の娘を守ってくれ」と指示を受けた。
坂は後にこう証言している。
「一般の婦女子をまもるために防波堤を築くことも考えました。慰安施設をつくり、働く女性を集める。矢面に立とうという人があったればこそ、あとの若い人たちは救われたのだと思う」
旧内務省出身者らの「大霞会」がまとめた「内務省外史 続」には、坂の別の証言も残されている。
「東久邇さんは南京に入城されたときの日本の兵隊のしたことを覚えておられる」
「それで、…