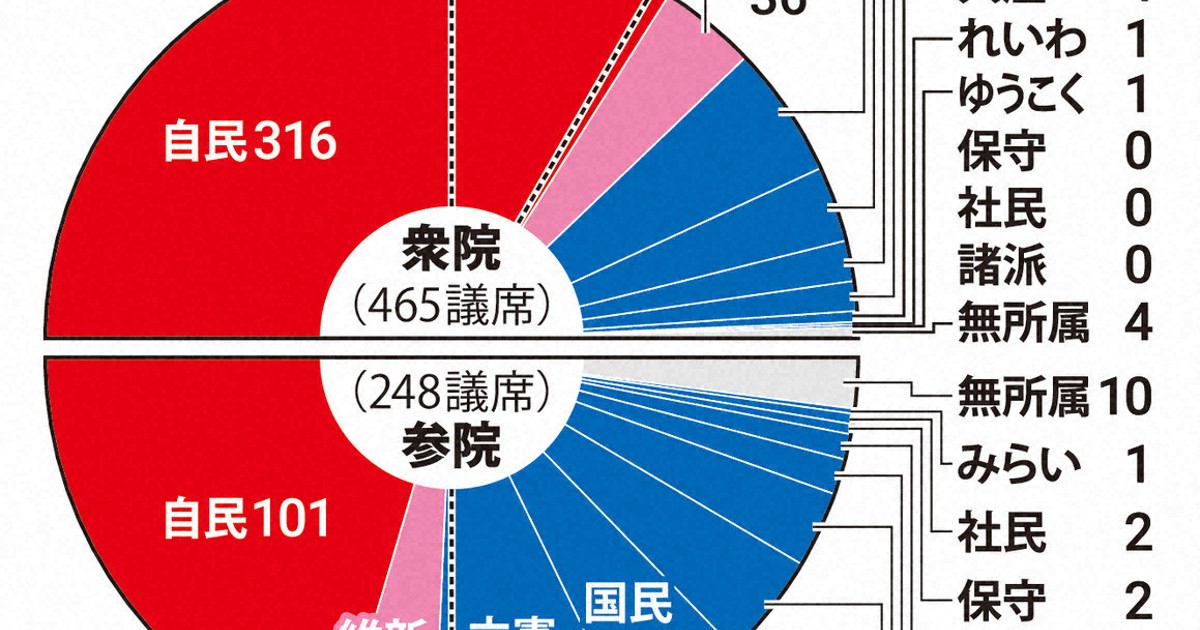10月21日はレモン彗星が1000年に一度の最接近、しかもオリオン座流星群と奇跡の競演!(ナショナル ジオグラフィック日本版)

宇宙空間には何もないわけではない。われわれの太陽系の周辺には、氷や塵(ちり)の粒子が散りばめられており、それらは惑星、恒星、さらには銀河の間にも存在する。 氷や塵が太陽系に存在することを示す証拠が彗星や小惑星だ。それらは約46億年前、巨大で濃密なガスと塵の雲から太陽系が形成された際に残された残骸なのだ。 太陽が活動を開始したあと、残されたガスや塵は徐々に集まって塊を作り始めた。その熱から遠く、冷え切った外縁部では、彗星が形成された。氷の多い領域は、やがて「カイパーベルト」(海王星の軌道より外側で、冥王星をはじめとする太陽系外縁天体がある領域)や、さらに遠方の「オールトの雲」(太陽系のさらに周縁を取り囲む氷微惑星などがある領域)へと発展し、凍りついた無数の彗星の巨大な貯蔵庫となった。 「彗星は非常に研究しがいのある天体です。なぜなら、太陽系の原始的な構成要素がたっぷりと詰まっているからです」とストラウド氏は言う。「彗星が凍結状態にあるということは、そこに含まれる塵や氷の多くが、何十億年もの間ほとんど変化していないということなのです」
1月3日に初めて姿を現したとき、レモン彗星の見た目はごく平凡で、ただ夜空に浮かぶぼんやりとした光の点でしかなかった。アリゾナ大学が運営する観測プロジェクト「カタリナ・スカイサーベイ」の責任者で、当日の観測を担当していたカーソン・フルス氏は、これはよくあることだと述べている。 「彗星は、"点灯"するまでは観測できないことがあります」と氏は言う。「点灯」とはつまり、彗星が太陽に十分に接近して氷がガスとなり、彗星特有の尾を形成するようになることだ。 フルス氏によると、今回の彗星は、これまでに70個ほど見つかっている「レモン彗星」のひとつだという。 彗星の名称は、それを発見した天文台、あるいはその天体を最初に発見し、すぐにそれが彗星であると気付いた人の名前にちなんでつけられることが多い(レモン彗星はレモン山天文台で発見された)。フルス氏が発見したとき、今回の彗星はまだ「点灯」しておらず、尾を引く彗星というよりもむしろ小惑星のように見えたという。 「天文台の望遠鏡を稼働させていると、一晩の間に彗星がいくつか見えるのは珍しいことではありませんが、それでもやはり心が踊ります」とフルス氏は言う。
Page 2
毎年、何十個もの彗星が内部太陽系(現在、地球や火星といった岩石惑星がある太陽に近いエリア)を通過するが、明るさ、特徴的な緑色の光、地球からの近さにおいて、レモン彗星は2025年で最も注目すべき存在と言える。そのエメラルド色の輝きは、二原子炭素(C2)という、太陽光によって分解されて緑色の光を放つ分子から生まれる。 淡い青色の尾は、実際には2本の尾からできている。1本は彗星自体に由来する氷と塵の尾(ダストテイル)、そしてもう1本は、彗星が太陽に近づいて「点灯」するときにできるガスのイオンの尾(イオンテイル)だ。 一般的に、彗星には一酸化炭素、二酸化炭素、水の氷が含まれているが、それらの分子比率は彗星ごとに異なると、ストラウド氏は言う。「探査機で近くから撮影した彗星は、どれも異なる姿をしています」 彗星はまた、よく変化する天体でもある。太陽光や熱によって、凍りついた表面が変化し、彗星本体から物質が吹き飛ばされて、数時間のうちに形や明るさが変化することもある。 「彗星から大きな塊が飛び散る様子が観測されることもあります。尾の中にさざ波のような模様が現れ、それがゆっくりと形を変えていくんです」とフルス氏は言う。「宇宙空間であれほどダイナミックな現象は、そうは見られません」 多くの彗星研究者が目指す次なる大きな目標は、彗星から凍ったままの塊を持ち帰り、そこに含まれる太古の氷と塵を研究するサンプルリターン・ミッションだ。 「彗星について知れば知るほど、自分と宇宙の歴史とのつながりを実感します」とストラウド氏は言う。「彗星の塵を追うことは、太陽系の誕生、そして究極的にはわれわれ人類の誕生の謎を解くために、パンくずを追うようなものなのです」
レモン彗星が地球に最接近するのは10月21日だ。この日は新月と重なり、空が暗いおかげで、光の弱い天体も見えやすくなる。 日没後まもなく、西北西の地平線付近で、さそり座、てんびん座の周辺に見える柔らかい緑色の光を探してみよう。レモン彗星は10月中旬から11月初旬まで観測することができ、地球から遠ざかるにつれて光が弱くなっていく。 「肉眼で見るだけでも楽しめますが、双眼鏡を使って、高画質のスマートフォンやデジタルカメラで写真を撮ることをおすすめします。そうすれば、彗星のコマがより鮮明に見えるでしょう」とストラウド氏は言う。コマとは、彗星の氷の核を取り囲んでいる、光を放つガスと塵の雲のことだ。 10月21日にはまた、ハレー彗星(1P/Halley)の残骸を起源とする非常に明るく速いオリオン座流星群が極大日を迎える。夜空で繰り広げられる2大イベントの奇跡の競演を楽しもう。なお、当日に天気が悪くて夜空が見えなくても、彗星は位置を次第に西から西南西へと変化させながら、11月上旬まで見えると予想されている。
文=Isabel Swafford/訳=北村京子